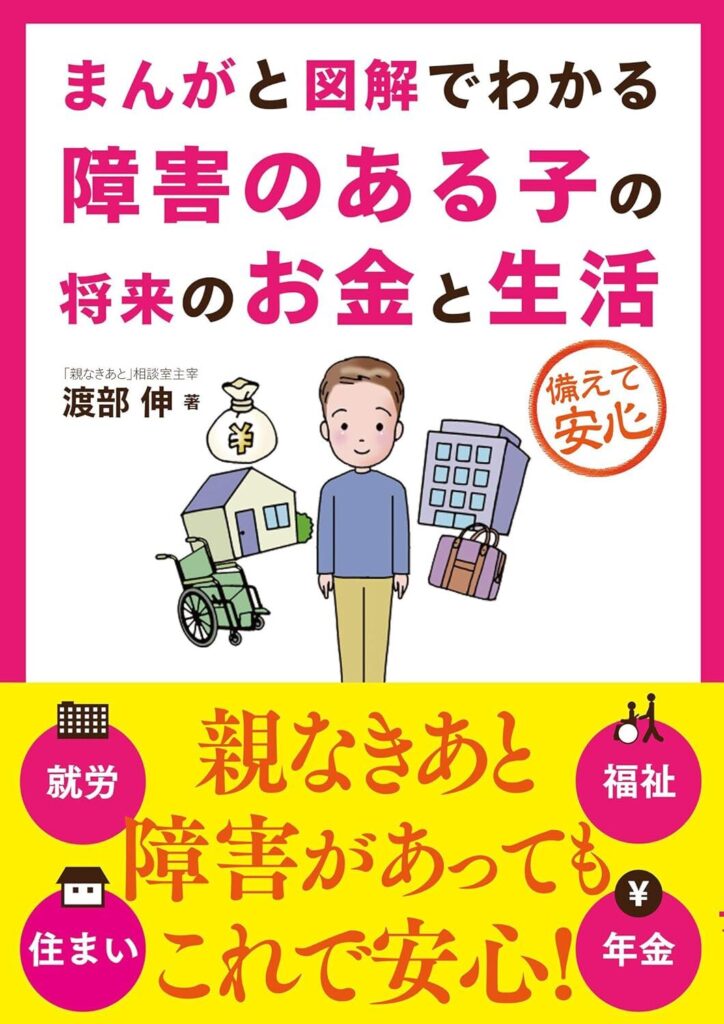
障害のある子を育てるご家庭にとって、「自分がいなくなった後、この子はどうやって生きていけるのだろう」という不安は、誰もが一度は直面する深い悩みです。支援の仕組みは複雑で、制度も頻繁に変わるなか、何から手をつけてよいのかわからず、不安だけが膨らんでしまう──そんな声を多く耳にします。

『まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活』は、そんな将来へのモヤモヤをひとつひとつ整理し、親がいま準備できることを、やさしく、具体的に解きほぐしてくれる一冊です。
文章を最小限にとどめ、まんがと図解をふんだんに用いることで、「難しそう」「読むのが大変そう」と感じていた制度の知識を、視覚的に、直感的に理解できるよう工夫されています。
制度の基本、就労や住まいの選択肢、お金の残し方、成年後見制度や信託などの活用方法まで。
読み終えたあとには、「やるべきこと」が見えてくる、そして「誰に相談すればいいのか」が分かる。
親子の未来を支えるための“最初の一歩”を踏み出したいすべての方に、心からおすすめしたい実用書です。

合わせて読みたい記事
-

-
障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年版】
障害のある子どもを育てている親御さんへ——日々の子育ての中で、こんなふうに感じたことはありませんか?「子どもの気持ちがうまくわからない」「どうサポートすればいいのかわからない」「このままでいいのかな… ...
続きを見る
書籍『まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活』の書評

本書は、障害のあるお子さんの将来に対する不安を抱えるご家庭に向けて、具体的な制度と準備の方法をわかりやすく示した実践的なガイドブックです。
その特徴を理解するために、以下の4つの観点から読み解いてみましょう。
- 著者:渡部 伸のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
読者にとって「この本がどれだけ信頼できるか」「どう役に立つか」が明確になるように解説していきます。
著者:渡部 伸のプロフィール
渡部 伸(わたなべ・しん)氏は、行政書士、社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士として、法律・年金・相続・福祉の分野にまたがる広範な専門知識を持つ実務家です。東京都世田谷区を拠点に「親なきあと相談室」を運営し、障害のある子どもを持つ家族に向けて、講演・執筆・個別相談など幅広い活動を展開しています。
また、彼自身が障害のある娘さんの父親でもあることから、単なる“制度の解説者”ではなく、“当事者の一人”として、親の目線で不安や疑問に寄り添った情報提供ができるのが特徴です。
著書には、『障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて』(自由国民社)などがあり、現場で生きた情報をもとにした実践的なガイドとして評価されています。

本書の要約
この本は、障害のある子どもや家族が将来に直面する問題を、まんがと図解で分かりやすく解説する実用書です。特に「親なきあと」に焦点を当て、親が亡くなった後や高齢になったとき、子どもがどうやって生活していけるかをテーマにしています。
章ごとに、よくある不安や疑問がまんがで提示され、それに対して制度や選択肢を解説するという構成になっています。例えば「親が遺してくれたお金を本人が管理できるのか?」という不安には、成年後見制度や信託の仕組みを紹介。「将来の住まいはどうなる?」という悩みには、グループホームや地域生活支援の情報を示します。
内容は5章に分かれています。第1章では不安の種類を明らかにし、第2章で早期の備えを提案。第3章ではお金の残し方を具体的に、第4章では金銭管理の方法を解説し、第5章では親が元気なうちにやるべきことをまとめています。
各ページにはイラストや図が豊富に使われており、文章を読むのが苦手な方でも理解しやすい作りです。福祉制度に詳しくない初心者でも、安心して読み進められるよう工夫されています。

本書の目的
この本の狙いは、障害のある子を持つ家族が抱える不安を、「知識」と「行動」に変えることです。とくに問題が起きてから対応するのではなく、あらかじめ準備することで安心して老後を迎えられるようにするための“先回りの本”です。
日本の福祉制度は充実している反面、とても複雑です。支援の種類や対象者、申請先がバラバラで、専門家でなければ理解が難しいという声も多くあります。そのため、支援を受けるべき人が制度にアクセスできずにいるという現実もあります。
本書では、そうした情報の分断を埋めるために、親の立場から知っておくべき制度をテーマ別に紹介しています。遺言の残し方、信託の活用、成年後見の選び方、障害者年金の手続きなど、実際にやるべきことがリストアップされており、読者が「次に何をするべきか」が明確になります。
また、著者自身が経験した親としての気づきや、相談現場でのエピソードも随所に挿入されており、机上の理論ではなく、実生活に即した視点で書かれている点も特長です。

人気の理由と魅力
本書が多くの読者から高く評価されているのは、内容の信頼性とわかりやすさのバランスが絶妙だからです。まんがと図解によって、福祉や法律の知識がない人でも無理なく読み進めることができ、しかも情報は専門的で深い内容までカバーされています。
例えば、成年後見制度については、制度の概要に加え、「どんなときに使うべきか」「どの種類を選ぶべきか」「後見人は誰にするか」といった実践的な疑問にも触れています。また、信託や遺言、年金制度など、一見複雑なテーマもやさしくほどかれており、読んでいるうちに「自分でもできそう」と思える内容になっています。
さらに、子どもを支える支援者とのつながりの築き方や、住まい選びの基準など、制度だけではなく暮らし全体の設計に役立つ情報が含まれているのも魅力です。単なるガイドブックを超えて、「人生設計を考えるきっかけ」を与えてくれる本としても機能します。

本の内容(目次)

本書は、「親なきあと」に備えるために必要なことを、5つの章に分けて体系的に解説しています。それぞれの章では、家族の不安や疑問にまんがで共感しつつ、図解を交えて解決の方向を示していきます。
以下の内容に沿って展開されています。
- 第1章 「親なきあと」の不安はそれぞれ
- 第2章 若いころから始めたい親なきあとの準備
- 第3章 本人や家族が困らない、お金の残し方
- 第4章 本人のお金の管理方法
- 第5章 親あるあいだの準備で一番大切なこと
それぞれの章には、制度や仕組み、実践方法などが盛り込まれており、「いま何をするべきか」が自然と見えてくる構成です。
第1章 「親なきあと」の不安はそれぞれ
この章は、障害のある子どもを育てている親御さんが感じる「親なきあと」への不安を整理するところから始まります。
子どもが成長していく中で、親は次第に「自分が先にいなくなったらどうしよう」「この子は一人で生きていけるだろうか」という将来への不安を強く意識するようになります。けれども、その不安があまりに漠然としていて、どこから備えればよいのか分からないというのが、多くのご家庭の現状です。
そこで本章では、以下のような代表的な不安を4つの視点から提示しています。
- 将来的に経済的に困窮しないか
- 残したお金を本人が安全に管理できるか
- 生活の拠点(住まい)はどう確保すればよいか
- 親以外に誰が子どもを支えてくれるのか
このように「不安の中身」を分類して明文化することで、漠然としていた悩みが具体的な課題として見えてくるのです。さらに、本書ではまんがの導入によって、実際の家族の会話や生活シーンを通して問題提起がなされるため、「これはうちのことかもしれない」と読者自身が自然と物語に引き込まれます。
章の最後には「本書の見方と使い方」も記載されており、今後の各章をどう読み進めると効果的か、読み手の理解を導くガイドも備えられています。

第2章 若いころから始めたい親なきあとの準備
第2章では、「備えは早ければ早いほどよい」という考えのもと、親がまだ若く、子どもも支援を受けながら将来の自立を模索していける時期にこそ、しておくべき準備を詳細に解説しています。
まず、障害者手帳や障害基礎年金など、障害者支援制度の入り口となる制度の紹介から始まります。たとえば、障害者手帳には身体・知的・精神の3種類があり、これを取得することで、福祉サービス、税制優遇、交通機関の割引など、さまざまな公的支援を受けることが可能になります。
また、「就労支援」に関する情報も充実しています。働くことに不安がある子どもたちにとって、福祉的就労は将来の生活を支える柱です。本書では、就労移行支援(一般就労を目指す)と、就労継続支援A型・B型(福祉的就労の場)との違いや、どんな人がどの支援を受けると効果的かを、分かりやすく図解で説明しています。
さらに、「障害年金」は20歳前後の申請が重要なタイミングとなる制度です。特に、先天性の障害や子ども時代から支援を受けてきたケースでは、「20歳前障害基礎年金」として申請することができ、家庭の経済的基盤を支える役割も果たします。
申請のタイミングや必要書類が具体的に記されているので、制度を「名前だけ知っている」状態から「実際に申請できる」レベルにまで読者を導いてくれます。

第3章 本人や家族が困らない、お金の残し方
この章は、障害のある子どもに親が財産を残すときに直面する問題について、法的・制度的な観点から深く掘り下げています。親としては「なるべく多くのお金を残してあげたい」と願うものですが、実際には“残し方”を間違えると、子どもが不利益を被る可能性があるのです。
たとえば、遺言書を書かずに亡くなると、相続人どうしで遺産分割協議を行う必要があります。しかし、障害が重く意思表示ができない場合、そもそも協議に参加できないこともあります。こうした事態を防ぐために、遺言書の作成は欠かせません。
また、「全部の財産を障害のある子に残す」という選択は、他のきょうだいとの関係性を悪化させたり、遺留分(法律上、最低限もらえる相続分)を侵害することでトラブルの原因になることもあります。
本章では、こうした問題を避けるために「家族信託」「福祉型信託」「生命保険信託」「特定贈与信託」など、財産の管理と活用を第三者に委ねる方法も紹介されています。これにより、本人が直接管理しなくても、必要なタイミングで必要な支出ができるようになるのです。
遺言の形式についても、自筆証書と公正証書の違い、遺言執行者を誰にするか、親の思いを「付言事項」として残す方法など、制度だけでなく実務に即した内容が充実しています。

第4章 本人のお金の管理方法
第4章では、「親が遺したお金を、子どもが安全に使えるようにするにはどうしたらよいか?」という視点から、法的な制度の活用法が詳しく解説されています。
中心となるのは「成年後見制度」です。この制度では、本人に代わって財産管理や契約を行う「成年後見人」が家庭裁判所により選任されます。本人の判断能力に応じて、補助・保佐・後見の3段階に分かれており、それぞれできることが異なります。
しかし成年後見制度は万能ではありません。後見人による不正や、制度の煩雑さ、費用面の負担など、利用にあたっての注意点もあります。そのため、「法人後見」や「任意後見」「日常生活自立支援事業」といった、柔軟性のある選択肢も取り上げられています。
たとえば任意後見は、本人が元気なうちに信頼できる人と契約しておくことで、将来的な判断能力の低下に備える制度です。行政書士や司法書士が専門的に関与するケースも多く、「将来のリスクを自分の意思で備える」ための重要な仕組みといえます。

第5章 親あるあいだの準備で一番大切なこと
最終章では、制度や法律では解決しきれない「人と環境」の支援づくりがテーマとなっています。お金や制度も重要ですが、それ以上に「誰とつながって生きていくか」「どこで安心して暮らせるか」が、親なきあとの生活の鍵を握ります。
住まいの選択肢としては、グループホームやケア付きの福祉住宅などが紹介され、費用や申し込み方法、支援体制の違いなどが詳しく説明されています。現場で起こりうるトラブルや、親が元気なうちにショートステイなどで「試してみる」ことの大切さも語られています。
また、「子どもの生活のトリセツ」を作っておくというアイデアも非常に実用的です。これは、本人の性格や習慣、好き嫌い、発作の傾向などをまとめたもので、将来支援にあたる人がスムーズに理解・対応できるようにする工夫です。
さらに、地域との関係性、支援者とのネットワーク構築の重要性も説かれています。「親なきあと」でも孤立しないために、支援者やきょうだい、専門職とつながり続ける仕組みが必要です。

対象読者

この本は、障害のある家族の将来に不安を抱える多くの方々に向けて書かれています。特定の立場や知識レベルを問わず、制度やお金、暮らしのことを基礎から丁寧に学びたいすべての人にとって、有益な入門書です。
読者のニーズや背景に合わせて、特に次のような方々におすすめできます。
- 障害のある子を育てている親御さん
- 高齢の親を持つ障害のある兄弟姉妹
- 障害者支援に関わる福祉・医療の関係者
- 制度やお金の知識をこれから学びたい方
- 文字よりも視覚的に理解したい読者
それぞれの立場ごとに、どのような視点でこの本を読むと理解が深まりやすいのか、詳しく見ていきましょう。
障害のある子を育てている親御さん
障害のある子を育てる親にとって、「自分がいなくなった後、この子はどうやって生活していくのだろう?」という不安は、常につきまとう切実な課題です。特に、将来に向けたお金の準備や生活の基盤づくりは、多くの家庭が直面する共通の悩みです。
本書は、そうした不安を少しでも軽減し、親としてできる備えを具体的に示してくれる一冊です。制度の知識がなくても理解できるように、複雑な内容をわかりやすい言葉と図解で解説し、「まず何から始めればよいのか」「どこに相談すればいいのか」を段階的に教えてくれます。
たとえば、障害者手帳の取得や障害基礎年金の申請方法、将来の住まいの選択肢、信託や相続のことまで、幅広い内容をカバーしているため、読者は読み進めるうちに、自然と将来設計の基礎を学べるようになります。

高齢の親を持つ障害のある兄弟姉妹
兄弟姉妹が障害を抱えている家庭では、親の高齢化とともに、将来的に自分がその役割を引き継ぐことへのプレッシャーを感じる方も多いでしょう。とくに、親がすでに高齢となり、介護や医療の問題も重なってくると、「この先、どうやって支えていけばいいのか」「法律的な責任はどうなるのか」など、多くの悩みが一気に押し寄せてきます。
本書は、そのような兄弟姉妹に向けて、実際にどんな準備が必要なのか、支援制度の使い方や遺産相続の基礎、信託の仕組みなど、専門的で難しいテーマをマンガと図解を用いて、非常にわかりやすく解説しています。
また、家族間で話し合いを進める際の注意点や、「きょうだい間でトラブルを避けるにはどうしたらよいか」といった人間関係にも踏み込んでおり、実用面と心理的配慮の両面が揃っているのも魅力です。

障害者支援に関わる福祉・医療の関係者
日々の支援活動において、福祉職や医療従事者が直面するのは、家族や本人からの「制度や将来に関する不安の声」です。しかし、現場で働く人であっても、法律や制度の全体像を体系的に理解しているケースは決して多くありません。実務に追われる中で、最新の情報に追いつけないという現状もあります。
本書は、支援者にとっても非常に有益な情報源です。障害年金や成年後見制度、信託制度の概要を、現実の相談事例を交えて解説しているため、現場で即活かせる知識が身につきます。また、障害者手帳の取得メリットや、雇用支援制度の違いなど、知っておくべき基本情報も押さえられています。
さらに、支援者自身が家族と一緒に読み進めることで、共通理解を深めることもでき、相談や支援の場面でより丁寧な対応が可能になります。

制度やお金の知識をこれから学びたい方
相続、年金、信託といったテーマは、一般の人にとっては取っつきにくく、どこか自分とは無関係に思えてしまいがちです。しかし、障害のある家族がいる場合、これらの知識は日常生活の延長線上にある「必要な生活術」となります。
本書は、制度やお金の知識をゼロから学びたいと考えている方にぴったりの入門書です。難しい言葉を使わず、制度のしくみを生活の具体例に照らし合わせて解説しており、読むほどに理解が進みます。
また、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」や「福祉型信託」など、時事的で新しい情報も取り入れており、最新の動向も自然に押さえることができます。読み終わったあとには、自分や家族の今後に必要な行動を具体的にイメージできるようになるでしょう。

文字よりも視覚的に理解したい読者
文字だけの文章が苦手な人にとって、「読む」こと自体が高い壁になることはよくあります。とくに高齢者や、知的障害のある本人、読み書きに困難のある方にとっては、「わかりやすく伝えてもらう」ことが情報取得の大前提です。
この本は、その点で非常に配慮された構成になっており、まんがと図解によって、文章を読み込まなくても内容を理解できる工夫が随所に施されています。図で説明される制度の流れ、登場人物同士のやり取りから自然と読み解ける支援の全体像など、視覚的な理解を重視して作られているため、読むことに苦手意識がある方にも安心です。
家族が読み聞かせたり、一緒にページをめくりながら話すことで、より深い理解や共有が生まれるきっかけにもなります。

本の感想・レビュー

親の気持ちに寄り添う本
私は現在、小学生のダウン症の娘を育てています。日常の生活は慣れてきたとはいえ、ふとした瞬間に「もし私が突然いなくなってしまったら、この子はどうなるのだろう」という不安が心を支配します。そうした心配は、誰に相談してよいかも分からず、ただひとり胸の奥に抱え込んでいました。
そんなときに出会ったのが、この本です。最初のページから、自分と同じような悩みを持つ家族が描かれたまんがが始まり、思わず涙があふれました。まるで自分の生活が描かれているようで、「わかってもらえた」と感じたのは初めてです。制度やお金の話は、いつもなら難しくて読むのをやめてしまうのに、この本は自然に頭に入ってくるように構成されていました。
特に「親なきあと」というテーマについて、真正面から語ってくれる姿勢に深く共感しました。著者が当事者の家族の視点に立って書いていることが伝わってきて、どんな小さな不安にも丁寧に答えてくれるような安心感がありました。この本に出会って、私だけが不安なのではないと気づけたこと、そして「やれることから始めよう」と思えたことが、何より大きな一歩になりました。
文字が苦手な親にも優しい
実を言うと、私は昔から活字を読むのがあまり得意ではありません。障害のある子どもを育てていると、福祉や年金、相続の制度など知らないといけないことが山ほどあるのに、どの本も文字が多くて難しい。読む前から尻込みして、ずっと放置してきました。
でもこの本は、最初から印象がまったく違いました。手に取ったときの軽さ、まんがのやさしいタッチ、図解のわかりやすさ。どれも「読んでほしい」と語りかけてくるようでした。特に印象に残ったのは、制度の仕組みが複雑な部分でも、図と吹き出しの説明が組み合わさっていて、目で見て直感的に理解できたこと。私のように文字の多さに苦手意識がある人間にとって、本当にありがたい構成でした。
母にも見せたところ、「これはわかりやすい」と感心して、いつもは本を読む習慣のない母が最後まで読み切ったのには驚きました。自分だけでなく、家族も一緒に理解できる――そう思えたことで、我が家の将来について話すきっかけにもなりました。
若いうちから準備が必要だと気づいた
私は現在40代で、障害のある長男がいます。仕事や家のことで毎日忙しく、「将来のことはそのうち考えよう」と思いながらも、つい先送りにしてしまっていました。でもこの本を読んで、今のうちから備えておくことの大切さに、ようやく気づかされました。
特に、「親が元気なうちにこそできる準備がある」というメッセージは、自分に突きつけられているようでした。就労や年金の制度、住まいの問題、相続やお金の管理方法など、どれも現実的で、他人事ではありません。章ごとにテーマが整理されているので、自分に必要な情報だけを選んで読み進められるのも助かりました。
「何から始めればいいのかわからない」というのが、これまで準備を後回しにしていた一番の理由でしたが、この本がその道しるべになってくれました。ページをめくるたびに、「これならできそう」というヒントが見つかり、今では家族と一緒に将来を考える時間を持つようになりました。何もしないでいるよりも、少しずつでも動き出すことが、こんなにも心を軽くするとは思いませんでした。
成年後見制度の基礎が理解できた
恥ずかしながら、これまで「成年後見制度」についてほとんど何も知りませんでした。名前は聞いたことがあっても、それがどういうときに使えるのか、どんな手続きが必要なのか、まったくピンと来ていなかったんです。
でもこの本を読んで、はじめてその全体像をしっかり把握することができました。制度の目的から仕組み、法定後見と任意後見の違い、さらにはどんな人が後見人になれるのかまで、非常に丁寧に説明されていて、読み終える頃には自分の中で「必要になったときにはこう動けばいい」という明確な道筋ができていました。
特に印象に残ったのは、「まだ使いたくない人」への言葉。無理に制度を使うのではなく、自分たちの生活や価値観に合わせて選んでいけばいいという視点は、強制的ではなく寄り添う姿勢が感じられ、ホッとしました。これまで避けていた制度に向き合えたことは、自分にとって大きな前進です。
家族信託という選択肢を知った
これまで相続や財産管理のことといえば、「遺言を書けばいい」と思っていました。ところが、本書を読んで「家族信託」という言葉に出会い、それがまさに我が家に必要な制度かもしれないと思いました。
信託と聞くと、どうしても「お金持ちが使う仕組み」という印象を持っていたのですが、この本では障害のある子どもを持つ家庭にとって、非常に現実的な選択肢であることが説明されていて目からウロコでした。誰に何を託すのか、どんな財産をどう使ってもらうのかを親が決めておけるという点に、強い安心感を覚えました。
ページごとに図解があり、法律や制度の説明も優しく書かれているので、読み進めるうちに信託のイメージが具体的に持てるようになりました。今は専門家に相談して、実際に家族信託の準備を進めようかと考えているところです。知らなかった選択肢を与えてくれたこの本に、心から感謝しています。
兄弟との話し合いのきっかけに
私は妹が重度の知的障害を持っており、両親と一緒に暮らしています。両親が元気なうちはなんとか生活が回っていますが、正直、自分が主に面倒を見ていく立場になる未来を思うと、不安が膨らむ一方でした。兄弟間でこうした話をするのはデリケートで、なかなか口にできずにいたのですが、この本を通じてようやくその第一歩を踏み出すことができました。
家族の将来を見据えた「親なきあと」の備えについて、実例をまじえてわかりやすく解説してくれる内容が、私の心に強く響きました。特に相続や遺言の章では、親や兄弟で話し合っておかないと将来大変なことになるという現実が丁寧に描かれており、それを読んで背中を押されるように、父と母に「少し、これについて考えてみよう」と話すことができました。
感情が絡む問題だからこそ、このような本を間に置いて会話を始めるのは有効だと感じました。今では兄とも定期的に話すようになり、「妹をどう支えていくか」を家族全体の課題として共有できるようになったのが大きな成果です。
親亡き後の住まいが具体的にわかった
これまで、息子の将来について漠然と「どこか施設に入るのかな」と考えていた程度で、住まいについて真剣に調べたことはありませんでした。でも、この本を読んで、自分がいなくなった後の「住む場所」が、いかに重要で、かつ選択肢が多様になってきているかを知り、衝撃を受けました。
特に印象に残っているのは、グループホームの章。支援のレベルや費用、運営団体による違いなど、必要な情報がわかりやすく整理されており、具体的な選択肢として現実味を持ってイメージすることができました。これまで見過ごしてきた「地域で暮らす」という可能性が、ぐっと身近に感じられるようになったのです。
さらに、住まいを選ぶために今からやっておくべき準備、相談できる場所についても書かれていて、「自分の代わりに支えてくれる人を、今から見つけていくことが大切」というメッセージが心に残りました。これまでは怖くて考えられなかったことを、ようやく正面から向き合えるようになりました。
就労や年金制度の情報がありがたい
我が子もそろそろ進路を考える時期に入り、将来の就労について本格的に調べ始めていたところでした。この本の就労支援の章は、今の自分にとってまさに必要な情報が詰まっていて、本当にありがたい内容でした。
支援機関の種類、就労継続支援A型・B型の違い、さらには年金との関係まで、今までは点だった情報が線でつながり、「なるほど、こういう仕組みで支援が成り立っているのか」と納得できました。また、障害基礎年金についての記述も非常に具体的で、手続きの流れや受給の条件などがしっかり書かれていたので、自分で役所に行く前の下調べとしても大いに役立ちました。
専門的な内容をここまでわかりやすく説明してくれている本は貴重だと思います。私自身が内容を理解できただけでなく、配偶者とも共有して話し合うことができました。支援制度は難しそうだからと敬遠していた自分を変えるきっかけをくれた一冊です。
まとめ

この本は、障害のある子どもやその家族が直面する「将来の不安」に向き合い、制度やお金、支援の仕組みを具体的に理解していくための第一歩として、大変有益な一冊です。全体を通じて、読者に寄り添う視点と、まんがや図解によるやさしい表現が印象的で、難しい内容もすんなりと頭に入ってきます。
本書を通じて得られる理解と知識の整理に役立つよう、最後に以下のような観点からまとめを構成しました。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
これらを通じて、「読んで終わり」ではなく、「行動につなげる」実践的な知識として、家族の将来設計に役立てていくことができます。
次項から、それぞれについて詳しく解説します。
この本を読んで得られるメリット
本書は、障害のある家族を支える人にとって、制度やお金の不安を取り除き、将来に向けた備えを一歩踏み出すための「道しるべ」となる一冊です。
以下のような点で、読者にもたらす実用的な価値があります。
難しい制度がやさしく理解できる
障害者を支えるための制度は非常に多岐にわたり、用語や仕組みも複雑です。例えば「成年後見制度」や「家族信託」、「就労継続支援A型・B型」など、制度の名前だけで拒否反応を示してしまう人も少なくありません。しかし本書では、そうした内容を「まんが」や「図解」という視覚的な手法で解きほぐしており、初心者でも内容を自然と吸収できます。文字が苦手な人でも、感覚的に読み進められる工夫が満載です。
お金と相続に対する不安が軽くなる
親として一番の悩みである「自分が亡くなった後、子どもが経済的に困らないか?」という問いに対し、本書は具体的な解決策を提示しています。例えば、遺言書や信託の使い方、生命保険信託やiDeCoの活用法など、資産の規模に関わらずできる備えを紹介。これにより「何をどこまで準備すべきか」という判断の軸が持てるようになります。
就労や住まいなど将来設計の道筋が見える
お金のことだけでなく、日常の生活設計にも光を当てているのが本書の特長です。就職、生活支援、グループホーム、地域生活支援など、「親がいなくなったあと、子どもがどこで誰と、どう暮らすのか」という核心に迫る内容が数多く取り上げられています。その情報を踏まえ、家族間での話し合いや、支援者との連携にすぐ役立てられます。
気持ちに寄り添ってくれる安心感がある
制度や法律の解説だけではなく、「こんな悩みを抱える方が多いですよ」というエピソードや、「こんなふうに準備した家族がいます」といった事例紹介も掲載されています。こうした構成によって、「自分だけが不安なわけではない」と感じられるようになり、精神的な負担が軽くなります。親なきあとを考えること自体が辛い人にとっても、読みやすく、心が前を向けるようになる内容です。

本書が特に優れているのは、「制度を学ぶ」ことにとどまらず、「行動に移す」ための道筋を視覚的に示してくれる点です。
情報の提供に加え、実践を後押しする設計こそが、多くの家族にとっての本当の“支え”になるのです。
読後の次のステップ
本書を読み終えたあとは、「わかった」で終わらせずに、実際に動き出すことが大切です。頭の中に描いた将来のイメージを現実に落とし込むために、何から始め、誰に相談し、どのように準備していけばよいのか――。
そのステップを具体的に示します。
step
1家族で話し合いの時間をもつ
まず取りかかるべきは、家庭内での対話です。障害のあるお子さんの将来について、どのような暮らし方を望むのか、誰がどのように関わっていけそうかを家族全員で確認します。特にきょうだいがいる場合には、今後の役割分担や思いを共有しておくことが大切です。「まだ早い」と思わず、親が元気なうちに声をかけておくことで、後のトラブルや誤解を避けることができます。
step
2相談窓口を見つけてつながる
次のステップは、信頼できる支援機関や専門家に相談することです。本書で紹介されたような「親なきあと」相談室や、地域の社会福祉協議会、障害者就業・生活支援センターなどは、その後の計画づくりをサポートしてくれます。一人で制度や手続きに向き合うのではなく、専門的な知識を持つ第三者とつながることで、より現実的な計画が立てやすくなります。
step
3必要な書類を準備・作成する
話し合いや相談の結果をふまえて、実際の準備に移ります。遺言書の作成、障害者扶養共済制度の加入、信託契約の検討、成年後見制度の申し立て準備など、書類作成は避けて通れません。それぞれに法律的な形式や注意点があるため、行政書士や弁護士に相談するのも有効です。「書くこと」が未来の安心を築く大きな一歩になります。
step
4子どもの「生活のしおり」を作る
将来、親以外の支援者が子どもの生活を支えることを想定して、「生活のしおり(トリセツ)」を用意しておくと安心です。健康状態や日常生活の工夫、本人の好き嫌いや性格など、文字にして伝えておくことで、支援の質が格段に上がります。施設や福祉職員に引き継ぐ際にも、大きな助けになるツールです。

制度の理解だけでは備えになりません。読後に重要なのは、「誰と、何を、いつまでにやるか」を具体的に可視化し、少しずつ行動に移すこと。
未来を守る準備は、思い立ったその日から始めることができます。
総括
『まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活』は、ただの制度解説書ではありません。これは、不安を抱える親や家族が、自分自身の手で将来の安心をつくり出すための「行動の道しるべ」となる一冊です。読みやすさを徹底的に追求しながら、内容は高度で実用的。まんがと図解という手法により、情報へのハードルを限りなく下げながらも、専門性を損なうことなく構成されている点が非常に特徴的です。
本書が扱うテーマは、制度やお金にとどまりません。親なきあとを見据えた住まいや後見制度の選択、きょうだいや支援者との関係づくりなど、多角的な視点から障害のある家族を取り巻く現実に向き合っています。だからこそ、読者は単に「知識を得る」だけでなく、「今後どう生きるか」「どう支えるか」といった人生設計の視座を得ることができるのです。
また、著者の渡部伸氏が「親なきあと」相談室の代表として、多くの家庭に寄り添ってきた経験が背景にあるため、内容は常に実践的でリアルです。現場で繰り返し問われてきた悩みや相談が反映されており、机上の理論ではなく、まさに「生活の中で使える知識」が詰まっています。

本書は、子どもの未来に対して不安を抱える親御さん、高齢の親に代わって責任を感じている兄弟姉妹、支援者、そして制度にまだ詳しくない初学者に至るまで、広い読者層に対して等しく価値を提供しています。
読了後には、行動の優先順位が明確になり、今からできる備えを着実にスタートできるという点で、まさに人生の「地図」となるような存在です。
障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめ書籍

障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめの本!人気ランキング
- 障害者の親亡き後プランパーフェクトガイド
- 障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて 第2版
- 改訂新版 障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本
- 障がいのある子とその親のための「親亡きあと」対策
- 障害のある子が安心して暮らすために
- 一生涯にわたる安心を! 障害のある子が受けられる支援のすべて
- まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活
- ダウン症の子をもつ税理士が書いた 障がいのある子の「親なきあと」対策

