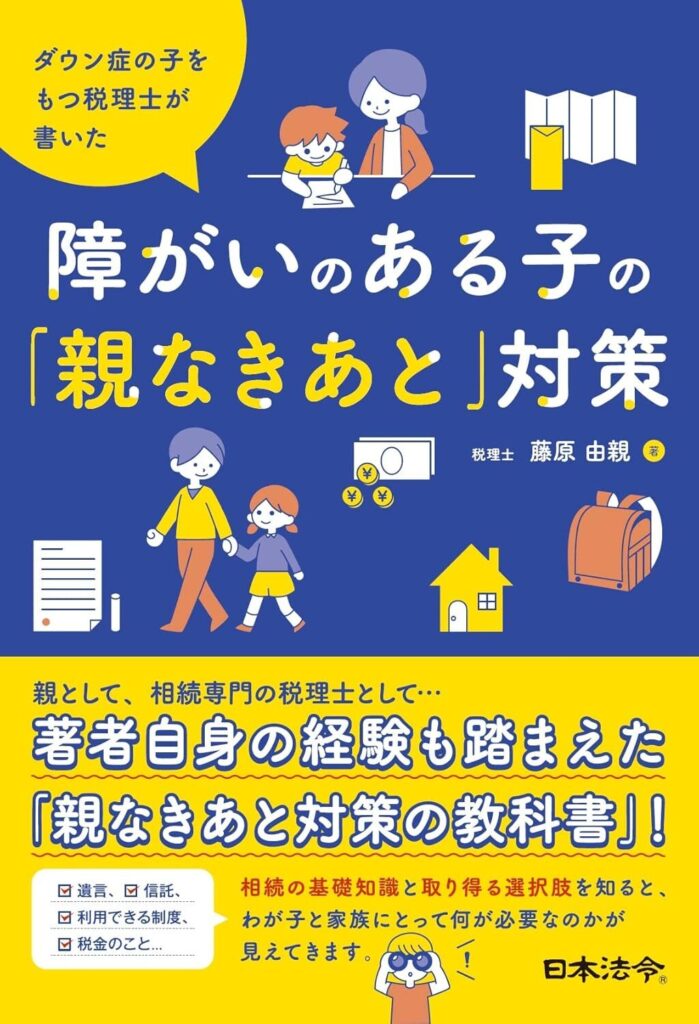
障がいのある子どもの将来を思うとき、「自分がいなくなったあと、この子はどうやって生きていくのだろう」と不安になる親御さんは少なくありません。社会の支援制度や法律が整いつつある今でも、現実的な準備ができていない家庭は多く、「何から始めればいいのか分からない」と悩む声も根強くあります。

そんな声に応えるのが本書『ダウン症の子をもつ税理士が書いた 障がいのある子の「親なきあと」対策』です。
著者自身も障がいのある子の親であり、相続専門の税理士として2,000件以上の相談に対応してきた実績を持つ人物。
自身の経験と専門知識を融合させながら、「親が元気なうちにやっておくべきこと」を、具体的かつわかりやすく提示してくれます。
遺言や信託といった制度の違いから、成年後見制度や税制優遇のポイント、さらには子どもの年齢ごとに整理された実行プランまで、網羅的かつ実用的に解説。
家族の将来設計に悩むすべての親にとって、“第一歩”を踏み出すための心強いガイドブックです。

合わせて読みたい記事
-

-
障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年版】
障害のある子どもを育てている親御さんへ——日々の子育ての中で、こんなふうに感じたことはありませんか?「子どもの気持ちがうまくわからない」「どうサポートすればいいのかわからない」「このままでいいのかな… ...
続きを見る
書籍『ダウン症の子をもつ税理士が書いた 障がいのある子の「親なきあと」対策』の書評

「親なきあと」。この言葉には、障がいのある子を育てる家庭にとって、非常に大きな不安と責任が込められています。将来、自分たち親が亡くなった後、子どもはどうやって暮らしていけるのか。金銭管理は?福祉サービスは?支援者は?誰もが一度は考えるものの、「何から手をつければいいのか分からない」という声も多いのが現実です。
そんな切実な問題に、当事者であり、かつ相続と税務の専門家でもある著者が、具体的な制度や準備の方法を一冊にまとめてくれたのが本書です。以下の4つの視点から、その価値をひもといていきます。以下の4つの視点から、その価値をひもといていきます。
- 著者:藤原 由親のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
制度の知識と、親としての経験。この2つを併せ持つ著者だからこそ書けた、実践的で信頼できる「親なきあと」対策書の魅力を、順を追ってお伝えしていきます。
藤原 由親のプロフィール
藤原由親さんは、大阪に拠点を置く税理士法人アクセスの代表社員であり、長年にわたって相続や事業承継を中心に活動してきた税理士です。これまでに2,000件以上の相続相談、300件以上の相続税申告に関わってきた経験を持ち、税務の現場を知り尽くした実務家といえます。
それだけではなく、藤原さんは二女がダウン症である父親でもあり、障がいのある子を持つ親としての立場からも「親なきあと」の問題に深く向き合っています。制度の専門家であると同時に当事者でもあるという、極めて貴重な視点が本書の内容にも色濃く反映されています。
また、一般社団法人「親なきあと相談室 関西ネットワーク」の代表理事として、講演会やセミナーでの啓発活動にも力を入れており、専門知識と現実の家庭事情の橋渡し役として全国の障がい児家庭から信頼を集めています。

本書の要約
この本は、障がいのある子を持つ親が「親なきあと」に備えるための実践的な知識をまとめた一冊です。遺言や成年後見、信託、相続税といった制度に加え、障害者扶養共済制度や生命保険などの利用可能な支援策まで、幅広い分野を扱っています。
ただし、単なる制度紹介にとどまらず、「どうしてその制度が必要なのか」「どんな家庭に向いているのか」「導入するにはどんな準備がいるのか」といった、実務に役立つ視点が常に意識されています。そのため、知識ゼロの初心者であっても、読み進めるうちに自分たちのケースに当てはめて考えることができます。
また本書では、子どもの年齢や家庭の状況に合わせて「やっておくべきこと」が時系列で整理されており、今から何に取り組むべきかが自然と明確になります。法律書のように難しくなく、実用書のように行動へつながる設計がなされている点が、本書の非常に大きな魅力です。

本書の目的
本書の根本にあるのは、「備えは親が元気なうちに始めないと手遅れになる」という危機意識です。多くの人は「いつか考えないといけない」と思いながらも、具体的な行動には移せていません。しかし著者は、遺言の作成や信託の設定、任意後見契約など、親に判断能力があるうちにしかできない対策が多いことを繰り返し強調します。
この本が目指しているのは、知識を増やすことではなく、具体的な行動につなげることです。読者が「自分の家庭でも準備を始めよう」と思えるように、あらゆる情報が実例やライフステージ別の提案とともに紹介されています。たとえば、「障がいのある子が15歳になったら印鑑登録を」といった具体的な指針は、すぐに動き出すきっかけになります。
また、親の年齢や子どもの成長に合わせたタイミングで必要な対応が変わることも丁寧に説明されています。「今やるべきこと」「あとでやるべきこと」が明確になるため、漠然とした不安が、現実的な課題として整理されていきます。

人気の理由と魅力
本書が多くの読者に支持されているのは、ただ制度を説明しているだけでなく、“誰のための本か”という視点が明確だからです。著者自身が障がいのある子の親であるからこそ、読者が抱えるであろう感情、不安、疑問を言葉にして先回りしてくれており、それが強い共感と信頼を生んでいます。
さらに、法的な内容でありながら、文章は平易で、図表やイラストも多く、法律書にありがちな堅さや専門用語の壁がありません。読み進める中で“つまずく”箇所がないように、構成や言葉選びに細やかな配慮がなされています。
また、一般的な相続・信託の解説本とは異なり、本書は「親なきあと」の現実に即して構成されているため、読者が自然と「我が家の場合はどうだろう」と考えることができます。読後には「やるべきことリスト」が自然と頭に浮かぶような仕上がりで、「読んだだけ」で終わらない実践的な一冊になっています。
口コミでも、「夫婦でこの本を共有した」「子どもの将来について話し合うきっかけになった」「信託や後見制度について初めて分かりやすく説明された」といった声が多く見られます。つまり、制度理解を超えて、家族の行動変化につながっているという点が、多くの読者にとっての真の魅力なのです。

本の内容(目次)

本書は、障がいのある子を育てる家庭にとって重要な「親なきあと」の課題を、体系的かつ実践的に解説した構成になっています。章ごとに学ぶべきテーマが明確に分かれており、順を追って読み進めることで、自然と自分に必要な知識と行動が見えてきます。
具体的には、以下の6章で構成されています。
- 序章 私が「親なきあと」に取り組む理由
- 第1章 「親なきあと」のために知っておきたい相続の基礎知識
- 第2章 「親なきあと」対策の選択肢
- 第3章 「親なきあと」の相続税
- 第4章 「親なきあと」対策のポイント
- 第5章 タイムリミットで考える 子のライフステージ別やっておくべき「親なきあと」対策
各章は、それぞれの段階で直面する課題や制度を詳しく取り上げています。特に、読者が「いつ・何を・どのように」備えるべきかを考える上で、大きな指針となる内容が詰まっています。
以下より、各章の要点と特徴を詳しく見ていきましょう。
序章 私が「親なきあと」に取り組む理由
本書の冒頭では、著者自身がなぜ「親なきあと」の問題に真剣に取り組むようになったのか、その原点が語られています。著者は相続を専門とする税理士であると同時に、障がいのある子の父親でもあります。その両方の立場から、「知識としての制度」ではなく「生活に直結する課題」として、本書のテーマを捉えています。
世の中には「親なきあと」という言葉が徐々に浸透してきているものの、実際に行動に移せている家庭はまだ少ないと著者は述べます。なぜなら、多くの人は制度を知らなかったり、何から始めればいいか分からずに時間だけが過ぎていくからです。著者は、相談を通じて見えてきた「知識の格差」や「情報の断片性」に危機感を持ち、それを埋める手段としてこの本を書き上げました。
序章ではまた、「親なきあと」が単に“親の死後”だけを指すのではないことも明確にされています。たとえば、親が認知症を発症したり、急病や事故で意思表示が困難になるケースも「親なきあと」に含まれます。このように、“ある日突然始まるかもしれない”という現実感をもって、今こそ備えを始めるべきだというメッセージが、真摯に伝わってきます。

第1章 「親なきあと」のために知っておきたい相続の基礎知識
この章では、相続に関する最も基本的な仕組みが解説されています。とはいえ、相続と一口に言っても、その中身は相続人の範囲、財産の分割方法、税金の扱いなど多岐にわたります。ここでは特に、障がいのある子が家族にいる場合に注意すべき点が詳しく取り上げられています。
例えば、遺産分割の場面では、障がいのある子が判断能力を持たないとされる場合、家庭裁判所によって後見人の選任が必要になることがあります。つまり、他の兄弟と話し合いで決めようとしても、法的な手続きなしでは進められないというわけです。
また、障がいのある子が不動産を相続した場合、その不動産を売却や賃貸に出すにも後見人の同意や家庭裁判所の許可が必要になります。これは、善意のつもりでも、子どもの財産が不利益を被らないよう、法律で厳しく守られているからです。
遺留分や代襲相続など、一般の人には耳慣れない法律用語も登場しますが、著者はそれぞれを生活の場面に引き寄せて、具体的なケースを通じて解説しています。法定相続分の割合なども図表を用いて示されており、読んで理解しやすい工夫がされています。

第2章 「親なきあと」対策の選択肢
続く第2章では、親が元気なうちに取れる具体的な備えの選択肢が紹介されます。この章は、制度の概要を説明するだけではなく、「どの制度がどんな家庭に適しているか」という観点からも解説がなされているのが特徴です。
まず登場するのが「遺言」です。自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、それぞれのメリット・デメリットが具体的に整理されています。公正証書遺言は法的に強く、安全性が高いものの、作成には費用がかかる。一方で、自筆証書遺言は手軽ですが、書き方に不備があると無効になる可能性もあります。
成年後見制度についても、法定後見と任意後見の違いがしっかり整理されています。法定後見は裁判所の関与が強い一方で、任意後見は自分で選んだ人に将来の支援を託す制度です。親が認知症になる前に契約しておく必要があり、制度の理解とタイミングが重要になります。
さらに注目されているのが「信託制度」です。信託とは、ある人(委託者)が別の人(受託者)に財産を託し、ある目的のために運用・管理してもらう仕組みです。本書では、障がいのある子を受益者として設定することで、将来的な生活費や住まいの確保を第三者が担う仕組みが紹介されています。
この他、特定贈与信託や生命保険信託、遺贈寄付といった手段についても取り上げられ、家庭ごとの状況に応じた選択肢を検討する材料が豊富に提供されています。

第3章 「親なきあと」の相続税
この章では、障がいのある子をもつ家庭にとって、避けては通れない相続税や贈与税に関する重要な知識がまとめられています。税金の制度は一見複雑に見えますが、本章では、必要なポイントが体系立てて解説されており、「何を理解しておけば損をしないのか」がクリアに分かります。
まず、相続税法の基本的な枠組みが示され、どのようなケースで申告が必要になるか、基礎控除の考え方、申告期限、課税対象となる財産の種類などが紹介されています。その上で、障がいのある子が相続する場合に使える「相続税の障害者控除」についても詳しく触れられています。
この控除制度では、相続人が障がい者である場合、将来にわたる生活支援の必要性を考慮して、一定額の相続税が軽減されます。ただし、控除額は「85歳までの年数 × 年間控除額」によって計算されるため、障がいの程度や年齢によって適用結果が変わります。
さらに、障害者扶養共済制度や生前贈与を活用した相続税対策など、知っておくと役立つ制度も登場します。特に生前贈与に関しては、将来的な制度変更に備えた注意点がコラムとして解説されており、最新情報に敏感であることの大切さが説かれています。

第4章 「親なきあと」対策のポイント
この章では、制度の仕組みというよりも、現実の生活の中で実際に起こり得るトラブルや手続き上の壁をどう乗り越えるかという“実務的な視点”からのポイントが列挙されています。
まず、障がいのある子が相続人となる場合、遺産分割協議をするには後見人の選任が必要であるという点が示されます。これは、法的な「意思能力」がないと見なされた場合、本人が自らの意思で財産分与の同意をすることができないためです。
また、たとえ不動産を相続しても、単独で管理・売却・貸与ができないという実務的な課題があります。不動産は流動性が低く、固定資産税や維持費もかかるため、放置することでかえって家族の負担となるリスクもあるのです。
加えて、ひとりっ子の場合、相続手続きそのものを引き継ぐ人がいない、または対応できないという問題も指摘されています。最終的には、相続財産が国庫に帰属する(国のものになる)可能性まであるという厳しい現実が明らかにされています。
本章の特徴は、「制度を知ること」と「実際に困らないように準備すること」の違いを明確に示している点にあります。問題が起こってからではなく、起こる前に“具体的な準備”を進める重要性を痛感させられます。

第5章 タイムリミットで考える 子のライフステージ別やっておくべき「親なきあと」対策
本書の締めくくりとなる第5章は、これまでの知識を「いつ・何をすべきか」という時間軸で整理してくれるパートです。子どもの成長段階ごとにやるべき対策が具体的に示されており、読者は自分の子どもの年齢や状況に応じて、必要な行動がすぐに把握できます。
たとえば、「障がいのある子が生まれたら、まず親の遺言を作成すること」や、「15歳になったら印鑑登録を行う」「成年になるまでに任意後見契約を検討する」といった内容が時系列で並び、まるで“行動チェックリスト”のようです。
さらに、生活環境が決まるタイミングでのマネープランニングや、後見人の選任など、実生活に直結するアドバイスも多数掲載されています。特に、著者自身が実践している対策を紹介したコラムは、リアルな事例として多くの読者の共感を呼ぶでしょう。

対象読者

『ダウン症の子をもつ税理士が書いた 障がいのある子の「親なきあと」対策』は、単なる相続や法律の知識にとどまらず、「わが子の未来を守りたい」と願う多くの人々にとって、実践的な道しるべとなる内容です。
とくに次のような立場や悩みを持つ方々にこそ、手に取っていただきたい一冊です。
- 障がいのある子を育てている親御さん
- 将来の財産管理に不安を感じる家庭
- 成年後見制度や福祉サービスに興味のある人
- 信託制度を具体的に知りたい人
- 障がい者支援に関わる専門職
それぞれの立場にとって、本書がどのように役立つのかを以下で詳しくご紹介します。
障がいのある子を育てている親御さん
最も本書の恩恵を受けるのは、障がいのある子どもを育てている親御さんです。日々の生活で精一杯な中でも、ふとした瞬間に頭をよぎるのが「この子が将来自立できないとしたら、私がいなくなった後はどうなるのか」という深刻な不安でしょう。
本書は、そんな親の胸に巣食う“ぼんやりとした不安”を、“今できる具体的な準備”へと変換するサポートをしてくれます。著者自身もダウン症の子をもつ父親として、同じ立場から語られる言葉のひとつひとつが親たちの共感を呼び、背中を押してくれるはずです。

将来の財産管理に不安を感じる家庭
障がいのある子が将来、自分自身で金銭管理をすることが難しい場合、親として最も気になるのが「財産をどう残し、どう管理させるか」という問題です。多額の預貯金や不動産を残しても、それを誰がどのように管理するのかが不明確なままでは、かえってトラブルの原因にもなりかねません。
本書では、遺言や信託、成年後見制度などを用いた財産の管理方法を具体的に紹介しています。また、制度ごとの利点・欠点だけでなく、「どのような家庭にどの制度が向いているか」という判断ポイントまで整理されており、制度の選び方にも迷いが生じにくくなっています。
さらに、家族構成や相続人の有無などによっても必要な準備は異なります。ひとりっ子である場合や、親以外に頼れる親族がいないケースにおける対応策についても言及されており、さまざまな状況に応じた対策が得られるのが本書の大きな魅力です。

成年後見制度や福祉サービスに興味のある人
福祉サービスや後見制度といった仕組みは、どこか堅苦しく難解に感じてしまうものです。とくに成年後見制度については、「いつ使うべきか」「任意後見と法定後見の違いは何か」「そもそも後見人を立てる必要があるのか」といった疑問がつきものです。
この本では、そうした制度の基本的な概要だけでなく、実際に制度を利用した家庭で起きやすいトラブルや課題も紹介されており、単なる制度の紹介にとどまらない実践的な知識が得られます。また、「後見人を立てると、かえって自由な財産管理が難しくなる」といった盲点も明かされており、制度の“良い面”と“気をつけたい面”の両方がしっかりと伝わってきます。
福祉サービスについても、国や自治体が提供する支援制度や保険商品の活用法が図解やコラム形式で丁寧に紹介されており、手続きの流れが視覚的に理解しやすくなっています。

信託制度を具体的に知りたい人
信託制度という言葉は聞いたことがあっても、「実際に使うとなるとよくわからない」という声が多いのも事実です。特に、障がいのある子の将来のために設計する信託は、感情的な要素と法的な仕組みが複雑に絡み合うため、正しく理解することが大切です。
本書では、「信託とは何か」という基礎から、家族信託・特定贈与信託・生命保険信託といった具体的な仕組み、それぞれの契約内容、関係者の役割、税務面の注意点に至るまで幅広くカバーされています。また、「信託制度と成年後見制度の違い」や、「どちらを選ぶべきか」といった実務的な比較も丁寧に整理されています。
何よりも特徴的なのは、実際に障がいのある子を育てる親の立場から、「どんなときにどの制度を使えばいいのか」という判断材料が明確に示されている点です。これにより、読者は制度の知識を“情報”としてではなく、“自分ごと”として吸収できます。

障がい者支援に関わる専門職
支援の現場に立つ福祉職、医療職、学校関係者、行政担当者、法律専門職にとっても、本書は実践的な知識源として役立ちます。親から「将来が不安で…」と相談を受けた際、制度名だけでなく「その制度をどう活かせるか」まで説明できるかどうかは、支援者の力量にも関わってきます。
この本では、制度の説明だけでなく、家庭の状況に応じた選択の考え方や、誤解されやすいポイントの解説も豊富です。専門職が自分の領域を超えて“広い支援”ができるようになる一助として、手元に置いておきたい一冊といえるでしょう。

本の感想・レビュー

安心感をくれる一冊
正直に言えば、私はずっと「親なきあと」のことを漠然とした不安として感じてきました。漠然、というのは「何が分からないかも分からない」状態ということです。何から調べればいいのか、どこに相談に行けばいいのかも知らず、ただ心の奥に暗い塊のように不安だけがあったのです。
この本を手に取ったとき、まず驚いたのは、その暗い塊に明かりをともすように「できること」「選べること」が明確に示されていた点です。遺言、成年後見、信託、贈与、保険、制度利用……それぞれがどう違い、どのように使えるのかを、現実の生活に根ざした形で説明してくれます。
しかも、単なる制度紹介ではありません。著者自身が障がいのある子の父親であり、税理士としても2,000件以上の相続相談を受けてきた経験をもとに、「親なきあと」に本当に必要な対策を、読者が行動に移せるレベルで書いてくれています。読了後は、不安が霧のように少しずつ晴れていくような感覚がありました。「今ならまだ間に合う」という、前向きな気持ちをもらえる一冊でした。
専門知識も平易な言葉で説明
私は普段から難しい制度や法律にアレルギーがあるタイプで、「相続」や「後見」なんて言葉が出ただけで気後れしてしまうのですが、この本だけはまったく違いました。専門的な話を扱っているにもかかわらず、どこまでも読みやすいのです。
たとえば、法定相続人の種類についても、単に制度名を並べるのではなく、「親なきあと」の現実の中でどう作用するのかという視点で語られていました。「障がいのある子の場合には、こういう点で注意が必要です」といった説明が随所に出てきて、「これは私のために書かれているんだ」と思えるくらいに具体的です。
図解も非常に効果的で、制度の関係性やフローが一目で分かるようになっています。さらに、ページの節々にあるコラムがまた絶妙で、制度の背景や考え方が自然に理解できるようになっています。知識ゼロからでも十分に読みこなせる構成で、むしろ「知らなかったこと」を知ることが楽しくなるような本でした。
「親なきあと」が“現実問題”として迫ってくる構成
読んでいて、何度も手が止まりました。というのも、内容が「いつか」の話ではなく、「いま」向き合わなければならない現実として迫ってくるからです。私自身、まだ子どもが10代ということもあり、「老後の心配なんてまだ先」と思っていた部分があったのですが、この本はその意識を根本から変えてくれました。
とくに序章に書かれていた、「何もしなかったら」を想像するという話が印象に残っています。親が突然入院したら?認知症になったら?家の手続きは?お金の管理は?そう考えると、確かに「親なきあと」は“死後”ではなく、“明日かもしれない”ことだと痛感しました。
そして、「早く始めるほど選択肢が広がる」という言葉が何度も出てきます。これは、読者を煽るための言葉ではなく、著者自身が当事者として実感してきた真理なのだと思います。実際、ライフステージ別の章では、子どもが何歳のときに何を考えておけば良いのかが具体的に書かれていて、自分のスケジュール帳に「親なきあと計画」の欄を作るきっかけになりました。
著者自身が当事者という説得力
この本が、ほかの制度解説本とはまったく違うと感じたのは、著者が「障がいのある子の父親」でもあるという点です。これは大きいです。たとえどんなに専門知識があっても、当事者の気持ちや日々の不安を知らなければ、本当の意味で寄り添うアドバイスにはなりません。
藤原さんは、税理士としての理論と、親としての感情、その両方を兼ね備えたまさに“当事者専門家”。その姿勢は、言葉の節々ににじみ出ています。「私も迷いながら試行錯誤している」という正直な告白に、どれだけ救われたことか。
また、読者に語りかける語り口も決して上からではなく、「一緒に考えていきましょう」という優しさと温かさに満ちていました。同じ立場の人にしか分からない痛みや悩みを理解しているからこそ、信頼して読み進めることができたのだと思います。
ライフステージ別の提案が実用的
この本のなかでも特に感銘を受けたのが、第5章の「ライフステージ別の『親なきあと』対策」です。子どもの成長に合わせて、親が取るべき行動が整理されていて、自分たちが今どの段階にいるのか、そしてこれから何を考えるべきかがはっきり見えてきました。
情報を「制度別」に並べるだけでは、初心者の私にはイメージが湧きづらかったと思います。でも、この章のおかげで、「うちはそろそろ印鑑登録のタイミング」「親権を使った任意後見の検討もしておくべきかも」と、実際の行動に繋げやすくなったのです。
しかも、ただタイミングを示すだけでなく、なぜその時期に必要なのか、どんな選択肢があるのかが丁寧に説明されています。障がいのある子を持つ親にとって、「今やるべきこと」を整理するのは思っている以上に難しい作業ですが、この本があったからこそ、焦らず段取りを組むことができました。
遺言や信託の違いが一目瞭然
私がこの本に感動した理由の一つは、遺言や信託といった法律・制度についての違いが、非常に分かりやすく整理されていた点です。今まで、そういった言葉を見聞きする機会はあっても、実際に何がどう違って、どの場面で使うのかまでは理解できていませんでした。
本書では、それぞれの制度のしくみや使い方、そして障がいのある子どもが対象となる場合に注意すべき点が丁寧に説明されています。特に信託に関する部分は、具体的な流れや登場人物(委託者・受託者・受益者など)の関係性が整理されていて、初心者の私でもすんなり理解することができました。
また、成年後見制度との違いや、どちらを選ぶべきかの判断材料もあり、「自分の家庭に適した方法を考えるための基礎知識」がしっかり身についた実感があります。ここまでクリアに制度の違いを教えてくれる本は、なかなかありません。
父親にも手に取ってほしいというメッセージ性
私はふだん子育てのことは妻に任せがちでした。「親なきあと」の話も、妻が講座に出かけて勉強しているのを横目で見ていたくらいでした。でもこの本を読んで、強い衝撃を受けたのです。
著者が、同じ障がいのある子どもを育てる「お父さん」として語りかけてくれていたからです。「母親任せにせず、お父さん自身が考えてほしい」というメッセージが、ぐっと胸に響きました。そこには責めるようなトーンはなく、「一緒に向き合おう」という力強くも温かい気持ちが感じられました。
特に印象的だったのは、セミナーに来るのは圧倒的に母親が多く、父親がまだ当事者意識を持てていないケースが多いという話。私自身、その典型だったと思います。この本を読んでからは、妻と一緒に「今後どうしていくか」を考えるようになりました。これまで無関心だったことを恥じる気持ちとともに、これからちゃんと向き合っていこうという覚悟をもらいました。
老後の備えにも応用可能
私は50代に差し掛かり、障がいのある子どもの将来だけでなく、自分たち夫婦の老後も意識するようになってきました。この本を読んで感じたのは、「親なきあと」対策は、実は親自身の老後準備にも大きく役立つということです。
たとえば、遺言の作成や信託の設計は、親自身が元気なうちに考えておくべきという点で、一般的なエンディングノートや終活と共通する部分があります。著者も繰り返し「元気なうちに」「気力があるうちに」と語っており、その言葉が心に刺さりました。
さらに、障害者控除や贈与税に関する解説は、我が家のように高齢の親が財産を持つ家庭にも重要な話です。親の資産をどう残すか、どう管理をバトンタッチするかという点で、子の支援と親の終活は表裏一体であると気づかされました。この本を読み進めるうちに、私自身の人生設計にも自然と目を向けるようになりました。
まとめ

本書は、障がいのある子の将来に備えるために「今できること」を一冊で学べる、信頼性と実用性を兼ね備えたガイドブックです。読み終えたとき、漠然とした不安が行動の力に変わるはずです。
このセクションでは、読者が得られるメリット、読了後に踏み出すべき次のステップ、そして総括として本書の価値を改めて確認していきます。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれの視点から、あらためて本書の魅力を振り返ってみましょう。
この本を読んで得られるメリット
本書を通じて得られる主なメリットを具体的にご紹介します。
法制度に対する“基礎理解”が身につく
最も大きなメリットの一つは、これまで漠然としていた「相続」「遺言」「後見」「信託」といった法制度について、体系的に理解できる点です。本書は、専門的な用語が多いこれらのテーマを、事例や家族の状況に即してかみ砕いて説明しています。たとえば、成年後見制度の法定後見と任意後見の違い、信託の仕組みや役割の明確な整理など、法律初心者でも確実に理解できるよう配慮された構成になっています。
また、各制度がなぜ存在するのかという「背景」や「目的」まで踏み込んで説明されているため、単なる知識にとどまらず、判断に役立つ“意味のある理解”へと昇華されます。
子どものライフステージに応じた“行動計画”が立てられる
本書のもう一つの特徴は、子どもの成長段階に応じて、親が何をすべきかが明確に示されていることです。年齢ごとに対応する法的な手続きや検討すべき制度が時系列で整理されており、今どこに立っていて、どこを目指せばよいのかが自然と見えてきます。
たとえば、子が15歳になったら印鑑登録、成年前には任意後見の検討、親の高齢化前に信託の設計――というように、「今できる備え」と「将来の備え」を同時に考える視点を養うことができます。
財産の管理・承継について“判断基準”が持てるようになる
障がいのある子がいる家庭では、「お金をどう残すか」「誰が管理するか」といった課題がつねに付きまといます。本書では、特定贈与信託や生命保険信託など、財産管理の実例を豊富に紹介し、それぞれの制度の使いどころや留意点まで詳細に解説されています。
ただ制度を列挙するのではなく、「どの家庭に向いているのか」「どんな家庭では不向きか」まで踏み込んでおり、読者は制度の“選び方”という観点をもつことができます。その結果、「我が家に必要なのはどの制度か」「いつ導入すべきか」といった判断を自ら下せるようになるのです。
「親としての責任と安心感」が行動を後押ししてくれる
この本を読み終えるころには、多くの親が「自分にもできる」という実感と、「今やらなければ」という前向きな責任感を持つようになります。それは著者自身が障がいのある子の父親であり、読者と同じ立場で語りかけてくれているからです。
読み進める中で、「制度を学ぶこと」が単なる法律知識ではなく、「子どもへの愛情を形にすること」だと感じられる構成になっています。その温かさと実用性が、読者の背中を確かに押してくれます。

読後の次のステップ
本書を読み終えたあと、得られた知識や気づきを“行動”へとつなげることが何より大切です。制度の理解だけでは、障がいのある子の将来を守る力にはなりません。「何から始めるべきか」「どのように進めるべきか」といった現実的なアクションを、家庭の状況に合わせて組み立てることが必要です。
以下では、読後に取るべき具体的なステップをご紹介します。
step
1家族構成と財産状況を整理する
最初に取りかかりたいのは、現在の家庭の状況を正しく把握することです。誰が財産を相続するのか、どのような資産があり、誰にどのように引き継ぐ必要があるのか。それらを一度書き出してみることで、目に見えなかった課題やリスクが明確になります。たとえば、預貯金だけでなく不動産の有無、保険契約、負債なども含めて整理し、「見える化」することが重要です。
これにより、信託や遺言の必要性の有無、成年後見制度の活用可能性など、今後の方向性がより具体的になります。
step
2利用すべき制度の選択肢を絞り込む
家庭の状況が明確になったら、次は「どの制度を使うか」の検討に入ります。本書では遺言、後見、信託など多くの制度が紹介されていますが、すべてを使う必要はありません。大切なのは、「自分たちの家庭に合った制度」を選ぶことです。
たとえば、障がいのある子に兄弟姉妹がいない場合は、特定贈与信託や信託型の生命保険が向いているかもしれません。一方、家族の中に財産管理を担える人がいる場合は、任意後見や家族信託も有力な選択肢になります。制度選択のポイントは「継続的に運用できるか」「費用が現実的か」「子の状況に合っているか」です。専門家のアドバイスを受けながら、柔軟に選ぶことが必要です。
step
3相談先を決め、実行計画を立てる
対策を行動に移すには、法律や税の専門家と連携することが不可欠です。たとえば、相続や信託の手続きは税理士や司法書士、弁護士との連携が必要となる場面が多く、事前の相談で方向性を固めておくと安心です。できれば、地域の社会福祉士や行政書士、障がい福祉の支援者とつながっておくと、制度利用のサポートもスムーズに進みます。
相談先が決まったら、実際のスケジュールを立てて一歩ずつ進めましょう。遺言の作成、公正証書の準備、後見制度の申請手続きなど、項目ごとに期限を決めて取り組むことで、先延ばしにならずに着実に前進できます。

総括
障がいのある子どもを育てる家庭にとって、「親なきあと」という言葉は、どこか胸の奥にずっと引っかかっている重いテーマです。しかし日々の生活に追われ、その不安にしっかりと向き合う余裕がないというのが、多くのご家庭の現実ではないでしょうか。
本書『ダウン症の子をもつ税理士が書いた 障がいのある子の「親なきあと」対策』は、まさにそんな“先送りにされがちな不安”を、明るい見通しへと変えていくための一冊です。単なる制度解説にとどまらず、「親としての想い」と「専門職としての知見」を融合させ、読者に“動く理由”と“動ける知識”を与えてくれます。
この本の特筆すべき点は、制度に対する網羅的な説明と、それぞれの制度を家庭の状況にどう当てはめていくかという実践的な視点が、非常に丁寧に組み立てられていることです。たとえば遺言や信託、成年後見制度など、聞き慣れない言葉も多い中で、それらがなぜ必要で、どのタイミングで検討すべきかが、子どものライフステージに沿って順序立てて紹介されています。まさに、“読むことで不安が構造化され、やるべきことが見えてくる”構成になっているのです。
さらに、著者自身が障がいのある子の父親であるという点は、何よりも大きな信頼感と説得力をもたらします。単に制度の説明をするだけではなく、「お父さんたちへ届けたい」という率直なメッセージを交えながら、読者に語りかけてくれる温かさがあります。「母親任せにしないで、父親も当事者として関わってほしい」という想いは、多くの家族の現実に響くことでしょう。

今の生活を大切にしながら、未来に向けた小さな行動を一つずつ積み重ねる。
その出発点として、本書は非常に信頼できる案内人となってくれるはずです。
障がいのある子どもの人生を、親としてどう支えていくか。
その答えを一緒に探し、実践へ導いてくれる本書は、すべての家族にとっての“備えの教科書”と呼ぶにふさわしい一冊です。
障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめ書籍

障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめの本!人気ランキング
- 障害者の親亡き後プランパーフェクトガイド
- 障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて 第2版
- 改訂新版 障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本
- 障がいのある子とその親のための「親亡きあと」対策
- 障害のある子が安心して暮らすために
- 一生涯にわたる安心を! 障害のある子が受けられる支援のすべて
- まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活
- ダウン症の子をもつ税理士が書いた 障がいのある子の「親なきあと」対策

