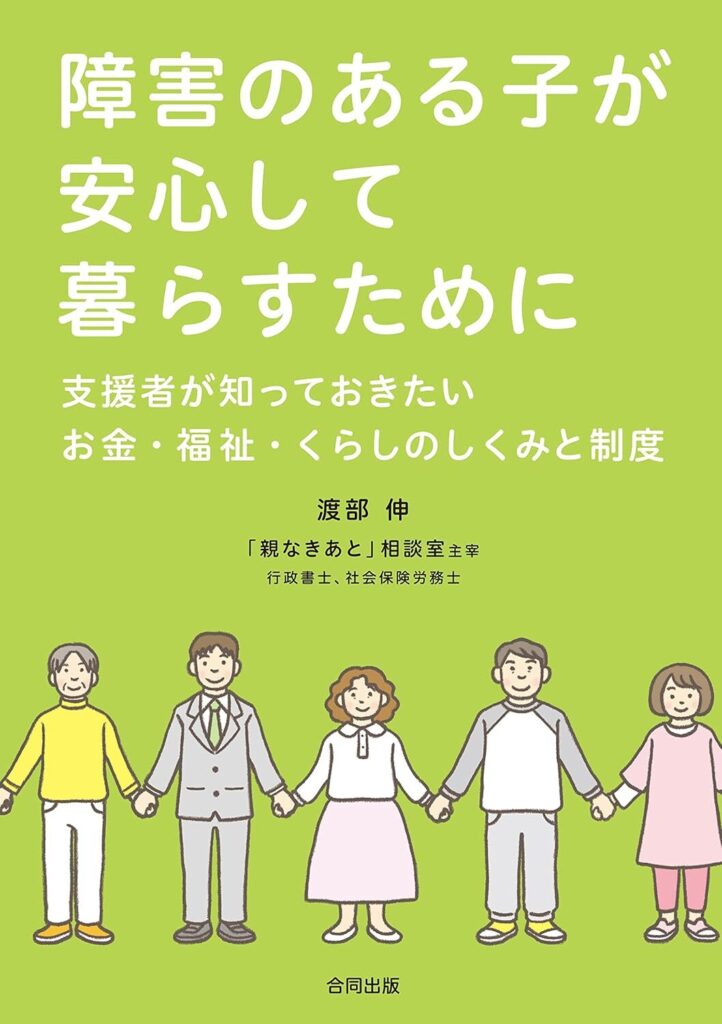
障害のある子どもを持つ親御さんにとって、「親なきあと」は決して他人事ではありません。自分たちがいなくなった後、わが子の生活はどうなるのか――。本書『障害のある子が安心して暮らすために』は、そうした親御さんの漠然とした不安に寄り添い、制度やお金、支援の選び方まで、実践的な解決策を具体的に示してくれる一冊です。

著者は、自身も障害のある子を育てる親であり、行政書士・社会保険労務士の専門家でもある渡部伸氏。
だからこそ、親の目線と専門家の知識、その両方で「何から始めたらいいのか」「どこに相談すればいいのか」をわかりやすく導いてくれます。
相談室で実際に寄せられた家族の声や、ケーススタディを豊富に掲載している本書は、家族だけでなく支援者にとっても心強いパートナーになることでしょう。
親御さん、支援者、そして地域の方々が一緒になって「親なきあと」を考えるきっかけとして、ぜひ手に取ってみてください。

合わせて読みたい記事
-

-
障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年版】
障害のある子どもを育てている親御さんへ——日々の子育ての中で、こんなふうに感じたことはありませんか?「子どもの気持ちがうまくわからない」「どうサポートすればいいのかわからない」「このままでいいのかな… ...
続きを見る
書籍『障害のある子が安心して暮らすために』の書評

障害のある子どもを持つ家族にとって、「親なきあと」は一生をかけて考え続けなければならないテーマです。本書『障害のある子が安心して暮らすために』は、そうした家族や支援者が抱える不安や悩みに応えるため、著者自身の体験と専門知識を織り交ぜながら、一歩踏み出すためのヒントと制度の解説を丁寧にまとめた一冊です。
以下の観点から本書の魅力と実用性を深掘りしていきます。
- 著者:渡部伸のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれ詳しく見ていきましょう。
著者:渡部伸のプロフィール
著者の渡部伸(わたなべ しん)氏は、1961年に福島県会津若松市で生まれました。慶應義塾大学法学部を卒業後、出版社勤務を経て独立し、行政書士、社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能士の資格を取得しています。自身の娘に知的障害があることから、当事者として「親なきあと」問題の現実を痛感し、2014年に「親なきあと」相談室を立ち上げました。そこでは、障害者本人とその家族が抱える将来の不安や悩みを専門家の立場からサポートしています。
さらに、渡部氏は世田谷区手をつなぐ親の会会長としても活動しており、障害児者の親同士のネットワーク作りや情報共有にも尽力しています。その実績から、多くのメディアや講演会で「親なきあと」問題の啓発を行い、全国的に活躍されています。

障害のある子どもの将来を考えるとき、親も支援者も「誰に相談すればいいんだろう」と悩みます。
渡部さん自身が当事者であり、プロの専門家でもあることが、本書の信頼感につながっています。
本書の要約
本書『障害のある子が安心して暮らすために』は、障害のある子どもを持つ家族が直面する「親なきあと」の課題を、家族自身と支援者が一緒に考え、具体的な準備を進めるためのガイドブックです。障害のある子どもを持つ親が抱える不安として、「自分たちがいなくなったら、誰が子どもの面倒を見てくれるのか」「経済的にどうやって生活を支えていけるのか」など、将来の生活設計に関する悩みは尽きません。
この本では、そうした不安を少しでも軽くするため、福祉サービスや成年後見制度、金銭管理の方法、地域とのつながりの作り方まで幅広く解説しています。特に特徴的なのは、実際に相談室で受けた家族の声や悩みをケーススタディとして紹介し、その問題に対してどのように制度を使って支援ができるのかを、具体的に示している点です。たとえば、学齢期の子どもを持つ親、高齢の親、きょうだいが抱える問題など、家族のライフステージに合わせた悩みに沿って対策が提案されています。
また、障害者の支援に関わる専門職や支援者が、家族からの相談を受けたときにどう答えればよいのか、どの制度をどのタイミングで提案すれば家族の不安が軽減できるのかなど、専門家としてのアドバイスも数多く盛り込まれています。そのため、家族だけでなく、支援者にとっても学びが多く、役立つ内容になっています。

本書の目的
この本の目的は、障害のある子どもを持つ家族が「親なきあと」に向けての備えを「何から始めるべきか」「どの制度をどのように活用すればよいのか」という行動レベルで具体的に示すことにあります。漠然とした不安を抱え続けるのではなく、制度や支援をうまく活用して一歩ずつ準備を進めるためのきっかけ作りを目指しているのです。
親が元気なうちにできること、そしていざという時に備えて準備しておくべきことを、著者の実体験と専門家としての知識の両方からアドバイスしてくれるのが、この本の大きな特長です。さらに、「親なきあと」は家族だけで抱え込むものではなく、地域の支援ネットワークや専門家のサポートを得ながら進めていくべきだという視点が随所にちりばめられています。
このように、本書は単なる知識の詰め込みではなく、実際に家族と支援者が一緒に考え、地域全体で「親なきあと」を支える仕組みづくりまでを提案しているのが魅力です。

人気の理由と魅力
この本が多くの家族や支援者に選ばれる理由は、著者が単なる専門家として制度を語るのではなく、自身も障害のある子どもの親として家族の悩みに真正面から向き合い、心から寄り添ってくれる姿勢にあります。そのため、読者は「この人なら信頼できる」と感じられるのです。
また、制度や法律の話になるとどうしても難しく感じる人が多いですが、本書は専門用語をわかりやすくかみくだいて説明し、具体的に「どのタイミングでどこに相談すればいいのか」という実践的なヒントが満載です。実際に相談室で受けた相談事例が豊富に掲載されており、読者は「自分もこういう状況になるかもしれない」と身近に感じながら読み進めることができます。
支援者の立場からも、「親なきあと」の課題にどのように寄り添い、どのように制度を紹介すればよいのかが明確にわかる構成になっていて、実務に直結するアドバイスが得られます。さらに、家族だけでなく地域や支援者全体で障害のある子どもの未来を支えていくべきだというメッセージが、読者に勇気を与えてくれる点も大きな魅力です。

本の内容(目次)

この本は、障害のある子どもを持つ家族が「親なきあと」に備えるために必要な知識と行動を、初心者でも分かりやすく体系的に学べるよう、全4章で構成されています。それぞれの章は、障害のある子どもの将来の生活を支えるために、支援者や家族が知っておきたいポイントが丁寧にまとめられています。
以下の4つの章立てで解説されています。
- 第1章 相談室の活動について
- 第2章 家族からの相談事例とアドバイス
- 第3章 「親なきあと」を支える制度としくみ
- 第4章 「親なきあと」相談室のこれから
それぞれの章の内容を分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
第1章 相談室の活動について
この章では、障害のある子どもを持つ家族が「親なきあと」に抱える不安に対して、どのように相談室が向き合い、支援しているかが解説されています。まず、親がいなくなった後に子どもの生活を誰がどう支えるのかという根本的な問題が、多くの家庭にとって共通の、そして大きな悩みであることが示されています。
特に、「親なきあと」は単に制度やお金の問題だけではなく、家族の心の整理や支援者の接し方など、幅広い課題が含まれていることが強調されます。例えば、相談のハードルを低くするためには「どんな小さなことでも話してOK」という安心感を作ることが大切であり、相談者が自分のペースで話せる場を整えることが重要です。また、親御さんの「身の上話」も含めて話題を受け止める姿勢や、制度説明だけでなく、目の前の人にとって本当に必要かどうかを一緒に考えることが求められます。
成年後見制度の使い方やきょうだいの気持ちへの配慮、地域を巻き込んだ支援の大切さなども丁寧に解説されており、単なる窓口業務ではなく「家族の安心をつくる場」としての相談室の役割が伝わってきます。

親なきあとの問題は「制度を教えて終わり」ではないということがよく分かりますね。
家族の心に寄り添う相談室の姿勢が印象的です。
第2章 家族からの相談事例とアドバイス
この章では、実際に家族が相談室に寄せた声や悩みを事例として取り上げ、それぞれのケースに対して著者が具体的なアドバイスを行っています。たとえば、まだ子どもが学齢期で目の前の生活で手一杯の家庭、親が高齢化し備えを急がなければならない家庭、本人の一人暮らしを考えたいけど地域とのつながりが不安なケースなど、さまざまな状況が網羅されています。
それぞれの事例は「Q&A形式」で紹介されており、「どんな準備を始めればいいの?」「経済的にどうすればいいの?」「支援のつながりはどう作ればいいの?」といった疑問に対して、制度の活用方法や家族間のコミュニケーション、支援者との関わり方まで具体的に解説されています。
加えて、成年後見制度や日常生活自立支援事業の説明も取り上げられており、難しそうな制度の話も家族が安心して読み進められるように工夫されています。地域の支援者がどのように家族と連携するか、実践的な視点が詰まっている点も大きな特徴です。

第3章 「親なきあと」を支える制度としくみ
この章では、「親なきあと」に向けた具体的な準備を進める際に家族や支援者が知っておきたい公的制度やお金の管理方法が網羅的に解説されています。障害者雇用制度、年金や手当、助成制度など、障害者本人や家族の生活を支える仕組みが一つずつわかりやすく整理されています。
さらに、福祉型信託や生命保険信託など、将来に備えてお金を残す方法についても詳しく紹介されており、「どんな方法で子どもの生活費を確保できるのか」という親の不安に応える内容です。成年後見制度についても「親族の後見人は裁判所が認めないのか?」という疑問に答える形でコラムが用意されており、家族が誤解しやすいポイントをフォローしてくれます。
また、日常生活自立支援事業や生活困窮者自立支援制度、生活保護、一人暮らしを支える仕組みまで、障害のある子どもの自立生活を支えるための最新情報が盛り込まれているので、家族だけでなく支援者にとっても必読の内容になっています。

第4章 「親なきあと」相談室のこれから
最終章では、これからの相談室のあり方や、地域との連携の必要性について紹介されています。著者自身が実際に立ち上げた相談室の経験から、親御さんが「何でも話していい」と思えるような場を作るために心がけていることや、地域全体での支援のネットワークを広げる方法が語られています。
大分県社会福祉事業団の取り組みなど、地域レベルで「親なきあと」に備える実例もあり、他の地域でも参考にできるヒントが詰まっています。さらに、支援者として「親なきあと」に関わるときに必要なスキルや知識、そして「多くの人が近くの支援につながるために」というビジョンも示されており、支援者自身の成長にも役立つ章になっています。

対象読者

この本は、「親なきあと」の不安を抱える家族だけでなく、その家族を支えるさまざまな立場の方々に向けて書かれています。
それぞれの読者が、自分に合った形で本書を活用できるよう、以下の対象者ごとに具体的な活用ポイントを紹介します。
- 障害のある子を持つ保護者
- 福祉・医療・教育分野の支援者
- 成年後見制度や信託に関心のある士業関係者
- 地域での支援活動に関わるNPO・自治体職員
- 将来の備えを考える障害当事者とその家族
それぞれの立場でどのように役立てられるか、以下で詳しく解説していきます。
障害のある子を持つ保護者
障害のある子どもを持つ親にとって、「親なきあと」は決して他人事ではなく、必ず訪れる問題です。自分たちが元気なうちは子どもを支えられるけれど、いざ自分がいなくなった時に誰が子どもの面倒を見てくれるのか、どんな場所で、どんなサポートを受けながら生活していけるのか…。そんな不安や心配は尽きることがありません。
本書では、障害のある子どもを持つ親が抱えるこうした悩みに正面から向き合い、どのタイミングで何を準備すればいいのかを具体的に教えてくれます。親の年金や遺産だけに頼るのではなく、地域や制度を活用しながら子どもの生活基盤を作っていく方法が、実際の相談事例をもとにわかりやすく説明されています。
また、「親がいなくなった後の話なんて縁起でもない」と感じてしまう方も多いかもしれませんが、本書では「いざというときに困らないための準備こそが、今を安心して暮らすことにつながる」とやさしく背中を押してくれます。

福祉・医療・教育分野の支援者
福祉施設や行政、特別支援学校など、障害のある子どもとその家族を支える立場にある支援者にとって、「親なきあと」は日々の相談業務で避けて通れないテーマです。制度の説明だけなら教科書で学べますが、実際の現場では、家族の想いを受け止め、どのように支援につなげるかというコミュニケーション力が求められます。
本書では、そうした支援者が「どのタイミングでどの制度を紹介すれば家族が安心できるのか」「家族の不安をどう受け止めればいいのか」といった実践的なヒントが豊富に紹介されています。支援者自身が「この家族にはどの制度が必要だろう」と具体的に考えられるよう、事例とともに分かりやすく解説されています。
また、地域の支援ネットワークの作り方や家族への説明の仕方など、現場で役立つノウハウも満載です。支援者としてのスキルアップにもつながる一冊と言えるでしょう。

成年後見制度や信託に関心のある士業関係者
成年後見制度や信託制度を専門分野として扱う士業(行政書士、司法書士、弁護士、ファイナンシャルプランナーなど)の方々にとっても、この本は非常に役立ちます。法的な仕組みや契約実務の説明だけでなく、「親なきあと」を迎える家族がどんな不安を抱え、どんな制度を必要としているのかという現場の声が数多く掲載されているからです。
士業の方々が相談を受けるとき、単に法律や制度を説明するだけでは、家族の安心感を十分に得られない場合があります。本書では、成年後見制度や福祉型信託の仕組みを家族の視点からかみくだいて解説し、さらにどのタイミングで制度を使えばいいのか、どの制度を組み合わせて使うと安心できるのかという現実的なアドバイスも紹介されています。
専門職の知識に加え、家族の不安に寄り添う「福祉の視点」まで学べる内容なので、士業の方が相談対応をする際に幅広い引き出しを持つことができます。

地域での支援活動に関わるNPO・自治体職員
NPOや自治体の福祉担当者、地域包括支援センターなどで障害者支援に携わる職員の方々にとっても、この本は非常に実践的で役立つ内容です。
「親なきあと」の問題は家族だけの問題ではなく、地域全体で支えていく必要があるテーマです。しかし、実際に地域で支援活動を進めようとすると、家族や本人の状況、制度の使い方、地域資源のつなぎ方など、多くの情報を整理して伝える必要があります。さらに、地域住民との連携や多職種のネットワークづくりなど、調整役としてのスキルも求められます。
本書では、相談室の事例を交えながら、地域全体で支えるための支援ネットワークづくりや、行政・福祉・教育が連携して家族をサポートする方法がわかりやすく解説されています。

将来の備えを考える障害当事者とその家族
障害のある本人やその家族にとって、自分の将来を主体的に考えることはとても大切です。しかし、制度や支援の話になると「難しくてよく分からない」と感じる人も多いのではないでしょうか。本書では、障害当事者自身が「自分は将来どう暮らしたいのか」「どんな支援があるのか」を、家族や支援者と一緒に話し合うきっかけになるように、優しく丁寧に解説されています。
具体的な事例や制度の使い方が紹介されているので、家族だけでなく本人自身も「将来の生活」をリアルにイメージできます。お金のこと、住まいのこと、支援のつながり方など、幅広いテーマを一つずつ学びながら、自分でできること、家族や支援者に相談したいことを整理するきっかけになります。
家族とともに読み進めることで、親子での話し合いも自然と深まり、将来の不安を少しずつ解消していけるでしょう。

本の感想・レビュー

制度の具体的な解説が役立つ
障害のある子どもを育てる親として、将来の生活設計は常に頭の片隅にありますが、制度の話になると、正直、専門用語が多くて難しく感じていました。そんなときにこの本に出会い、一気に視界が開けたような気持ちになりました。
本書は、制度の解説がただの説明ではなく、「どの場面で」「どんな手続きが必要か」といった実践的な情報まできちんと網羅されているんです。例えば障害者手帳や年金制度のこと、そして成年後見制度の活用まで、実例を交えて一つひとつ丁寧に解説されているので、頭の中で「あ、うちの場合はこうすればいいんだ」とイメージしやすくなりました。
これまで、制度と聞くだけで難しそうと敬遠していた私でも、読み進めるうちに「これなら自分でもできそう」と思えたのが大きな収穫でした。将来の不安が少しだけ軽くなった気がします。
実際の相談事例が参考になる
私は障害のある弟と一緒に暮らしているのですが、両親も高齢になり、「親なきあと」について漠然とした不安を抱えていました。実際にどう準備すればいいのか分からず、悩んでいたときにこの本を手に取りました。
中でも助かったのは、いろいろな家族のケースが実際の相談事例として紹介されていたことです。どの事例も、他人事ではなく「自分たちも同じような状況になるかもしれない」と思えるものばかりで、読んでいて胸が熱くなりました。
特に、親が高齢で経済面も不安という家庭の相談事例は、私たち家族の状況と重なるところが多く、「こうやって準備していけばいいんだ」と勇気づけられました。相談事例があることで、本に書かれている制度やアドバイスがよりリアルに感じられ、すぐに行動に移せそうな気持ちになりました。
支援者としての視点が得られる
私は地域で障害のある方の相談を受ける仕事をしているのですが、この本を読んで改めて気づかされたのは、「支援者は制度を説明するだけじゃダメなんだ」ということでした。
普段の仕事では、どうしても「この制度がありますよ」「この手続きが必要です」と、一方的な説明で終わってしまうことが多かったんです。でもこの本を読んで、親御さんや家族の気持ちを汲み取ることの大切さ、そして「どんな順番で制度を活用していくのか」を一緒に考えることが大事なんだと実感しました。
著者の経験談や相談室でのエピソードがふんだんに盛り込まれているので、支援者としてのリアルな現場の声を聞いているような気持ちになりました。これからは、もっと寄り添う支援ができるように、自分自身のスキルアップにもつなげていきたいと思います。
家族間の話し合いの重要性を再認識
正直言うと、「親なきあと」のことは気になっていたけど、家族みんなで話し合うなんて、なかなかできなかったんです。でも、この本を読んで、家族でちゃんと話すことの大切さを痛感しました。
本書では、家族それぞれの気持ちや状況を確認しながら、どんな風に話し合いを始めればいいかが分かりやすく書かれていました。親だけでなく、障害のある子ども本人の意向を尊重することや、兄弟姉妹の気持ちも大切にすることが書かれていて、「ああ、うちも一度みんなで話し合おう」と思えるきっかけになりました。
実際に親とも少し話してみたら、ずっと心配していたことをお互い話せて、少しだけ気持ちが楽になったんです。この本のおかげで、一歩踏み出す勇気が持てました。
成年後見制度の理解が深まる
成年後見制度って言葉は知っていたけど、実際にどう使うのかは全然分かっていませんでした。手続きが難しそうだし、どんな場面で必要になるのかも曖昧だったんです。
この本では、成年後見制度の仕組みや必要になるタイミング、注意点まで、実際の相談事例を交えながら丁寧に説明してくれていました。特に「親族が後見人になれない場合がある」といったリアルな話があって、「そうなんだ!」と驚きました。
今まで「なんとなく怖いもの」というイメージだった成年後見制度が、「ちゃんと知っておけば怖くない」と思えるようになりました。これから親と一緒に準備していこうと思えたのが一番の収穫です。
地域とのつながりの大切さを実感
私はこれまで、障害のある子の将来を考えるとき、家族でなんとかしなくてはと肩に力を入れていました。だからこそ、「親なきあと」という言葉に向き合うたび、胸が苦しくなっていたんです。でも、この本を読んで、自分たち家族だけで抱え込む必要はないのだと、心から思えました。
本書では、地域の支援者や相談室、NPOの役割がとても丁寧に説明されています。最初は「地域の支援って役所に頼るしかないのかな」と思っていましたが、相談室の取り組みや支援ネットワークの事例が紹介されていて、「こんな形で地域とつながれるんだ」と目からウロコでした。
特に印象に残ったのは、支援室のスタッフが家族だけでなく地域の人たちとも協力し合い、本人の生活を支えていく様子でした。親が年を取っていく中で、家族だけではどうにもできないことが必ず出てくると思うのですが、地域の人たちや支援者と手を取り合うことで、子どもの生活を支える安心感が得られるのだと気づかされました。
一人暮らしの準備に関する具体策がある
私の子どもは障害があり、いずれは一人暮らしをさせたいと願ってはいるものの、どう準備すればいいのか、何から手をつければいいのか、ずっと分からずにいました。そんなときにこの本を読んで、霧が晴れるような思いがしました。
本書では、一人暮らしを目指すために必要な支援のステップが、本人の状況や家族の不安に寄り添いながら書かれているんです。親としては、「自分がいなくなったらこの子は一人で暮らせるのか」というのが一番の心配ごとですが、実際にどんなサポートがあれば安心して暮らせるのか、どんな制度が利用できるのか、具体的に知ることができて本当にありがたかったです。
また、一人暮らしの準備は急ぐ必要はないという言葉が、とても心に響きました。今すぐ完璧にするのではなく、本人のペースに合わせて少しずつ進めればいいというアドバイスをもらえたことで、親の私も焦らずに前向きな気持ちで準備を進められると思えました。読後、家族で話し合ってみようという気持ちになれたのが、本当に大きな一歩でした。
福祉とお金の両面からのアプローチが新鮮
これまで「親なきあと」のことを考えると、正直言ってお金の心配ばかりが先に立っていました。でも、この本を読んで、「お金だけでなく、福祉サービスを組み合わせることが何より大事なんだ」と気づかされました。
年金や手当、信託や保険の制度については、聞いたことがあるけど難しそうで手が出せなかったのですが、著者が一つひとつ丁寧に解説してくれていて、「これなら私にもわかる」と感じられました。さらに、福祉サービスや地域の相談室と連携しながら経済面を整えていくという考え方が新鮮で、今まで自分にはなかった視点だなと感じました。
この二つをうまく組み合わせることで、子どもの将来だけでなく親の安心も得られるんだと分かり、親としての責任感が少しずつ前向きなものに変わっていくのを感じました。「福祉もお金も一緒に準備していけばいい」と思えるようになったのが、一番の収穫でした。
まとめ

ここまで、書籍『障害のある子が安心して暮らすために』について、内容説明や対象読者、目次などを詳しく解説してきました。
最後に、この本を手に取ることでどのようなメリットが得られるのか、読後にどのような行動を起こせば良いのか、そして全体のまとめとしてのメッセージを整理しておきましょう。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
この本を読んで得られるメリット
「障害のある子が安心して暮らすために」は、親なきあとを考える家族や支援者にとって、多くの気づきと実践的なヒントを与えてくれる一冊です。
ここでは、読後に特に得られると感じるメリットを紹介します。
制度の知識が初心者でも身につく
本書では、障害者雇用制度、年金、助成金、信託など、難解に思える制度が実例とともにわかりやすく解説されています。専門用語や法律用語が多い分野でも、著者が実際に家族や支援者と接してきた経験から「どのように制度を活用すればいいのか」「どのタイミングで動けばいいのか」が丁寧に説明されているので、初心者でも安心して学べます。
実際の事例で自分のケースに当てはめやすい
「親なきあと」の問題は、家庭によって状況が異なります。本書では、親の年齢や子どもの状況、地域の支援体制など、さまざまなケースを取り上げながら、具体的なアドバイスをQ&A形式で紹介しています。そのため、読者自身が「自分の家庭ではどうすればいいのか」を具体的に考えやすく、すぐに実践に移しやすいのが特徴です。
家族の不安に寄り添う姿勢が伝わる
制度や法律を解説するだけの本と違い、本書では家族の悩みや不安に寄り添う「対話」の大切さが繰り返し強調されています。制度を使うことが目的化してしまいがちな場面でも、著者は「本当にその家族に必要なのか」「本人の気持ちをどう反映させるか」といったポイントを大切にしており、読者は安心してステップを踏むことができます。
支援者や地域との連携のヒントが得られる
「親なきあと」の問題は家族だけで抱えるものではなく、地域の支援者やNPO、行政と一緒に考えていくことが大切です。本書では、地域のネットワーク作りや相談窓口の作り方、支援者同士の連携のあり方が具体的に紹介されているため、家族と地域がつながって問題解決に取り組むヒントが得られます。

読後の次のステップ
本書を読んだあと、安心して未来に向けた準備を進めていくためには、具体的な行動を始めることが大切です。
ここでは、実際にどのようなステップを踏めば良いのかを解説します。
step
1家族で「親なきあと」を話題にする
まずは、家族内で「親なきあと」についてオープンに話し合うことから始めてみてください。普段は話題にしづらいテーマかもしれませんが、本書に出てきた事例やQ&Aをきっかけにして、「私たちは将来どうしたいんだろう?」という問いを投げかけてみるとよいでしょう。家族みんなで考えることで、一人で抱え込んでいた不安が少しずつ解消され、共通の目標が見えてくるはずです。
step
2自分に必要な制度をリストアップする
本書では、障害者手帳、成年後見制度、信託、助成金、福祉サービスなど多岐にわたる制度が解説されています。読後には、自分の家庭の状況に照らし合わせて「どの制度を利用できそうか」「いつから準備すればいいのか」を整理してみましょう。具体的な制度名や利用条件が分かれば、次に相談すべき窓口や準備する書類も見えてきます。
step
3専門家や支援者に相談してみる
本書を読むことで、「どこに相談すればいいのか分からない」という壁を乗り越えるヒントが得られた方も多いでしょう。実際に行動を起こすときには、一人で抱え込まずに地域の福祉事務所や相談室、専門家(行政書士、社会福祉士、司法書士など)に相談してみてください。自分たちだけでは気づけなかった支援の選択肢が見つかるかもしれません。
step
4地域の支援ネットワークに参加する
「親なきあと」の問題は、家族だけでなく地域全体で支えるべき課題です。地域のNPOや相談室、親の会などに参加し、同じ立場の家族や支援者と情報を交換してみてください。地域の事例紹介や支援者同士のネットワーク作りが進めば、自分たちが受けられるサポートの幅が広がります。
step
5ライフプランを見直す
「親なきあと」の問題は、単なる制度利用の話だけではありません。親として、障害当事者として、「自分たちのこれから」をどのように設計していくかを考えるきっかけにもなります。収入や住まい、支援体制など、ライフプラン全体を見直しながら、「できること」「準備すべきこと」を一つずつ整理していきましょう。

総括
『障害のある子が安心して暮らすために』は、「親なきあと」という、障害のある子どもを持つ家族が抱える大きな不安に対して、実践的かつ丁寧に向き合った一冊です。単に制度を羅列するだけでなく、著者自身の現場経験をもとに、家族の声やリアルな相談事例を織り交ぜながら、読者が自分事として捉えられるように構成されている点が大きな魅力です。
この本の特徴は、障害者手帳や成年後見制度、信託、助成金といった「制度の知識」だけでなく、それらをどう活かすか、家族や支援者とどうつながっていくかという「実践の知恵」まで学べるところにあります。福祉とお金という、どちらも避けて通れないテーマを、専門用語をかみくだいて説明しているので、初めてこの問題に向き合う方でも安心して読めます。
また、「親なきあと」の備えは一度きりの答えがあるわけではなく、家族や本人の状況、地域の支援体制によって異なります。本書は「こうしなければならない」という押し付けではなく、「あなたの家庭の場合はどうだろう」と問いかけながら、一緒に考えていくスタンスが感じられます。その柔らかさと寄り添いが、読者の背中をそっと押してくれるのです。

障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめ書籍

障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめの本!人気ランキング
- 障害者の親亡き後プランパーフェクトガイド
- 障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて 第2版
- 改訂新版 障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本
- 障がいのある子とその親のための「親亡きあと」対策
- 障害のある子が安心して暮らすために
- 一生涯にわたる安心を! 障害のある子が受けられる支援のすべて
- まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活
- ダウン症の子をもつ税理士が書いた 障がいのある子の「親なきあと」対策

