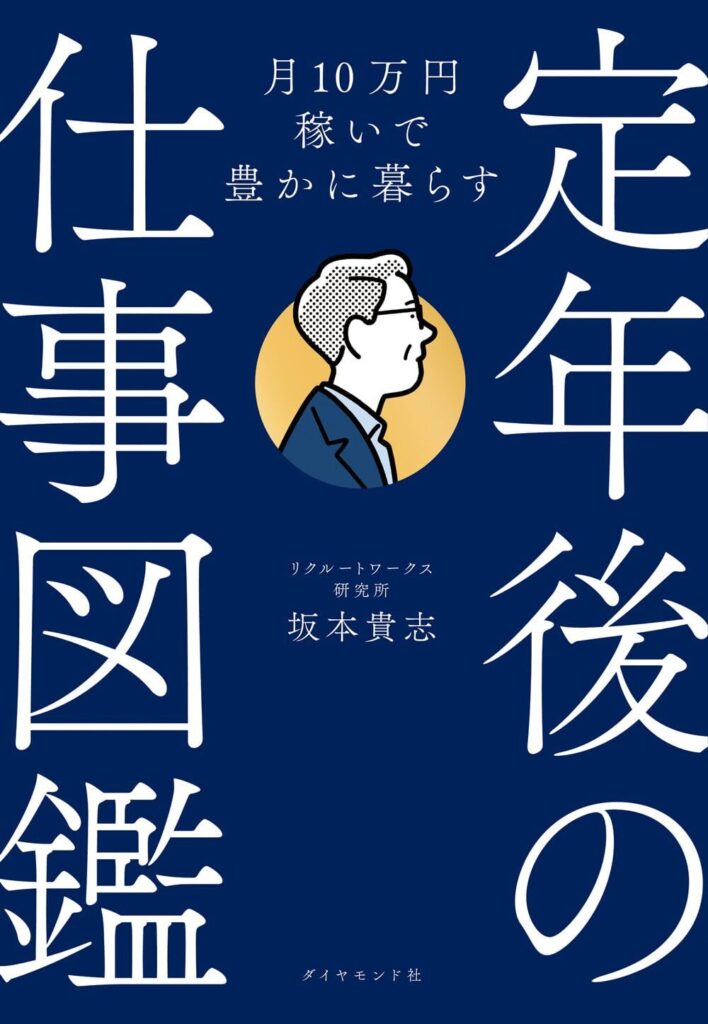
定年退職を迎えた後、「これからどう働けばいいのだろう?」と不安を抱く人は少なくありません。年金だけでは生活が心もとない、けれど体力や健康も気になる。そんな思いに応えるのが、坂本貴志氏による『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』です。

本書は、65歳以上・640万人のデータ分析と、実際に働くシニアの声をもとに、定年後に取り組める「厳選100職種」を徹底解説しています。
事務や営業といった経験を活かせる仕事から、農業や接客といった新たなチャレンジまで、具体的な仕事内容や収入の目安、働きやすさの実例が豊富に紹介されているのが特徴です。

合わせて読みたい記事
-

-
定年前後に読むべきおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】
定年が近づくと、これからの暮らしやお金、健康、働き方について考える機会が一気に増えます。 退職金や年金の受け取り方、再雇用やセカンドキャリアの選択、生活スタイルの見直しなど、人生の岐路で直面するテーマ ...
続きを見る
書籍『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』の書評

「定年後の仕事」をテーマにした本は数多く出版されていますが、本書は「図鑑」という切り口で網羅的に整理されている点が最大の特徴です。多くの人が直面する「退職後どう働くか」という課題に対し、データと実例を基に「定年後のキャリア選びの地図」を提供しています。
以下の観点から、著者や内容の魅力について掘り下げていきます。
- 著者:坂本 貴志のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
これらを順に見ていくことで、本の背景や狙いが理解しやすくなるでしょう。
著者:坂本 貴志のプロフィール
坂本貴志氏は、一橋大学大学院国際公共政策研究科を修了後、厚生労働省に勤務し、社会保障制度の設計や政策立案に携わりました。その後、内閣府では官庁エコノミストとして「経済財政白書」や「月例経済報告」の作成に参画し、日本経済をデータに基づいて分析・発信する役割を担っています。さらに三菱総合研究所にて国際経済分野を担当した後、リクルートワークス研究所に移り、シニア雇用や働き方の変化を研究してきました。
このように行政・研究・民間シンクタンクのすべてを経験している点が、彼の分析に厚みを与えています。著書には『ほんとうの定年後』や『統計で考える働き方の未来』などがあり、社会構造の変化を数字と現場の声から読み解くスタイルが特徴です。社会保障や高齢期の労働市場に関する専門家として、新聞やビジネス誌でも頻繁に取り上げられる存在です。

本書の要約
本書は「定年後にどのように働けば安心して暮らせるのか」をテーマに、具体的な働き方を提示した実用的なガイドです。内容の柱は大きく二つあります。
第一部では「定年後の基礎知識」として、なぜ「月10万円」という収入が大切なのかを説明しています。老後資金を「ストック(貯蓄)」に頼るのではなく、「フロー(収入)」を維持することが豊かな生活に直結する、という考え方が示されています。これは「利息で暮らす」のではなく「細く長く働き続ける」ことの合理性をデータで解説している部分です。
第二部では「100種類の仕事」が紹介されています。事務・営業、警備員、施設管理人、運転手、販売員、介護職、農業など、シニアが挑戦しやすく、また続けやすい仕事をジャンル別に体系化。そのうえで「仕事内容・収入の目安・必要な体力・就業場所」などが整理されています。さらにインタビュー記事も多く収録され、実際に働いている人の声が読者の理解を助けています。

本書の目的
この一冊の核心は「定年後を新しいキャリアのスタートとする」ことにあります。著者は、現役時代の延長線上で老後を考えるのではなく、自分の体力、生活リズム、家計状況に応じて新しい働き方を再構築する必要性を強調しています。
過去には「定年=引退」という考えが一般的でしたが、年金額の減少や健康寿命の延びにより、70代でも働き続ける人は珍しくなくなりました。本書の目的は、この現実を悲観的に捉えるのではなく、「選択肢が広がった」と前向きに受け止めるための視点を提供することです。
つまり本書は、シニア層に「働かされる」のではなく「自ら選ぶ」という主体的な姿勢を持たせるための羅針盤でもあります。

人気の理由と魅力
本書が多くの読者に支持されている理由は、まず第一に「データに裏打ちされた信頼性」です。640万人に及ぶ高齢者就労の統計をもとに書かれているため、単なる理想論ではなく現実に根差した内容となっています。
第二に「具体性と実用性」が挙げられます。100種類の職種を体系的に整理し、それぞれの仕事内容や収入の目安を示しているため、読者はすぐに自分の条件と照らし合わせて選ぶことができます。また、実際に働いているシニアのインタビューが随所に掲載されており、机上の空論ではなくリアルな労働現場の息遣いを感じられるのも魅力です。
第三に「心理的ハードルを下げる仕組み」があります。「月10万円」という具体的かつ現実的な目標設定は、多くの人にとって「これなら自分でも可能かもしれない」と思わせてくれる絶妙な水準です。高額な収入を目指す必要はなく、生活を安定させるための“もう一本の柱”を作ることに焦点を当てているからこそ、幅広い世代から共感を得ています。
さらに、身体的な負担が少ない仕事から社会貢献度の高い仕事までバリエーションが広い点も評価されています。「働くこと」が経済的な補填にとどまらず、生きがいや健康維持、社会とのつながりの再構築につながることを教えてくれる点が、多くの読者にとって新鮮な気づきとなっているのです。

本の内容(目次)

本書は「お金」「キャリア」「働き方」の三つの切り口を基盤としながら、多様な職業を体系的に整理しています。さらに、性別や体力、生活スタイルに合わせて選べる職種が網羅されているため、自分に合った選択肢を見つけやすいのが特徴です。
以下のような構成によって、読者は順を追って理解を深められるようになっています。
- 第1章 「定年後のお金」について知る
- 第2章 「定年後のキャリア」について知る
- 第3章 経験を活かせる仕事 ── 事務・営業
- 第4章 マイペースでできる仕事 ── 警備員・施設管理人
- 第5章 体を動かす仕事 ── 運転手・運搬・清掃員・包装
- 第6章 女性が活躍する仕事 ── 販売員・調理・接客・給仕
- 第7章 人とつながる仕事 ── 介護・保健医療サービス・生活衛生サービス・生活支援
- 第8章 自然と触れ合う仕事 ── 農業・林業・漁業
- 第9章 モノづくりの仕事 ── 生産工程
- 第10章 長く続けられる仕事 ── その他専門職・その他サービス・その他運搬・清掃等
これらを順に読み進めることで、「資金計画」から「ライフスタイル別の働き方」まで、一連の流れとして理解できる仕組みになっています。
特に第2部は19のカテゴリに分かれた具体的な職種紹介が中心で、現実的な選択肢を手に入れやすい構造です。
第1部 定年後、仕事探し「以前」の基礎知識
第1章 「定年後のお金」について知る ── なぜ月10万円が必要なのか?
定年後の生活で最も大きな不安のひとつが「お金」です。本章では、年金だけに頼る暮らしのリスクに触れながら、なぜ「月10万円の追加収入」が必要になるのかを具体的な数字で示しています。平均的な世帯の年金額は20万円超とされていますが、住宅ローンや医療費、生活費を考えると、それだけでは安心できない現実が浮き彫りになります。
また、本書では「ストック(貯蓄)」よりも「フロー(収入)」を重視する姿勢を提案しています。つまり、老後資金を切り崩していくのではなく、年齢に合った働き方で収入を継続的に得ることで、経済的にも精神的にも安定できるという考え方です。これにより「お金を減らさずに暮らす」というより前向きな老後のイメージが描けます。
さらに、60代半ばまでに住宅ローンなど大きな支出を減らしておくことが推奨されています。固定費が少なければ、月10万円の収入でも十分に豊かな生活を実現できるのです。つまり「定年後のお金」は単に数字の問題ではなく、家計の構造と働き方のバランスを見直すことが重要になります。

第2章 「定年後のキャリア」について知る ── 仕事探しはどう変わるのか?
この章では、定年後に直面する「仕事選びの新しいルール」について解説しています。かつてのように現役時代の延長としてキャリアを続けるのではなく、まったく異なる働き方に切り替える人が増えている現実が紹介されます。シニア層は「出世」や「達成感」よりも「健康」や「社会とのつながり」を重視する傾向が強くなっているのです。
50代以降の転職は「なんとなく」ではなく戦略的に行う必要があると本書は強調します。これは、自分の得意分野を生かすのか、それとも未経験でも負担の少ない仕事に挑戦するのか、事前に見極めて準備することが大切だからです。また、65歳以降は会社員以外の働き方にシフトする人が増えており、フリーランスやパート、地域の仕事など選択肢は多様化しています。
さらに、定年後のキャリアは「どこで探すか」という点も重要です。従来は会社やハローワークが中心でしたが、今ではインターネットの求人サイトや地域コミュニティ、シニア向け就職フェアなど、多様なチャネルが利用可能になっています。選択肢を広げることが新しい可能性を切り開く第一歩です。

第2部 月10万円稼ぐ「定年後の仕事」厳選100
第3章 経験を活かせる仕事 ── 事務・営業
この章では、長年の経験やスキルを活用できる分野として、事務や営業職が取り上げられています。一般事務員、会計事務員、営業事務員などは、パソコン操作や事務処理能力をそのまま活かすことができ、再就職しやすい領域です。営業では金融や不動産関連の仕事なども挙げられています。
実際に働く人の事例も豊富に紹介されており、英語力を活かして外資系企業に再就職した人や、会計経験を財団法人で発揮している人のケースがあります。これらは、定年後でもスキルを適切にアピールすれば、新しい活躍の場を得られることを示しています。
さらに、営業分野では「人脈」や「信頼」が大きな資産となります。長年培った顧客対応力は、年齢を重ねても失われず、むしろ信頼感を高める要素となります。成果が数字として表れる営業職は、やりがいと収入を両立できる仕事としても魅力的です。

第4章 マイペースでできる仕事 ── 警備員・施設管理人
この章では、体力的な負担が比較的少なく、安定した需要がある分野が紹介されています。警備員や施設管理人の仕事は、シフト勤務や短時間労働が可能で、自分のペースで働ける点が大きなメリットです。特に警備員は需要が高く、未経験から始めやすい職種の一つです。
実際の事例では、定年後に1年間無職だった人が警備の仕事に就き、小さな仕事にシフトして生活リズムを整えたケースや、日給1万円以上を得ながら健康維持にも役立てている人が紹介されています。施設管理人としても、マンションや駐車場の管理を通じて安定収入を得ている人がいます。
こうした仕事は「収入」と「健康維持」の両立が可能であり、また人との交流が適度にあるため孤立防止にもつながります。精神的にも無理なく続けやすい職種として、多くのシニア世代に支持されています。

第5章 体を動かす仕事 ── 運転手・運搬・清掃員・包装
ここでは、適度に身体を動かす仕事が紹介されています。運転手、配送業務、清掃、包装といった分野は体力を必要としますが、健康維持や生活リズムの安定にもつながる働き方です。特に送迎ドライバーやタクシー運転手は、利用者との会話を楽しめる点も魅力です。
実例としては、好きな運転を仕事にして利用者との交流を楽しむ人や、退職後に清掃のアルバイトを始めて新しい生活習慣を作った人が紹介されています。地方にUターンして公園清掃を行いながら家庭菜園に励むケースもあり、収入と趣味を両立するライフスタイルが描かれています。
さらに、包装作業は比較的軽作業であり、女性や高齢者でも無理なく取り組める点が評価されています。単純作業ながら社会に必要とされる役割を担えることで、自尊心を保ちながら働けるのも魅力です。

第6章 女性が活躍する仕事 ── 販売員・調理・接客・給仕
この章では、特に女性が得意とする分野が多く取り上げられています。スーパーやコンビニでの販売員、飲食店や宿泊施設での調理、ホテルや飲食店での接客など、生活に身近な仕事が中心です。これらは資格や特別な経験がなくても始めやすく、短時間勤務やシフト制も多いため、家庭との両立もしやすい点が特徴です。
また、年齢を重ねても働き続けられる実例が紹介されています。例えば、配偶者を亡くして80歳から販売スタッフを始めた人や、年金だけでは不足する生活費を補うためにスーパーで働く女性など、現実的な姿が描かれています。これらの事例は、年齢や境遇に関係なく社会で活躍できる可能性を示しています。
さらに、人との交流が多い仕事であるため「人と接するのが好き」という性格を活かすこともできます。特に接客業は、顧客の反応を直接感じられるため、やりがいを得やすい分野といえるでしょう。収入だけでなく、生きがいや楽しみを得られる仕事として紹介されています。

第7章 人とつながる仕事 ── 介護・保健医療サービス・生活衛生サービス・生活支援
ここでは、介護や医療補助といった「人の役に立つ仕事」が取り上げられています。ホームヘルパーや施設介護職員、看護助手、歯科助手などは、専門資格が必要な場合もありますが、未経験から始められる職種も少なくありません。高齢社会における需要が大きいため、安定した就業先を見つけやすい分野です。
また、生活衛生サービスや生活支援といった分野では、美容師やクリーニングスタッフ、家事代行やベビーシッターなどが紹介されています。こうした仕事は、日常生活に密接に関わるため需要が絶えず、また人との交流が多いことから、働く喜びを得やすいのも特徴です。
実際の事例としては、専業主婦を経て添削指導の仕事を20年、その後ヘルパーを15年続けている女性など、ライフステージに応じて仕事を切り替えながらキャリアを重ねている人もいます。このように、定年後に人とかかわる仕事は「収入」と「社会的貢献」を両立できる魅力があります。

第8章 自然と触れ合う仕事 ── 農業・林業・漁業
この章では、自然を相手にした働き方が紹介されています。農業や造園、果樹栽培、さらには林業や漁業まで、多岐にわたる仕事が取り上げられています。これらは体力を必要とする場合もありますが、自然の中で働くことによる充実感やリフレッシュ効果が大きいのが魅力です。
定年後に母から果樹園を引き継いで果物づくりを始めた人や、Uターンして地域に根ざした農業を営む人など、具体的なエピソードも多数掲載されています。都会でのキャリアから一転して、地方で自然と共生する生き方を選ぶ事例は、多くの読者に新しい可能性を示しています。
林業や漁業はやや専門的な技術や経験を必要としますが、地域の指導や支援制度を利用することで未経験者でも挑戦できる道があります。体力があるうちは積極的に、加齢に応じて作業量を調整する働き方が可能です。

第9章 モノづくりの仕事 ── 生産工程
ここでは、製造業や加工業などの現場で活躍できる仕事が紹介されています。金属加工、食品製造、繊維製品の製造、機械の組み立てや検査など、手先の器用さや集中力を活かせる分野が多いのが特徴です。特に単純作業が中心のライン作業は、年齢を問わず取り組みやすい仕事として位置付けられています。
インタビュー事例では、定年後も勤務先の会社で週2回パートとして働き続ける人や、業務委託で高い自由度を持ちながら80歳を超えても現役で働く人などが紹介されています。これらの実例は「長く続けられる仕事」としての具体的な姿を示しています。
また、モノづくりの仕事は「社会に形として残る成果を生み出せる」点がやりがいにつながります。収入面だけでなく、自分の作業が商品やサービスに直結することが働く喜びを強めています。

第10章 長く続けられる仕事 ── その他専門職・その他サービス・その他運搬・清掃等
最後の章では、特定の資格や専門知識を活かした仕事から、比較的軽作業に分類されるものまで幅広く取り上げられています。塾講師や家庭教師、図書館司書といった知識や経験を生かす仕事もあれば、学童保育や観光案内、ポスティングなど地域に根ざしたサービス業も含まれます。
また、スーパーの商品補充や学校の用務員、放置自転車の整理といった、比較的軽い肉体労働の仕事も紹介されています。これらは短時間勤務が可能で、無理のない範囲で長期間続けられる点が大きな魅力です。インタビューでは「NGO活動を経て小学校の用務員として働く」「ドラッグストアで品出し業務に従事する」など、社会との接点を持ち続ける実例が描かれています。
この章全体を通じて共通しているのは「無理をせず長く続けられること」が重視されている点です。経済的な安定だけでなく、生活リズムや健康維持、社会参加の観点からも重要な役割を果たす仕事群として整理されています。

対象読者

この書籍は、定年後の働き方を考えるすべての人に役立つ内容ですが、特に次のような立場にある方に強い関心を持っていただけるでしょう。
- 定年退職を控えている会社員
- 再雇用後のキャリアに不安を抱く人
- 年金だけでの生活に不安を感じている人
- 健康や体力に配慮しながら働きたい人
- 自分の経験を活かした仕事を探したい人
これらの人々に共通するのは「将来への安心感」を求めている点です。本書は、データに基づく解説と実際の就業者の体験談を通じて、老後の生活を豊かにするための現実的な選択肢を示しています。
定年退職を控えている会社員
定年を迎える直前の会社員にとって、本書は未来を描くための実践的なガイドブックです。長年の勤続を終えると、多くの人は「これから先どうやって生活を支えていくのか」という不安に直面します。本書は、単なる再雇用の選択肢にとどまらず、新たなキャリアの可能性や現実的な収入の確保方法を、データと事例を通して明示しているため、老後を前にした不安を具体的な行動指針に変えてくれるのです。
さらに、この本は「定年=引退」という固定観念を打ち破り、人生100年時代における「第二のキャリア形成」の重要性を説いています。これまで積み上げてきたスキルをどう活かせるのか、あるいは新たに挑戦できる分野はどこにあるのかを知ることで、退職を不安ではなく前向きな節目と捉え直すきっかけになるでしょう。

再雇用後のキャリアに不安を抱く人
再雇用で同じ職場に残っても、仕事内容や収入は現役時代とは大きく変わります。そのため、将来に対する不安を強く感じる人も少なくありません。本書では、再雇用以降の新しいキャリアチェンジの可能性を広く提示し、職場環境に縛られない働き方を具体的に紹介しています。
データだけでなく、実際にキャリアチェンジを果たした人々の声が載っているため、「自分にもできるかもしれない」というリアルな希望が持てます。従来の枠組みにとらわれない柔軟な働き方を模索する人にとって、本書はキャリアの再設計を支援する手引きとなります。

年金だけでの生活に不安を感じている人
公的年金は安定的な収入源ですが、生活費全般をまかなうには不足を感じる人が多いのが現実です。本書は、年金を前提としたうえで「不足分をどのように補うか」という観点から仕事を紹介しているため、現実的な対策を立てやすくなっています。
また、収入だけでなく働く時間や体力とのバランスを考慮した仕事の選び方が強調されているのも特徴です。年金で基本生活を維持しつつ、月10万円をプラスすることで、旅行や趣味などの余裕資金を確保できる具体的なイメージを得ることができます。

健康や体力に配慮しながら働きたい人
高齢になると、どれだけ稼げるかよりも「どれだけ無理なく続けられるか」が重要になります。本書では、体に負担をかけずにできる仕事や、短時間勤務でも続けやすい働き方が多く紹介されているため、健康を最優先に考える人に適しています。
また、適度に体を動かせる職種や、人との交流を通じて心身の活力を保てる働き方も掲載されています。仕事をすることで生活リズムが整い、健康寿命を延ばすことにもつながるため、「働きながら元気でいたい」と考える人にとって、本書は人生設計の強い味方となります。

自分の経験を活かした仕事を探したい人
長年培ってきたスキルや知識をそのまま眠らせてしまうのは惜しいと考える人も多いでしょう。本書では、事務や営業といった専門性を活かせる仕事や、講師・指導員といった教育関連の職種も数多く取り上げています。過去のキャリアを再活用することで、新しいステージでも自信を持って働ける道が開かれます。
さらに、インタビューを通じて「経験を活かしながらも新しい形で働く人々」の実例が紹介されており、自分のキャリアに置き換えて想像しやすい構成になっています。経験を積み重ねてきた人ほど、この本から得られる示唆は大きいでしょう。

本の感想・レビュー

「月10万円」という現実的な指標
読んでいて何よりも心に残ったのは、「月10万円」という具体的な金額が提示されていたことです。これまで老後の収入について考えるとき、どれくらい働けばいいのか明確な目安がなかったため、ただ漠然と「足りないかもしれない」と不安を募らせていました。しかし、この数字を一つの基準として示されたことで、自分の生活設計に現実味が増しました。
この10万円という水準は、贅沢すぎず、それでいて生活にゆとりを与える絶妙なバランスです。年金だけに依存する生活ではなく、少しでも安定した収入を得ることが、精神的な安心感につながるのだと理解できました。過大な収入を追い求める必要はなく、自分らしく暮らすための「適度な収入」が重要だという視点が得られたのは大きな収穫です。
さらに、この目安があることで、自分に合った働き方を探す際の判断材料が明確になりました。収入を目的化するのではなく、生活を支えるための必要額を見極めることが、これからの人生設計をよりシンプルで前向きなものにしてくれると感じました。
インタビュー事例がリアル
この本を読みながら強く共感したのは、実際に働いている人たちのインタビューが豊富に掲載されている点です。机上の空論ではなく、現場で活躍している方々の声が載っていることで、読者である自分との距離が一気に縮まりました。データや理論の裏にある「生きた体験談」が、想像以上に説得力を持って響いてきました。
インタビューの内容は、決して派手な成功談ばかりではなく、むしろ等身大の取り組みや小さな苦労、そしてその中で見つけた喜びが中心でした。そのリアルさが、自分の未来を現実的にイメージさせてくれました。「自分でもこういう働き方ならできるかもしれない」という気持ちが芽生えたのは、この実感にあふれた声のおかげです。
本を閉じた後も印象に残り続けるのは、数字や解説よりも、実際に働く人の笑顔や生活の場面です。そこには単なる仕事以上のもの、つまり「人生の続き方」が映し出されており、自分の定年後を前向きに描く手がかりとなりました。
定年後も選択肢が多いと実感
ページをめくるごとに驚かされたのは、紹介されている仕事の種類がとにかく多岐にわたっていたことです。これまで定年後の働き方といえば、ごく限られた範囲しか思い浮かびませんでした。しかし、本書には100を超える職種が体系的に示されており、「自分の年齢や体力でもまだ挑戦できる分野がある」と知ることができました。
その多様さは単に数の多さではなく、ライフスタイルや目的に合わせて選べる柔軟さにつながっています。体力を重視する仕事から、人と関わる役割、専門性を生かす分野までが網羅されていて、どんな人にも合う道が見つかるのではないかと感じました。こうした幅広い視野を与えてくれる点が、この本の最大の魅力のひとつだと思います。
「年齢を重ねると選択肢が限られる」という先入観は、この本を読むことで大きく覆されました。むしろ、定年後だからこそ自由度の高い選択が可能になるのだと気づき、未来に対する見方が前向きに変わったのです。
お金とキャリアの両面をカバー
この本を読みながら感じたのは、単なる収入の確保にとどまらず、キャリア全体のあり方にも目を向けている点でした。年金に頼るだけではなく、どのように収入を組み合わせ、どう生きがいを見つけていくかが描かれていて、「働くことの意味」を幅広い観点から考えることができました。
特に印象的だったのは、現役時代の延長ではなく、新たなキャリアをどう築くかに焦点を当てていることです。役職や肩書に縛られず、社会とのつながりを維持しながらも、自分に合ったペースで取り組めるという提案は、新鮮で心強いものでした。経済的な面と精神的な充実感が両立できる働き方の提示は、多くの人にとって大きな支えになると思います。
読み進めるうちに、定年後の人生が単なる「余生」ではなく、むしろ新たなキャリアの章として意味を持つのだと実感しました。この視点を得られたことで、自分自身の将来を考える際にも前向きな選択肢を描けるようになったのです。
ストレスの少ない仕事が見つかる
この本を読んで感じたのは、「定年後にまで無理をして働かなくてもいい」という安心感でした。働き続ける以上、どうしても心配になるのが人間関係の摩擦や過度なノルマです。しかし、本書ではストレスの少ない仕事が具体的に紹介されており、「自分の体力や気持ちに合った仕事を選んでいいんだ」と思わせてくれました。
仕事というとどうしても「頑張りすぎる」イメージがありますが、本書で紹介される職種は、むしろ「続けやすさ」が重視されています。精神的な負担が少ないからこそ長く続けられ、毎日の生活リズムを安定させることにつながるのです。その点が、これから働き方を考える人にとって非常に参考になると感じました。
「自分の身の丈に合った仕事」を選ぶことが、定年後の暮らしにとって大切だと実感できたのは大きな学びでした。やりがいや社会とのつながりを得ながらも、無理なく働ける仕事の数々が紹介されていることで、不安が少しずつ解消されていったのです。
資格不要の職種が多いのが魅力
私は資格を持っていないため、再就職となると不安が大きかったのですが、この本を読んで大きな希望を持てました。紹介されている職種の多くは特別な資格が不要で、未経験からでも始めやすい点が強調されていたからです。専門的な知識や試験勉強に追われることなく、すぐに取り組める選択肢があると知ったことで肩の荷が下りました。
実際のところ、資格やキャリアに自信のある人ばかりではありません。そうした現実を前提に、多くの人が気軽にチャレンジできる仕事が紹介されているのは非常にありがたいと感じました。年齢を重ねると「もう新しいことは無理」と思い込みがちですが、本書はそうした固定観念を優しく覆してくれます。
資格がない自分でも挑戦できる仕事があると分かっただけで、未来に対する見方が前向きになりました。「やりたい」と思える気持ちを尊重してくれるような内容で、読後には自然と行動したくなるエネルギーが湧いてきました。
働く意義を再認識できる
この本を読み進めるうちに、ただお金を稼ぐためだけでなく、働くこと自体の意味を考え直すきっかけになりました。仕事は単に収入を得る手段ではなく、人とのつながりを持ち続け、自分自身の存在価値を感じられる場でもあることが伝わってきます。定年後だからこそ、その意義がいっそう大きくなるのだと実感しました。
特に印象に残ったのは、年齢を重ねたからこそ発揮できる力や経験があり、それを社会で生かすことができるという視点です。達成感や出世ではなく、地域や人への貢献という新しい意味づけが提示されており、「働くことが生きることにつながる」というメッセージが心に深く残りました。
読後には、仕事を続けることは単なる義務ではなく、むしろ「人生を豊かにする選択肢」であると感じられるようになりました。働く意義を改めて問い直し、それを前向きに受け止められることが、この本の大きな魅力だと思います。
「老後の安心」につながる内容
心に残ったのは、この本全体から伝わってくる「安心感」でした。年金や貯蓄だけでは不安を拭えない現実のなかで、働き方を工夫すれば老後をより豊かに過ごせるという希望を与えてくれるのです。漠然とした将来への恐れを和らげてくれる一冊だと感じました。
仕事を持ち続けることで経済的な安定を得るだけでなく、生活リズムや社会とのつながりを維持できることが繰り返し示されていました。これが「老後の安心」につながるのだと理解できました。単なる理論ではなく、実際のデータや事例をもとに描かれているので説得力があります。
読後には、「これなら自分も定年後を恐れずに迎えられる」と思えるようになりました。不安が希望に変わる感覚を与えてくれる点こそ、この本の最大の魅力だと感じます。
まとめ

本書は単なる「仕事図鑑」ではなく、定年後の人生をどう設計するかを考えるための実践的なガイドです。現役時代の延長ではなく、新しい環境での働き方を選ぶためのヒントが豊富に盛り込まれています。
このまとめでは以下の観点から整理してお伝えします。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
これらを理解することで、老後の生活に向けた準備を段階的に進めやすくなり、自分らしい働き方を実現するための確かな道筋が見えてきます。
この本を読んで得られるメリット
本書を読むことで、その不安を体系的に整理し、自分に合った選択肢を冷静に見極められるようになります。
ここでは、特に大きな価値として得られる4つのメリットを紹介します。
将来の生活設計が明確になる
定年後に必要とされる収入の目安を「月10万円」と設定し、その背景となるデータや事例が丁寧に解説されています。漠然とした不安を抱えていた読者も、この具体的な数値を基準にすることで、自分に必要な生活費と働き方を現実的にイメージできるようになります。これにより、定年後の資金計画や家計のバランスを考える際に、しっかりとした指針を持つことが可能になります。
多様な選択肢から自分に合った道を探せる
本書の中心をなすのは、厳選された100種類の職種です。ここでは、収入の目安や仕事内容、必要なスキルなどが詳細にまとめられており、読者は自分の体力や経験に合わせて職業を比較することができます。特別な資格が不要な仕事から専門的な知識を活かす分野まで幅広く紹介されているため、自分に合った選択肢を見つけやすい仕組みになっています。
実際の声から現実感を得られる
抽象的な情報だけではなく、実際に働いている人々のインタビューが豊富に収録されています。定年後にキャリアチェンジを果たした人や、無理のない働き方で充実した生活を送っている人の事例は、読者にとって強い共感と勇気を与えます。「この人にできたなら自分もできる」という実感が、次の行動を後押ししてくれるのです。
働く目的を再確認できる
本書は単に収入を得るための手段を示すだけではありません。健康維持や社会参加、生きがいの再発見といった観点からも「なぜ働くのか」を問い直す構成になっています。定年後の仕事をお金のためだけではなく、人生の質を高めるものとしてとらえる視点を提示してくれる点は、他の実用書にはない大きな特徴です。

本書のメリットは「情報量の豊富さ」と「生活に直結する実践性」の両立にあります。
単なる知識提供ではなく、行動に直結するデータと事例を融合させている点で、シニアのキャリア形成を考える上で極めて有効なリソースとなっています。
読後の次のステップ
本書を読み終えた後に大切なのは、知識を得ただけで終わらせず、自分の生活にどう落とし込むかを考えることです。定年後の働き方は「情報を集める段階」から「行動に移す段階」へと進むことで、初めて現実味を帯びてきます。
ここでは、読了後に実践したい三つの方向性を紹介します。
step
1自分のライフスタイルを見直す
本を読み終えた後、最初に取り組むべきは自分自身の生活を客観的に点検することです。毎月の支出や家計のバランスを洗い出し、「年金だけでは不足する部分がどれくらいあるのか」「副収入としてどの程度が必要なのか」を把握することが重要です。こうした作業を通じて、自分にとって本当に必要な金額や働く目的が明確になっていきます。
step
2興味のある職種をリストアップして調べる
次の段階では、本書で紹介されている多様な仕事の中から、自分に合った分野を絞り込む作業が必要になります。漠然と「働きたい」と考えるだけではなく、「体力に見合った仕事」「これまでの経験を活かせる分野」「新しく挑戦してみたい職種」といった観点から選び出すことが効果的です。紙に書き出したり、家族や友人に相談したりすることで、より現実的な選択肢が見えてきます。
step
3行動計画を立てて実践する
候補を見つけたら、実際に行動に移すステップへ進みます。ハローワークやシニア向けの求人サイトにアクセスしたり、地域の就労支援センターに相談したりすることが第一歩です。最初から完璧な仕事を見つける必要はなく、パートや短時間勤務など小さな一歩から始めることが大切です。経験を重ねる中で、自分のペースに合った働き方を確立していくことが可能になります。

学んだことを「具体化」し「実践」に移すためには、段階的なアプローチが欠かせません。
情報を知識として終わらせず、現実の行動に接続させることが、定年後キャリアの成否を左右します。
総括
本書『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』は、単なる就職ガイドではなく、定年後の人生そのものを見つめ直すための羅針盤となる一冊です。老後の経済的不安を解消することを目的に据えながらも、人生の新しい段階でどう働き、どう生きるかという問いに多面的に答えてくれます。そのため、読み終えた後にはお金や仕事の知識だけでなく、生活全体を設計するための考え方が身につく構成になっています。
本書が特に優れている点は、統計データと実際の声を組み合わせているところにあります。65歳以上640万人の就労データに基づき、客観的に「何が現実的か」を示す一方で、実際に働いている人々のインタビューを通じて「どう感じながら働いているか」を生々しく伝えています。数字だけでは見えないリアルな生活感を補完することで、読者が自分自身の将来をより具体的にイメージできる仕掛けになっています。
また、定年後の仕事を「収入の確保」だけでなく「健康の維持」「社会参加」「生きがいの再発見」といった広い視点でとらえている点も特徴的です。これにより、働くことを単なる義務としてではなく、自分の人生を豊かに彩る活動として位置づけることができます。こうした価値観の転換は、定年後を前向きに迎えるために欠かせない視座を提供しています。

この書籍は不安を安心に変えるだけでなく、新たな挑戦を後押しする役割を果たしています。
働くことへの柔軟な考え方を示し、現役時代とは異なる価値観で「働く」ことを楽しむ可能性を広げてくれるのです。
読者にとっては、自分らしい第二のキャリアを築くための出発点となり、定年後の人生を自らの手で豊かにデザインするきっかけを与えてくれる一冊といえるでしょう。
定年前後に読むべきおすすめの書籍

定年前後に読むべきおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 定年前後に読むべきおすすめの本!人気ランキング
- 夫と妻の定年前後のお金と手続き 税理士・社労士が教える万全の進め方Q&A大全
- 月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑
- ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う
- 1日1分読むだけで身につく定年前後の働き方大全100
- マンガでかんたん! 定年前後のお金の手続き ぜんぶ教えてください!
- 知らないと大損する! 定年前後のお金の正解 改訂版
- 定年前、しなくていい5つのこと 「定年の常識」にダマされるな!
- 定年後 50歳からの生き方、終わり方
- 図解即戦力 定年前後のお金と手続きがこれ1冊でしっかりわかる教科書
- 定年後 自分らしく働く41の方法

