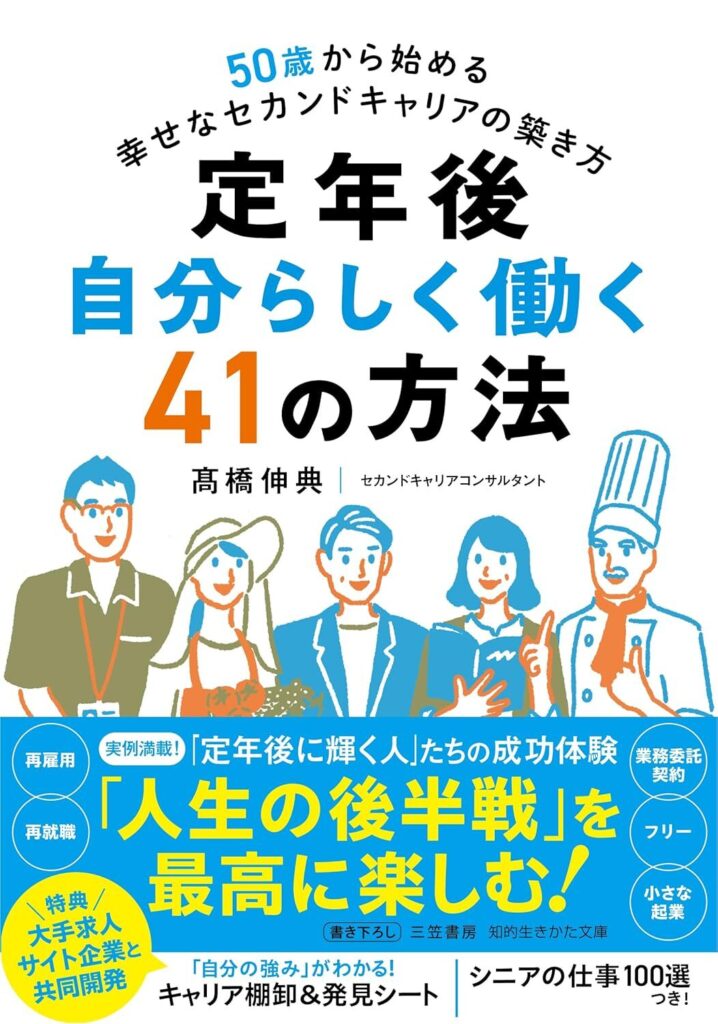
人生100年時代を迎え、「定年」はもはや“終着点”ではなく“新しいスタートライン”になりました。
本書『定年後 自分らしく働く41の方法』は、50歳からのキャリア再構築に悩む人々に向けて、幸せで実りある「第2の働き方」を提案する一冊です。
著者・髙橋伸典氏は、早期退職を機に苦労と再挑戦を重ね、現在はセカンドキャリアコンサルタントとして活躍しています。
その経験をもとに、誰にでも実践できる「自分らしい働き方の見つけ方」を体系的にまとめています。

本書の魅力は、理論だけでなく“リアルな成功事例”をふんだんに紹介している点にあります。
企業人から僧侶、新聞記者から行政書士へ転身した人など、定年後に輝く人々の姿が丁寧に描かれています。
さらに、「キャリア棚卸&発見シート」や「シニアの強み・仕事100選」といった実用ツールも掲載され、読むだけでなく、手を動かして自分自身の適職を探せる構成となっています。
これまでの仕事人生を「終わり」とするのではなく、「経験という資産」に変えていく。そのための考え方、行動、心構えがこの一冊に凝縮されています。
生活のために働く時代から、自分のために働く時代へ──。
定年後を“人生の後半戦の舞台”として輝かせたいすべての人に、確かな希望と行動の指針を与えてくれる書籍です。

合わせて読みたい記事
-

-
定年前後に読むべきおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】
定年が近づくと、これからの暮らしやお金、健康、働き方について考える機会が一気に増えます。 退職金や年金の受け取り方、再雇用やセカンドキャリアの選択、生活スタイルの見直しなど、人生の岐路で直面するテーマ ...
続きを見る
書籍『定年後 自分らしく働く41の方法』の書評

本書は、単なる「定年後の再就職マニュアル」ではありません。これは、人生の後半戦をもう一度“設計し直す”ための再構築プログラムであり、働くことの意味そのものを問い直す書です。
髙橋伸典氏は、企業勤めを経て独立した実践家として、数多くの中高年のキャリア相談に携わってきました。本書では、その経験から導き出された“再出発の成功パターン”を、理論よりも現場感覚で描いています。
理解を深めるために、以下の4つの視点で本書を詳しく掘り下げていきます。
- 著者:髙橋 伸典のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれを順に深掘りしていきます。
著者:髙橋 伸典のプロフィール
髙橋 伸典氏は、1957年に兵庫県で生まれ、同志社大学を卒業後、外資系製薬会社に入社しました。入社当初は営業職として全国を飛び回り、その後は人事や教育部門に異動。社員教育や採用、人材配置の分野で長年実務を積み、組織運営と人材育成の両面に精通するようになりました。企業での勤務はおよそ34年に及び、まさに“企業人の道”を歩んできた人物です。
50代半ばに差しかかる頃、会社の経営方針転換に伴い早期退職を余儀なくされました。長年勤め上げた会社を離れたことで、「この先、自分は何をして生きていくのか」という根源的な問いに直面します。再就職を試みるも、年齢の壁や環境の変化に阻まれ、なかなか思うような結果を得られませんでした。その経験こそが、彼を「セカンドキャリア支援」という新たな道へと導く転機となったのです。
その後、試行錯誤を重ねながら独立し、株式会社セカンドエールを設立。セカンドキャリアコンサルタントとして活動を開始しました。彼が掲げる理念は「誰もが“第二の職場”を笑顔で選べる社会をつくること」。再雇用・再就職・業務委託・小規模起業など、様々な選択肢を持つ50代・60代の人々に、現実的かつ希望の持てるキャリアの描き方を指南しています。
現在では、全国の自治体や企業で中高年向けキャリア研修を実施し、個別相談にも応じるなど幅広い支援を行っています。受講者は延べ5,000人を超え、TBS「ビビット」やNHKなどのテレビ番組出演、新聞・雑誌での取材も多数。講師としての活動だけでなく、執筆家としても精力的に活動し、「定年後の働き方」をテーマにしたセミナーやオンライン講座を多数手がけています。

彼の発言や文章からは、理屈よりも実践を重んじる姿勢が一貫しています。
机上のキャリア論ではなく、実際に「組織を出た後に何が起こるのか」を体験した人間の言葉として、読者に深い説得力を与えているのです。
本書の要約
『定年後 自分らしく働く41の方法』は、50歳以降の人生を再構築するための「働き方の教科書」です。単なる再就職のハウツー本ではなく、「どうすれば心豊かに働き続けられるか」という心理的・実践的な指針を体系的にまとめています。全体は七章構成で、読者が自分の強みを見つけ、将来の働き方を具体的に設計できるように段階的に導かれます。
第一章では、実際に定年後に新しい道へ進んだ人々の事例が紹介されます。新聞記者が行政書士へ転身した人、金融業から僧侶になった人、会社員からNPO活動に関わるようになった人など、いずれのエピソードも「人生の再出発」を象徴しています。これらの実例を通じて、読者は「働き方に正解はない」という柔軟な発想を得ることができます。
続く第二章では、再雇用や業務委託、再就職、小さな起業、社会貢献など、さまざまな働き方の形が紹介されます。それぞれのメリットとリスクが具体的に描かれ、「今の自分に合うスタイル」を考えるヒントが得られます。第三章では、「好き・できる・役立つ」の三条件から仕事を見直し、価値観に合った働き方を見つける重要性が説かれます。
特に注目すべきは第四章「キャリア棚卸&発見シート」です。髙橋氏が大手求人サイトと共同開発したツールを使い、これまでの経験やスキル、価値観を可視化し、自分の「本当の強み」を導き出すことができます。このシートを使うことで、読者は自分が何を得意とし、どんな場面で最も輝いていたのかを具体的に思い出せるのです。それは単なる自己分析ではなく、“自分という人材の再定義”にほかなりません。
後半では、心理面のサポートにも重点が置かれています。第五章では「働く不安を希望に変える考え方」を提示し、第六章では「サラリーマン脳から自立脳へ」という思考転換を促します。最終章では「ジョブクラフティング(仕事の再設計)」という新しい概念を紹介し、自分でやりがいを創り出す働き方が解説されています。つまり本書は、読むだけではなく「考え、行動し、変化する」ための実践書なのです。

本書の構成は、キャリア理論の“スーパーのライフスパン・ライフスペース理論”に基づいています。
これは「人生の中で役割を再定義し、成長し続けること」が幸福につながるとする考え方であり、本書はその実践モデルといえるでしょう。
本書の目的
本書の目的は、定年を「終わり」ではなく「始まり」として再定義することにあります。著者は、「働くことは、生活のためではなく、人生を楽しむためにある」と強調しています。定年前の働き方が“義務”であったなら、定年後は“自由と創造の時間”であるという視点を提案しているのです。
多くの人が定年後に感じる最大の不安は、「自分の存在意義を失うこと」です。長年、会社という組織の中で役割を果たしてきた人ほど、退職によって「自分はもう社会に必要とされないのではないか」と感じやすいといわれます。髙橋氏は、そのような心の空白を埋める方法として、「自分の強みを活かす」「誰かの役に立つ」「学び直して成長する」という三つの柱を掲げています。これらを循環的に回していくことで、定年後の人生はより豊かで充実したものになるのです。
また、本書は「ウェルビーイング(well-being)」という概念を中心に据えています。これは、心身の健康、社会的つながり、経済的安定などを含む「持続的な幸福状態」を意味します。著者は、働くことを通じてこのウェルビーイングを実現できると説いています。仕事をすることで身体が元気になり、人と関わることで孤独が防げ、社会との接点を保てる。つまり「働く=生きる」ことそのものが幸福の循環になるのです。

目的の本質は、“自己再雇用”という発想にあります。
誰かに雇われるのではなく、自分自身をもう一度“雇う”。これこそが真の意味でのセカンドキャリア形成です。
人気の理由と魅力
『定年後 自分らしく働く41の方法』が幅広い読者層から高く評価されている理由は、その「実践性」と「共感力」にあります。著者自身が普通の会社員として苦労を経験した人であり、上から目線の理屈ではなく、読者と同じ目線で語っている点が最大の魅力です。だからこそ、多くの読者が「これは自分の物語だ」と感じることができるのです。
また、本書のもう一つの特徴は、理論よりも“人の物語”を軸にしていることです。第一章に登場するさまざまな転身事例は、どれも現実に即しており、読者に希望を与えます。「自分のやりたいことをもう一度形にできるかもしれない」と思わせる力があります。これは、心理学でいう「社会的証明」の効果であり、他者の成功体験が自己効力感を高めるという重要な心理的要素です。
さらに、付録として収録された「シニアの強み100選」「シニアの仕事100選」も、本書の大きな価値です。自分の経験やスキルを整理する際のヒントとして非常に役立ち、「これまでの仕事人生も、まだまだ活かせる」と実感させてくれます。机上の理論ではなく、「明日から何をすればよいか」が具体的に見える構成になっている点が、多くの支持を集めている理由でしょう。
そして、終盤で語られる「マインドチェンジ」の章も印象的です。「上から目線をやめる」「若い人と関わる」「今さらを捨てる」といった言葉は、年齢や立場に関係なく心に響きます。これらは単なる心得ではなく、心理的なリフレーミング(認知の再構築)を促す具体的な行動指針です。このような前向きな思考転換が、本書に深い説得力を与えています。

この本が支持されるのは、ノウハウではなく“人間理解”が中心にあるから。
著者はキャリア支援を通じて、人がどうすれば再び誇りを持って生きられるのかを描いています。それがこの本の本質的な魅力です。
本の内容(目次)

本書は、50代からの人生を再設計するための「実践型キャリア指南書」です。全体はステップを踏むように構成されており、読者が自分の経験を見直し、新しい働き方を形にしていくプロセスを体系的に導いています。
内容は次の通りです。
- 第1章 「『定年後に輝く人たち』の成功例に学ぶ」
- 第2章 「自分らしい『幸せな働き方』を考えてみよう」
- 第3章 「そもそも『あなたに合う仕事』って何?」
- 第4章 「『キャリア棚卸&発見シート』で本当の適職が見つかる」
- 第5章 「『働く不安』が『希望』に変わる考え方」
- 第6章 「定年後は、この『マインドチェンジ』が武器になる」
- 第7章 「セカンドキャリアをさらに充実させるために」
- 巻末付録 「シニアの強み100選/シニアの仕事100選」
これらの章は、前半で“現実を知る”ための事例紹介、中盤で“自分を知る”ための分析、後半で“未来をつくる”ための行動理論という三段階構成になっています。
単なる成功体験の寄せ集めではなく、心理学・キャリア理論・社会構造の視点を統合的に整理している点が本書の特徴です。
第1章 「定年後に輝く人たち」の成功例に学ぶ
この章では、実際に定年後に新たな道を歩み、充実した人生を送っている人々の事例を紹介しています。読者は、さまざまな分野に再挑戦した人たちの姿を通して、「働き方は年齢で決まるものではない」という現実を知ることができます。
こうした事例に共通するのは、いずれも「自分らしさ」を基軸にしている点です。社会的地位や収入よりも、「やりたい」「役に立ちたい」といった内面的な動機を重視しているのです。この姿勢が、定年後のキャリアにおいて幸福感を得る最大の要因となっています。
本章は、読者にとって「定年=終わり」ではなく、「再出発のチャンス」という考え方を自然に受け入れられる導入部といえるでしょう。

キャリア心理学では、定年期以降の再出発を「再構築期(Reconstruction Stage)」と呼びます。
この段階では、過去の経験を活かしつつ、新たな意味や目的を見出すことが幸福度を高める鍵とされています。
第2章 自分らしい「幸せな働き方」を考えてみよう
ここでは、働き方の多様性に焦点が当てられています。再雇用や再就職、業務委託契約、小規模な独立、公務員への転身、社会貢献、農業など、さまざまな選択肢が紹介されています。特に「業務委託契約」や「小さな独立」といった現代的な働き方に関しては、著者自身の体験をもとに、リスクを最小限に抑える方法が具体的に語られています。これは、会社に残りながら徐々に独立の準備を進める“セーフティ・インディペンデンス”という発想に近く、安定と挑戦を両立できる現実的なアプローチです。
この章のもう一つの特徴は、「社会的意義」と「個人の満足」の両立を重視している点です。たとえば、公務員として地域のために働く道や、NPO活動・ボランティアへの参加など、経済的報酬以外の“心の報酬”を得る働き方も紹介されています。著者は、幸せとは「自分の強みが誰かの役に立つ瞬間」に感じるものであり、定年後はその体験を増やす時期だと説きます。
さらに、農業体験を通じて自然と関わる働き方や、趣味を副業化するケースも取り上げられています。これらの例は、働くことの意味を再定義するヒントに満ちています。つまり、幸福な働き方とは「経済的に報われる」ことよりも「心理的に満たされる」ことに重点を置くことだと、著者は読者に気づかせてくれます。

キャリア心理学では、幸福な働き方は“内的キャリア”と呼ばれます。
外的な報酬ではなく、内面の充実を追求する働き方が、定年後の持続的幸福を支えます。
第3章 そもそも「あなたに合う仕事」って何?
第三章では、自分に合った仕事を見極めるための判断軸が示されています。著者は「好き」「できる」「役立つ」という三つの条件がそろうことを、理想の仕事選びの基準としています。どれか一つでも欠けると、長続きせず、満足感も得にくいというのが髙橋氏の考えです。
さらに、「価値観との一致」が重要だと説かれています。どれほど条件が良くても、自分の人生観や働く目的に合わなければ、ストレスを感じやすくなります。たとえば、スピードを重視する職場で慎重さを大切にする人が働くと、能力を発揮できません。定年後のキャリアでは、自分のリズムや生き方に合う環境を選ぶことが、長く続けられる鍵となります。
著者はまた、「雇用か独立か」という選択にこだわる必要はないと述べています。重要なのは、自分にとって心地よい距離感で働けること。たとえ組織に属していても、主体的に働く意識を持てば、それは“自立した働き方”なのです。この章は、「自分を知る」ことこそがセカンドキャリアの出発点であるという気づきを与えてくれます。

“好き・できる・役立つ”の重なりは、キャリア理論でいう“スイートスポット”です。
ここを見つけた人ほど、モチベーションが長続きし、再就職後の満足度も高い傾向があります。
第4章 「キャリア棚卸&発見シート」で本当の適職が見つかる
第四章は本書の中でも特に実践的なパートであり、読者が自分の強みを“見える化”するためのツールが紹介されています。それが、著者が大手求人サイト企業と共同開発した「キャリア棚卸&発見シート」です。このシートを使えば、これまでの経験やスキル、価値観を整理し、自分がどんな分野で貢献できるのかを体系的に把握することができます。
ステップは3段階で進みます。まず、過去の職務経験や成果を振り返り、自分の得意分野や成功体験を洗い出します。次に、それらを「スキル」「人間的特性」「価値観」という3カテゴリーに分類し、自分の本質的な強みを明確化します。最後に、それらの強みを組み合わせて「自分だけの独自価値」を見つけ、適職の方向性を導き出します。
このプロセスの素晴らしい点は、単なる職務経歴の整理ではなく、“自分の人生の物語”を再構築できることです。
著者は、「経験に無駄はない」と強調しています。これまで積み重ねてきたキャリアを振り返ることで、過去が未来を照らすヒントになる──それがこの章の核心です。

このワークは、組織心理学者エドガー・シャインの「キャリア・アンカー理論」に基づいています。
人が持つ“動機・価値・才能”を言語化することで、ブレないキャリア軸を形成することができるのです。
第5章 「働く不安」が「希望」に変わる考え方
この章は、定年後に多くの人が直面する「不安」を解きほぐし、それを前向きなエネルギーへと変換するための“思考法”を解説しています。著者はまず、「定年後の生活費はいくら必要か」という現実的なテーマから読者に問いかけます。漠然とした心配の多くは、情報不足から生まれると指摘し、年金や生活費を数値化して可視化することが、最初の不安解消ステップだと説いています。数字で見える化することで、恐怖が曖昧な敵ではなく“解決できる課題”に変わるのです。
続いて、著者は「これまでの仕事人生を宝の山と捉える視点」を提示します。人は失ったものに目を向けがちですが、実際には定年まで積み上げてきた経験・知識・人脈・習慣など、すべてが再スタートの貴重な資源です。これらをどう活かすかが、希望を再構築するカギになります。特に、「褒められた経験」や「上手くいった場面」を振り返ることで、自分の価値を再認識し、行動意欲がよみがえるといいます。
本章の締めくくりでは、「あなたはオンリーワンの存在である」というメッセージが語られます。人と違うことを恐れず、個性を強みに変える視点を持つことこそ、定年後の精神的な自由につながるというのです。つまり、働くことは「不安の解消手段」ではなく、「希望を育てる手段」なのです。

心理学的に、不安は“制御できない状況”から生まれます。
著者が提案する「数値化」と「棚卸し」は、自己効力感(自分で状況を変えられる感覚)を高める代表的な手法です。
第6章 定年後は、この「マインドチェンジ」が武器になる
この章では、定年後に必要な“意識の切り替え”がテーマになっています。著者は、「スキルよりもマインドが成否を分ける」と断言し、特に会社員時代の価値観を引きずらないことの重要性を説いています。たとえば、「上から目線をやめて謙虚になる」「若い人と積極的に交流する」「まずは自分でやってみる」といった姿勢は、環境を変えるうえで決定的な違いを生みます。職場では肩書や役職が通用したとしても、社会に出た瞬間にリセットされるため、フラットな関係構築が成功の第一歩になるのです。
さらに、著者は「サラリーマン脳から自立脳へ」というキーワードを提示します。これまで会社に守られていた立場から、自分の判断で行動する「自立型思考」へのシフトが求められます。そのためには、成功体験よりも失敗談を語れる人間になることが大切だと述べています。失敗を共有できる人ほど信頼され、周囲とのつながりが強化されるというわけです。
本章の最も核心的なメッセージは、「柔軟さこそ最大の武器」という点です。特にシニア世代にとって、過去の常識を手放し、新しい価値観に適応する力は、どんな資格や経験よりも強力な“成功因子”になります。著者はそれを「人生100年時代の必須スキル」と表現しています。

マインドチェンジはキャリア理論でいう“アンラーニング(学びほぐし)”の実践です。
過去の前提を意識的に捨てることが、新しい学びを吸収する土台になります。
第7章 セカンドキャリアをさらに充実させるために
最終章では、セカンドキャリアを「持続的に楽しむ」ための考え方が紹介されています。ここでのキーワードは、「ジョブクラフティング」「ウェルビーイング」「ありがとうの数」という三つです。これらは単なる仕事術ではなく、人生を豊かにする哲学として描かれています。
「ジョブクラフティング」とは、与えられた仕事を自分なりに意味づけ、やりがいを再設計する手法です。たとえば、同じ業務でも「人の役に立つ」と意識を変えるだけで、仕事のモチベーションが大きく変わります。次に「ウェルビーイング」は、心身の健康・人間関係・生きがいのバランスを取る考え方です。著者は、定年後の働き方こそ、この三要素を調和させる絶好の時期だと述べています。
最後に登場する「ありがとうの数」は、本書の締めくくりにふさわしい象徴的な言葉です。自分の働きが誰かの感謝につながることこそ、人生の最終的な報酬だと説かれています。収入や地位を超えて、人とのつながりや貢献が幸福をもたらすというメッセージに、多くの読者が共感を覚えるでしょう。

ジョブクラフティングとウェルビーイングは、近年のポジティブ心理学と組織開発の中心概念です。
自分の仕事に意味づけを加える人ほど、幸福度と生産性が高いという研究結果もあります。
巻末付録 「シニアの強み100選/シニアの仕事100選」
対象読者

本書は、定年を前にして「これからの働き方」を真剣に考え始めた中高年層に向けて書かれています。現代では「定年=引退」ではなく、「もう一度、自分らしい働き方を選び取るチャンス」です。
ここでは、本書が特に役立つ5つの読者層を紹介します。
- 50歳前後でセカンドキャリアを模索している人
- 定年後も働き続けたいが方向性が定まらない人
- 再就職・再雇用・起業を考えている人
- 自分の強み・適職を見つけたい中高年層
- 人事・再就職支援担当者・キャリアコンサルタント
どの立場にいても、「これからの人生を自分の意思でデザインする」ための指針が、本書には詰まっています。
それぞれの立場から見た活用ポイントを解説していきましょう。
50歳前後でセカンドキャリアを模索している人
50歳を迎える頃、多くの人がキャリアの節目に立ちます。会社でのポジションも安定し、ある程度の成果を上げてきた一方で、「このまま同じ仕事を続けるのか」「新しい挑戦をするのか」といった葛藤を抱く時期でもあります。本書は、まさにそうした迷いを持つ人に最適です。著者自身が57歳で会社を辞め、再就職や独立を経て「自分らしい働き方」を確立した経験をもとにしており、同世代の読者にリアリティと安心感を与えます。
また本書では、実際に定年後に輝いている人たちの事例を通して、「年齢を理由に諦めなくてもいい」という確かな希望を提示しています。たとえば、新聞記者から行政書士になった人や、金融マンから僧侶になった人など、思い切った転身を果たしたケースが紹介されており、自分の過去のキャリアを“資産”として再定義するヒントが得られます。これにより、「何歳からでもキャリアは再構築できる」という実感を持つことができるのです。

50代は“キャリアの再構築期”です。
これまで積み上げた経験を再編集することで、次の10年の働き方に新しい意味づけを与えることができます。
定年後も働き続けたいが方向性が定まらない人
「まだ働きたいけれど、何をしたらいいのかわからない」――そんな人にとって、本書は羅針盤のような存在になります。著者は、再雇用・再就職・独立・社会貢献など、多様な働き方を具体的に紹介し、それぞれの利点と注意点を整理しています。特に「会社にいながら独立準備を進める方法」や「リスクの少ない副業スタイル」などは、現実的な選択肢として多くの読者に参考になる内容です。
さらに本書の特徴は、“考える”だけで終わらせない点にあります。「キャリア棚卸&発見シート」を使って自分の強みを可視化し、次のステップへと行動を促します。方向性が見えずに立ち止まっている人でも、シートを通して自分の価値を再確認することで、「自分にもまだできることがある」という前向きな気持ちを取り戻せるでしょう。

キャリアの再設計において、“方向性の明確化”は最初の一歩です。
迷いがあるのは悪いことではなく、むしろ自分を見つめ直すためのサインです。
再就職・再雇用・起業を考えている人
定年後の働き方を選ぶ上で、多くの人が直面するのが「雇われ続けるか」「独立するか」という選択です。本書は、そのどちらを選んでも後悔しないための判断基準を与えてくれます。著者自身、再就職と独立の両方を経験しており、その過程で感じた葛藤や現実的な課題を率直に語っています。単なる成功談ではなく、「再雇用の壁」や「独立のリスク」なども包み隠さず解説している点が信頼できます。
また、再就職希望者には「シニア世代が求められる職種や業界の特徴」、起業志向の人には「小さく始めてリスクを抑える独立法」など、具体的な戦略が提示されています。つまり本書は、“働き方を選ぶためのマニュアル”というより、“自分で選び取るための思考ツール”なのです。

定年後のキャリア設計で大切なのは、“安全な選択”ではなく、“納得できる選択”。
その基準を持つことで、迷いは減り、行動が明確になります。
自分の強み・適職を見つけたい中高年層
長年働いてきたにもかかわらず、「自分の強みがわからない」という中高年は少なくありません。本書は、そうした人が再び自信を取り戻すための仕組みを提供しています。特に注目すべきは、著者が開発した「キャリア棚卸&発見シート」です。これを使うことで、過去の職務経験や人間関係、成功体験から自分の“活かせる資質”を言語化できます。単なる自己分析ではなく、次のキャリアに直結する「実践的な自己理解」を促す内容です。
さらに、著者は“強みを掛け合わせて独自性を生み出す”という方法を提唱しています。たとえば、営業スキルと地域活動の経験を組み合わせれば、地方ビジネス支援の専門家になれる、といった具合です。こうした発想は、自分の強みを新しい文脈で活かす力を養い、キャリアの幅を広げることにつながります。

キャリアの再設計では、“強みの発見”よりも“強みの活用”が重要です。
自分の価値を社会のニーズと結びつける視点が、適職発見の鍵になります。
人事・再就職支援担当者・キャリアコンサルタント
この本は、定年後を迎える本人だけでなく、シニア世代を支援する立場の人にとっても貴重な資料となります。人事担当者やキャリアコンサルタントにとって課題となるのは、「本人の意欲を引き出し、自信を回復させること」です。本書には、実際に中高年がどのような不安を抱え、どのようなきっかけで希望を見出したかという生の事例が多数収録されており、支援現場での理解を深める教材として活用できます。
さらに、キャリア棚卸シートや「シニアの強み100選」といったツールは、支援者がクライアントと共にワークを行う際の実践的素材としても有効です。キャリア支援のプロが使う理論にも通じる内容であり、クライアントの自己効力感を高める面談技法のヒントも豊富です。支援者自身が“定年後キャリア”という新しい領域を理解するための一冊といえるでしょう。

キャリア支援の本質は、“答えを与えること”ではなく、“気づきを促すこと”。
この書籍は、そのための対話の“きっかけの本”として最適です。
本の感想・レビュー

これでいいんだと背中を押された
定年を迎えてからの数年間、何をすればいいのか分からず、日々の小さな不安に押しつぶされそうでした。仕事を辞めて時間はできたものの、社会とのつながりを失ったような感覚に戸惑っていたのです。そんなときに出会ったこの本は、まるで霧の中に差し込む光のように感じました。著者が「定年後は人生を楽しむために働く」と語る一文が、心にまっすぐ届きました。
読んでいくうちに、「働くこと=生活のため」という固定観念が少しずつほぐれていくのを感じました。これまでの仕事中心の価値観から離れ、「自分のために働く」という発想を受け入れたとき、肩の力が抜けました。仕事をすることが義務ではなく、選択であり、楽しみである――その気づきが、自分の中で新しいスタートラインを引いてくれたように思います。
そして何より、著者自身が「普通のサラリーマンだった」と語っていることに安心しました。特別な才能や人脈がなくても、自分らしい働き方は見つけられるというメッセージに、自然と前を向く力が湧いてきました。この本を読み終えたとき、「焦らなくてもいい、今の自分のままで進めばいい」と、心の中で小さくつぶやいていました。
働く意味を人生視点に戻せた
私は定年を数年後に控え、これからの人生設計をどうするか考え始めていましたが、頭の中は「収入」「老後資金」「再雇用」など、数字ばかりでいっぱいでした。そんなときにこの本を読み、「働くとは、生き方そのものをデザインすること」という考え方に出会いました。その瞬間、視点が180度変わったような感覚を覚えました。
著者が語る「働くことは人生を楽しむための行為」という言葉は、単なる理想論ではなく、数々の具体例を通じて現実味をもって伝わってきます。再雇用、公務員、独立、ボランティアといった選択肢を並列に示しながら、「どの道にも“幸せ”がある」と教えてくれるのです。読後には、「自分が何を得たいのか」よりも「どう生きたいのか」という問いが自然と浮かんできました。
今はまだ、はっきりした答えは出ていません。でも、この本をきっかけに、“働く=自分の人生を再構築する行為”だと捉えられるようになりました。焦りではなく希望をもって、これからを見つめられるようになったことが、私にとって最大の収穫です。
状況が変わっても挑戦したくなる
私は長年務めた会社を早期退職し、正直なところ途方に暮れていました。再就職は難しく、年齢の壁を痛感していた時期に、この本に出会いました。読んでいて印象的だったのは、どんな状況からでも再スタートを切った人たちの事例が丁寧に紹介されている点です。それが“特別な人”ではなく、普通の人たちだということに勇気をもらいました。
とくに心に残ったのは、「人事マンが給食の調理員に転職した」り、「金融マンが僧侶になった」エピソード。彼らは年齢を理由に立ち止まらず、自分の中の“もうひとつの願い”に素直に従って動いています。その姿勢に触れることで、「変化を恐れず挑戦していいんだ」と心の中で火がともりました。
本書を読み終えた今、私は新しい挑戦に前向きになれています。小さな一歩でもいい、何かを始めてみようという気持ちが芽生えました。
過去が宝になる瞬間を感じた
この本を読みながら、長年積み上げてきた自分のキャリアを初めて“誇れるもの”として見つめることができました。正直、私はこれまでの仕事人生を“普通”だと思っていました。特別なスキルも成果もない、平凡なサラリーマン生活。でも、「キャリア棚卸&発見シート」を通じて、自分の経験が他者にはない強みだと気づかされたのです。
著者は、「経験には必ず意味がある」と繰り返し語ります。その言葉に導かれながら、これまでの職務経歴や人との関わりを振り返ると、自分が築いてきた小さな信頼や努力が一つひとつの価値に変わっていくのを感じました。それはまるで、心の中で眠っていた宝箱の蓋を開けるような体験でした。
自分なりのキャリア地図が見えてきた
私はこの本を、まるで“人生再設計の教科書”のように感じました。4章の「キャリア棚卸&発見シート」で自分の強みを言語化する過程は、単なる自己分析を超えた“再発見”の時間でした。書きながら、「自分はこういう場面で力を発揮していたのか」と、忘れていた自分に再会するような感覚を覚えました。
特に印象に残ったのは、「強みを掛け合わせるとオンリーワンの強みになる」という考え方です。単体では平凡に思えるスキルも、他の要素と組み合わせることで独自性が生まれる。この視点を得たことで、キャリアに対する視野が一気に広がりました。今では、“できないこと”よりも“できることの組み合わせ”に意識が向いています。
この本を読み終えて感じたのは、人生後半を不安ではなく“設計”できるという安心感です。自分の人生を地図のように整理し、未来の行き先を自分の手で描く――そんな前向きな気持ちが湧いてきました。
毎日の習慣づくりが楽しくなった
読み進めるうちに感じたのは、「大きな転職や起業をしなくてもいい」という安心感でした。本書には、働き方を変えるだけでなく、「暮らし方を変える」ためのヒントが詰まっています。著者が語る「働くことは生活を楽しむための手段」という言葉を読んだとき、日常の一つひとつが仕事の延長線上にあると気づかされました。
本の影響で、私は日々の習慣を見直しました。朝起きる時間を少し早めて、読書や散歩に時間を使うようになったのです。それだけで、1日のリズムが整い、気持ちにも張りが出ました。働くことの原点は、こうした“小さな積み重ね”なのだと実感します。
棚卸シート×ワークが実践を後押し
4章で紹介される「キャリア棚卸&発見シート」は、読書という受け身の行為を“行動”に変える強力な仕組みでした。読者が自分の経験や強みを具体的に書き出し、整理していく過程は、まるで専門家と対話しているような感覚になります。項目に沿って考えるうちに、これまで意識してこなかった自分の得意分野や価値観が浮かび上がってきました。
特に印象的だったのは、「強みを掛け合わせてオンリーワンの強みにする」というステップ。自分の中にある点と点をつなげるようにして、新しい可能性を発見していく感覚はワクワクします。棚卸をしているうちに、長年培ってきた小さなスキルや習慣が、大きな力になり得ることを実感できました。
このシートを通して感じたのは、「年齢を重ねたからこそ、できる仕事がある」という確信です。経験の蓄積は武器であり、それを言語化できるかどうかが大切なのだと学びました。この章を読み終えるころには、私自身の行動計画が自然と描かれていました。
働き方の多様な選択肢を示す
この本の魅力のひとつは、働き方の選択肢が驚くほど幅広く提示されていることです。再雇用、業務委託、再就職、公務員、独立、農業、社会貢献――そのどれもが実在する事例とともに紹介され、現実味があります。読み進めるうちに、「働くことの正解は一つではない」という考えが自然に腑に落ちました。
私は特に、「自分の好きなことを仕事にする」という章に惹かれました。これまでの人生では、好きなことを仕事にするなんて夢物語だと思っていましたが、著者の語る“リスクを抑えた独立”の方法を知ることで、現実的な選択肢として見えるようになりました。
まとめ

この記事の締めくくりとして、本書の魅力を整理しておきましょう。『定年後 自分らしく働く41の方法: 50歳から始める幸せなセカンドキャリアの築き方』は、単なる「働き方の提案書」ではなく、読者一人ひとりが“自分の人生を再構築するための実践書”です。
以下の3つの観点から、その価値を振り返ります。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれ詳しく見ていきましょう。
この本を読んで得られるメリット
ここでは、本書を手に取ることで得られる代表的な利点を整理してみましょう。
自分の“強み”と“可能性”を再発見できる
本書の最大の魅力は、自己分析の具体的な方法が紹介されていることです。著者が大手求人サイト企業と共同開発した「キャリア棚卸&発見シート」を使えば、これまでの経験・スキル・価値観を整理しながら、自分が本当に得意としてきたことや、他者から評価されてきた要素を明確にできます。単なる振り返りではなく、“これからのキャリアに活かせる強み”を可視化できるのが特徴です。長年会社で培ったスキルも、角度を変えて見れば新しい仕事の武器になる──その発見が、この本を読むことで得られる最初の成果です。
現実的で多様な働き方の選択肢が見つかる
本書では、再雇用・再就職・業務委託・起業・社会貢献活動など、41通りの働き方が事例として紹介されています。しかもそれぞれの事例が「なぜその道を選んだのか」「どうやって始めたのか」「どんな困難を乗り越えたのか」というストーリー形式で描かれており、自分の状況に照らし合わせやすい構成になっています。抽象的なアドバイスではなく、実際に行動した人々の“生の声”が載っているため、読むことで「自分にもできるかもしれない」という具体的なイメージが湧いてきます。
不安を“希望”に変える思考法が身につく
定年後に働くことへの不安は、経済的な問題だけでなく、心理的な面にも大きく関わります。本書の第5章「働く不安が希望に変わる考え方」では、年金・生活費・やりがい・社会とのつながりといったテーマを掘り下げ、どのように心の軸を立て直すかを紹介しています。「お金のために働く」から「自分のために働く」へと意識を変えることで、働くことそのものが人生の喜びに変わっていく。このマインドセットの転換は、定年後の幸福度を大きく左右する重要な要素です。
実践的なツールと行動への後押しが得られる
理論や概念にとどまらず、すぐに行動に移せる仕組みが整っているのも本書の特長です。「キャリア棚卸シート」に加えて、「シニアの強み100選」「シニアの仕事100選」など、具体的な事例リストが巻末に掲載されています。これらは単なる参考資料ではなく、自分に合った働き方を見つけるための“行動のチェックリスト”として活用できます。読後には、実際にシートを記入しながら、自分の将来設計を具体的に描けるようになるでしょう。
自分らしい“生き方”を再定義できる
この本が伝えたい本質は、「働くことは人生を楽しむこと」だというメッセージです。定年後を“余生”ではなく“新しい始まり”として捉え直すことで、自分の生き方を根本から再定義できます。これまで家族や組織のために働いてきた人が、“自分のために働く”という生き方へと舵を切る。そうした意識の変化が、心の自由をもたらし、セカンドキャリアをより充実したものにします。

この本の真の価値は、“働き方”を超えて“生き方”を見直すきっかけを与えてくれることです。
キャリアとは単なる職業の話ではなく、人生そのものの設計図なのです。
読後の次のステップ
本書を読み終えたあと、最も大切なのは「読んで終わり」にしないことです。『定年後 自分らしく働く41の方法』は、“行動に移してこそ真価を発揮する実践書”です。
ここでは、読了後にどんなアクションを取れば、より効果的にセカンドキャリアの構築へとつなげられるのか、その具体的なステップを3つの方向から紹介します。
step
1キャリアの棚卸を実践する
まず取り組むべきは、著者が推奨する「キャリア棚卸&発見シート」を使った自己分析です。これまでの職務経験や人生経験を整理し、「自分が何を得意としてきたのか」「どんな環境で力を発揮してきたのか」を可視化することが重要です。キャリア棚卸は、いわば自分自身の“資産リスト”を作る作業。これを行うことで、単に職種を選ぶのではなく、「自分の強みをどう活かすか」という視点から次の働き方を選べるようになります。書き出す過程で、自分でも意識していなかったスキルや経験が浮かび上がり、自信の再構築にもつながるでしょう。
step
2行動に移す小さなチャレンジを始める
次のステップは、学んだ内容を小さく試してみることです。たとえば、副業やボランティア、地域活動など、リスクの少ない行動を通して自分の興味を確かめることから始めましょう。本書で紹介されている成功事例の多くも、“いきなり独立”ではなく“小さな一歩”からスタートしています。大きな決断をする前に、まずは新しい分野に触れてみることで、失敗を恐れず経験値を積むことができます。行動の中で得た実感こそが、次のキャリアを形成する基礎になるのです。
step
3学びを継続し、人とのつながりを育てる
そして最後に、学びを止めず、社会との接点を保ち続けることが大切です。セカンドキャリアの成功は、スキルだけでなく「人脈」と「情報感度」にも左右されます。セミナーへの参加やオンラインコミュニティへの加入など、同世代の仲間や専門家とのネットワークを広げることで、チャンスは格段に増えます。本書を通して得た考え方を日常の中で意識的に活かし、自分の成長を実感できる環境を整えることが、長期的な充実感につながるのです。

キャリアの転換期では、完璧な準備よりも“試行”が最も価値ある学びになります。
小さな行動を重ねることこそが、セカンドキャリア成功の最短ルートです。
総括
『定年後 自分らしく働く41の方法』は、定年を単なる“終着点”ではなく、“人生の第二幕の始まり”として再定義する一冊です。著者・髙橋伸典氏が自身の体験と数多くの事例をもとに語る内容は、現実的でありながらも前向きなエネルギーに満ちています。本書の本質は、「働くことを通じて、人生をより豊かにする」というメッセージにあります。年齢を重ねても、社会に貢献し、自己実現を果たすことは決して遅くありません。そのための“思考と行動の地図”を提示してくれるのがこの本です。
この書籍の価値は、単なるキャリア論にとどまらない点にあります。再雇用や再就職といった制度的な選択肢だけでなく、起業・ボランティア・地域活動といった“自分らしい生き方”を具体的に描けるよう導いてくれます。特に「キャリア棚卸&発見シート」は、読者が自分の人生を客観的に見つめ直し、“どんな未来を生きたいのか”を自分の言葉で定義するきっかけとなるでしょう。
さらに本書は、心の持ち方にも焦点を当てています。経済的不安や健康への心配といった現実的な課題にも触れつつ、それらを乗り越えるための心理的なマインドチェンジを提示しているのです。「働くことを人生の楽しみとする」「ありがとうの数だけ幸せになれる」という哲学は、定年世代だけでなく、すべての働く人に通じる普遍的なテーマです。

本書は「定年後も自分らしく生きる」ための最良の道しるべと言えます。
読むことで、自分の経験が価値に変わり、年齢が制約ではなく可能性になる。
そんな意識の変化をもたらしてくれる本書は、キャリアに悩むすべての中高年にとって、人生の再スタートを後押しする“羅針盤”となるはずです。
定年前後に読むべきおすすめの書籍

定年前後に読むべきおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 定年前後に読むべきおすすめの本!人気ランキング
- 夫と妻の定年前後のお金と手続き 税理士・社労士が教える万全の進め方Q&A大全
- 月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑
- ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う
- 1日1分読むだけで身につく定年前後の働き方大全100
- マンガでかんたん! 定年前後のお金の手続き ぜんぶ教えてください!
- 知らないと大損する! 定年前後のお金の正解 改訂版
- 定年前、しなくていい5つのこと 「定年の常識」にダマされるな!
- 定年後 50歳からの生き方、終わり方
- 図解即戦力 定年前後のお金と手続きがこれ1冊でしっかりわかる教科書
- 定年後 自分らしく働く41の方法

