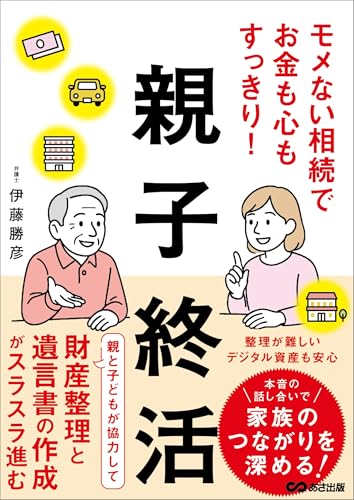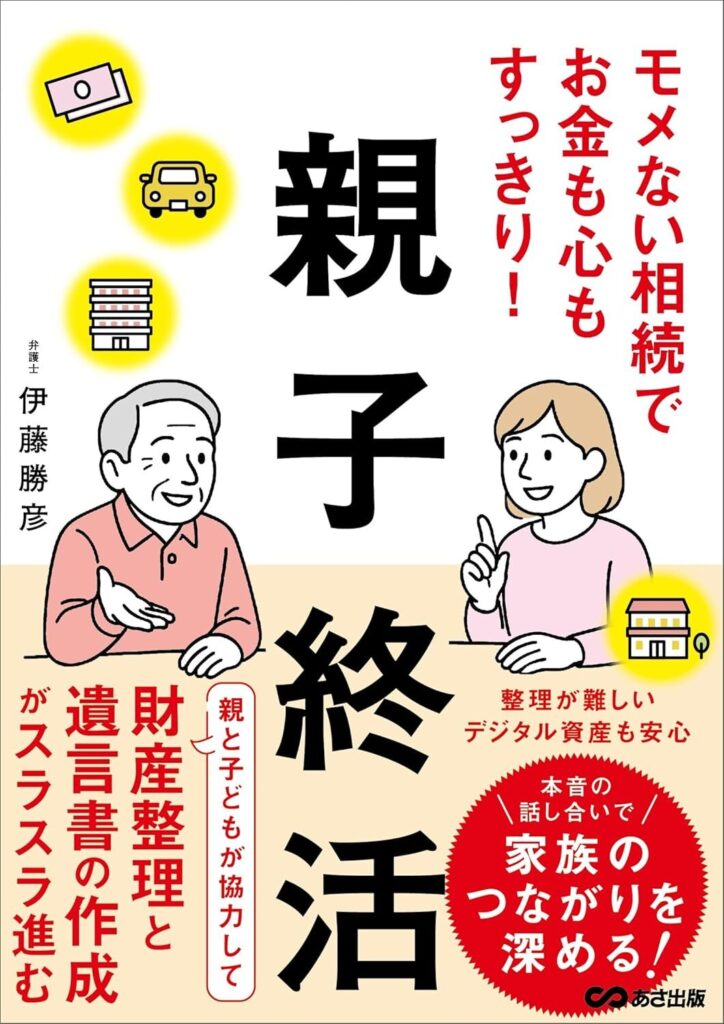
終活という言葉が一般化して久しいものの、「何から始めればいいのかわからない」「親にどう切り出してよいか迷う」という声はいまだに多く聞かれます。
そんな不安を抱くすべての家族に向けて書かれたのが、弁護士・伊藤勝彦氏による『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』です。
本書は、法律の専門家として数多くの相続・遺言案件に携わってきた著者が、“親子で一緒に進める終活=親子終活”の重要性を説きながら、実践的なステップをわかりやすく示しています。

この本の最大の特徴は、「法的な知識」と「家族のコミュニケーション」を両立させている点にあります。
エンディングノートの書き方、遺言書の作成、相続税の基礎知識といった制度的な部分だけでなく、親子で話し合うきっかけ作りや、心情面での配慮にまで踏み込んでいるのが魅力です。
たとえば、親の気持ちを引き出すための質問例や、兄弟間の誤解を防ぐための会話法など、現場経験に基づく具体的なアドバイスが満載です。
“終活=死の準備”というイメージを払拭し、家族の絆を深める前向きな活動として再定義しているのも本書の特徴です。
読後には、「終活は怖いものではなく、自分と家族を守る愛情の形なのだ」と実感できるはずです。
法律に詳しくない人でもすぐに行動に移せる構成になっており、これから終活を始めたい人、親との関係をより良くしたい人にとって、まさに“最初の一冊”としてふさわしい内容です。

合わせて読みたい記事
-

-
終活について学べるおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年】
人生の終わりをより良く迎えるために、自分の意思で準備を進める「終活(しゅうかつ)」。 近年では、50代・60代だけでなく、30代・40代から学び始める人も増えています。 終活は、死に向き合うことではな ...
続きを見る
書籍『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』の書評

弁護士として1,000件を超える相続・終活相談を受けてきた伊藤勝彦氏が提案する「親子終活」は、単なる“財産整理”ではなく、“家族関係の再構築”を目的とした終活の新しい形です。本書『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』は、法務の現場経験に裏打ちされた確かな知識をベースにしながらも、専門書というより「家族の教科書」として、読みやすさと実践性を兼ね備えた一冊です。
ここでは、より深く本書の魅力を理解するために、以下の4つの視点から丁寧に解説します。
- 著者:伊藤勝彦のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれの項目を通して、本書が単なる終活のガイドではなく、“家族をつなぐ実践型の人生デザイン書”であることを明らかにしていきます。
著者:伊藤勝彦のプロフィール
伊藤勝彦(いとう・かつひこ)氏は、弁護士法人みお綜合法律事務所の弁護士であり、相続・遺言・家族信託・成年後見など、いわゆる「人生の終盤に関わる法務」を専門とする実務家です。2000年に弁護士登録をして以来、25年以上にわたり個人の終活や相続問題に携わり、これまでに寄せられた相談件数は1000件を超えます。その膨大な経験をもとに、依頼者一人ひとりの「家族の事情」や「思い」を汲み取りながら、単なる法律的な解決ではなく、“人と人との関係を再構築する支援”を行ってきました。
伊藤氏の特徴は、法律家としての厳密さと同時に、心理的な洞察力を持ち合わせている点にあります。多くの弁護士は「法的に正しいかどうか」に重点を置きますが、伊藤氏は「人間関係としてどうすれば平和にまとまるか」という視点を欠かしません。たとえば、遺言書の作成ひとつにしても、「文面の正しさ」だけでなく「家族が納得して受け入れられる内容か」を丁寧に検討します。この姿勢は、彼の掲げる信条「納得と調和」に象徴されています。法律を“争いの道具”ではなく、“絆を守るための手段”として使うという哲学が、すべての実務に貫かれているのです。
また、伊藤氏は単に法律を語るだけではなく、一般市民の生活に密着した啓発活動にも力を注いでいます。セミナーや講演活動では、法律を難解にせず、誰もが理解できる言葉に翻訳して伝える工夫を欠かしません。たとえば、「相続とは、財産の受け渡しではなく“想いの引き継ぎ”です」と説明し、法的概念に温かみを与えています。その柔らかい語り口と温厚な人柄が多くの依頼者に安心感を与え、弁護士という職業にありがちな「堅い」「近寄りがたい」というイメージを一新しています。

伊藤氏は、いわば「法律の翻訳者」です。
法律という難解な言語を、一般の人の感情や生活に通じる言葉へと置き換え、家族の会話の中に落とし込む力があります。
本書の要約
『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』は、タイトルの通り「揉めない相続」と「家族の安心」を両立させるための実践書です。しかし、この本の魅力は単なる“遺言書の書き方”や“税金の知識”といったハウツーにとどまりません。最大の特徴は、「家族が共に進める終活」という新しい考え方にあります。
著者はまず、終活を「一人で抱え込むもの」と捉えている人が多いことを指摘します。たとえば、エンディングノートを書こうとして途中で挫折してしまう人、親が高齢になっても話を切り出せない子どもなど、終活を始めたくても進まないケースが数多くあります。伊藤氏は、そうした「進まない終活」の根本原因を“家族間のコミュニケーション不足”と見抜きます。だからこそ本書では、親と子が一緒に準備する“親子終活”を提案しているのです。
全7章構成の本書では、初めて終活に取り組む人でも迷わないよう、具体的な順序が示されています。第1章では「なぜ今、親子終活なのか」を解き、第2章では参加者の決め方やノートの作り方、第3章・第4章では親と子それぞれの立場から実際に取り組むべき内容を紹介します。その後、第5章以降では、成年後見制度や任意後見、信託契約、死後事務委任契約、家族信託など、より制度的で専門的な内容へと進んでいきます。さらに最終章では、葬儀やお墓の準備までを包括的に扱い、家族が「死後のこと」を安心して話し合える道筋を提示します。
この本は“読む終活本”ではなく、“実践する終活本”です。具体例やケーススタディが豊富で、法律の手続きや制度がどのように現実に役立つのかがリアルに描かれています。また、「うまくいった親子終活の事例」などのコラムが随所にあり、成功事例を通じてモチベーションを高める構成も巧みです。

本書の構造は、法的知識を“教科書的”に並べるのではなく、実際の家族関係をモデルにして展開されています。
つまり、理論と現実の橋渡しが非常に上手い。
読者は自然と「自分の家庭ではどうすればいいか」を考えながら読み進めることができるのです。
本書の目的
この本の目的は明確で、「家族が揉めないようにするための、心と手続きの準備」を支援することです。終活という言葉は、一般的に「老後の備え」や「遺言書の作成」といった手続き的なイメージで捉えられがちですが、伊藤氏はそれを「家族全員で取り組む共同プロジェクト」と位置づけています。
その背景には、著者が実際に経験してきた多くの相続トラブルの事例があります。たとえば、遺言書がないまま親が亡くなり、兄弟が対立して関係が断絶してしまったケース。あるいは、親の判断能力が衰えてから後見人を選ぼうとしても、すでに手遅れだったケース。これらの問題はすべて「事前の話し合い不足」が原因で起こると著者は断言します。だからこそ本書は、“事前対策”を徹底的に重視しています。
本書の目的は、「法律を学ぶこと」ではなく、「家族が納得する仕組みを作ること」にあります。読者が制度を理解するだけでなく、実際に家族と話し合い、合意形成を図ることをゴールとして設計されています。伊藤氏はそのための手段として、エンディングノートや家族会議、デジタル資産の整理、葬儀の事前準備など、非常に現実的なステップを提示しています。つまり、“知識を知識で終わらせない”構成なのです。
また、本書では「終活は不安を減らすためのものではなく、希望を見出すためのもの」だと繰り返し強調されています。親の想いを理解し、子が支え、世代を超えて絆を深める――そのプロセスそのものが、終活の最大の価値であると説いています。

法制度を整えるだけでは家族は幸せになりません。重要なのは「心の納得」です。
本書は、手続きの合理性と家族の感情のバランスを取ることを目的としており、まさに“実践心理法務”の教科書といえるでしょう。
人気の理由と魅力
この本が多くの読者に支持されている最大の理由は、「専門性が高いのに、読みやすく、行動につながる」点にあります。弁護士が書いた本というと、堅くて難解な印象を持たれがちですが、本書はまるで“家族の相談に乗ってくれる温かい先生”のような語り口で進みます。専門用語が出てくると、必ず身近な例えや図解を交えて説明してくれるため、法律に苦手意識を持つ人でもスムーズに理解できます。
また、他の終活書と決定的に異なるのは、「感情面へのアプローチ」が非常に丁寧な点です。たとえば、「親に終活の話を切り出せない」「子どもに老後の話をしたくない」といった葛藤に対し、心理的な準備の整え方や、言い出すタイミングの工夫まで解説されています。まさに、心理カウンセリングと法的アドバイスが融合したような内容です。
さらに本書の魅力は、制度の横断的な扱いにもあります。相続税、生前贈与、家族信託、成年後見制度、死後事務委任契約など、複数の法律分野を一冊に整理し、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく比較しています。普通なら複数冊の専門書を読まないと理解できない内容を、家庭の実情に即した形でコンパクトにまとめているのです。
読後には、「知識が増えた」だけでなく、「家族と話してみよう」と思える心理的変化が起こります。つまりこの本は、“行動を生み出す終活書”です。読者の多くがレビューで「読み終えた後にすぐ家族と話したくなった」と述べているのは、その設計の巧みさを物語っています。

この本の真価は、「専門知識を心の通訳に変える力」にあります。
制度を説明するだけでなく、どうすれば家族が“納得して動けるか”までデザインされている。
その点で本書は、実務家・一般読者の双方から信頼を得ている希少な一冊です。
本の内容(目次)

本書『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』は、終活を「一人で抱え込む作業」から「家族全員で取り組む共同プロジェクト」へと転換させる一冊です。全体は7章構成で、親子終活の基本から制度活用、そして葬儀・お墓の準備まで、すべてのプロセスを実践的に学べるように設計されています。
それぞれの章では、次のテーマが展開されています。
- 第1章 今日から始める「親子終活」
- 第2章 お金も心もすっきりする「親子終活」の始め方
- 第3章 親が主体となって進めること
- 第4章 子が主体となって取り組むべきこと
- 第5章 いざというときに備える! 終活に使える制度と手続き
- 第6章 家族を困らせないための死後に備えた制度の使い方
- 第7章 将来への安心につながる葬儀・埋葬・お墓の決め方
それぞれ詳しく見ていきましょう。
第1章 今日から始める「親子終活」
この章では、終活を「今すぐ始めるべき理由」と、「親子で取り組むことの意義」が解説されています。
著者はまず、「終活は人生の終わりの準備ではなく、“安心して生きるための活動”である」と定義しています。多くの人が「まだ早い」と思って先延ばしにしてしまいますが、判断能力が低下してからでは手遅れになりがちです。終活を早く始めることで、相続や介護などのリスクを未然に防げるだけでなく、心の整理も自然に進むのです。
さらに、「親子終活」という新しい視点が提示されます。親が一人で抱え込むのではなく、家族がチームとして取り組むことで、感情的な摩擦を避けながら現実的な解決策を導けます。章の後半では、実際に親子終活を行ってうまくいったケースが紹介されており、家族で話し合うことがいかに関係を良好にするかが具体的に描かれています。

終活は“老い支度”ではなく“生活設計の延長”です。
問題が起こる前に動くことで、法律・税金・介護すべてのリスクを最小限にできます。
第2章 お金も心もすっきりする「親子終活」の始め方
この章では、実際に親子終活をスタートさせるための具体的な手順と準備が紹介されています。まず重要なのは、「誰と一緒に進めるか」を明確にすること。親、子、きょうだいのほか、場合によっては配偶者や専門家を含めた“終活チーム”をつくることで、情報の共有がスムーズになります。次に、終活の全体像を把握するために著者が提案する「6つのステップ」を理解します。これは、財産整理から制度理解、葬儀準備までを段階的に進めるための道しるべで、初心者でも全体を見失わずに取り組める仕組みです。
特にユニークなのが、“サブノート”の作成というアプローチです。多くの人が途中で挫折してしまうエンディングノートを、まず簡単なメモ形式で始めることを提案しています。たとえば、「葬儀で流したい音楽」「連絡してほしい人」「思い出の品リスト」など、小さな記録からスタートすれば、書く習慣が自然と身につきます。

エンディングノートは“記録”ではなく“対話の起点”です。
書き込むことが目的ではなく、家族と話すきっかけにすることが最大の効果を生みます。
第3章 親が主体となって進めること
この章では、終活における主役=親が中心となって行うべき取り組みが紹介されています。最初のテーマは「思い出の整理」。単なる断捨離ではなく、“家族に引き継ぐ価値のある記憶”を残す作業です。たとえば、古いアルバムや日記、趣味のコレクションなどを整理することで、家族が知らなかった親の想い出や生き方を再発見できます。また、「デジタル化による記録保存」にも触れられ、現代的な方法で思い出を後世に残すアイデアも提示されています。
続いて、相続と遺言書の基本知識が解説されます。公正証書遺言や自筆証書遺言の違い、相続税の計算の仕組み、生前贈与の活用方法など、法的な手続きが分かりやすく説明されています。さらに、介護・医療に関する希望を記録しておく重要性にも言及。たとえば「延命治療を希望するか」「介護施設に入りたいか」など、事前に意思を伝えておくことで、家族が迷わずに判断できる環境を整えることができます。

遺言書は“財産の書類”ではなく“想いの手紙”です。
形式を守りながらも、家族への感謝やメッセージを添えることで、争いのない相続へとつながります。
第4章 子が主体となって取り組むべきこと
ここでは、子ども世代がどのように親の終活を支えるかを中心に解説しています。まず大切なのは、きょうだい同士での情報共有です。親の財産状況や介護方針を兄弟間でオープンに話し合うことで、誤解や対立を防ぐことができます。そのうえで、親の負担を軽くする実践的なサポートとして「荷物整理」や「デジタル終活の支援」が紹介されています。特にデジタル関連は親世代が苦手とする分野であり、子が一緒に作業することでスムーズに進められます。
また、親の預金を管理する際の注意点や、寄与分(介護や援助をした子の貢献分)の記録の仕方も詳しく説明されています。相続トラブルを防ぐためには、“透明性のあるお金の扱い”が欠かせません。さらに、相続登記の手続きや名義変更の流れなど、子世代が知っておくべき法律知識も紹介されており、実践的な理解を助ける構成になっています。

子どもの支援は“介入”ではなく“伴走”です。
親の意思を尊重しながら、記録を残すことで、家族全員が納得するプロセスを築けます。
第5章 いざというときに備える! 終活に使える制度と手続き
この章では、判断能力が低下したときに利用できる法的制度を中心に解説しています。特に、「成年後見制度」と「任意後見制度」の違いをわかりやすく説明し、それぞれのメリットと注意点を紹介しています。成年後見制度は家庭裁判所が関与するため公的な安心感がありますが、柔軟性に欠ける面があります。一方、任意後見制度は本人が信頼できる人を選べるため、より個人の意思を反映できます。著者は、元気なうちから任意後見契約を結んでおくことを推奨しています。
さらに、判断力が低下する前から使える仕組みとして「財産管理等委任契約」や「見守り契約」も取り上げられています。これらは、家族や専門家に日常のサポートや財産管理を委任する契約で、孤立やトラブルを防ぐ効果があります。読者が制度を難しく感じないように、実際の手続きの流れや必要書類の説明も具体的に掲載されています。

成年後見制度は“守るための法律”ですが、任意後見制度は“信頼をつなぐ契約”です。
本人の意思を最大限に尊重できる制度を選ぶことが重要です。
第6章 家族を困らせないための死後に備えた制度の使い方
この章では、亡くなった後の手続きを確実に行うための制度や方法が詳しく紹介されています。中心となるのは「死後事務委任契約」。これは、葬儀や役所手続き、遺品整理などを第三者に委任できる契約で、特に独居高齢者や子どもに負担をかけたくない人に有効です。また、遺言書の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言)の使い分けや、自筆証書遺言保管制度の活用によって改ざん・紛失のリスクを防ぐ方法も解説されています。
さらに、近年注目されている「家族信託」についても詳細に触れられています。これは、財産を信頼できる家族に託して管理してもらう制度で、認知症や入院などに備えた柔軟な資産管理が可能になります。また、ペットの飼育費や遺贈寄付など、“従来の相続では扱いにくかったテーマ”にも対応しており、現代的な終活の幅を感じさせる内容です。

死後の制度設計は“残された人の負担軽減”であると同時に、“自分らしい生き方の証明”でもあります。
制度を活用してこそ、真の安心が得られます。
第7章 将来への安心につながる葬儀・埋葬・お墓の決め方
最終章では、葬儀やお墓といった「人生の最終段階の選択」について、前向きに考えるためのヒントが紹介されています。葬儀の形式や規模を事前に決めておくことで、家族の負担を軽減し、本人の希望を反映した見送りが可能になります。さらに、近年人気が高まっている「樹木葬」「海洋散骨」「合同墓」など、新しい葬送スタイルの特徴とメリットが解説されています。
また、伝統的なお墓の管理者を決める「祭祀承継者」の設定や、墓じまいの手続き方法についても実務的な説明があります。これにより、「自分の死後、家族に負担を残さない」という現実的な目的を達成できるようになります。最終的にこの章は、「死を語ることは、生を整えること」というメッセージで締めくくられ、読者に安心と納得をもたらします。

葬儀やお墓の準備は“死のため”ではなく“生きる人のため”です。
形を決めておくことが、家族の心を守る最大の思いやりになります。
対象読者

本書は、終活をまだ始めていない人から、すでに準備を進めている人まで、幅広い層に向けて書かれています。
特に、次のような人にとって大きな助けとなる内容です。
- 終活を始めたいけれど何から手をつけていいか迷っている人
- 親が高齢になり話を切り出せずモヤモヤしている子世代
- 遺言・相続・家族信託など制度的知識を求める人
- 家族の絆を深めながら未来への不安を軽くしたい人
- デジタル資産・ペット・葬儀関係まで包括的に終活したい人
それぞれ詳しく見ていきましょう。
終活を始めたいけれど何から手をつけていいか迷っている人
このタイプの読者にとって本書は、「終活」という言葉のハードルを下げ、明確な行動の道筋を示してくれる実用的なナビゲーションです。多くの人が「終活を始めなければ」と思いながらも、何から手をつければよいのか分からず立ち止まってしまいます。本書では、そうした迷いを抱える人のために、最初の一歩を踏み出すための具体的なガイドを提示しています。財産や持ち物の整理、エンディングノートの書き方など、実務的な内容を図解付きで解説しており、「これならできそう」と思える工夫が満載です。
さらに、著者の伊藤勝彦氏は、弁護士としての豊富な経験から「順序立てて整理することが、家族を守る第一歩」と説いています。つまり、終活は“法律の準備”だけでなく、“生き方の整理”でもあるのです。自分の人生を振り返り、感謝や想いを言葉にする作業としての終活が、本書では丁寧に導かれています。

本書は、終活を“義務”ではなく“自己理解の旅”として導いてくれます。
実務的なノウハウに加え、心理的な側面にもしっかり寄り添っており、初めて終活に向き合う方が安心して取り組めるようにデザインされています。
親が高齢になり話を切り出せずモヤモヤしている子世代
親に「終活」という言葉を持ち出すのは、たとえ仲が良くても簡単ではありません。「気を悪くしないだろうか」「縁起でもないと言われるのでは」とためらう人も多いでしょう。本書は、そんな子世代の悩みに寄り添い、自然に会話を始めるための工夫や心理的アプローチを紹介しています。親のプライドを尊重しながらも、無理なく話題にできるタイミングや言葉の選び方など、実際に役立つテクニックが具体的に示されています。
また、伊藤氏は「話し合いのタイミングは早ければ早いほど良い」と強調します。親が元気なうちに希望を確認しておくことで、判断力の低下や認知症などの問題を未然に防ぐことができるからです。本書では、家族間で話を進めるためのステップを体系的に紹介しており、読者が自信を持って会話をリードできるようサポートします。

親子の間で終活の話題を出すのは、単に“勇気”ではなく“技術”が必要です。
本書はその技術を体系的に解説しており、読者が“対話を恐れない力”を自然に身につけられる内容です。
遺言・相続・家族信託など制度の実践的知識を求める人
法律や相続の知識を正しく理解したい人にとって、この書籍は最良の入門書でありながら、専門性も兼ね備えた実務書です。遺言書の作成方法や家族信託の仕組み、相続税対策など、弁護士ならではの視点から“トラブルを防ぐ制度活用法”を具体的に解説しています。特に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の違いや、家族信託を利用する際のメリット・デメリットは、図表と事例を交えて丁寧に紹介されており、初心者でも実践レベルで理解できます。
著者はまた、「制度を知ることは家族を守ること」と述べています。法律の知識を持つことで、不要な争いや誤解を防ぎ、家族間の信頼を維持できるからです。制度の理解は、家族関係を“守る盾”であり、“未来への保険”でもあると説かれています。知識がある人ほど冷静に判断し、感情的な対立を避けられる——この本はその第一歩を与えてくれます。

法的な知識を“冷たい制度”としてではなく、“家族の思いを形にする技術”として解説している点が際立っています。
法律の専門家としての経験と、人の感情を汲み取る筆致が融合しており、制度理解と実践の両面で学びの多い構成です。
家族の絆を深めながら未来への不安を軽くしたい人
終活というと「残された人のための準備」と思われがちですが、本書はむしろ「今ある家族の絆を強めるプロセス」として終活を捉えています。親がどんな最期を望んでいるのか、どんな思いを子どもに伝えたいのか——そうした本音を共有することで、家族の信頼関係が深まります。著者はこれを「心の終活」と呼び、会話を通じて互いの価値観を理解し合う大切さを強調しています。
また、伊藤氏は“親子終活”という概念を提唱し、親だけが頑張るのではなく、家族全体で支え合う姿勢を推奨します。そうすることで、親は安心して老後を過ごし、子どもは将来に対する不安を軽減できます。この「一緒に進める終活」は、単なる手続きではなく“家族の未来をデザインする時間”なのです。

本書は、終活を“家族間の心理的ケア”として位置づけている点が素晴らしい。
法的準備と心の整理を同時に進めることで、家族全員が“安心して未来を迎える力”を得られる構成になっています。
デジタル資産・ペット・葬儀関係まで包括的に終活したい人
現代の終活では、相続や遺言だけでなく、デジタル資産・ペット・葬儀・お墓など、多岐にわたる課題が浮上しています。本書はそれらをすべて網羅し、時代に即した“トータル終活ガイド”として構成されています。特に、SNSアカウントやネット銀行などのデジタル資産は放置されやすい分野ですが、本書では「死後の手続きを円滑にするための整理法」や「安全な情報管理方法」をわかりやすく解説。ペット信託や死後事務委任契約など、近年注目される制度も具体的に紹介されています。
さらに、葬儀やお墓の選び方についても、費用相場や形式の違い、家族の負担を減らすための工夫まで丁寧に説明されています。自分らしい最期を迎えるために何を決め、どのように家族に伝えるか——その全体像を理解できる一冊です。単なる“終活のチェックリスト”を超え、人生設計書としての価値を備えています。

デジタル遺品やペットなど、これまで“見過ごされがち”だった終活領域を網羅的に解説しているのが本書の強みです。
法律・実務・倫理のバランスが見事で、現代社会における“包括的終活”の指針として高く評価できます。
本の感想・レビュー

家族対話のきっかけをくれる本
この本を読み終えて真っ先に感じたのは、「家族との対話を恐れなくなった」という変化でした。終活という言葉には、どうしても「死の準備」という重い印象がつきまといます。しかし本書では、終活を「家族と人生を見つめ直すための時間」として描いており、その温かい視点に心を動かされました。著者・伊藤勝彦さんの言葉には、弁護士として数多くの事例を見てきた経験に裏打ちされた説得力があります。それでいて、堅苦しさはまったくなく、まるで“家族会議のアドバイザー”がそっと寄り添ってくれているような安心感がありました。
特に印象的だったのは、親子が「終活」を通して互いの気持ちを理解し合う過程です。単に遺言や財産の話をするのではなく、「どんな最期を迎えたいか」「どんな思い出を残したいか」という“心の整理”を重視している点が素晴らしいと感じました。私自身、親と向き合うきっかけがつかめずにいたのですが、この本を読んだ後は、「一緒にノートをつけてみよう」と自然に思えたのです。
また、終活が“家族をつなぐ行為”として描かれている点に深く共感しました。親子間で避けがちなテーマを、思いやりと実践をもって前向きに語ることができる。その勇気を与えてくれる一冊でした。
制度知識と感情視点のバランスが絶妙
法律の専門書にありがちな堅苦しさがまったくなく、制度と感情のバランスが見事に取れている本だと感じました。著者は弁護士としての専門知識をベースにしながらも、法律や手続きを“冷たいもの”としてではなく、“家族を守る道具”として描いています。制度を紹介する際も、単なる条文解説ではなく、その背後にある「なぜその制度が必要なのか」をやさしく伝えてくれるのです。
特に印象的だったのは、「成年後見制度」や「任意後見制度」を紹介する章です。これらは一見難しく思えますが、本書では具体的な状況に即して説明しており、制度の本来の目的がすっと理解できました。法律知識がない人でも、「これなら自分たちでも準備できそう」と感じられる丁寧さがあります。しかも、感情面への配慮が随所に見られ、法律の話の合間に“家族の気持ちを大切にする”というメッセージが通底しています。
自分事として動きやすいステップ設計
この本の構成はとにかく実践的で、読んだ瞬間から「次に何をすればいいか」が明確になります。終活というテーマは漠然とした不安を伴いますが、本書では「親子終活の6ステップ」という形で流れを可視化しており、読者が自分の状況を整理しながら進められるようになっています。最初は終活の知識を学ぶつもりで読み始めたのに、いつの間にか“行動マニュアル”として使っていました。
印象に残ったのは、「小さな一歩から始めよう」というメッセージです。すぐに遺言書を作る必要もなく、まずは家族で“話し合う時間を持つ”ところから始めればいいと書かれています。この優しい提案が、心理的ハードルを下げてくれました。多くの人が「終活=大掛かりな準備」と思い込んでいますが、本書は“今日からできる終活”を明確に示してくれます。
デジタル終活にも踏み込んだ先進性
終活に関する本は数多くありますが、この本のすごさは「現代のリアルな課題」まできちんと踏み込んでいる点にあります。特に、スマートフォンやSNSアカウントなどの“デジタル資産”をどう整理するかについて丁寧に説明しているのが印象的でした。著者は、現代の終活が「紙とデジタルの両立」を前提にすべきだと明確に述べています。これは、時代に即した実践書として非常に価値がある視点だと思います。
デジタル情報は、遺族にとって扱いが難しい分野です。パスワードの管理、サブスクリプション契約、写真やメッセージの保管など、誰もが直面するにもかかわらず、明確な答えがない問題です。本書ではその点にしっかり光を当て、「感情の整理」と「実務的な対策」を両立させています。親世代だけでなく、子世代にとっても学びの多い章でした。
制度・手続きガイドとして頼れる一冊
「法律のプロが書いた終活本」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、本書はむしろ“家庭で使える実用書”のような親しみやすさがあります。遺言書、家族信託、成年後見など、専門的な制度を扱いながらも、読者が自分の状況に当てはめて理解できるように構成されています。章ごとにテーマが明確で、どの部分から読んでも内容がわかりやすいのも魅力です。
特に印象に残ったのは、制度ごとに「どんな人に向いているか」「どんなリスクを回避できるか」が具体的に書かれていること。専門家らしい正確さと、一般読者への配慮が見事に共存しています。また、図解や整理表を用いて要点をまとめており、実際に制度を利用する際の“手引き書”として活用できるレベルです。
終活を「感情の話」だけで終わらせず、「手続きの面」まできちんと導いてくれる。この信頼感こそ、伊藤勝彦さんが長年の実務を通して培った経験の賜物だと感じました。
家族関係を壊さずに進められる安心感
終活や相続というテーマには、どうしても「揉めごと」や「衝突」といったイメージがつきまといます。私もそう思っていました。しかしこの本を読むうちに、その不安が少しずつ和らいでいきました。著者が何度も強調しているのは、「終活は家族の信頼を築く機会になる」という考え方です。その言葉に救われた気がしました。
本書では、家族で話し合うときの心構えや、意見がぶつかりそうなときの対応方法まで丁寧に触れられています。特に「相手を責めない話し方」や「気持ちを受け止める聞き方」など、心理的な側面にも配慮が行き届いており、実践的です。法律の話をしていても冷たさがなく、むしろ“心の整理術”のように感じました。
読後、私は終活を「関係を壊す話題」ではなく、「家族の思いを確かめ合う時間」として見直せました。大切な人たちと向き合う勇気をくれる、穏やかで信頼できる本です。
事例・コラムがリアルで納得感あり
この本の魅力は、リアルな事例やコラムが随所に盛り込まれていることです。著者は弁護士として多くの家族と向き合ってきたからこそ、机上の空論ではなく“現場で起きた問題”をもとに書いています。読み進めるうちに、「自分の家庭にも同じことが起こり得る」と感じるほど、具体的で実感のあるエピソードが続きます。
特に印象に残ったのは、「親の判断能力が落ちてからでは遅い」という一節です。言葉の重みが違いました。終活を先送りにすることのリスクを、感情に訴えるような形で理解できたのはこの本が初めてです。難しい説明よりも、“なぜ今すぐ動くべきなのか”が心に響く構成でした。
こうした事例やコラムがあることで、読者はただ学ぶだけでなく、自分の現実に照らして考えられるようになります。実務的な知識と人間ドラマの両面を備えた、説得力のある内容でした。
読後すぐ家族に手渡して話したくなる本
読み終えたあと、真っ先に感じたのは「この本を家族にも読んでほしい」という気持ちでした。終活の本というと、どうしても一人で静かに読むイメージがありますが、本書は違います。内容があまりにも“親子の会話”に寄り添っているため、「みんなで読んだ方が効果がある」と思わせてくれるのです。
本書の中で繰り返し語られるのは、“終活は家族の共同作業である”という理念です。その考え方が読者の心に染み込み、読後には自然と誰かと話したくなります。私の場合は母に本を渡し、「一緒に少しずつ話してみようか」と声をかけるきっかけになりました。お互いに不安を抱えていたことを素直に話せたのは、この本のおかげです。
この本は、知識を得るためのものではなく、“家族の時間を生み出す本”だと感じます。終活を前向きにとらえ、親子の絆を深める。そんな読後感を持てる一冊でした。
まとめ

ここまで、弁護士・伊藤勝彦氏の著書『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』を詳しく紹介してきました。
最後に、この本を読んで得られる価値を整理しながら、読後にどんな行動を起こすべきかを見ていきましょう。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれ詳しく見ていきましょう。
この本を読んで得られるメリット
ここでは、この本を読むことで得られる具体的な利点を4つの観点から紹介します。
相続・遺言・制度の知識が体系的に身につく
本書の最大の特徴は、法律や制度の知識を専門家レベルでわかりやすく整理している点です。遺言書の種類、家族信託の仕組み、相続税対策、成年後見制度など、一般の人がつまずきやすい部分を、実際の相談事例をもとに丁寧に解説しています。法律用語をただ説明するだけでなく、「どんな場面で使う制度なのか」「間違えるとどうなるのか」まで具体的に示してくれるため、知識が“実践力”へと変わります。専門家に相談する前の予備知識としても非常に役立ち、読者自身が自信を持って判断できる力を養えます。
家族の対話を促し、信頼関係を深められる
終活は一人で行うものではなく、家族全体で共有しながら進めることが理想です。本書はそのための「親子終活」という新しいアプローチを提案しています。親の本音を引き出す方法、子どもが話を切り出すタイミング、家族間の意見のすり合わせ方など、心理的な面まで踏み込んだ実践的なアドバイスが豊富です。これにより、感情的な対立を避けながら、家族の信頼関係を築くプロセスを自然に進めることができます。読後には、「終活を通じて親子の距離が近づいた」と感じる人も多いでしょう。
不安の原因を可視化し、現実的な解決策が見える
「終活をしたいけれど、何から始めればいいのか分からない」という人にとって、本書は行動の指針となります。親の財産、思い出の品、医療・介護の希望、葬儀やお墓に関することまで、項目ごとに整理の手順が示されており、「見える化」によって漠然とした不安を具体的な課題に変えていきます。そのうえで、各課題に対する現実的な解決策や制度利用のポイントを紹介しており、読者は自分の家庭に合った形で計画を立てやすくなります。
専門家の知識を自分の人生設計に活かせる
著者・伊藤勝彦氏は、25年以上にわたり1,000件以上の終活・相続案件を手がけてきた弁護士です。その経験から導き出された知識は、机上の理論ではなく、実際の生活に落とし込める「生きた知恵」として紹介されています。特に、成年後見制度や財産管理契約など、聞き慣れない制度の選び方を具体的なケースに沿って解説しているため、制度を“知識として知る”段階から“現実に活かす”段階へと導いてくれます。読者は、自分自身の老後や家族の将来を見据えた判断を下せるようになるでしょう。

この本の真の魅力は、「知識」「実践」「対話」「安心」のすべてが一冊に凝縮されていることです。
読むことで、終活が“義務”ではなく“家族と未来を整える時間”へと変わっていきます。
読後の次のステップ
本書『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』を読み終えたあとに大切なのは、学んだことを“知識”として終わらせず、“行動”へつなげることです。終活は頭で理解するだけでは意味がなく、実際に手を動かし、家族と話し合うことで初めて形になります。
ここでは、読後に踏み出すべき4つのステップを紹介します。
step
1親子で最初の一歩を踏み出す
本書を読んだ直後に取り組むべきは、親子で「最初の会話」を持つことです。どんなに小さなきっかけでも構いません。「この本を読んで、少し話したいことがあるんだけど」と自然に切り出すだけで、終活への第一歩が始まります。著者は、終活の核心は“コミュニケーション”だと強調しています。親の気持ちを聞くことは、意見を押し付けることではなく、「どう思っているのかを知る」ことから始まります。この会話を通して、親子の信頼関係がより深まり、次の行動への準備が整っていきます。
step
2エンディングノートやサブノートを活用する
次の段階では、本書で紹介されている「エンディングノート」や「サブノート」を使って、親子で情報整理を始めます。財産や保険、医療・介護の希望など、書き出していくうちに意外な発見があるものです。特に、サブノートは「気軽に書けるメモ版エンディングノート」として設計されており、途中で挫折せずに続けられる仕組みが整っています。この作業を共同で行うことで、家族間での理解や共有が進み、後のトラブルを防ぐ基盤が築かれます。
step
3専門家への相談を検討する
終活を進める中で、制度や税務の壁にぶつかることがあります。そんなときは、弁護士・司法書士・税理士といった専門家に相談することが最も確実です。本書では、専門家の活用タイミングや相談時のポイントも詳しく紹介されています。自己判断に頼らず、早めに専門的な視点を取り入れることで、後悔のない選択が可能になります。著者自身が長年の経験から導いた「相談する価値のある局面」を押さえることは、終活の成功に直結するステップです。
step
4家族で定期的に振り返る
終活は一度で終わるものではありません。人生の節目や家族の状況変化に応じて、内容を見直す必要があります。本書では、「一度作ったら終わり」ではなく、「家族で年に一度見直す」ことを推奨しています。これは単なる確認作業ではなく、“家族の対話を続けるための時間”としての意味を持ちます。少しずつアップデートを重ねていくことで、より現実的で心のこもった終活が完成していくのです。

終活は“準備を整えること”よりも、“行動を始めること”に価値があります。
まず一歩を踏み出せば、家族の未来はより穏やかで、確かなものになります。
総括
『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』は、単なる「終活のハウツー本」ではなく、家族の関係を見直し、人生の最終章を穏やかに迎えるための「心のマニュアル」とも言える一冊です。著者・伊藤勝彦氏は、25年以上にわたって1,000件以上の相続・終活相談を受けてきた実務家として、現場で培った知識と人間理解をもとに、“法律の本質”と“家族の感情”を橋渡しするように書き上げています。難しい法律や手続きの話であっても、読者が自分の家族に置き換えて考えられるような温かさと現実感が貫かれています。
この本が多くの人に支持されている理由は、終活を「死に備えること」ではなく、「これからを安心して生きるための整理」として再定義している点にあります。読者は、相続や介護、葬儀などの重たいテーマを前向きに捉え直すことができ、「終活=前向きな家族時間」という新しい価値観を見出せるでしょう。特に、家族との対話を重視する構成は、従来の終活書籍にはない人間的な温かみを感じさせます。
また、制度や仕組みの説明に留まらず、「なぜその準備が必要なのか」「どんな失敗が起こり得るのか」といったリアルな視点が盛り込まれているため、読者は“他人事”ではなく“自分事”として理解できます。法律や制度を知るだけでなく、それを家族の幸せのためにどう活かすかを具体的に学べる構成は、終活をこれから始める人にとって大きな指針となるはずです。

最終的に、本書が伝えるメッセージは「終活とは、家族への最大の思いやりである」という一点に集約されます。
将来の不安を取り除くだけでなく、親子の絆を深め、心からの安心を生み出す行為としての終活。
その本質を知ることで、読者は“人生を整える”という前向きな目的意識を持ち、穏やかで豊かな未来を描く力を得ることができるでしょう。
終活について学べるおすすめの書籍

終活について学べるおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 終活について学べるおすすめの本!人気ランキング
- モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活
- 人に迷惑をかけない終活~1000人の「そこが知りたい!」を集めました
- 90分でざっくりわかる!終活の本
- よくわかる「終活・相続の基本」
- 図解でわかる高齢者と終活
- 相続・遺言・介護の悩み解決 終活大全
- おひとりさま・おふたりさまの相続・終活相談
- これが知りたかった! 終活・相続コンサルタントが活躍するための実践手引書