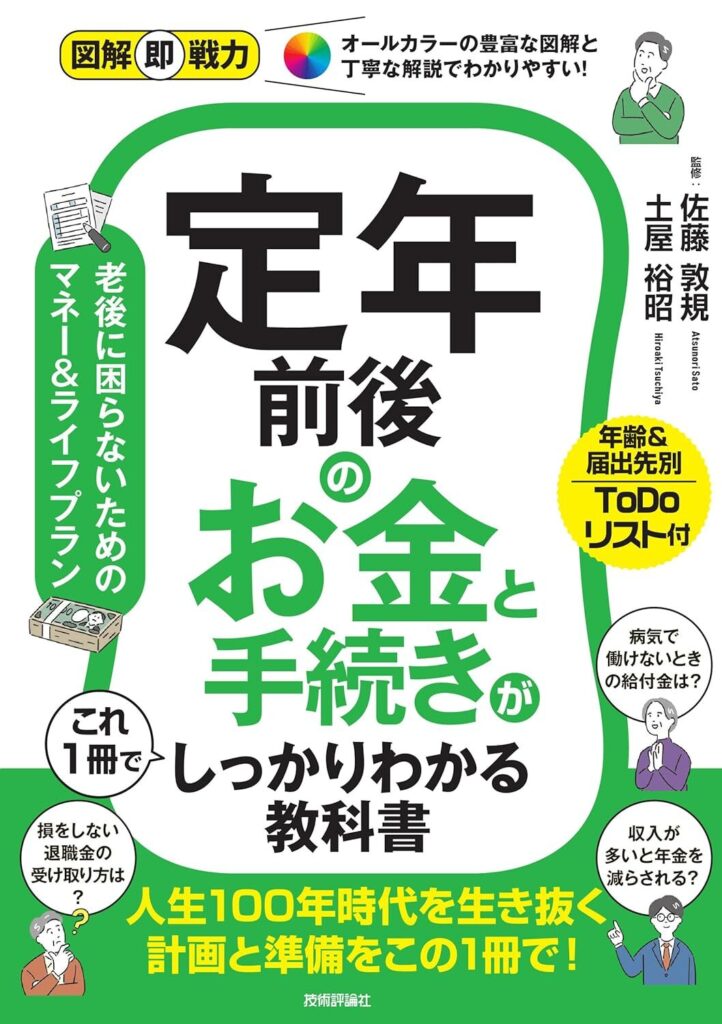
人生100年時代を迎えた今、「定年」はもはや“終わり”ではなく“新しいスタート”の入り口です。
60歳を一区切りとして、働き方や暮らし方、そしてお金との付き合い方をどう変えていくか――そのすべてが、これからの人生の質を左右します。
書籍『図解即戦力 定年前後のお金と手続きがこれ1冊でしっかりわかる教科書』は、そんな人生の転換期に立つ人々に向けて、お金・制度・手続きのすべてを体系的にまとめた“定年前後の総合ガイド”です。

本書は、退職金や年金といった「収入の柱」だけでなく、税金・健康保険・再就職・介護・住まいといった“老後の現実的なテーマ”までを、専門家監修のもとに図解でやさしく解説しています。
特に、複雑な制度を年齢別・手続き別に整理した「ToDoリスト」や、「どこで何をすればいいのか」が一目でわかる対応表は、実務的に非常に役立ちます。
制度の仕組みを理解するだけでなく、「今、何をすべきか」「何を準備しておくべきか」が具体的に行動に移せる構成です。
この1冊を手に取ることで、定年を“漠然とした不安の始まり”ではなく、“人生後半の設計図を描くチャンス”に変えることができます。
読者は、働き方や資産運用を見直しながら、心の面でも経済の面でも自立した老後を築く準備ができるでしょう。
まさに、「定年を迎えるすべての人のための、未来設計の教科書」と呼ぶにふさわしい一冊です。

合わせて読みたい記事
-

-
定年前後に読むべきおすすめの本 10選!人気ランキング【2026年】
定年が近づくと、これからの暮らしやお金、健康、働き方について考える機会が一気に増えます。 退職金や年金の受け取り方、再雇用やセカンドキャリアの選択、生活スタイルの見直しなど、人生の岐路で直面するテーマ ...
続きを見る
書籍『図解即戦力 定年前後のお金と手続きがこれ1冊でしっかりわかる教科書』の書評

定年前後に直面する「お金」と「手続き」の不安を、図解でわかりやすく整理した実務書です。複雑な制度を専門家が丁寧に解説しており、読後には“行動できる知識”が身につきます。
ここでは以下の5つの観点から本書を詳しく紹介します。
- 監修:佐藤 敦規のプロフィール
- 監修:土屋 裕昭のプロフィール
- 本書の要約
- 本書の目的
- 人気の理由と魅力
それぞれ詳しく見ていきましょう。
監修:佐藤 敦規のプロフィール
佐藤敦規(さとう・あつのり)氏は、社会保険労務士として長年にわたり企業の人事・労務分野を支えてきた実務のプロフェッショナルです。中央大学法学部を卒業後、一般企業での勤務経験を経て社会保険労務士として独立。以後、社会保険労務士法人やコンサルティング会社で数多くの企業の労務体制整備、定年延長制度、再雇用契約などのサポートを行ってきました。特に「定年前後の働き方」や「高年齢者雇用安定法」に関する専門知識に精通し、企業の人事担当者だけでなく、個人のキャリア支援や生活設計の相談にも対応できる稀有な存在です。
佐藤氏の指導は、法律の条文をそのまま解説するのではなく、現場の課題に即した“実務目線”が中心です。たとえば「定年退職者が退職後にどの社会保険へ切り替えるか」「再雇用後の雇用契約をどのように結ぶべきか」といった現場で頻発する疑問を、法律・制度・会社運用の3つの視点で整理しながら、具体的な行動に落とし込む手法を得意としています。
本書では、社会保険制度・再雇用制度・定年後の働き方を中心に監修を担当。特に「働く」「辞める」「年金を受け取る」の境界線にある制度変更のタイミングをわかりやすく示す点で、読者から高く評価されています。社会保険労務士としての専門性だけでなく、“読者が制度を使いこなすための設計”という視点を持つことが、彼の大きな強みです。

社会保険労務士の役割は、働く人の「安心の橋渡し」です。
制度を知っているだけでは不十分で、それを“正しいタイミングで使える”ように導くことこそが実務の要です。
監修:土屋 裕昭のプロフィール
土屋裕昭(つちや・ひろあき)氏は、税理士・CFP(ファイナンシャルプランナー)として、退職金・年金・相続・資産運用の分野で豊富な実績を持つマネープランの専門家です。早稲田大学政治経済学部を卒業後、税理士資格を取得し独立。現在は税理士法人の代表として、法人税務だけでなく、個人のライフプランや老後資金設計の支援も幅広く手がけています。
土屋氏の真骨頂は、「税金を負担としてではなく、人生設計の一部として捉える」アプローチにあります。退職金を一時金で受け取るか、年金形式にするかによって税金がどう変わるか、健康保険や年金との関係で社会保険料がどう増減するか、といった実践的な視点を常に重視します。特に「定年退職後の税金と社会保障の境界」に関しては、税理士とファイナンシャルプランナーの両面から分析できる数少ない専門家です。
本書では、退職金・年金・住民税など“お金の出口”に関する章を中心に監修しています。単なる制度説明にとどまらず、読者が「どうすれば手取りを最大化できるか」「どの順番で手続きを行えば損を防げるか」という行動指針を提示しています。数字の羅列ではなく、「制度を理解して戦略的に使う」という考え方を普及させる姿勢が貫かれています。

税金とは“取られるもの”ではなく、“調整できるもの”です。
定年前後は社会保険料・年金・税金が同時に動く時期。正しい知識があれば、見えない損失を防ぐことができます。
本書の要約
『図解即戦力 定年前後のお金と手続きがこれ1冊でしっかりわかる教科書』は、定年という人生の大きな節目を迎える人々が抱える「お金」と「制度」に関する不安を、体系的かつ実務的に解消してくれる一冊です。退職金や年金の受け取り方、税金の計算方法、健康保険や介護保険の切り替え、住まいや相続に関する問題まで、あらゆる分野を横断的に網羅しています。
この書籍の最大の特徴は、「定年後の生活を設計するための実用マニュアル」であることです。単に制度の概要を説明するだけでなく、「いつ、どこで、何を、どうすればよいか」という手続きの流れを、時系列で具体的に解説しています。冒頭には「年齢別ToDoリスト」や「行先別手続きリスト」が掲載されており、年金事務所、ハローワーク、市区町村役場、税務署などで行う手続きが整理されているため、初めての人でも迷わずに行動できます。
また、文章だけでなく、図解・チャート・フローチャートを多用している点も魅力です。制度の全体像や流れを視覚的に理解できるため、難解な制度の壁を感じずに読み進めることができます。特に、年金の受給開始年齢の変更による受給額の増減や、退職金の受け取り方法による税金の違いなどは、イラストや数値シミュレーションを使ってわかりやすく説明されています。
さらに、本書は「知識を得るための本」ではなく、「行動を起こすための本」です。読者が読み終えたあとに、実際に年金事務所に行く、手続きを始める、資産運用を見直すといった行動に移せるように構成されています。内容は机上の理論ではなく、現実的かつ即効性のある実践知に満ちています。

この本は“読むだけの知識”ではなく、“実際に動ける知識”を提供する設計書。
制度を理解するだけでなく、使いこなす力が身につく構成になっています。
本書の目的
本書の目的は、「老後の生活を計画的に、かつ損をせずに迎えるための行動指針を提供すること」です。単に制度を知識として学ぶのではなく、“どの制度をいつ使うか”という具体的な行動レベルに落とし込む点に重きが置かれています。
定年前後の制度は、退職金、年金、税金、健康保険、雇用保険などが複雑に絡み合い、わずかな選択の違いで受け取れる金額や支払う税金が大きく変わります。たとえば、退職金を「一時金」で受け取るのか「年金形式」で分割するのかで、税負担が数十万円単位で変わることもあります。こうした“見えない差”を事前に理解し、最適な選択をするための知識を体系的に整理しているのが本書の特徴です。
また、本書は「制度を正しく理解して、自分で判断できる力を養う」ことにも主眼を置いています。たとえば、公的年金の繰り下げ受給は年率8.4%増となりますが、その代わりに受給開始が遅れるデメリットもあります。こうした制度の“裏側のリスク”も隠さず説明し、読者が自分にとって最適な選択をできるよう設計されています。
さらに、仕事・健康・介護・住まいといった生活領域も含めて、老後の「お金の動き」と「暮らしの変化」を同時に整理できる点が大きな強みです。読者は制度の知識を学ぶだけでなく、「どんな暮らし方を選ぶか」という人生設計そのものを見直すきっかけを得ることができます。

知識は“行動”に結びついてこそ意味を持ちます。
制度を知るだけでは不十分。自分の生活に合わせて最適なルートを描くことが、真の定年準備です。
人気の理由と魅力
『図解即戦力 定年前後のお金と手続きがこれ1冊でしっかりわかる教科書』が高く評価されている理由は、三つの柱にあります。それは「信頼できる専門性」「圧倒的なわかりやすさ」「行動につながる構成力」です。
まず、監修を務めるのは社会保険労務士と税理士という、それぞれの分野の実務専門家です。彼らは長年、年金・雇用・税務・社会保障といった分野で現場に立ち、制度の運用実態を熟知しています。そのため、机上の理論ではなく「実際にどう動くか」「どこでつまずくか」というリアルな現場知識が詰まっています。この点が、一般的な制度解説書との大きな違いです。
次に、構成のわかりやすさが群を抜いています。制度を“分野別”ではなく“ライフイベント別”に整理しているため、読者は「自分に今必要な情報」から順に読み進めることができます。退職金の受け取り、年金の申請、健康保険の切り替え、介護保険の利用、住まいの見直しなどが流れに沿って並んでおり、「何から手をつければいいのか」が直感的にわかります。
さらに、図解やフローチャートによる説明の質が非常に高く、ビジュアル資料としても優れています。専門用語を排し、制度の仕組みを「お金の流れ」や「手続きの順序」として示しているため、読者は全体像をつかみながら理解を深めることができます。特に「公的年金の繰下げ受給」「健康保険の任意継続」「退職金の税金控除」など、難解な部分も図で一目瞭然です。
そして何よりの魅力は、「読むだけで行動が変わる」実践性です。本書の内容は抽象的な説明に終わらず、「今、何をすべきか」「どこで手続きするか」まで具体的に示されています。まるで専門家がそばでサポートしてくれているような感覚で、読者は自信をもって手続きを進めることができます。

人気の理由は、“読んで終わり”にならない構成。
制度理解を“行動力”に変える本として、多くの定年前後世代に支持されています。
本の内容(目次)

本書は、定年前後の人生設計に必要な「お金」「制度」「手続き」を体系的に整理した実践ガイドです。構成は10章で、退職直前の準備から老後の資産管理、住まい、介護まで幅広くカバーしています。
特に、定年前後の不安や疑問を段階的に解消していく流れが特徴で、読者が自分の状況に合わせて必要な章から読み進められるように構成されています。各章は、手続きや制度の知識に加え、実際の行動に移せるように実務的なステップまで落とし込まれています。
本書の章立ては以下のとおりです。
- 第1章 みんなが不安!定年前後のココが知りたい
- 第2章 定年後に向けたお金を増やすヒント
- 第3章 定年前後の手続きのキホンをおさえる
- 第4章 退職金の受け取りで損をしないための手続き
- 第5章 定年後に選べる健康保険の6つの加入手続き
- 第6章 定年後の働き方と手続き&仕事の探し方
- 第7章 もらえるものはもらう!年金の正しい知識と手続き
- 第8章 万が一に備えて知っておきたい介護保険の手続き
- 第9章 定年後も逃れられない所得税・住民税のキホン
- 第10章 定年前後で解決しておきたい住まいの問題とお金
それぞれの章が「定年」という人生の節目を軸に、どのようなテーマを扱っているのかを以下で詳しく解説します。
第1章 みんなが不安!定年前後のココが知りたい
この章では、定年前後に誰もが抱く「働き方」「収入」「制度」の疑問を整理し、現実的な選択肢を明らかにしています。読者がまず直面するのは、「定年後の生活はどうなるのか?」という根源的な不安です。本章はその答えをデータと制度の両面から丁寧に解説します。
最初に、自社の定年制度の確認方法や、再雇用・再就職などの雇用形態の違いを明確にします。例えば「再雇用」は同じ会社で条件を変えて働く制度であり、「嘱託」や「業務委託」といった形態は雇用契約ではなく請負契約になるため、社会保険の扱いも変わります。これらの違いを理解することが、損を防ぐ第一歩です。
さらに、定年後の就業率や平均年収の実態を通じて、働くことが生活資金の安定だけでなく、社会とのつながりを維持する上でも重要であることを説いています。制度としては「高年齢者雇用安定法」により、希望すれば65歳まで働ける環境が整いつつありますが、その裏には「雇用延長」と「再雇用」の違いという現実的な課題も存在します。

定年後の働き方を検討する際は、「給与」「雇用契約」「社会保険」の三要素をセットで確認するのが基本です。
契約形態が変われば、失業給付や年金にも影響します。
第2章 定年後に向けたお金を増やすヒント
第2章では、定年後の家計を安定させるための実践的な資金管理術を紹介します。最初に、自身の収支・資産・負債の「棚卸し」を行う重要性を説いており、ねんきん定期便の確認やねんきんネットの活用方法を通じて、自分の将来の年金額を把握する手順が解説されています。こうした現状分析は、老後資金の不足を早期に発見する第一歩です。
続いて、公的年金を増やす方法や、資産運用を行う際の考え方が登場します。特に、本書では“低リスク運用”の重要性を強調。新NISAやFXなどの金融商品が持つ「見えないリスク」にも言及し、安定した資産形成を目指すための判断基準を示しています。また、生命保険や医療保険の見直し、住宅ローンの完済、ふるさと納税による節税など、生活に密着した改善策も多数紹介されています。
老後の資金対策というと「増やす」ことに意識が向きがちですが、本章では“減らさない工夫”に重点が置かれています。そのため、投資初心者でもリスクを抑えながら将来への安心を築くヒントが得られます。

「老後の資産形成=投資」ではなく、「収支の最適化」と「制度の活用」が核心です。
最初に“守る”姿勢を持つことが、長期的に見れば“増やす”戦略になります。
第3章 定年前後の手続きのキホンをおさえる
ここでは、退職時に必要な書類や行政・保険関連の手続きを網羅的に整理しています。多くの人がつまずくのは「いつ」「どこで」「何をするか」という具体的な流れを把握していないことです。この章は、まさにその“抜け漏れ”を防ぐための手引きです。
まず、会社に返却すべき物(社員証や保険証など)と、受け取るべき書類(源泉徴収票、雇用保険被保険者証、年金関係書類など)を確認します。これらの書類は、後の失業手当や年金請求、税金手続きに直結するため、一つでも紛失すると後々の申請に支障をきたします。
また、配偶者の社会保険の切り替えや、失業給付・傷病手当金などの申請もここで扱われています。特に「65歳未満」と「65歳以上」では受け取れる給付金の名称も異なり、ハローワークや職業訓練の利用方法も変わる点に注意が必要です。

退職時の手続きは“スピードと正確さ”が命。
期限を過ぎると、もらえるはずの給付金を逃す可能性もあります。
第4章 退職金の受け取りで損をしないための手続き
この章は、退職金の「受け取り方」で大きく変わる税金の仕組みと、賢い運用方法を詳しく解説しています。定年後の資金計画の中で最も重要な項目のひとつが、この退職金の扱いです。
退職金は一括受け取りと年金方式(分割受け取り)で税制上の扱いが異なります。一括で受け取る場合は「退職所得控除」が適用され、長く勤続した人ほど税金が軽減される仕組みです。一方、分割受け取りは所得税の課税が年ごとに発生しますが、長期的な生活資金の安定化という利点があります。
また、退職金専用の定期預金や個人年金保険を活用する方法も紹介されており、これにより資金を安全に運用しながら、インフレリスクを和らげることができます。どの方法が自分に合うかを判断するためには、税金・運用・ライフプランを総合的に見通すことが大切です。

退職金は“もらう瞬間”よりも“使い方”で差が出ます。
税制優遇の仕組みを理解し、最初の分配計画を誤らないことが最大の節税策です。
第5章 定年後に選べる健康保険の6つの加入手続き
定年を迎えた後、最も多くの人が直面するのが「健康保険をどうするか」という問題です。この章では、6つの選択肢を比較し、それぞれのメリット・デメリットを明確に示しています。
代表的な選択肢として、「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養に入る」「再就職による社会保険加入」などがあります。例えば、任意継続は退職前の保険を最長2年間延長できる制度で、収入が一時的に減る人に有利です。一方で、国民健康保険は自治体ごとに保険料が異なり、所得によって負担が大きくなるケースもあります。
さらに、特例退職被保険者制度や併用加入など、あまり知られていない制度も解説されています。これらを知ることで、「保険料を最小化しつつ、保障を維持する」判断が可能になります。制度を理解せずに安易に選ぶと、数十万円単位の差が出ることもあります。

健康保険の選択は“収入・家族構成・再就職予定”の3要素で最適解が変わります。
自分に合った制度を比較検討するのが、老後の安心を守る第一歩です。
第6章 定年後の働き方と手続き&仕事の探し方
この章では、定年を迎えた後も「働く」ことを選ぶ人に向けて、雇用制度や給付金、仕事探しの手順をわかりやすく解説しています。年金だけでは不安な老後資金を補うために再就職する人、社会とのつながりを維持したい人など、働く理由はさまざまですが、そのすべてに共通して「制度を理解しておくこと」が重要です。
まず、継続雇用制度を利用した際の社会保険の取り扱いから始まり、「高年齢雇用継続基本給付金」や「高年齢再就職給付金」など、定年後の働き方に連動する給付制度が紹介されています。特に前者は、60歳以降の賃金が定年前より75%未満になった場合に、最大15%相当が支給される仕組みで、再雇用者の生活を支える重要な制度です。
また、再就職やフリーランス、業務委託など多様な働き方が可能になった現代において、それぞれの契約形態に応じた社会保険の加入や税務上の違いも丁寧に解説。仕事を探す方法としては、ハローワーク、シルバー人材センター、マルチジョブホルダー制度などが紹介され、状況に応じて複数の選択肢を組み合わせることが推奨されています。

定年後の働き方は「安定」よりも「柔軟性」がカギです。
公的給付制度を組み合わせることで、収入を減らさず、働くモチベーションを維持することが可能になります。
第7章 もらえるものはもらう!年金の正しい知識と手続き
この章は、年金制度の全体像を体系的に学び、「どのように、いつ、いくらもらえるのか」を自分で判断できるようになることを目的としています。老後の生活の柱である年金を正しく理解することが、経済的不安を解消する第一歩です。
まず、年金の仕組みを「基礎年金」と「厚生年金」の2階建て構造で説明し、加入期間や未納期間の確認方法を丁寧に解説。ねんきんネットの活用や、年金記録漏れへの対応手順も紹介されています。
続いて、受給の開始時期を繰り上げ・繰り下げすることで年金額が変動する仕組み、在職老齢年金制度のルール、働きながら年金を増やす「在職定時改定」なども詳細に解説。さらに、加給年金や振替加算、遺族年金、iDeCo(個人型確定拠出年金)など、補助的な制度も網羅されています。

年金は「請求しなければもらえない」仕組みです。
受給開始年齢をどう設定するかが、生涯の受取総額に大きく影響します。
シミュレーションで最適な開始時期を見極めましょう。
第8章 万が一に備えて知っておきたい介護保険の手続き
この章では、将来の介護リスクに備えるための制度や手続きを、具体的な流れで説明しています。介護は突然訪れることが多く、知識がないまま手続きを行うと、必要なサービスを受け損ねる可能性があります。
まず、介護保険の基本構造として、「40歳から保険料を支払う仕組み」「65歳以上での利用対象」などが整理されています。介護サービスを利用するためには、市区町村への「要介護認定申請」が必要で、その後「ケアマネジャー」と共にケアプランを作成する流れが紹介されています。
さらに、介護保険で利用できる在宅・施設サービスの種類、70歳以降の医療費の自己負担割合、介護にかかる費用の目安なども具体的に説明。加えて、認知症対策として「任意後見契約」「家族信託」「尊厳死宣言」など、法的な備えも重要なトピックとして触れられています。

介護は「制度」よりも「準備の早さ」がカギ。
家族での話し合いと、ケアマネジャーとの早期連携が、介護負担を最小限にする最良の手段です。
第9章 定年後も逃れられない所得税・住民税のキホン
第9章では、退職後に避けて通れない税金の仕組みを、やさしくかつ実務的に解説します。退職金、年金、保険金など、定年後も発生する所得と課税の関係を整理し、「どの所得にどんな税金がかかるのか」を明確に理解できる構成です。
退職金の税金については、退職所得控除の具体的な計算方法を例示し、退職所得がどのように優遇されているかを説明。また、公的年金の課税対象額の計算式や、確定申告が必要なケース・不要なケースも紹介されており、間違いやすい部分を丁寧にフォローしています。
さらに、住民税や固定資産税など、退職後も支払いが続く税金についても具体的に触れています。特に、年金生活者が非課税世帯になる条件や、税金を減らすための控除制度など、生活防衛のための知識を実務的に整理しています。

税金の理解は“お金を増やす”ことより“減らさない”ための武器。
正しい知識が安心な老後を守ります。
第10章 定年前後で解決しておきたい住まいの問題とお金
最終章では、「住まい」という生活基盤に関する経済的・制度的な課題をまとめています。リフォーム、買い替え、賃貸、相続など、人生の後半で必ず直面するテーマを包括的に扱っています。
まず、戸建て・マンションそれぞれのリフォーム費用の目安や、国や自治体の助成金・税額控除制度を紹介。バリアフリー改修や耐震リフォームなどを行うと、翌年の固定資産税が軽減される制度もあり、老後の安全と経済性を両立させるポイントが具体的に示されています。
また、リバースモーゲージや親子二世帯ローンなど、シニア層向けの住宅資金制度についても詳述。自宅を賃貸に出す際の注意点、相続した空き家のリスク、介護施設への住み替え判断基準など、多様な住まいの選択肢とそれに伴う税・契約上のリスクを総合的に理解できる構成になっています。

住まいの決断は「資産」だけでなく「生活の質」を左右します。
老後の住環境を“支出の削減”ではなく“安心の投資”と捉える視点が重要です。
対象読者

本書は、定年前後の人生設計に関わるあらゆる立場の人に向けて作られています。制度の理解や手続きの準備はもちろん、老後に向けた「新しい働き方」や「家計の整え方」を現実的に考えるための内容が豊富に盛り込まれています。
そのため、対象となる読者層は幅広く、次のような人たちに特に役立つ構成になっています。
- 55歳を過ぎた企業勤めの人
- 定年退職を控える人自身
- 定年退職を迎える家族・配偶者
- シニア世代の再就職・副業を検討する人
- FP・社会保険労務士・税理士等、相談業務に関わる人
本書を読むことで、自分が「どの立場で」「どんなリスクや選択肢を持っているのか」を具体的に把握できるようになります。
単なる制度の知識ではなく、現実的なライフプランを描くための“指針”を得ることができる点が、本書の大きな特徴です。
55歳を過ぎた企業勤めの人
この世代の会社員にとって、「定年」という言葉は現実味を帯びたテーマとなります。本書は、給与・退職金・年金などの“これから変わるお金の仕組み”をわかりやすく整理しており、働きながら老後の準備を始めたい人に最適です。特に、再雇用制度や勤務延長の仕組み、社会保険の継続条件など、実務に直結する情報が多く、将来を見据えた行動計画を立てやすくなっています。
また、55歳以降は、ライフスタイルや健康、家族構成の変化によって家計の見直しが必要となる時期でもあります。本書はそうした変化を前提に、収支バランスを保ちながら老後資金を準備するための実践的なノウハウを提供しています。将来の不安を“見える化”することで、安心して次のキャリアステージへ進む支援となる一冊です。

この世代では「社会保険料の仕組み」や「退職金の受け取り方」によって、数十万円単位の差が生まれることがあります。
本書で基礎を押さえておくことが、最も効率的な資産防衛につながります。
定年退職を控える人自身
定年退職を目前に控えた人にとっては、まさに「手続きの嵐」の時期です。退職金の申請、年金の受給手続き、健康保険や税金の切り替えなど、数多くの書類と期限に追われる時期でもあります。本書はそうした実務的なステップを網羅的に整理しており、「何を」「どこで」「いつまでに」行えばよいかが明確に理解できます。
さらに、再雇用や再就職を希望する場合の契約形態や社会保険の扱い方まで、実際のケーススタディを交えて解説しています。自分の働き方を見直しながら、損をせずスムーズに次の生活段階へ移行できるための「実践マニュアル」として心強い一冊です。

退職直前の数年間で、年金の受給タイミングや税制の優遇措置を理解するだけでも、生涯資金に大きな違いが出ます。
本書を活用して“引退準備の最終チェックリスト”を整えましょう。
定年退職を迎える家族・配偶者
定年を迎えるのは本人だけではありません。配偶者や家族にとっても、生活設計や収入構成が大きく変化する節目になります。本書は、共働き家庭・専業主婦(夫)家庭それぞれのケースに合わせ、社会保険の切り替えや扶養の扱い方など、家族単位で理解しておくべきポイントを丁寧に解説しています。
また、退職後の医療保険や介護保険の制度変更、住まいの見直しなど、家庭全体の支出構造に関わるテーマも扱っています。家族全員が安心して次のステージを迎えられるよう、配偶者の立場からの「サポート方法」まで明示されている点が特徴です。

職は“世帯単位のイベント”です。
配偶者の年金・健康保険・税制上の扶養を整理することで、家計全体の最適化が実現します。
シニア世代の再就職・副業を検討する人
定年後も社会と関わり続けたい、あるいは新たな働き方を模索したいと考えるシニア世代にとって、本書はキャリア再設計の「出発点」となります。再雇用・業務委託・フリーランス・法人設立といった多様な選択肢を比較し、それぞれの長所と注意点を制度面から整理しています。
特に、働きながら年金を受給する際の「在職老齢年金制度」や「高年齢雇用継続給付金」などの仕組みをわかりやすく説明しており、働く意欲を持つ人にとって収入を最大化するための知識が得られます。これにより、“老後=引退”ではなく、“新しい働き方への転換期”として定年を捉えられるようになります。

定年後も働く場合、給与と年金のバランス設計が重要です。
本書はその「損をしない境界線」を理解する助けになります。
FP・社会保険労務士・税理士等、相談業務に関わる人
本書は一般読者だけでなく、専門家にとっても価値の高いリファレンスブックです。制度の概要だけでなく、実際の申請手続きや提出書類、相談時の留意点まで整理されているため、クライアントへのアドバイスに直結する情報が得られます。
また、定年前後の制度変更は頻繁であり、現場で相談を受ける専門職にとって最新知識のアップデートは欠かせません。本書は図解と具体例が豊富なため、専門家が顧客にわかりやすく説明する際の“教材”としても機能します。相談業務の質を高めたい専門職にとって、実務の裏付けとなる一冊です。

本の感想・レビュー

難しい制度をやさしく解説してくれる安心感
この本を読んでまず感じたのは、制度や仕組みの説明がとても親切で、専門知識がなくても自然に理解できるように工夫されているという点です。年金や退職金、社会保険など、普段の生活ではなじみが薄いテーマを扱いながらも、難しい言葉を平易に言い換え、重要な部分を図で補ってくれているため、読むほどに理解が深まります。文章のテンポも穏やかで、専門書というよりは信頼できるガイドと一緒に歩んでいるような感覚になりました。
また、各制度の説明では、実際の手続きや必要書類などの流れが丁寧に整理されており、何から始めればよいかが明確に分かります。特に定年前後の社会保険や税金の切り替えなどは、間違えると損をすることもある分野ですが、本書では「ここを確認しておけば大丈夫」というポイントを具体的に示してくれているため、安心して読み進められました。
読み終えたときには、これまで漠然と抱えていた「老後のお金の不安」がずいぶん軽くなっていました。専門用語に圧倒されることなく、知識がすっと身につく構成は、初めてこうしたテーマに触れる人にこそふさわしいと感じます。
図解とフローチャートで直感的に理解できる構成
制度や手続きの本はどうしても文字が多くなりがちですが、この本はページを開いた瞬間に“分かる”という感覚があります。図やフローチャートが豊富に盛り込まれており、情報が視覚的に整理されているので、文章をすべて読まなくても全体像がつかめます。特に、どの制度をどの順番で手続きすればよいかを示す構成が秀逸で、読むたびに自分の行動が具体的にイメージできました。
また、レイアウトの工夫によって、どのページにも「読みやすさ」が意識されています。専門的な内容を扱いながらも、難解な印象を与えず、むしろ読者のペースに寄り添うような設計がされています。まるで「ここが今知りたいところでしょう?」と問いかけてくれるような構成で、自然とページをめくりたくなる仕掛けが感じられました。
文章と図が補い合うことで、ただ情報を知るだけでなく、“理解して使える”知識になる。このバランスのよさが、本書を他の解説書とは一線を画すものにしていると思います。
定年前後のToDoが一目でわかる実用性
定年を間近に控える人にとって、「何をいつまでにやればいいのか」という具体的な行動指針が最も重要です。この本では、年齢や状況ごとに整理されたToDoリストが冒頭にあり、まず全体を見渡せる点が非常に実用的でした。その後の各章で個々の項目が詳しく解説されるため、自然と行動の順序が理解できます。
特に印象的だったのは、制度や手続きを単なる説明で終わらせず、「行動に移すための情報」としてまとめていることです。ToDoリストに沿って準備を進めることで、今の自分の立ち位置や、これからすべきことが明確になります。読書というより、“人生の棚卸し”をしながらページを進めていく感覚でした。
読みながら何度も、「もっと早く知っておけばよかった」と感じました。この本は、読んで満足するためのものではなく、“読むことで前に進める”実践型の教科書だと思います。
手続き・税・年金・介護を横断的にカバーする網羅性
定年前後に直面するテーマは、実は一つではありません。働き方やお金のことに加えて、税金、健康保険、年金、介護、そして住まいなど、複数の課題が同時に押し寄せてきます。この本のすごいところは、それらを一冊に体系的にまとめている点です。分野ごとに独立した説明ではなく、相互に関係する制度を横断的に解説しているため、「あれとこれはどうつながっているのか」が自然に理解できます。
章立てもよく練られていて、冒頭の不安解消から始まり、収入の確保、手続き、税・保険・介護・住まいへと流れるように進んでいきます。まさに「人生の設計図」を描くような感覚で、自分の状況を整理しながら読める構成です。老後の不安を漠然と抱えている人にとって、読むほどに頭の中が整理されていく実感を持てるでしょう。
制度を点で説明するのではなく、人生全体の流れで解説してくれる。この“網羅性とつながりの可視化”こそ、本書が多くの読者に評価されている理由だと感じました。
退職金や年金の“もらい方”が明確になる具体性
退職金や年金のテーマは、多くの人が最も関心を持ちながらも、最も誤解が多い分野です。この本では、その“もらい方”を制度的な仕組みから丁寧に解きほぐし、どう受け取るのが自分にとって最適かを判断できるよう導いてくれます。難しい税制上の仕組みも、順序立てて説明されているため、読み進めるうちに自然と理解が深まります。
印象的だったのは、退職金や年金を“ただもらうもの”としてではなく、“どう活用するか”まで視野に入れている点です。老後の収入をいかに安定させるか、税負担をどう抑えるかといった現実的な視点から、制度を“自分の武器”として使えるように導いてくれます。
専門家監修による情報の信頼性と正確さ
この本を手に取ってまず感じたのは、「情報がしっかりしている」という安心感でした。世の中には定年や年金について断片的に語る記事や書籍が多い中で、本書は社会保険労務士やファイナンシャルプランナーなどの専門家による監修が入っており、制度や数字の扱いに一切の曖昧さがありません。説明の一つひとつに裏付けがあり、「自分の老後をこの知識に託しても大丈夫だ」と思わせてくれる説得力があります。
制度の改定や手続きの最新情報にも目配りが効いていて、古い知識のままでは誤った判断をしかねない部分も、しっかりアップデートされた内容で書かれています。そのため、読みながら「これは今の自分にもすぐ役立つ」と確信できました。信頼できる情報源に出会うことが、ここまで心を落ち着かせるものなのかと実感しました。
60代の生活設計を考えるきっかけになる
私はこれまで、定年後の生活についてなんとなく考えていた程度でした。しかしこの本を読み進めるうちに、「いつ」「どのように」行動すればよいのかが明確になり、老後の生活を自分の手で設計する意識が芽生えました。単に制度を説明するだけでなく、その背景にあるライフイベントや心構えまで触れているため、自然と「自分ごと」として読み込める構成になっています。
特に印象的だったのは、働き方やお金だけでなく、健康や家族との関わり、住まいといった広い視点から“定年後の人生”を描いている点です。年金や退職金の数字にとらわれず、「どう生きるか」というテーマを読者に静かに投げかけてきます。この本を通じて、人生の後半戦をより前向きに捉えられるようになりました。
読み終える頃には、老後を「終わり」ではなく「もう一つのスタート」と考えられるようになります。本書は知識を得るための書ではなく、“自分の未来を見つめ直す鏡”のような一冊です。
見やすいレイアウトで読み進めやすい
制度やお金の本というと、どうしても文字がぎっしり詰まっていて途中で挫折してしまうものが多いですが、この本はまったく違いました。ページ構成がとても見やすく、どのページを開いても「読む前から内容が整理されている」印象を受けます。章ごとに色分けや見出しデザインが工夫されており、重要なポイントが自然と目に入る設計になっています。
また、章の中で情報がだらだらと続くことがなく、テンポよくテーマが切り替わるため、長時間読んでいても疲れません。読み進めるごとに理解が深まる構成になっていて、まるで授業を受けているかのような感覚です。さらに、難しい専門語にはその都度わかりやすい補足説明が添えられているので、知識のない人でも安心して読み進められます。
まとめ

本記事の最後に、これまで紹介してきた『図解即戦力 定年前後のお金と手続きがこれ1冊でしっかりわかる教科書』を総括します。この本は、単なる制度解説ではなく、「定年後の人生をどう設計し、どのように安心して生きるか」を読者とともに考える実践的な指南書です。
締めくくりとして、以下の3つの視点から整理してみましょう。
- この本を読んで得られるメリット
- 読後の次のステップ
- 総括
それぞれ詳しく見ていきましょう。
この本を読んで得られるメリット
ここでは、本書を通して得られる主なメリットを詳しく紹介します。
定年前後の手続きを一元的に理解できる
定年退職を迎える際には、会社への手続き、年金や健康保険の切り替え、税金の申告など、複数の窓口で多くの申請が必要です。本書ではそれらを「年齢別」「手続き先別」に整理して紹介しているため、どのタイミングでどこに行けばよいかが明確になります。特に「年金事務所」「ハローワーク」「市区町村」「税務署」での手続きの流れが一目でわかる構成は、煩雑な公的制度に不慣れな人にとって大きな助けとなるでしょう。
退職金・年金・税金の仕組みを具体的に理解できる
退職金の受け取り方や年金の繰り上げ・繰り下げ受給の判断は、老後資金に大きく影響します。本書では、退職金の税金計算方法や年金制度の最新ルールを図解付きで丁寧に説明しています。さらに、住民税や所得税がどのように変化するのかを、ケーススタディを交えて解説しているため、「自分の場合どうなるのか」を具体的にイメージできるのが大きな特徴です。
定年後の働き方を現実的に設計できる
再雇用、嘱託、フリーランスなど、定年後の働き方は多様化しています。本書では、それぞれの雇用形態の違い、社会保険の扱い、高年齢雇用継続給付金の受給条件などを実例を交えて紹介。単に「働ける・働けない」という視点ではなく、「働くと何が変わるのか」「どんなメリット・デメリットがあるのか」を整理して理解できます。自分に合った働き方を選びたい人にとって、指針となる章です。
介護・住まい・医療費など“老後の生活”も具体的に想定できる
定年後の暮らしには、介護や医療、住まいに関する出費も大きな要素となります。本書では、介護保険の申請方法や介護サービスの利用プロセス、リフォームやバリアフリー化に関する助成金制度までを網羅。特に、70歳以降の医療費負担割合や高齢者施設の選び方など、家族にも役立つ情報が多く、将来の不安を軽減する内容になっています。
将来設計の“行動計画”を立てられる
本書の巻頭にある「年齢別ToDoリスト」は、定年準備の実践的な羅針盤です。「いつ」「何を」「どこで」行うべきかを一覧で把握でき、読後すぐに行動へ移せます。また、ふるさと納税やiDeCoなど、節税・資産形成の選択肢も紹介されており、「制度を知る」から「活用する」へとステップアップできる構成になっています。

定年前後の準備は“知識の広さ”より“正しい順序”が大切です。
本書のように制度・手続き・資金を一連の流れで理解することが、老後のリスクを最小限に抑える最大のポイントになります。
読後の次のステップ
本書を読み終えたあと、最も大切なのは「知識を行動に変えること」です。制度や手続きの理解だけでは、老後の安心は手に入りません。実際に自分の年金記録を確認したり、再雇用や資産運用のプランを立てたりすることで、初めて“実践的な定年準備”が始まります。
ここでは、本書を読んだあとに踏み出すべき具体的な行動のステップを紹介します。
step
1現状を見える化して整理する
まずは、自分の収入・支出・資産・負債・年金見込みなどの現状を「数字」で把握することから始めます。書籍内で紹介されている「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を活用し、公的年金の受給見込み額を確認しましょう。また、退職金の支給予定額や住宅ローン残高、医療保険や生命保険の内容も一覧化して整理しておくと、次のステップで行う「資金計画」が立てやすくなります。
現状を可視化することで、感覚的に捉えていた不安が数値で整理され、解決すべき課題が明確になります。
step
2ライフプランを立ててシミュレーションする
次に行うべきは、今後の人生設計を基にした「資金シミュレーション」です。定年後にどんな生活を送りたいのかを具体的にイメージし、そのために必要な支出を算出します。
旅行や趣味、子や孫への支援、住宅リフォームなど、ライフイベントごとの出費を見積もり、それに対して年金・貯蓄・投資収益をどう組み合わせるかを検討します。本書で紹介されている低リスク運用や税金控除策(ふるさと納税など)も、シミュレーションに組み込むとより現実的です。
自分だけで難しい場合は、ファイナンシャルプランナーに相談し、第三者の目線でプランを磨くのも効果的です。
step
3定年後の働き方と生き方を見直す
最後のステップは、経済面だけでなく「生き方の再設計」です。定年後の再就職、継続雇用、副業、フリーランスなど、働き方の選択肢は多様化しています。
本書では、社会保険との関係や給付金制度、フリーランス登録や法人設立まで丁寧に解説されています。これを参考に、自分に合った「働き続ける形」を見つけることが大切です。
step
4家族と将来設計を共有する
定年前後の変化は、本人だけでなく家族全体に影響します。住まいのリフォームや介護の準備、資産の相続など、早い段階で家族と話し合うことが重要です。特にパートナーとの間で「いつまで働くのか」「どこに住むのか」「年金はいくらもらえるのか」を共有しておくと、生活の見通しが立ちやすくなります。本書の「介護保険」「住まい」「相続」の章を参考に、家族ミーティングの議題を整理しておくとよいでしょう。

定年後の人生設計は、金融知識だけではなく「社会制度の理解」と「タイミングの戦略」が鍵です。
年金や税金、保険、雇用制度は連動しており、一つの判断が複数の結果に影響を与えます。
早めの情報整理と実践的な計画こそが、豊かなセカンドライフの基盤を築くのです。
総括
本書『図解即戦力 定年前後のお金と手続きがこれ1冊でしっかりわかる教科書』は、単なる制度解説書ではなく、「定年」という人生の大きな節目に直面する人々が、安心して次のステージへ進むための“人生戦略書”です。多くの人が不安を抱くお金や手続きの問題を、制度の背景から実践まで一貫して理解できる構成になっており、知識だけでなく“行動につながる理解”を得られるのが大きな特徴です。
特に優れているのは、定年前後の複雑な手続きを年齢や制度別に整理して解説している点です。退職金、年金、健康保険、税金、再雇用といったテーマが章ごとに体系的にまとめられており、どの段階で何をすべきかが一目でわかります。単なるマニュアル的な説明ではなく、「なぜこの制度があるのか」「どう選択すれば損をしないのか」といった意図や背景も示されているため、理解が深まりやすく、読後の行動にも迷いがありません。
また、介護や住まいといった老後生活のリアルな課題にも触れている点は、本書を“生涯設計の教科書”として際立たせています。定年を機に生活環境を見直す人にとって、経済面だけでなく、心と暮らしを整える視点を持つことができる内容です。リフォーム費用や介護保険の利用方法など、将来的な支出に関する具体的な準備をサポートする実用性も兼ね備えています。

本書は、「定年」という言葉に不安を抱く人々に対して、“準備すれば怖くない”という安心を与える1冊です。
制度を正しく理解し、自分の生活に合った選択をするための知識を得ることで、老後の生活をより豊かにデザインする力が身につきます。
読後には、将来に対して前向きな気持ちを持ち、自信をもって人生の次の章を歩み出せるはずです。
定年前後に読むべきおすすめの書籍

定年前後に読むべきおすすめ書籍です。
本の「内容・感想」を紹介しています。
- 定年前後に読むべきおすすめの本!人気ランキング
- 夫と妻の定年前後のお金と手続き 税理士・社労士が教える万全の進め方Q&A大全
- 月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑
- ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う
- 1日1分読むだけで身につく定年前後の働き方大全100
- マンガでかんたん! 定年前後のお金の手続き ぜんぶ教えてください!
- 知らないと大損する! 定年前後のお金の正解 改訂版
- 定年前、しなくていい5つのこと 「定年の常識」にダマされるな!
- 定年後 50歳からの生き方、終わり方
- 図解即戦力 定年前後のお金と手続きがこれ1冊でしっかりわかる教科書
- 定年後 自分らしく働く41の方法

