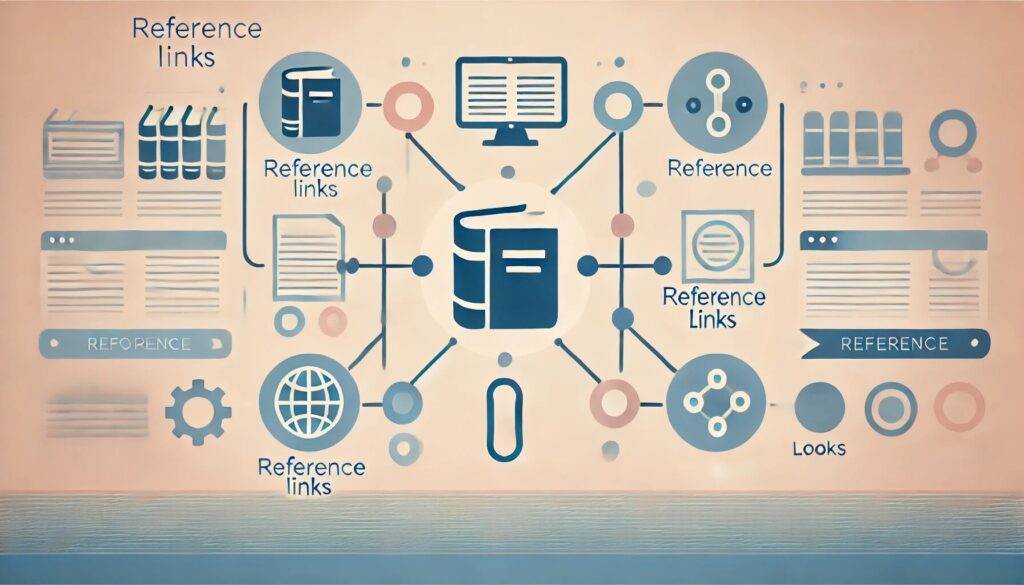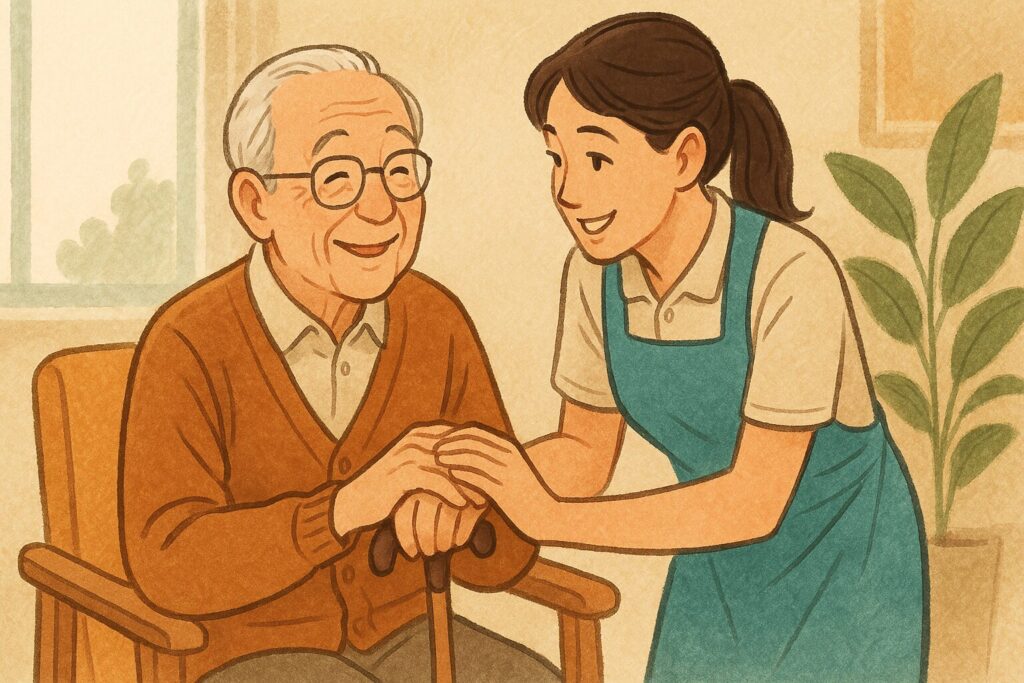
「介護給付」という言葉を聞いたとき、どんなイメージが浮かぶでしょうか?
「介護保険とは違うの?」「誰が使える制度なの?」「どうすれば受けられるの?」
そんな疑問を持つ方も多いかもしれません。
介護給付は、障害のある方が地域で自立した生活を続けるために、国や自治体が提供している障害福祉サービスのひとつです。日常生活の支援から、重度の障害を持つ方への専門的なケアまで、さまざまな支援が含まれています。

ご本人だけでなく、ご家族や支援に関わるすべての方にとって、介護給付を正しく知ることは大きな助けになります。
これから制度を利用したいと考えている方や、仕組みをしっかり理解しておきたい方は、ぜひ最後までお読みください。

この情報を深掘りする
-

-
障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年版】
障害のある子どもを育てている親御さんへ——日々の子育ての中で、こんなふうに感じたことはありませんか?「子どもの気持ちがうまくわからない」「どうサポートすればいいのかわからない」「このままでいいのかな… ...
続きを見る
-

-
障害者福祉について学べるおすすめの本3選【2026年版】
この記事では、障害者福祉について学べるおすすめの本を紹介していきます。障害者福祉を扱っている本は少ないため、厳選して3冊用意しました。障害者福祉とは、身体、知的発達、精神に障害を持つ人々に対して、自立 ...
続きを見る
-

-
障害年金について学べるおすすめの本4選【2026年版】
障害を負う可能性は誰にでもあり、その時に生活の支えになるのは障害年金です。その割に障害年金について理解している人は少ないのではないでしょうか?この記事では、障害年金について学べるおすすめの本を紹介して ...
続きを見る
介護給付とは何か?

障害のある方が地域で自立した生活を送るためには、日常生活に関するさまざまなサポートが必要です。その支援を制度として提供するのが「介護給付」です。この制度は、行政が責任を持って実施し、対象となる人に必要なサービスを提供しています。
ここではその基本的な枠組みを理解するために、以下の3点に分けて説明していきます。
- 制度の概要
- 必要とされる背景
- 実施主体
それぞれを確認することで、仕組みや導入された理由、どこが実施の責任を担っているのかが明確になるはずです。
制度の概要
介護給付とは、障害のある人が日常生活を送るうえで必要となる介助や支援を、専門の福祉サービスを通じて提供する制度です。これは、障害者総合支援法に基づいて定められており、障害の状態や支援の必要性に応じて、多様なサービスが利用できるようになっています。
たとえば、自宅での入浴や排泄の介助、外出時の同行支援、食事の準備や掃除といった家事の手伝いなどが含まれます。これらの支援は、単に身体的な補助を行うものではなく、本人の自立を助け、地域での生活を可能にするためのものです。
利用にあたっては、自治体が本人の状態を評価し、どのようなサービスがどれくらい必要かを判断して支給決定を行います。支援は必要な範囲で無理なく利用できるよう、一定のルールと制度設計のもとで提供されています。

市区町村が行う「障害支援区分」の認定結果や本人の希望、生活の様子をもとに判断されます。
専門職が関わって、個別の状況に応じた支援計画が作成されるんです。

必要とされる背景
この制度がつくられた背景には、障害のある人たちの生活の選択肢を広げる必要があったことが挙げられます。かつては、障害があると入所施設に入ることが一般的で、地域での暮らしは難しいとされてきました。しかし、時代とともに障害のある人も地域の一員として普通に暮らす権利があるという考え方が社会に広がりました。
現在では「地域共生社会」の実現が国の方針として掲げられ、誰もが住み慣れた場所でその人らしく暮らせるようにすることが重視されています。そのなかで、家族や地域の力だけでは支えきれない部分を補うために、公的な福祉制度が必要不可欠となったのです。
さらに、少子高齢化や核家族化の進行によって、家庭内だけで介護を完結させるのが難しくなっている現実もあります。こうした社会的背景が、制度を充実させる大きな後押しとなっています。

それは「ノーマライゼーション」という考え方が広まったからです。
障害があっても地域で普通に暮らせる社会をつくるという理念で、国際的にも主流の福祉の方向性なんですよ。

実施主体
介護給付を実際に提供する責任を担っているのは、市区町村です。具体的には、申請の受付やサービスの支給決定、事業所の指定や管理などを行い、地域における支援体制の中心となっています。支援の内容を検討するにあたっては、本人や家族からの聞き取りを踏まえ、専門職が関与して計画が立てられます。
サービス自体は、市区町村が直接行うのではなく、指定を受けた民間の福祉事業所やNPOなどが実際の現場で提供します。市区町村はこれらの事業所の監督や質の向上にも責任を持っており、制度全体の調整役となっています。
財政的には、国・都道府県・市区町村が費用を分担して支え合う仕組みになっています。たとえば、サービスの提供にかかる費用のうち、およそ半分を国が負担し、残りを地方自治体が分け合う形です。このように、制度は自治体主導で動きながらも、広い行政単位で支えられています。

基本的には、お住まいの市区町村役所にある「障害福祉課」や「福祉サービス課」が窓口になります。
迷った場合は、地域の相談支援事業所に問い合わせると、丁寧に案内してもらえますよ。

介護給付の種類と対象者
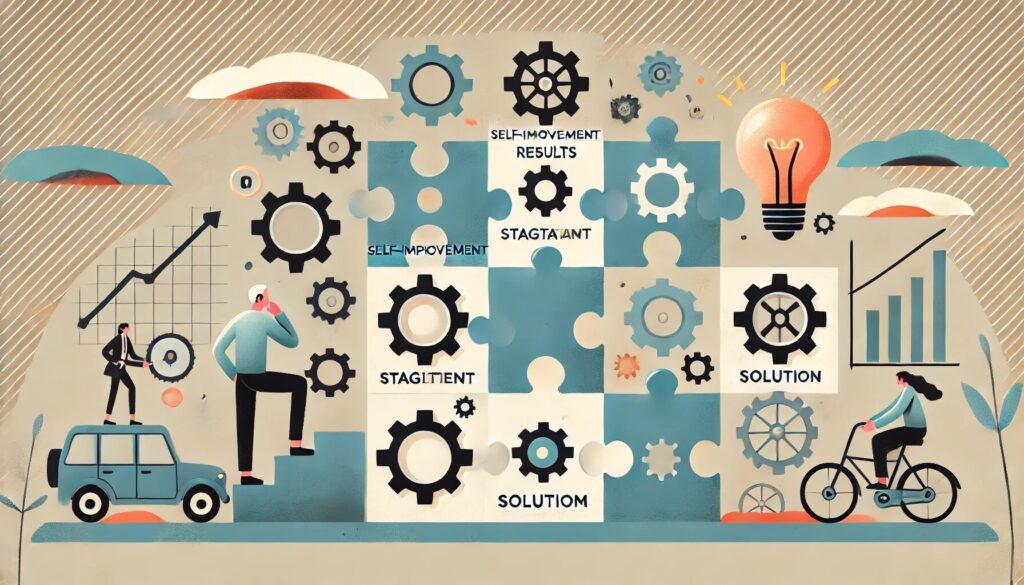
障害のある方が地域での生活を営むには、その人の状態や環境に応じた支援が必要不可欠です。介護給付には多様なサービスが用意されており、生活の場や支援の必要度に応じて組み合わせて利用できる仕組みになっています。
ここでは、それぞれのサービス内容や誰が対象となるかを整理して紹介します。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 短期入所(ショートステイ)
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援
それぞれの支援について具体的に見ていきましょう。
居宅介護(ホームヘルプ)
このサービスは、障害のある方が自宅で安心して生活を続けられるよう、必要な日常的支援を行うものです。具体的には、入浴や排泄、食事の介助といった身体介護に加えて、掃除や洗濯、調理などの家事援助、さらには生活上の困りごとに対する相談や助言までが含まれます。自立を目指す利用者にとって、生活のあらゆる場面において支えとなる重要なサービスです。
対象となるのは、障害支援区分が区分1以上の方です。障害のある子どもも、これと同程度の支援が必要と認められた場合には利用できます。また、通院等の付き添いを希望する場合には、区分2以上であることに加えて、移動や排泄などの特定の行動項目において、支援が必要であると認められることが条件となります。

調理や洗濯、掃除などの家事はもちろん、生活全般に関わるアドバイスや将来設計の相談まで支援の範囲に含まれます。
ただし、利用回数や内容は支給決定の範囲内で定められます。

この情報を深掘りする
-

-
居宅介護支援とは何か?「対象者」や「サービス内容」をわかりやすく解説
居宅介護支援は、自宅での生活を維持しながら介護サービスを受けるために欠かせないサポートです。 ケアマネジャーが個々の状況に応じたケアプランを作成し、身体介護や家事援助など、さまざまなサービスが提供され ...
続きを見る
重度訪問介護
重度訪問介護は、重い知的障害や精神障害、または肢体不自由があるために、日常生活すべてにわたって継続的な介護が必要な方に対して提供される支援です。このサービスでは、自宅での入浴や排泄、食事といった身体介助を中心に、家事、相談援助、外出時の付き添いや見守りなど、包括的なサポートが行われます。
支援時間が長時間にわたることを前提としている点も大きな特徴で、たとえば1日中支援が必要な方の場合、複数の介助者が交代で支援に入ることが想定されており、そのための報酬単価も設定されています。
対象となるのは、障害支援区分が4以上の方であり、さらに両手足に麻痺がある、または歩行や移乗、排泄などの項目で何らかの支援が必要とされていることが条件となります。加えて、行動関連項目の点数が一定以上であることも要件とされています。入院中や入所中の方がこのサービスを利用する場合には、区分6が必要となります。

このサービスは長時間の介護にも対応できるように設計されており、実際に24時間近く支援を受けて在宅で暮らしている方もいます。
必要に応じて、適切な人員体制が整えられますよ。

この情報を深掘りする
-

-
重度訪問介護とは何か?「対象者」や「サービス内容」をわかりやすく解説
重度訪問介護は、重度の身体的・知的・精神的な障害を抱える方々が自宅で自立した生活を送るために不可欠な支援を提供する制度です。 このサービスは、利用者が自宅で日常生活を営むために必要なサポートを幅広く行 ...
続きを見る
同行援護
同行援護は、視覚に障害のある方が安心して外出できるように、移動時の支援を行うサービスです。外出先での危険を避けるための誘導や、周囲の情報を言葉で伝える情報支援、さらには代筆や代読など、視覚的な障壁を補うための援助が含まれます。
このサービスの大きな特徴は、単なる移動支援にとどまらず、「その人が社会の中で安心して行動するための全体的な支え」であるという点です。たとえば、病院や役所に行く際に何が書いてあるのかを読み上げてもらったり、手続きを一緒に進めたりと、実際の生活に即した支援が行われます。
対象となるのは、視覚障害により移動が著しく困難な方であり、同行援護アセスメント調査において、視力障害や視野障害、夜盲などの評価があり、かつ移動障害についても一定以上の評価があることが必要です。このサービスでは、障害支援区分の認定は要件に含まれていません。

はい。外出に伴う一連の行動全体が支援対象になるため、買い物や役所の手続きなども含まれます。
ただし、個人の状態に合わせた支援計画に基づいて行われます。

この情報を深掘りする
-

-
同行援護とは何か?「対象者」や「サービス内容」をわかりやすく解説
視覚障害を持つ方が安心して自立した生活を送るために欠かせない「同行援護」。 このサービスは、視覚障害者が安全に外出し、必要な情報を得られるようにサポートするもので、単なる移動支援を超えた重要な役割を担 ...
続きを見る
行動援護
行動援護は、知的障害や精神障害により行動に著しい困難がある方に対して提供されるサービスです。外出や日常の行動に伴って生じる危険を回避するための援助や、移動中の支援、さらには行動自体を促すための介助が行われます。
支援を行うスタッフには、障害特性に対する理解と対応力が求められ、適切な距離感と配慮をもって関わる専門性が重要とされています。たとえば、急な不安やパニックに対する対応、感覚過敏への配慮など、個別性の高い援助が行われるのが特徴です。
対象者は、障害支援区分が3以上であり、行動関連項目において12項目の合計が10点以上ある方が該当します。18歳未満の場合には、それに相当する支援が必要であると認められることが条件となります。

行動援護の支援者は、そうした不安や困難に配慮した関わりができるよう専門的に訓練されています。
無理なく安心して外出できるよう、本人のペースに寄り添った支援が受けられますよ。

この情報を深掘りする
-

-
行動援護とは何か?サービス内容や対象者をわかりやすく解説
行動援護は、重度の知的障害や精神障害を持つ方々が安全に、そして自立して生活を送るために欠かせない支援サービスです。 この記事では、行動援護の具体的な内容や利用方法について、初心者でも理解しやすいように ...
続きを見る
重度障害者等包括支援
重度障害者等包括支援は、最重度の障害があり、日常生活すべてにおいて継続的な介護を必要とし、かつ意思疎通に著しい困難がある方に対して提供される、複数の障害福祉サービスをまとめて一括で支援する制度です。居宅介護や重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などが対象となり、状況に応じてこれらを柔軟に組み合わせて利用することができます。
この制度の大きな特徴は、必要な支援を分割して申請する手間を省き、包括的に支援内容を整理・提供する点にあります。利用者一人ひとりの状態にあわせた最適な組み合わせで支援が計画されるため、より切れ目のない支援が実現します。
対象となるのは、障害支援区分が6であり、かつ意思疎通が著しく困難な方です。そのうえで、四肢麻痺がある方、人工呼吸器を使用している方、最重度の知的障害者、行動関連項目で高い支援ニーズが認められる方など、いくつかの具体的な類型に基づいて判断されます。

この制度を利用すれば、状態に応じた支援を包括的に受けられるので、手続きの負担も大幅に軽減されます。
支援の漏れやズレを防ぎ、安定した在宅生活の維持にもつながりますよ。

この情報を深掘りする
-

-
重度障害者等包括支援とは?「対象者」や「支援内容」をわかりやすく解説
重度障害者等包括支援は、重度の障害を持つ方々が地域社会で自立した生活を送るために、多岐にわたる支援を包括的に提供する制度です。 この支援を通じて、利用者は居宅介護や訪問介護、短期入所など、日常生活に必 ...
続きを見る
短期入所(ショートステイ)
短期入所は、介護を担う家族が一時的にその役割を果たすことが難しくなったときに、障害のある方が施設に宿泊しながら必要な支援を受けられるサービスです。たとえば、冠婚葬祭や出張、病気、介護疲れによる休息などの理由で在宅介護が一時的に困難になった場合に利用されます。
このサービスでは、入所期間中、障害者支援施設や児童福祉施設などの環境で、入浴、排泄、食事などの介助が提供されます。利用者は、普段の生活環境とは異なる場所であっても、安心して過ごせるように支援を受けることができ、家族にとっても精神的・身体的なリフレッシュにつながります。
対象となるのは、障害支援区分が1以上の方や、必要な支援の程度に応じて国が定めた区分に該当する障害児です。また、医療型の短期入所では、ALSや遷延性意識障害、重症心身障害などの方が対象となり、病院や診療所などで医療的ケアを受けながら短期的に生活することが可能です。

短期入所は、そんなときのために用意されたサービスです。
一時的に安心して介護を預けられる場があることで、家族の負担を減らし、介護が継続しやすくなりますよ。

この情報を深掘りする
-

-
短期入所(ショートステイ)とは?「利用のメリット」や「注意点」をわかりやすく解説
短期入所サービスは、介護を必要とする方が一定期間施設に滞在し、専門的なケアを受けることができる介護支援サービスです。 このサービスは、介護者が一時的に介護から解放されるためのサポートであると同時に、利 ...
続きを見る
療養介護
療養介護は、医療的なケアを必要とする障害のある方が、医療と介護の両方を受けながら日中を過ごすことができるサービスです。主に病院や診療所などの医療機関で提供され、看護や機能訓練、療養管理に加えて、食事や排泄といった日常生活上の支援が行われます。
このサービスは、単に医療的処置を受けるだけでなく、生活の場として安心して過ごせるよう配慮された内容になっています。たとえば、人工呼吸器を装着している方や、常時医療的な観察や支援を必要とする方が、安定して過ごせる体制が整えられています。
対象となるのは、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの疾患を持ち、人工呼吸器を使用している方、筋ジストロフィーや重症心身障害などにより、常時の医療と介護の両方が必要とされる方です。また、かつて児童福祉法に基づく医療機関や施設を利用していた方も、条件によって対象となります。


この情報を深掘りする
-

-
療養介護とは何か?「対象者」や「サービス内容」をわかりやすく解説
療養介護とは、医療的ケアと日常生活の支援が一体となった、重度の障害を持つ方々を対象とする重要な福祉サービスです。 このサービスは、利用者が安全かつ安心して生活を続けられる環境を提供することを目的として ...
続きを見る
生活介護
生活介護は、日中に常に介護が必要な方に対して、食事や入浴、排泄などの支援を行うとともに、日中活動や創作的な作業などを通じて、生活能力の向上や社会参加を支援するサービスです。サービスは、障害者支援施設や通所施設などで提供されます。
このサービスの特長は、日々の暮らしを支えるだけでなく、自立に向けたステップとしての機能も担っている点です。生活支援だけでなく、利用者が調理や軽作業に挑戦したり、他の利用者と交流したりすることを通じて、社会とのつながりや自己肯定感を育むことも目的とされています。
対象となるのは、障害支援区分が3以上の方です。ただし、施設に入所している場合には区分4以上が必要です。また、50歳以上の方は区分2以上であれば利用可能です。さらに、生活介護と施設入所支援の組み合わせを希望する方については、市町村がその必要性を認めた場合に限り、条件を緩和して利用できる場合もあります。

生活介護では、介護だけでなく、作業や交流を通じた日中活動が用意されています。
支援を受けながら安心して参加できる環境が整っているので、自分らしく過ごすことができますよ。

この情報を深掘りする
-

-
生活介護とは何か?「対象者」や「サービス内容」をわかりやすく解説
生活介護は、障害を持つ方々が日常生活を安定して送るための支援を提供する障害福祉サービスの一つです。 しかし、具体的にどのような支援が受けられるのか、誰が利用できるのかについては意外と知られていないこと ...
続きを見る
施設入所支援
施設入所支援は、障害のある方が指定された施設に入所して生活する際に、夜間や休日を中心に生活全般の支援を受けることができるサービスです。提供される支援は、食事や排泄、入浴などの介護をはじめ、生活や将来に関する相談援助、情緒面での安定を図る関わりなど、日々の暮らしを支える包括的な内容となっています。
このサービスは、日中に生活介護などの別の福祉サービスと併用して利用することが基本であり、夜間や日常のすき間時間を安心して過ごせるようにする仕組みとして機能しています。たとえば、昼間は作業やリハビリを行い、夜間は施設で介護を受けながら休むという生活が可能になります。
対象者は、生活介護を受けており障害支援区分が4以上の方(50歳以上の方は3以上)です。また、自立訓練や就労支援などの福祉サービスと連携して、入所生活のなかで訓練を行うことが効果的と判断された方も対象になります。さらに、やむを得ない理由で通所が困難な方や、法改正以前から施設に継続して入所していた方も支援の対象とされます。

通所が困難な状況や生活の安定のために必要だと認められれば、施設入所支援の利用が可能です。
生活介護などと併せて支援を受けることで、より安心した日常が実現しますよ。

この情報を深掘りする
-

-
施設入所支援とは何か?「対象者」や「サービス内容」をわかりやすく解説
施設入所支援とは、障害を持つ方が安心して日常生活を送るために必要なサポートを提供する福祉サービスです。 特に夜間における入浴、排せつ、食事の介助や、生活に関する相談・助言などを通じて、利用者の生活を包 ...
続きを見る
介護給付の利用手続き

介護給付を受けるためには、いくつかのステップを踏んで手続きを進めていく必要があります。これは行政による正式な審査を経て行われるため、順序立てて対応することが重要です。
ここでは、どのような段階を経てサービスの利用に至るのかを分かりやすく解説していきます。
- step1 サービス利用の申請
- step2 障害支援区分の認定
- step3 サービス支給の決定
流れを把握しておくことで、手続きの途中で戸惑うことなくスムーズに対応できるようになります。
それぞれの段階について、詳しく見ていきましょう。
step1 サービス利用の申請
介護給付を利用したいと思ったら、最初のステップは自治体への相談です。具体的には、お住まいの市区町村の福祉窓口、もしくは指定された特定相談支援事業者に相談します。ここでは、生活の中でどんな支援が必要なのか、現在の状況にどのような困りごとがあるのかを整理していきます。
申請を進めるにあたっては、市区町村が指定する特定相談支援事業者によって「サービス等利用計画案」を作成してもらう必要があります。この計画案には、本人がどんな生活を望んでいるか、どのようなサービスが必要かといった内容が含まれます。これが、申請時に市区町村へ提出する大事な書類の一つとなります。

相談って、役所じゃないとできないのかな?手続きも自分でやらないとダメ?
地域の特定相談支援事業者が親身になって支援してくれます。
申請の準備から書類作成まで一緒に進めてくれるので、初めての方でも安心して手続きを始められますよ。

step2 障害支援区分の認定
申請が受理されると、次に行われるのが支援の必要性を測るための評価です。これは「障害支援区分の認定」と呼ばれ、申請者の身体的・精神的な状況、生活環境などをもとに、どの程度の支援が必要かを市区町村が判断します。
まず、市の職員などが自宅などに訪問し、日常生活における動作や困りごとについて聞き取り調査を行います。ここで得られた情報と、医師の意見書の一部をもとに、コンピューターによる一次判定が実施されます。次に、市区町村の審査会にて、一次判定の結果に加えて調査時の特記事項や医師の所見を総合的に検討し、二次判定が行われます。
その結果として、障害支援区分(1~6のいずれか、もしくは非該当)が決定され、申請者に通知されます。なお、18歳未満の児童の場合には、原則としてこの認定は実施されません。
なお、ここで言う「支援区分」とは、障害の種類や重度さに応じて、どの程度の支援が標準的に必要かを示す目安であり、今後のサービス量を決める基準となる重要な指標です。

はい、支援区分はサービスの内容や利用できる時間数に直結する大切な要素です。
適切に認定されることで、必要な支援がしっかり届くようになりますよ。

step3 サービス支給の決定
支援区分が決まると、それをもとにして実際の支給内容が検討されます。ここでは、申請者本人や家族の希望、介護者の状況、生活環境、そしてすでに提出されている「サービス等利用計画案」の内容が総合的に考慮され、どのサービスをどれくらい利用できるかが市区町村によって判断されます。
支給の決定に基づき、相談支援専門員は申請者と改めて話し合い、どの事業所を利用するかの調整を行います。この際、「サービス担当者会議」が開かれ、実際に支援を行う事業所の担当者も参加して、具体的な支援方針を共有します。その後、改めて「サービス等利用計画」が完成し、これに基づいて利用者と事業所が契約を交わすことで、実際のサービス利用が開始されます。

地域差はありますが、申請から利用開始までは1〜2か月ほどが目安です。
急ぎの事情がある場合は、早めにその旨を相談すると、柔軟に対応してもらえることもあります。

介護給付の費用と負担額

障害福祉サービスのひとつである介護給付には、原則として利用者の自己負担が生じますが、その仕組みは所得や生活状況に応じて細かく調整されています。実際には「使いたくても費用が心配」という声も少なくありませんが、制度には公平性を保つための配慮が数多く盛り込まれています。
以下の3つの視点から、金銭的な仕組みを整理しておくことで、安心してサービスを検討できるようになります。
- 利用者負担の基本的な仕組み
- 所得区分別の負担上限額
- 負担軽減のための各種制度
仕組みを理解することは、必要な支援を継続的に受ける第一歩です。
順番に読み進めながら、ご自身やご家族の状況にあてはめて確認してみてください。
利用者負担の基本的な仕組み
障害福祉サービスを利用するときには、原則として費用の一部を自己負担する必要があります。具体的には、サービス提供にかかる費用の1割が利用者の負担となります。残りの9割は公費によってまかなわれるため、利用者が支払う金額は抑えられています。
ただし、使えば使うほど負担が増えるわけではありません。月ごとの上限額があらかじめ設定されており、それを超えて支払う必要はありません。この上限は、個人や世帯の所得状況に応じて異なります。たとえば、収入の少ない世帯にはより低い上限額が設けられ、生活の負担を軽くできるよう配慮されています。
こうしたしくみは、制度を利用する人が経済的な理由で必要な支援を受けられなくなることを防ぐために整備されています。負担額が事前に明確であることで、安心してサービスを利用することができるのです。

たしかに費用は気になりますよね。でも安心してください。
収入に応じて月額上限が決められており、その範囲を超えることはありません。
詳細は受給者証に記載されていますので確認しやすいですよ。

所得区分別の負担上限額
利用者は受けるサービスに係る費用の一定額を自己負担することになります。
ただし、世帯の所得に応じた負担上限額が設定されており、1ヶ月に利用したサービス量にかかわらず負担は上限額までとなります(市町村民税非課税世帯の人に係る福祉サービスの利用者負担は無料)。
また、食費や光熱費は別途負担することになります。
| 所得区分 | 負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(居宅で生活する障害児) | 4,600円 |
| 一般1(居宅で生活する障害者および20歳未満の施設入所者) | 9,300円 |
| 一般2 | 37,200円 |
一般1
市町村民税課税世帯に属する者のうち、市町村民税所得割額16万円未満(世帯収入が概ね600万円以下)のもの(20歳未満の施設入所者、グループホームは除く)ただし、障害者および20歳未満の施設入所者の場合は市町村民税所得割額28万円未満(世帯収入が概ね890万円以下)のもの。
一般2
市町村民税課税世帯に属する者のうち、一般1に該当しないもの
医療に係る部分の負担上限額は、低所得の場合は、低所得1(市町村民税非課税世帯であって障害者または障害児の保護者の年収80万円以下)が15,000円、低所得2(市町村民税非課税世帯であって低所得1以外の場合)が24,600円、一般1・2の場合は40,200円となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、障害のある人が18歳以上(20歳未満の施設入所者は除く)の場合は本人および同じ世帯に属するその配偶者、18歳未満(20歳未満の施設入所者は除く)の場合は原則として保護者の属する住民基本台帳での世帯になります。

住民票のある市区町村の障害福祉窓口に問い合わせると、世帯収入や課税状況にもとづいて、適切な区分を案内してもらえます。
証明書の提出が必要な場合もあるので、事前に確認しておくとスムーズです。

負担軽減のための各種制度
経済的に厳しい状況にある方や、特別な事情を抱える利用者に対しては、さらに負担を軽くするための仕組みが用意されています。その一つが、医療と福祉サービスの自己負担額を合算し、限度を超えた分を支援する制度です。たとえば、療養介護を受けている人で医療費がかさむ場合、手元に一定の生活費が残るように調整されるようになっています。
また、施設に入所している方には、食費や光熱費、家賃の一部を公的に補助する制度もあります。特にグループホームの利用者には、所得に応じて月額の家賃補助が設けられています。こうした補助があることで、住む場所を確保しながらサービスを継続して利用することが可能になります。
さらに、同じ世帯内で複数の障害福祉サービスを併用していて、その合算額が基準を超えた場合には、超えた分が支給される仕組みもあります。これにより、支援が重なっても負担が増えすぎないよう工夫されています。

意外と知られていない支援も多いですが、条件を満たしていれば誰でも利用可能です。
不安があれば一度自治体の窓口や相談支援専門員に相談してみましょう。
個別の状況に合った制度を提案してもらえます。

この情報を深掘りする
-

-
障害福祉サービス の「利用者負担額」と「負担上限額」、「負担の軽減制度」について解説
障害福祉サービスの利用にかかる負担は、利用者の経済状況や世帯の収入に応じて異なり、誰もが安心して必要な支援を受けられるよう、多段階の仕組みが設けられています。 原則として、サービス利用料の1割を自己負 ...
続きを見る
介護給付を利用するメリット

介護給付は、単なる介助にとどまらず、本人の生活の質や家族の生活全体にも大きな影響をもたらします。この制度を活用することで、暮らしの選択肢が増え、日常がより豊かに、そして安心して過ごせるものへと変わっていきます。
支援を通じて得られる主な利点は次のとおりです。
- 日常生活の質の向上
- 社会参加の機会の拡大
- 家族の介護負担の軽減
- 専門的な支援による安心感
- 経済的負担の軽減
制度の活用によって得られる恩恵は、支援そのものの範囲にとどまらず、心身の安定や生活の選択肢を広げるきっかけにもなります。
ここからは、それぞれの観点について詳しくご紹介していきます。
日常生活の質の向上
障害がある方にとって、日常の動作ひとつひとつが大きな負担になることがあります。そこで介護給付を活用することで、入浴や食事、排せつといった生活の基本的な部分に対する支援を受けられます。たとえば居宅介護では、自宅での介助に加えて、調理や洗濯などの家事や、生活に関する相談や助言まで幅広く対応してくれます。
これらの支援は、ただ単に生活の手助けをするというものではありません。自分らしく暮らすための基盤を整え、精神的にも安心感をもたらします。安心して日々の暮らしを送れることで、本人の意欲や自尊心の回復にもつながっていくのです。

最初はそう感じる方も多いですが、支援員は専門の研修を受けたうえで訪問しており、プライバシーに配慮した対応を心がけています。
少しずつ信頼関係を築くことができれば、暮らしに欠かせない存在になっていきますよ。

社会参加の機会の拡大
障害があることで、外出や社会とのつながりを持つことが難しくなってしまうケースは少なくありません。しかし、介護給付の中には、外出の際に付き添い支援を行うサービスもあり、移動時の危険回避や必要な情報の提供などを受けることで、安全に外の世界へ踏み出せるようになります。
このような支援を活用することで、通院や買い物だけでなく、趣味や地域イベントへの参加など、生活の幅が広がっていきます。他者との関わりを持つことは、精神的な充実や社会的な役割意識の醸成にもつながるため、生活全体をより豊かにしてくれる大きな要素となります。

支援員が同行してくれることで、周囲の状況に応じた対応や、視覚・聴覚に関する補助が行われます。
安心して外出できる環境を整えるのが目的なので、無理のない範囲で活動を楽しめます。

家族の介護負担の軽減
日常的に介護を担っている家族にとって、支援が得られることは大きな助けになります。特に、常に目が離せないような状況では、家族自身が休息をとることもままならず、心身の疲労が蓄積されていきます。
こうしたときに短期入所サービスを活用すれば、一時的に施設に預かってもらうことができ、家族は冠婚葬祭や旅行、病気などの事情にも対応しやすくなります。さらには在宅支援サービスの併用により、日々の介護そのものも分担できるようになります。

家族だけで支えることは決して当たり前ではありません。
公的サービスを活用することは、家族が健康で長く寄り添っていくための大切な手段です。

専門的な支援による安心感
介護給付に関わる支援者は、障害のある方への対応について専門的な知識と経験を持っています。ただ身体を支えるだけでなく、障害特性に応じた声かけや行動サポート、緊急時の適切な判断など、専門性の高い対応が行えるのが大きな特徴です。
このような支援を受けることで、利用者本人だけでなく、その周囲の家族にとっても大きな安心につながります。たとえば、発作がある人や、突然混乱する可能性のある方にも、冷静に対応できる職員がそばにいることで、日々の暮らしに余裕と安定が生まれます。

支援員は研修や資格取得を通じて、障害の種類ごとに必要な知識と技術を習得しています。
定期的な研修で最新の支援方法を学び続けているのも特徴です。

経済的負担の軽減
サービスを利用する際には一部自己負担が発生しますが、その額は所得に応じた上限が定められており、想定外の高額負担が生じないよう設計されています。たとえば生活保護世帯や住民税非課税世帯は原則として負担が免除されており、それ以外の世帯でも月額の上限が設定されています。
この仕組みにより、継続的な支援の利用が必要な場合でも、費用面での心配を和らげながらサービスを活用することが可能となります。金銭的な理由で支援を諦めることがないよう、制度には細かな調整と工夫が凝らされています。

所得に応じた負担上限制度があるため、毎月の費用には一定の目安が設けられています。
さらに、補助制度や減免制度を利用すれば、負担を抑えながら必要な支援を継続できますよ。

介護給付を利用するデメリット

障害福祉サービスの介護給付には多くの利点がありますが、その一方で、利用者の状況や制度の仕組みによって不都合や不安を感じることもあります。支援を受ける上でどのような注意点があるのかを事前に理解しておくことで、制度をより自分らしく活用できるようになります。
以下のような点について、利用前に確認しておくとよいでしょう。
- 65歳到達時のサービス変更と自己負担増加の可能性
- 介護保険優先適用によるサービス制限の可能性
- 障害者手帳取得に対する心理的抵抗感
これらの要素は、個々の事情によって影響の度合いが異なりますが、知っておくことで後から困るリスクを減らすことができます。
65歳到達時のサービス変更と自己負担増加の可能性
障害福祉サービスは年齢を問わず利用できますが、65歳になると介護保険制度の対象年齢となるため、これまで受けていた支援が変更になることがあります。特に、障害者総合支援法に基づく介護給付を利用していた方は、原則として介護保険が優先適用となり、同じような支援を受ける場合でも制度が切り替わります。
この切り替えによって変わるのが、費用の負担のあり方です。障害福祉サービスでは所得に応じて上限額が設けられる「応能負担」が基本ですが、介護保険では一律で費用の一割(または二割・三割)が求められる「応益負担」となります。そのため、特に低所得の方にとっては、これまでよりも負担が重く感じられるケースもあります。
また、介護保険では原則として要介護認定が必要になるため、認定の結果によっては希望するサービスが受けられない可能性も出てきます。

介護保険への移行は原則ですが、例外的に障害福祉サービスの継続が認められるケースもあります。
制度上は併用も可能ですので、事前に自治体や相談支援事業者に確認することが大切です。

介護保険優先適用によるサービス制限の可能性
障害福祉と介護保険は、それぞれ独立した制度ですが、重複するサービスがある場合には、介護保険が優先的に適用されます。これは「制度の重複を避ける」という行政上の原則に基づくものであり、結果として、障害福祉サービスで受けていた支援が制限されることにつながることもあります。
例えば、これまで障害福祉サービスで受けていた訪問介護が、介護保険の訪問介護に切り替わった場合、支給限度額やサービス内容が異なるため、同じ量・同じ内容の支援を継続することが難しくなることがあります。とくに日中の見守りや長時間の付き添いが必要な方にとっては、介護保険の範囲では対応しきれないこともあるのが現状です。
このような制限を避けるには、障害福祉サービスが必要不可欠であることを説明し、例外的に継続利用を申請する必要があります。

介護保険では支援内容に上限があるため、十分なサービスが提供されないこともあります。
その場合、必要性を証明することで障害福祉サービスとの併用が可能です。
相談支援専門員にしっかりと伝えることが大切です。

障害者手帳取得に対する心理的抵抗感
障害福祉サービスを受けるためには、原則として障害者手帳の取得が必要です。しかし、この取得に対して精神的な抵抗を感じる方は少なくありません。たとえば、「障害者」と正式に認定されることに対する戸惑いや、周囲の視線を気にする気持ちが、そのハードルを高くしています。
とくに、長く社会生活を送ってきた方や、自立した生活を大切にしてきた方にとって、「手帳を持つこと=レッテルを貼られること」のように感じてしまう場合もあります。このような感情は、制度の合理性や利便性とはまた別の、人間らしい心の葛藤として存在しています。
しかしながら、手帳の取得は制度上の入り口にすぎません。必要がなくなれば返納も可能であり、何よりも支援やサービスを受ける権利を広げるための手段です。制度の存在が、生活の質を高めるきっかけとなることも多くあります。

障害者手帳は、困りごとを抱える方が必要な支援を受けるための「資格」のようなものです。
社会との関わりをより良いものにするためのツールと捉えることで、前向きに利用しやすくなります。

介護給付の提供事業所の選び方

障害福祉サービスを安心して利用するには、制度そのものの理解と同じくらい、どの事業所を選ぶかが大切です。利用者本人に合った支援が受けられるかどうかは、事業所の体制や環境に大きく左右されるため、慎重な見極めが求められます。
比較する際には、以下のような視点を意識するとよいでしょう。
- サービス内容と提供体制の確認
- 職員の資格と経験
- 事業所の設備と環境
- 利用者や家族からの評判
- アクセスと立地条件
こうした複数の要素をバランスよく見ながら、自分にとって最も使いやすく、安心できる支援を提供してくれる場所を見つけていくことが大切です。
サービス内容と提供体制の確認
介護給付を利用する際には、まずどのような支援を行っているのかを明確に把握しておくことが大切です。提供されるサービスには、入浴や食事、排せつなどの身体介助、家事の援助、生活相談、外出支援などがあり、事業所ごとに支援の幅や力を入れている分野が異なります。
また、提供体制にも注目する必要があります。たとえば、支援を受けられる曜日や時間帯、夜間や緊急時の対応の有無、利用者に対してどのような担当体制が組まれているかといった点は、日常の暮らしやすさに直結します。
サービスの内容や提供の仕組みが自分のニーズとずれてしまうと、せっかくの支援も十分に活かせなくなってしまいます。希望や必要性を事前に整理し、事業所と丁寧に確認することが重要です。

パンフレットだけでは違いが分かりにくいこともあります。
見学の際に支援内容を具体的に尋ねたり、自分の生活で必要なサポートが可能かどうかを直接聞いてみると違いが見えてきますよ。

職員の資格と経験
支援の質は、実際に支援に関わるスタッフの知識やスキルに大きく影響を受けます。そのため、どのような資格を持った職員が在籍しているかを確認しておくと安心です。たとえば、介護福祉士や看護師、または行動援護のような専門的な支援を提供するための研修を受けた職員など、それぞれの専門性が求められる場面は多くあります。
経験年数も大切な判断材料です。支援の現場では、マニュアル通りに進まないことも多いため、現場での判断力や柔軟な対応力が必要になります。経験豊富なスタッフが多い事業所であれば、安心して日々の支援を任せることができます。

もちろんです。安心してサービスを受けるためには、気になることを率直に確認することが大切です。
資格の有無だけでなく、どのような経験をしてきたかも尋ねてみてください。

事業所の設備と環境
施設内の設備や空間の使い方は、利用者が安心して過ごせるかどうかに直結します。たとえば、車いすでも安全に移動できるようバリアフリー設計が施されているか、室内が清潔に保たれているか、必要な福祉用具や医療機器が整っているかといった点を確認しておきましょう。
また、日々の生活を支える空間としての快適さも見逃せません。落ち着いた雰囲気や明るさ、換気の状態、他の利用者との距離感なども、支援を受ける上での安心感につながります。
見学をすることで、パンフレットでは分からない現場の雰囲気や職員の対応の様子も見えてきます。日常を過ごす場所として、自分に合った空間であるかどうかを感じ取ることが大切です。

遠慮は不要です。大切な暮らしの場になるかもしれない場所ですから、納得できるまで確認して構いません。
気になることは見学時にしっかり質問しましょう。

利用者や家族からの評判
実際にその事業所を利用している人や家族の声は、サービスの質を見極める上で非常に参考になります。表面的な情報では見えにくい対応の丁寧さやトラブル時の対応力、長期間の利用に対する満足度など、生の意見を知ることでリアルな姿が見えてきます。
情報を得る方法としては、インターネット上のレビューサイトや福祉関連のSNS、地域の福祉相談窓口での紹介、地域で活動する支援者からの紹介などが考えられます。直接的な口コミが難しい場合でも、複数の情報を組み合わせて判断することが重要です。
ただし、口コミは個人の感じ方に左右されやすい点もあるため、良い評判・悪い評判ともに、背景や事情を踏まえて受け取るようにしましょう。

口コミはあくまで「一つの声」として参考にするのが基本です。
実際の対応については、見学や面談を通じてご自身で確かめることをおすすめします。

アクセスと立地条件
サービスを定期的に利用する場合、事業所の場所や交通手段も大切な選択基準になります。自宅からの距離が遠かったり、バスや電車での移動が難しかったりすると、通うこと自体が大きな負担になってしまいます。
特に通所型のサービスでは、通いやすさが継続利用に大きく影響します。送迎の有無や公共交通機関の利用可能性、周辺の道路状況なども含めて検討するとよいでしょう。見学時には実際の移動時間やルートを確認しておくと安心です。
また、災害時の避難経路や安全対策が取られているかどうかも、立地とあわせて見ておくべきポイントです。

サービス内容と距離のバランスを見ながら検討しましょう。
送迎がある場合は、少し遠くても無理なく通えるケースもあります。

介護給付に関するよくある質問(FAQ)

介護給付に関して数多く寄せられています。
ここでは、利用を検討している方やそのご家族からよく寄せられる内容をまとめました。
- 利用するための手続きは?
- 自己負担額はどのくらい?
- 介護保険と一緒に使えるのか?
- 支援区分の認定について知りたい
このようなポイントを順に解説していきますので、気になる部分から読み進めてみてください。
制度の仕組みや使い方が、きっとクリアになるはずです。
介護給付を利用するための手続きは?
介護給付を受けるには、まず市区町村の障害福祉担当窓口や、地域の相談支援事業者に相談することから始まります。相談支援専門員は、サービスの内容や申請方法について丁寧に案内してくれるため、初めて利用を検討する方でも安心して手続きを進めることができます。
正式な申請を行うと、市区町村が心身の状態や生活状況を調査します。この認定調査には、本人との面談や日常動作の確認、医師の意見書の提出が含まれます。調査の結果は、まずコンピュータによる一次判定が行われ、その後、専門家による審査会で最終的な区分判定(いわゆる二次判定)が行われます。
申請者の支援の必要度をもとに、サービスの内容や利用量が決まり、通知が届いた後、事業所と契約してサービスの利用が始まります。なお、申請時には「サービス等利用計画案」の提出が必要で、これは指定された相談支援事業者が作成します。

大丈夫です。
相談支援専門員が一緒に進めてくれますし、不安がある場合は市区町村の障害福祉担当窓口に相談すれば、手続きの流れや必要書類について丁寧に案内してくれますよ。

介護給付の自己負担額はどのくらいですか?
介護給付を利用する際には、原則としてサービス費用の1割を利用者が負担することになっています。ただし、すべての人が無制限に支払うわけではなく、月あたりの自己負担には上限額が設定されています。
この上限額は、本人とその世帯の所得状況に応じて以下のように区分されています。
- 生活保護を受けている世帯:0円
- 市町村民税が非課税の世帯:0円
- 市町村民税が課税されているが、所得割が16万円未満の世帯:月額上限 9,300円
- 上記以外の世帯(高所得者など):月額上限 37,200円
つまり、1か月にどれだけサービスを利用しても、世帯区分に応じた上限額以上の負担は生じません。これは「負担上限月額」と呼ばれる仕組みで、経済的な負担を最小限に抑えるために設けられています。
この制度によって、安心して必要なサービスを受けやすくなっています。実際にどの区分に該当するかは、前年の所得状況をもとに市区町村が判定します。

そうなんです。介護給付では利用者の経済状況をふまえて負担額に上限が設定されています。
生活保護世帯や非課税世帯であれば自己負担はゼロになりますので、必要な支援を無理なく利用できる制度設計になっていますよ。

介護給付と介護保険サービスの併用は可能ですか?
65歳以上になると、原則として介護保険が優先されます。つまり、介護保険で受けられる支援は、そちらから使うことが求められ、障害福祉サービスとの併用には制限がかかる場合があります。ただし、障害特性や支援の必要性によっては、介護保険だけでは補えない部分に対して、引き続き障害福祉サービスの利用が認められるケースもあります。
この併用に関する判断は、個別の状況に応じて市町村が行います。支援の内容や必要度をしっかり伝えることが、適切な制度の併用につながります。介護保険のサービスだけでは生活が成り立たないと感じる方は、遠慮なく相談支援専門員や自治体に相談してみることが大切です。


介護給付を受ける際の障害支援区分の認定について
障害支援区分とは、支援がどの程度必要かを判断するための基準で、区分1から区分6までが設定されています。区分の数字が大きくなるほど、より多くの支援を必要としていると判断されます。これにより、支給されるサービスの種類や時間数が決まります。
区分の認定は、市区町村が行う認定調査と医師の意見書をもとに、一度目は機械による自動判定(一次判定)、その後は審査会による最終的な決定(二次判定)という2段階で進みます。対象者の生活状況や心身の状態が総合的に評価される仕組みです。
なお、18歳未満の児童の場合には、障害支援区分の認定は原則として行われず、支援の必要性を基に個別に支給内容が判断されます。

はい、本人の心身の状態や生活動作の内容を詳しく調べて、それに応じて必要な支援量を判定します。
決定された区分に応じて受けられる支援の量や種類が決まりますよ。

介護給付の課題と展望

障害福祉サービスにおける介護給付は、多くの方々の生活を支える重要な役割を果たしています。しかし、現状にはいくつかの課題が存在し、今後の展望とともに解決策が求められています。
以下に、主な課題とその展望について整理します。
- サービスの多様化と個別ニーズへの対応
- 人材不足と専門性向上の必要性
- 地域間格差とサービス提供の均衡化
- 財政的制約と持続可能な制度設計
- ICT・AI技術の活用によるサービス効率化
これらの課題に対する具体的な内容と展望について、以下で詳しく説明します。
サービスの多様化と個別ニーズへの対応
障害者の状態や生活環境は一人ひとり異なり、その支援に求められる内容も多様化しています。身体・知的・精神などの障害種別ごとに必要な配慮はもちろんのこと、同じ障害でもライフステージや住環境によって適切な支援のあり方は大きく変わります。しかし現状の介護給付制度は、あくまで標準化された支援メニューを中心に設計されているため、細かな個別ニーズに十分応えきれていないという課題があります。
たとえば、重度の障害とともに精神的な不安を抱える方への対応や、発達障害を持つ方へのコミュニケーション支援など、従来の枠組みでは対応が難しいケースも少なくありません。今後は、利用者ごとの生活実態や希望を丁寧に把握し、柔軟な支援を組み合わせる仕組みづくりが求められます。


人材不足と専門性向上の必要性
介護給付を支える現場では、専門知識と経験を持った支援者の存在が欠かせません。しかし、福祉分野では慢性的な人手不足が続いており、特に障害特性に応じた高度な対応が求められる場面では、支援者側の負担も大きくなっています。新規参入の担い手が少ないことに加え、離職率の高さや待遇面の課題も指摘されています。
また、福祉現場では即時の判断や個別対応が求められることが多く、一定以上の専門性がなければ、支援の質を安定して保つことはできません。そのため、支援者の育成とスキルアップのための研修制度の拡充や、キャリアパスの整備、処遇改善など、総合的な人材政策が不可欠です。

地域や事業所によってはそのようなことも起こりえます。
そのためにも人材確保や定着に向けた国や自治体の支援が重要視されています。

地域間格差とサービス提供の均衡化
都市部と地方部では、サービスの選択肢や事業所の数、支援の内容に大きな開きがあります。人口の少ない地域では、事業所そのものが不足していたり、特定の障害種別に対応できる人材がいないことも珍しくありません。これにより、利用者が本来受けられるはずの支援を断念したり、無理に遠方の施設まで通わなければならないといった状況が発生します。
このような地域間格差を是正するためには、全国的な支援体制の整備とともに、地域資源を活用した独自の仕組みづくりも求められます。たとえば、訪問支援の拡充や、ICTを活用した遠隔相談支援の導入など、地域の特性に応じた柔軟な対応が期待されています。

はい、実際に事業所の数や種類に差があるため、同じ制度でも提供される中身には開きがあります。
今後は、地域格差を是正するための国の取り組みがより一層重要になります。

財政的制約と持続可能な制度設計
障害福祉にかかる公的支出は年々増加しており、介護給付も例外ではありません。高齢化の進展と相まって、限られた財源の中で障害者支援をどう維持していくかは、社会全体の大きな課題です。現在の制度設計では、国と自治体が費用を分担するしくみですが、今後さらにサービス需要が増えた場合、支出の増大が避けられません。
このような状況をふまえ、制度を長期的に維持するためには、財源配分の見直しや、無駄の削減といった効率化だけでなく、必要とされる支援の範囲や優先順位を見極める作業も求められます。また、利用者負担の在り方を見直す議論も今後進む可能性があります。

必要な人への支援は継続される方向ですが、効率性や公平性を保つために制度の見直しが進められています。
支援の質を下げない工夫が、国や自治体に求められているのです。

ICT・AI技術の活用によるサービス効率化
近年では、ICT(情報通信技術)やAI(人工知能)を活用した福祉支援の取り組みが注目されています。たとえば、記録業務の自動化、利用者の状態把握の効率化、職員間の情報共有の迅速化などが進められています。
また、支援者がタブレット端末を用いて支援内容をリアルタイムで記録できる仕組みや、AIが利用者の行動パターンを分析して最適なケア方法を提案する仕組みも一部で導入されています。
これにより、職員の業務負担が軽減され、より本質的な対人支援に時間を割くことが可能となります。ICT導入には設備投資や研修などの課題もありますが、将来的な人材不足への対応や支援の質の向上に向けた鍵とされています。

全てを置き換えるわけではなく、あくまで人の支援を補完する道具としての活用が主です。
うまく使えば、利用者にも支援者にも大きなメリットがあります。

まとめ

介護給付は、障害のある方が安心して地域で自分らしい生活を送るための土台となる大切な制度です。支援の内容は多岐にわたり、日常生活のサポートから、医療的なケアや社会参加の促進まで、利用者一人ひとりの状況に応じて多様な形で提供されています。
申請手続きや支援区分の認定など、制度の仕組みにはやや複雑な部分もありますが、相談支援専門員や市区町村の担当窓口がしっかりと支えてくれますので、迷ったときには気軽に相談してみることが大切です。
介護給付を正しく理解し、必要な支援を適切に受けることで、本人はもちろん、そのご家族にとっても生活の質が大きく向上します。この制度の持つ力を知ることが、誰もが安心して暮らせる地域社会への第一歩です。今後の人生や身近な人の支援を考えるうえでも、ぜひこの知識を活かしていただけたらと思います。
参考リンクとリソース