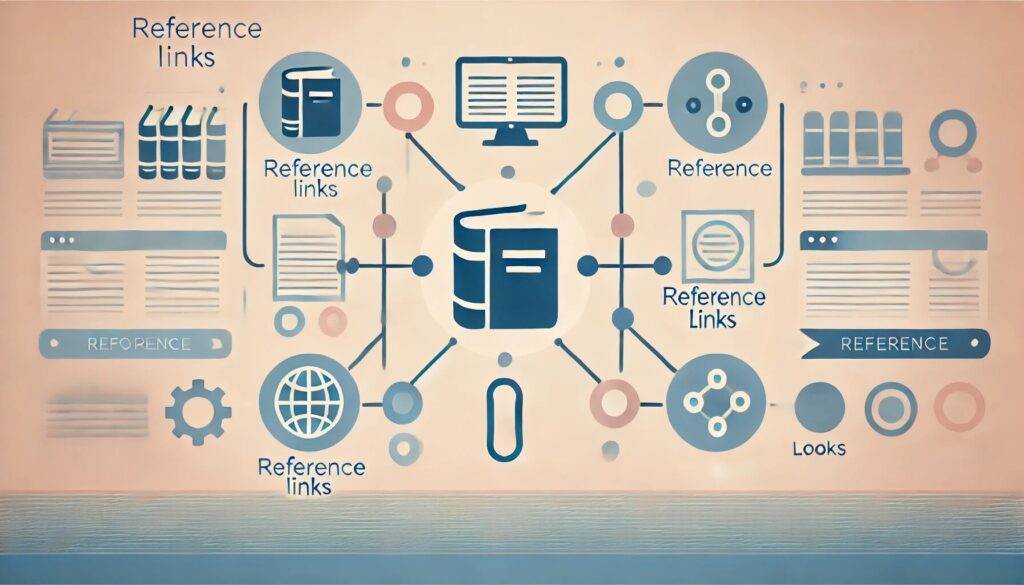「療育手帳」という言葉を聞いたことはあるけれど、具体的にどのようなものなのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
療育手帳は、知的障害のある方が適切な支援やサービスを受けるための手帳ですが、その仕組みや取得方法、対象者の条件について詳しく知られているわけではありません。

例えば、「どの程度の障害があれば取得できるのか?」「手帳を持つことで、どんな支援を受けられるのか?」「取得や更新の手続きは大変なのか?」といった疑問を持つ方もいるでしょう。
また、療育手帳にはメリットだけでなく、取得に伴う心理的な負担や、自治体による基準の違いといった課題もあります。
さらに、発達障害者への対応の曖昧さや、他の障害者手帳との違いなど、知っておくべき点も少なくありません。
本記事では、療育手帳の基本的な仕組みから、対象となる人の条件、申請の流れ、手帳を取得するメリット・デメリット、そして制度上の課題まで詳しく解説します。
初めて療育手帳について調べる方でも理解しやすいように、分かりやすく説明していきますので、ぜひ最後までお読みください。

合わせて読みたい記事
-

-
障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年版】
障害のある子どもを育てている親御さんへ——日々の子育ての中で、こんなふうに感じたことはありませんか?「子どもの気持ちがうまくわからない」「どうサポートすればいいのかわからない」「このままでいいのかな… ...
続きを見る
-

-
障害者福祉について学べるおすすめの本3選【2026年版】
この記事では、障害者福祉について学べるおすすめの本を紹介していきます。障害者福祉を扱っている本は少ないため、厳選して3冊用意しました。障害者福祉とは、身体、知的発達、精神に障害を持つ人々に対して、自立 ...
続きを見る
-

-
障害年金について学べるおすすめの本4選【2026年版】
障害を負う可能性は誰にでもあり、その時に生活の支えになるのは障害年金です。その割に障害年金について理解している人は少ないのではないでしょうか?この記事では、障害年金について学べるおすすめの本を紹介して ...
続きを見る
療育手帳とは何か?

知的障害を持つ方々が、社会でより良い支援を受けるために必要なのが「療育手帳」です。
この手帳を持っていることで、日常生活や社会参加において、さまざまな福祉サービスが受けやすくなります。
しかし、「療育手帳」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
初めて耳にする方でも理解しやすいように、以下の3つの観点から詳しく解説します。
- 療育手帳の定義と概要
- 療育手帳が必要とされる背景
- 法律や制度に基づく療育手帳の概要
それぞれについて、わかりやすく説明していきます。
療育手帳の定義と概要
療育手帳は、知的障害があると認定された方に対して交付される証明書です。
この手帳は、知的障害があることを公的に証明し、福祉サービスや支援制度を利用する際に必要となります。
例えば、公共交通機関の割引や税金の控除、医療費の助成といった支援を受ける際、療育手帳がその利用資格を証明します。
日本全国で導入されている制度ですが、実は都道府県によって名称が異なることもあります。
たとえば、東京都では「愛の手帳」と呼ばれることもあります。

これは、日常生活の支援を受けやすくするための公式な証明書です。
割引や助成制度の利用に必要となることが多いです。

療育手帳が必要とされる背景
知的障害を持つ方々は、日常生活や社会参加において多くの困難を抱えることが少なくありません。
たとえば、学習の遅れやコミュニケーションの難しさ、社会的なルールへの適応が難しいといった課題が挙げられます。
こうした課題に対処するためには、専門機関によるサポートが不可欠です。
しかし、支援を受けるためには、まずその人が適切な支援を受けるべき対象であることを証明しなければなりません。
そこで必要となるのが療育手帳です。
この手帳は、支援が必要であることを公式に示す証明書となり、スムーズに行政や支援機関とつながるための「パスポート」のような役割を果たします。

知的障害のある方々が支援を受けやすくするための公的な証明が必要だからです。
これがないと、一部の支援制度は利用できません。

法律や制度に基づく療育手帳の概要
療育手帳の運用は、各都道府県や指定都市の自治体によって行われています。
判定基準や支援内容は、地域によって異なる場合がありますが、基本的には障害者総合支援法に基づいています。
具体的な判定は、児童相談所(18歳未満の場合)や知的障害者更生相談所(18歳以上の場合)で実施されます。
判定が行われた後、手帳が交付され、各種サービスの利用が可能になります。
また、手帳は等級(A1、A2、B1、B2など)に分けられ、その等級に応じて受けられるサービスが変わる仕組みです。
これは、障害の程度に応じた適切な支援を提供するためのものです。

基本的な枠組みは全国共通ですが、具体的な支援内容や交付基準は自治体ごとに異なります。
引っ越しをするときは注意が必要です。

療育手帳の対象者

療育手帳は、知的障害がある方が、日常生活や社会参加において適切な支援を受けられるように設けられた制度です。
対象となるかどうかは、障害の種類や程度、年齢、自治体ごとの基準によって異なります。
ここでは、制度の対象者がどのように定義されているのかを詳しく解説します。
以下の5つの観点から順に見ていきましょう。
- 知的障害の定義と判定基準
- 対象となる障害の種類
- 年齢別の判定機関と手続き
- 発達障害者への適用条件
- 自治体による判定基準の違い
これらの要素を理解することで、療育手帳がどのような基準で交付されるのかが明確になります。
知的障害の定義と判定基準
知的障害は、知的機能の発達に遅れや停滞が見られる状態を指します。
医学的には、知能指数(IQ)が70程度以下であることが基準とされ、さらに適応行動(日常生活での自立性や社会性)にも制限があることが条件となります。
これらの制限は、18歳未満の発達期に現れることが必要です。
判定は、心理検査(知能検査)や医師の診断をもとに行われます。
日常生活での行動観察や、本人および家族からの聞き取りも含まれるため、総合的な評価が重要となります。


療育手帳の対象となる障害の種類
療育手帳の対象となるのは、主に知的障害を持つ方々です。
ただし、知的障害と併せて他の障害(視覚、聴覚、肢体不自由など)を併発している場合も、支援の必要性に応じて対象となることがあります。
発達障害(自閉スペクトラム症や注意欠陥多動性障害など)については、知的障害を伴わない場合は療育手帳の対象外となることが多いです。
この場合は、別の障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の取得が必要になることがあります。


年齢別の判定機関と手続き
申請や判定における担当機関は、年齢によって異なります。
- 18歳未満:児童相談所が担当
- 18歳以上:知的障害者更生相談所が担当
申請の流れは、各機関に相談してから判定を受け、結果に基づいて手帳が交付される形になります。
判定結果は、知能検査や専門家の面談を通じて総合的に評価されます。


発達障害者への療育手帳の適用条件
発達障害がある方でも、知的障害を併せ持つ場合は療育手帳の交付対象となります。
例えば、自閉スペクトラム症で知能指数が低い場合は、支援が必要と判断され、療育手帳の申請が可能になります。
一方で、知的機能に問題がない場合は、療育手帳の対象外となることがほとんどです。
その場合、他の障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の取得が適切とされることが多いです。

はい、療育手帳は知的障害が主な対象です。
知的障害がない場合は、他の支援制度の利用を検討しましょう。

自治体による判定基準の違い
療育手帳の交付基準は全国共通の制度ですが、具体的な運用は各自治体に委ねられています。
そのため、同じ程度の障害でも、自治体によって支援の内容や判定の厳しさが異なる場合があります。
特に、支援内容の充実度や手帳の交付基準に地域差があるため、引っ越しをする場合は事前に転居先の自治体の基準を確認しておくことが重要です。

はい、自治体によって基準や支援の内容が異なることがあります。
引っ越し前には必ず確認しておきましょう。

療育手帳のメリット

療育手帳は、知的障害のある方が受けられる支援やサービスを利用する際に役立つ手帳です。
この手帳を取得することで、日常生活や社会参加においてさまざまなメリットを享受できます。
以下に、療育手帳を持つことで得られる主な利点を紹介します。
- 交通機関の割引
- 税金の控除・減免
- 各種手当の受給
- 医療費の助成
- 生活関連サービスの割引・免除
- レジャー施設や公共施設の優待
- 就労支援の活用
- 教育支援の充実
これらの特典を活用することで、生活の質を向上させることが可能です。
以下で、それぞれの項目について詳しく説明します。
交通機関の割引
療育手帳を所持していると、公共交通機関を利用する際に運賃の割引を受けられることがあります。
割引の対象となるのは、鉄道、バス、タクシー、フェリー、航空機など多岐にわたります。
例えば、JRでは本人と介助者1名分の運賃が半額になるケースが多く、長距離移動の負担を軽減することができます。
また、地下鉄や市バスでも、各自治体の運営する交通機関によって割引率や条件が異なります。
特に都市部では、障害者向けの定期券が設定されており、通勤や通学における費用負担を大幅に減らせることが特徴です。
加えて、タクシー料金の割引制度も利用できます。
タクシーの場合、利用料金の10%割引が適用されることが一般的で、外出が難しい方や公共交通機関の利用が困難な場合に大きな助けとなります。


税金の控除・減免
療育手帳を持つことで、所得税や住民税などの税金が軽減される優遇措置を受けることができます。
具体的には、障害者控除という制度があり、一定額の所得が非課税となります。
この控除により、年間の税負担が大きく軽減され、経済的な負担が和らぎます。
たとえば、障害者控除として27万円、特別障害者控除として40万円の控除を受けられる場合があります。
控除額は、障害の程度や個人の収入状況によって異なりますので、詳細は税務署や市区町村の窓口で確認する必要があります。

その通りです。
特に、家族に知的障害を持つ方がいる家庭にとって、税制上の優遇は大きな支えとなります。

各種手当の受給
療育手帳を持っていると、国や自治体が支給するさまざまな手当を受給できる可能性があります。
代表的なものに、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当などがあり、これらの支援は日常生活の安定や福祉サービスの充実を目的としています。
障害児福祉手当は、20歳未満で著しい障害を持つ児童に対して支給されるもので、特別児童扶養手当は障害を持つ子どもを扶養する家庭を対象にしたものです。
これらの手当は所得制限が設けられている場合も多く、家庭の経済状況に応じた支給が行われます。
特別障害者手当は、20歳以上で日常生活において常に特別な介護が必要な方を対象とし、重度の障害を持つ成人に対して支給されます。
これらの手当は、障害の程度や世帯収入などに応じて受給額が変わるため、申請の際には詳細な条件を確認することが必要です。

手当の種類や支給条件は障害の程度や所得状況によって異なります。
お住まいの自治体の福祉担当窓口で相談するのが最も確実な方法です。

この情報を深掘りする
-

-
重度の障害児を育てることになると給付される「障害児福祉手当」とは
この記事では「障害児福祉手当」について解説していきます。重度の障害児を養育することになると、精神的・物質的な負担がかかってきます。日本の社会保障では、重度の障害児を養育する父母などの負担を軽減する「障 ...
続きを見る
-

-
障害児を育てる事になると給付される「特別児童扶養手当」とは
この記事では「特別児童扶養手当」について解説していきます。障害児の養育することにより、手がかかりパートに出ることができなくなったり、車いすや眼鏡などに費用がかかる事態が発生します。日本の社会保障では、 ...
続きを見る
-

-
特別障害者手当とは?支給される金額と認定基準をわかりやすく解説
重度の障害者を家庭内で介護することになると、特別な負担をすることになります。介護することの負担のみならず、そのためにパートやアルバイトをする時間がなくなることになります。日本の社会保障には、20歳以上 ...
続きを見る
医療費の助成
療育手帳を持っていると、医療費の助成制度を利用することができます。
その代表的なものが、自立支援医療制度です。
これは、知的障害を持つ方が必要な医療サービスを受けやすくするために設けられているもので、自己負担額が軽減される制度です。
多くの自治体では、医療費の自己負担額が無料、もしくは大幅に減額される制度があり、定期的な通院や治療が必要な場合でも安心して医療を受けることができます。
また、入院費用や治療にかかる交通費の一部を助成する制度もあります。

その通りです。
特に長期的な治療が必要な場合、医療費助成は経済的な負担を大幅に軽減します。

この情報を深掘りする
-

-
自立支援医療とは何か?「対象者」や「サービス内容」をわかりやすく解説
自立支援医療は、精神疾患や身体障害、先天性の疾患を持つ方々が、経済的な負担を軽減しながら必要な医療を継続して受けられるように設けられた公的制度です。 医療費の自己負担が原則1割に抑えられるこの制度は、 ...
続きを見る
生活関連サービスの割引・免除
療育手帳を所持していると、日常生活に関連するさまざまなサービスの料金が割引されたり、場合によっては免除されることがあります。
これは、知的障害を持つ方が快適に生活できるように配慮された制度の一環です。
たとえば、水道料金やガス料金、電気料金などの公共料金が減額される場合があります。
これらの割引は、各自治体によって異なりますが、手帳を持っている本人だけでなく、扶養している家族にも適用されることがあるため、家計全体の負担を軽減する効果があります。
また、NHK受信料の免除もその一例です。
知的障害を持つ方がいる家庭では、申請することで受信料の全額免除や半額免除が受けられることがあります。

はい、毎月の生活費が減ることで、経済的な負担が大きく軽減されます。
特に長期的に見れば、家計への影響はかなり大きくなります。

レジャー施設や公共施設の優待
療育手帳を提示することで、レジャー施設や公共施設の入場料が割引される、または無料になることがあります。
これにより、障害を持つ方も気軽に外出でき、レクリエーション活動の幅が広がります。
具体的には、テーマパーク、動物園、水族館、美術館、博物館などの施設で割引が適用されるケースが多いです。
多くの場合、本人だけでなく、付き添いの介助者も同様の優待を受けられることがあります。
これにより、外出先での経済的負担が軽減され、家族でのお出かけもしやすくなります。
また、公共施設でも割引制度が導入されている場合があります。
市民体育館や図書館、プールなどでは、利用料が減額されることが多く、地域での活動への参加も促進されます。

そうですね。
知的障害を持つ方が安心して楽しめる環境が整っているので、家族や友人と一緒にさまざまな体験を楽しむことができます。

就労支援の活用
療育手帳を所持していると、就労に関するさまざまな支援制度を活用することができます。
これは、知的障害を持つ方が社会での自立を目指し、安定した職業生活を送るために設けられた制度です。
まず、障害者雇用促進法に基づいて、企業は一定の割合で障害者を雇用する義務があります。
療育手帳を持っていることで、この制度の対象となり、障害者枠での就職活動が可能となります。
また、職場での合理的配慮が受けられるため、無理のない範囲での勤務が期待できます。
さらに、ハローワークや障害者就業・生活支援センターでは、職業訓練や就労支援プログラムが提供されています。
これにより、仕事に必要なスキルを身につけたり、就職活動のサポートを受けることが可能です。

企業は、働きやすい環境を整えるための合理的配慮を行う義務があります。
例えば、作業内容の調整や勤務時間の短縮、専用の支援員の配置などが挙げられます。

教育支援の充実
療育手帳を持つことで、教育面でもさまざまな支援を受けることができます。
特別支援教育の対象となることで、個々の学習ペースや能力に合わせた教育プログラムが提供されるようになります。
具体的には、特別支援学校や特別支援学級での授業が用意されており、専門の教員が指導にあたります。
また、通常学級に在籍しながら支援を受ける「通級指導教室」もあり、必要に応じたサポートが柔軟に提供されます。
さらに、学費の減免や奨学金制度も利用できる場合があります。
これにより、経済的な負担を軽減し、教育の機会を広げることが可能になります。
学校生活における環境整備や教材の提供など、学習に集中しやすい環境を整えることが目的です。

特別支援学校では、障害の特性に応じた専門的な指導が受けられます。
個別の支援計画に基づき、生活スキルの向上や将来的な自立に向けた教育が行われます。

療育手帳のデメリット

療育手帳の取得には多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。
以下に主なものを挙げ、それぞれ詳しく説明します。
- 療育手帳取得に伴う心理的負担
- 申請や再判定手続きの手間
- 周囲からの偏見や差別の可能性
- 障害者雇用枠での就労における給与や昇進の制限
- 生命保険やローン契約等への影響
これらの点について、以下で詳しく解説します。
療育手帳取得に伴う心理的負担
療育手帳を取得することで、知的障害を公式に認定されることに対して心理的な負担を感じる方もいます。
特に軽度の知的障害のある方やその家族にとって、「障害者」として分類されることに抵抗を感じる場合があります。
周囲の目を気にして手帳の取得をためらうケースも少なくありません。
また、療育手帳を持つことで自分や家族の将来に対する不安が増すこともあります。
「手帳を持つことで、社会的なレッテルを貼られてしまうのではないか」「この先、普通の生活ができなくなるのではないか」という懸念が生まれることがあります。
しかし、療育手帳は支援を受けるためのツールであり、取得すること自体が人生の選択肢を狭めるものではありません。

手帳の取得は本人が必要な支援を受けるためのものです。
他人に知られる必要はなく、必要な場面でのみ活用すれば問題ありません。

申請や再判定手続きの手間
療育手帳の取得には、申請手続きが必要となります。
また、一度取得した後も定期的な再判定が求められる場合があります。
手続きには医師の診断書や知能検査の結果などが必要となり、各自治体によって必要な書類や手順が異なるため、申請者にとって負担となることがあります。
さらに、療育手帳の再判定では、知的障害の程度が軽減されたと判断されると手帳が更新されない場合があります。
このため、引き続き支援を受けたいと考えている家庭にとっては、大きな不安要素となることがあります。
特に、成人後の更新では、判定基準が厳しくなるケースもあり、取得時と同じ支援を受けられなくなる可能性もあります。

確かに手続きには手間がかかりますが、一度取得すれば長期的な支援を受けられます。
自治体の窓口で相談すれば、必要な手続きをスムーズに進めることができます。

周囲からの偏見や差別の可能性
療育手帳を持っていることが知られると、周囲から偏見を持たれるのではないかと心配する方もいます。
特に、障害への理解が十分でない職場や学校では、偏見によって不利な扱いを受けるのではないかと不安に感じることがあるかもしれません。
しかし、療育手帳は支援を受けるためのものであり、日常生活の中で他人に見せる必要はありません。
むしろ、必要な支援を受けることで、より安定した生活を送ることができるようになります。
また、近年では障害者に対する理解が進んでおり、多くの企業や教育機関では個々の特性に合わせたサポートを行うようになっています。
そのため、過度に気にしすぎる必要はなく、適切な支援を受けることを優先することが大切です。

療育手帳は必要なときにのみ提示すればよく、普段の生活で他人に知られることはほとんどありません。
社会の理解も進んでおり、安心して支援を受けることが大切です。

障害者雇用枠での就労における給与や昇進の制限
療育手帳を取得すると、障害者雇用枠での就職がしやすくなります。
しかし、障害者雇用枠は一般の雇用と異なり、給与水準が低く設定されていることがあるため、収入面での不安を抱える人も少なくありません。
また、昇進の機会が少ない企業もあり、キャリアアップを目指す際に制限を感じることがあるかもしれません。
そのため、一般雇用と障害者雇用のどちらが自分にとって適しているかを慎重に検討する必要があります。
一方で、障害者雇用枠には、業務内容や勤務時間の調整など、働きやすい環境が整っているというメリットもあります。
無理のない範囲で働き続けられるような制度が整っているため、自分に合った働き方を選択することが重要です。

そうですね。ただし、企業によっては昇給やキャリアアップのサポートが充実しているところもあります。
事前に職場環境をよく確認することが重要です。

生命保険やローン契約等への影響
療育手帳を取得することで、生命保険の加入や住宅ローンの審査に影響が出ることがあります。
保険会社や金融機関は、契約者の健康状態や収入状況を審査の基準にしているため、障害の有無が考慮されることがあるのです。
例えば、生命保険では加入時の審査で障害の程度が評価され、場合によっては契約が難しくなることがあります。
また、住宅ローンや自動車ローンを組む際にも、安定した収入を証明することが求められるため、条件が厳しくなる可能性があります。
しかし、全ての保険会社や金融機関が一律に制限を設けているわけではなく、障害者向けの保険商品やローンの選択肢も増えてきています。
事前に各社の基準を調べ、適切なプランを選ぶことが重要です。

そうですね。ただし、すべての金融機関や保険会社が一律に制限を設けているわけではありません。
事前に相談することで、対応してくれるところを見つけることができます。

療育手帳の取得方法

療育手帳の取得方法について、以下の項目に分けて詳しく説明します。
これらの手順を理解することで、スムーズに手続きを進めることができます。
- 申請に必要な書類
- 申請手続きの流れ
- 判定機関と年齢区分
- 手帳交付までの期間
以下で、それぞれの項目について詳しく解説します。
申請に必要な書類
療育手帳を申請する際には、いくつかの書類を準備する必要があります。
必要なものは自治体ごとに多少異なる場合がありますが、一般的には以下のような書類が求められます。
- 申請書
- 本人の写真(縦4cm×横3cm)
- 印鑑(必要な場合)
- 診断書または意見書(自治体によっては、指定の機関での検査が求められる)
- マイナンバーカードまたは通知カード(個人番号を確認するため)
これらの書類を事前に揃えておくことで、スムーズに申請を進めることができます。
詳細は、事前にお住まいの自治体に確認するとよいでしょう。


申請手続きの流れ
療育手帳の申請手続きは、以下のような流れで進められます。
- 窓口での相談・申請書の提出
市区町村の障害福祉窓口や児童相談所で申請書を提出します。窓口では必要書類の確認も行われます。 - 知能検査や面談の予約
知的障害の判定には、心理士や医師による知能検査や適応能力の評価が必要になります。予約を取って指定の日時に検査を受けます。 - 判定の実施
知能検査や面談を受け、知的障害の程度が評価されます。知能指数(IQ)だけでなく、日常生活の適応能力も考慮されます。 - 審査と手帳交付の決定
判定結果をもとに、関係機関で審査が行われ、療育手帳の交付が決定されます。自治体によっては判定会議が開かれ、最終的な判断が下されます。 - 手帳の交付
交付が決定された場合、指定の窓口で療育手帳を受け取ります。受け取り時には本人確認が必要になる場合があります。
このように、申請から交付までにはいくつかのステップがあります。
スムーズに進めるためにも、事前に手続きの流れを確認し、必要書類を揃えておくことが大切です。

自治体の窓口では、手続きをサポートしてもらえるので、一人で悩む必要はありません。
必要書類を揃えて、窓口で相談しながら進めれば、スムーズに手続きできます。

判定機関と年齢区分
療育手帳の判定は、申請者の年齢によって異なる機関で行われます。
それぞれの担当機関は以下の通りです。
- 18歳未満:児童相談所が担当
知的障害の診断は、小児科医や心理士による知能検査と面談によって行われます。発達の度合いや日常生活の適応能力も評価され、必要な支援が検討されます。 - 18歳以上:知的障害者更生相談所または精神保健福祉センターが担当
成人の場合、発達期の知的機能の遅れが持続しているかどうかを評価し、必要な支援が判断されます。職業生活や社会参加における困難の有無も考慮されることがあります。
このように、年齢によって判定を受ける機関が異なるため、事前にどこに相談すればよいのかを確認しておくことが重要です。

児童相談所は18歳未満の子どもを対象に発達や福祉の支援を行う機関で、更生相談所は18歳以上の知的障害者の相談や判定を行う機関です。
どちらも、本人の特性を正しく評価し、適切な支援を受けられるようにする役割を担っています。

手帳交付までの期間
療育手帳の申請から交付までにかかる期間は、一般的に2ヶ月から2ヶ月半程度とされています。
ただし、自治体の処理状況や審査の混雑状況によっては、これより長くかかることもあります。
手帳が必要となるタイミングが決まっている場合(例えば、障害者手当の申請や福祉サービスの利用開始時期など)は、余裕をもって申請を行うことが重要です。
また、審査に時間がかかるため、事前に自治体の窓口でスケジュールを確認することをおすすめします。

審査や判定には時間がかかるため、できるだけ早めに申請することをおすすめします。
自治体によって処理期間が異なるため、具体的な目安を知りたい場合は、福祉担当窓口に問い合わせてみましょう。

療育手帳の更新と再判定

療育手帳は一度取得すればずっと使えるわけではなく、一定の期間が経過すると更新や再判定が必要になります。
これは、知的障害の状態が時間とともに変化する可能性があるため、適切な支援を継続するために行われるものです。
手続きの詳細は自治体ごとに異なることがありますが、基本的な流れは共通しています。
更新や再判定について知っておくべき重要なポイントは以下の通りです。
- 更新・再判定の必要性
- 更新・再判定の時期
- 更新・再判定の手続きに必要な書類
- 更新・再判定の手続きの流れ
- 手帳交付までの期間
- 更新・再判定時の注意点
それぞれの内容を理解し、スムーズに更新手続きを進められるようにしましょう。
更新・再判定の必要性
療育手帳の更新や再判定は、適切な支援を継続するために必要な手続きです。
障害の状態は成長や環境の変化によって変わることがあり、その状況に応じた支援を受けるために定期的な見直しが求められます。
特に、子どもの場合は発達段階によって知的能力や適応能力が変化することがあるため、幼少期から成人期にかけて複数回の再判定が行われます。
成人後も、生活環境や社会的な状況が変わることで、支援内容の見直しが必要になることがあります。

障害の状態は変化することがあるため、適切な支援を受けるために定期的な評価が必要です。
更新の結果、より適したサービスが利用できるようになることもあります。

更新・再判定の時期
再判定が必要なタイミングは、自治体や対象者の年齢によって異なります。
一般的には以下の基準で実施されます。
- 18歳未満:多くの自治体では2年ごとに再判定が行われる
- 18歳以上:10年ごとに判定が必要なケースが多い
- 40歳以上:一部の自治体では再判定が不要になる場合がある
再判定の時期が近づくと、自治体から通知が送付されることが多いですが、次回の判定時期は療育手帳にも記載されているため、事前に確認しておくことが大切です。

自治体の手続き状況によっては通知が遅れることもあります。
療育手帳に記載された判定時期を確認し、期限が近づいたら自治体に問い合わせましょう。

更新・再判定の手続きに必要な書類
療育手帳の更新や再判定には、いくつかの書類を用意する必要があります。
一般的に求められるのは以下のような書類です。
- 再判定申請書:自治体の障害福祉課で入手可能
- 現在の療育手帳:更新手続きのために提出が必要
- 顔写真:縦4cm×横3cm程度の証明写真(不要な自治体もある)
- 医師の診断書や意見書:障害の状態を評価するために必要(自治体によっては不要な場合もある)
自治体によって書類の内容や提出方法が異なるため、事前に確認することが大切です。
また、診断書が必要な場合は取得に時間がかかることもあるので、早めに準備するとスムーズに進みます。

事前に自治体の窓口で確認し、必要なものを整理しておくとスムーズに進められます。
特に写真や本人確認書類は早めに準備しておくと安心です。

更新・再判定の手続きの流れ
療育手帳の更新や再判定の流れは自治体ごとに多少異なりますが、基本的には以下のようなステップで進められます。
- 申請書類の提出
窓口または郵送で、必要な書類を自治体の障害福祉担当窓口へ提出します。 - 面談・判定
児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)で、心理士や医師による面談や知能検査が行われます。 - 審査・結果の通知
判定結果をもとに自治体の審査会で療育手帳の更新可否が判断され、結果が通知されます。 - 新しい手帳の交付
更新が認められた場合、新しい療育手帳が発行されます。自治体によっては郵送での受け取りが可能な場合もあります。
この手続きには一定の時間がかかるため、再判定の通知を受け取ったらできるだけ早く準備を進めることが望ましいです。

申請から交付までに時間はかかりますが、自治体の窓口でサポートを受けることができます。
早めに準備を始めるのがポイントです。

手帳交付までの期間
療育手帳は、期限切れの3か月前から更新手続きが可能になります。
再判定の申請をしてから手帳が交付されるまでの期間は自治体によって異なりますが、一般的には1〜2ヶ月程度かかることが多いです。
混雑状況や審査の進行具合によっては、それ以上の時間がかかることもあります。

審査や手続きに時間がかかるため、通常は1〜2ヶ月ほどかかります。
早めに申請することで、手帳の有効期限が切れる前に新しいものを受け取ることができます。

療育手帳に関するよくある質問(FAQ)

療育手帳に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
以下の項目について詳しく説明します。
- 引っ越しや氏名変更があった場合の手続きは?
- 療育手帳を紛失・破損した場合はどうすればいいですか?
- 療育手帳の申請に費用はかかる?
- 大人でも療育手帳を申請できる?
- 手帳が必要なくなった場合はどうすればいいですか?
- 療育手帳と他の障害者手帳との関係は?
これらの質問に対する回答を以下にまとめました。
引っ越しや氏名変更があった場合の手続きは?
療育手帳を持っている方が引っ越しをした場合、新しい住所地の市区町村で住所変更の手続きをする必要があります。
氏名が変更になった場合も同様に、手帳の記載情報を変更するための手続きを行わなければなりません。
手続きの際には、以下のものを持参するとスムーズに進められます。
- 療育手帳
- 新しい住所が確認できるもの(住民票やマイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
引っ越しの際、元の市区町村での手続きが必要な場合もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
自治体によって手続きの流れが異なることがあるため、早めに窓口へ問い合わせると安心です。
療育手帳を紛失・破損した場合はどうすればいいですか?
療育手帳をなくしてしまったり、破損して使えなくなった場合は、再発行の手続きを行うことができます。
市区町村の障害福祉窓口で申請し、再交付を受ける流れになります。
再発行の際に必要となる主な書類は以下のとおりです。
- 再交付申請書
- 本人の写真(縦4cm×横3cm)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
自治体によっては、紛失届の提出を求められることもあります。
紛失に気づいたら、早めに手続きを行うことが大切です。
療育手帳の申請に費用はかかる?
療育手帳の申請や更新には、基本的に費用はかかりません。
申請手続き自体は無料ですが、手続きに必要な写真代や、自治体によっては医師の診断書が求められる場合があり、その場合は診察料が発生する可能性があります。
また、再交付の際も手帳の発行に手数料はかかりませんが、申請に必要な書類の準備や写真の撮影にかかる費用は自己負担となることがあります。
自治体によって異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。
大人でも療育手帳を申請できる?
療育手帳は、基本的に知的障害の発症が18歳未満であることが条件となります。
そのため、大人になってから知的障害と診断された場合は、新たに手帳を取得することはできません。
しかし、過去に知的障害の診断を受けたことがあるが、療育手帳を取得していなかった場合や、幼少期に知能検査を受けていないため診断が曖昧だった場合などは、大人になってからでも申請が可能なことがあります。
その際には、幼少期の発達状況や学習歴を確認し、必要な検査を受けることが求められます。
申請を希望する場合は、自治体の障害福祉担当窓口に相談し、必要な書類や検査の手順を確認するとよいでしょう。
手帳が必要なくなった場合はどうすればいいですか?
療育手帳が不要になった場合や、手帳の対象者が亡くなった場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に返還する必要があります。
特に、就職や進学などの理由で手帳を返還する場合は、手帳がなくなることで受けられなくなる支援制度や福祉サービスがあるため、慎重に判断することが大切です。
一度返還してしまうと、再度取得するには新たに審査を受ける必要があるため、手帳の有無が生活にどのように影響するのかを確認したうえで、手続きを進めましょう。
療育手帳と他の障害者手帳との関係は?
療育手帳は、知的障害のある方を対象とした手帳ですが、障害の種類によっては身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳も併せて取得することができます。
- 療育手帳:知的障害を持つ方が対象
- 身体障害者手帳:身体的な障害がある方が対象
- 精神障害者保健福祉手帳:精神疾患がある方が対象
知的障害に加えて身体的な障害や精神的な疾患がある場合、それぞれの障害に応じた手帳を取得することで、より幅広い支援を受けることができます。
どの手帳が取得できるかは、診断結果や自治体の基準によって異なるため、詳細は障害福祉担当窓口で相談するとよいでしょう。
この情報を深掘りする
-

-
身体障害者手帳とは何か?「対象者」や「メリット・デメリット」をわかりやすく解説
身体障害者手帳とは、障害を持つ方が生活のさまざまな場面で支援を受けるための大切な制度です。 この手帳を取得することで、医療費の助成や税制上の優遇、公共交通機関の割引など、日常生活をサポートするさまざま ...
続きを見る
-

-
精神障害者保健福祉手帳とは何か?「対象者」や「メリット・デメリット」をわかりやすく解説
精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患を持つ方が生活のしやすさを向上させるために利用できる制度の一つです。 この手帳を取得することで、税制の優遇措置や医療費の助成、公共料金や交通機関の割引、障害者雇用枠 ...
続きを見る
療育手帳の課題

療育手帳制度には、以下のような課題が存在します。
- 自治体間での判定基準のばらつき
- 発達障害者への対応の不明確さ
- 手帳取得者への社会的偏見と差別
これらの課題を理解することで、療育手帳制度の現状と改善点について考える一助となれば幸いです。
自治体間での判定基準のばらつき
療育手帳の判定基準は、自治体ごとに異なる場合があります。
これは、療育手帳が国の制度ではなく、都道府県や政令指定都市が独自に運用しているためです。
その結果、知的障害の程度を判断する基準や手帳の交付条件に違いが生じることがあります。
例えば、ある自治体では知能指数(IQ)が75以下であれば手帳の対象となるのに対し、別の自治体ではIQ70以下でないと交付されない場合があります。
また、日常生活の適応能力に関する評価方法も異なるため、同じ障害の状態であっても、住んでいる地域によって手帳が取得できるかどうかが変わる可能性があります。
この違いは、特に引っ越しをした際に問題となることがあります。
元の自治体で療育手帳を取得していた場合でも、新しい自治体の基準では手帳が更新されず、福祉サービスの継続が困難になることがあります。
こうした自治体ごとの差異があることで、支援の公平性が損なわれる可能性があります。

確かにその通りです。
全国的に統一した基準を設けることが求められていますが、現状では自治体ごとに判断される仕組みになっています。

発達障害者への対応の不明確さ
療育手帳は、知的障害がある方を対象とした制度ですが、発達障害のある方への適用については自治体ごとに判断が分かれることがあります。
発達障害(自閉症スペクトラム、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)など)を持っていても、知的障害がない場合は療育手帳の対象外となることが一般的です。
しかし、発達障害がある方の中には、知的障害を伴わなくても社会生活に大きな困難を抱えているケースがあります。
例えば、適応行動の面で支援が必要な場合でも、IQの基準を満たさないために療育手帳を取得できず、福祉サービスを十分に受けられないことがあります。

基本的には知的障害がないと交付対象になりません。
ただし、一部の自治体では発達障害の方に対して独自の支援策を実施している場合があります。

手帳取得者への社会的偏見と差別
療育手帳を取得することで、さまざまな支援やサービスを受けることができますが、一方で手帳を持つことによる社会的な偏見を感じる人も少なくありません。
特に、学校や職場で「障害者」として扱われることに不安を感じ、手帳の取得をためらうケースもあります。
また、就職活動の際に手帳の所持を申告したことで、不採用になったり、昇進に影響が出るといった声も聞かれます。
このような状況があるため、手帳を持つことを周囲に知られたくないと考える人も多くいます。
こうした偏見や差別をなくし、誰もが適切な支援を受けられる社会をつくるためには、障害に対する理解を深める啓発活動が重要です。

療育手帳は必要な支援を受けるためのものなので、他人に知らせる義務はありません。
偏見をなくすためには、社会全体の理解を深めることが大切です。

まとめ

療育手帳は、知的障害のある方が適切な支援やサービスを受けるために必要な手帳です。
制度の概要や対象者、取得方法、メリット・デメリット、更新手続きなどを詳しく見てきました。
手帳を持つことで、医療費の助成や税金の控除、公共交通機関の割引、教育支援、就労支援など、さまざまな支援を受けることができます。
一方で、取得に伴う心理的負担や手続きの手間、自治体ごとの基準の違いなど、課題も存在しています。
また、発達障害者への対応や他の障害者手帳との違い、社会的偏見など、今後の制度改善が求められる点もあります。
療育手帳は、本人や家族が安心して生活できるよう支援するための大切なツールです。
適切な知識を持ち、必要に応じて活用することで、より良い生活を実現することができます。
療育手帳の取得や更新を検討している方は、まずは自治体の障害福祉窓口に相談し、自分に合った支援を受けられるよう準備を進めましょう。
障害に対する社会の理解が深まり、すべての人が生きやすい環境が整うことを願っています。
参考リンクとリソース