
認知症になると、本人はもとよりその家族も大変な思いをすることになります。
65歳以上の認知症の人の数は約600万人と推計され、2025年には約700万人(高齢者の約5人に1人)が認知症になると予測されています。
親兄弟に一人はいる計算になり、他人事ではありません。
この記事では、認知症を理解したい人におすすめの本を紹介していきます。
様々なジャンルの本を用意していますので、きっとあなたに必要な本が見つかるはずです。
認知症に対する正しい知識を得る事で、上手に認知症の方と接することができるようになり、今よりも余裕をもって過ごしていけるはずです。
合わせて読みたい記事⇩
-

-
介護について理解が深まる初心者におすすめの本7選【2025年版】
介護については義務教育で学ぶことはないため、実態を知っている人は少ないです。知識を深めたいなら、自ら行動を起こして情報を取りに行く必要があります。この記事では、介護について理解が深まる初心者におすすめ ...
続きを見る
-

-
介護保険について学べるおすすめの本4選【2025年版】
日本では、40歳以上の人は全員介護保険に加入することになり、要支援認定を受けた場合には介護サービスを受けることができます。その割に、介護保険の制度について詳しく知っている人は少ないのでないでしょうか? ...
続きを見る
マンガでわかる!認知症の人が見ている世界

認知症の人の不可解な言動にも、理由や意味があります。実は、認知症の人が見えている世界がわかれば、介護者の心理的な負担が軽減するのです。
認知症ケアの第一人者が、認知症の人の心理や考え、感じ方をマンガを交えて解説します。
日本の認知症の患者数は増加の一途を辿っており、数年後には「誰しも認知症の人と接する社会」が訪れます。認知症の人とのコミュニケーション法は、今や誰にも必要な知識です。
しかし、「何度も同じことをいう」「家族の顔がわからなくなる」「財布を盗んだといわれる」「理由もなく歩きまわる」など、家庭介護の場面では、認知症の人の不可解な言動にイライラしたり、疲弊したりすることが少なくありません。
本書は、認知症ケアの現場で数多くの認知症の人と接してきた著者の豊富な知見をもとに、不可解な行動の裏にある心理をマンガ形式で紹介。
その言動の理由がわかれば、認知症の人が愛おしくなり、介護がらくになるのです。
レビュー・口コミ
非常にわかりやすい
認知症の人が感じていることや心の動きが漫画で描かれているため、非常にわかりやすいです。
一つのテーマ毎に認知症の人への対応が簡潔に書かれてあるため、実践的で役立ちます。
マンガのテーマに沿った説明ページもあり、漫画の参考書にありがちな説明不足感がありません。
認知症の人を介護をするには、まずは相手のことを理解することが先決だと思います。
そのためにも、本書は最初に読むべき本だと思いました。
この本ともっと早く出会いたかった
もっと早くこの本を読んでいたら、認知症になった母にもっと優しく接することが出来たかも…。と思いました。
当時の私は、何が起こるかわからない恐怖で、いつもビクビクしていました。
認知症になった人と接している人なら、「そうなんだよね」と、うなづけるような出来事が、わかりやすく紹介されています。
この本があれば、身近な人が認知症になっても動じずに済むかもしれません。
ボケ日和―わが家に認知症がやって来た!どうする?どうなる?
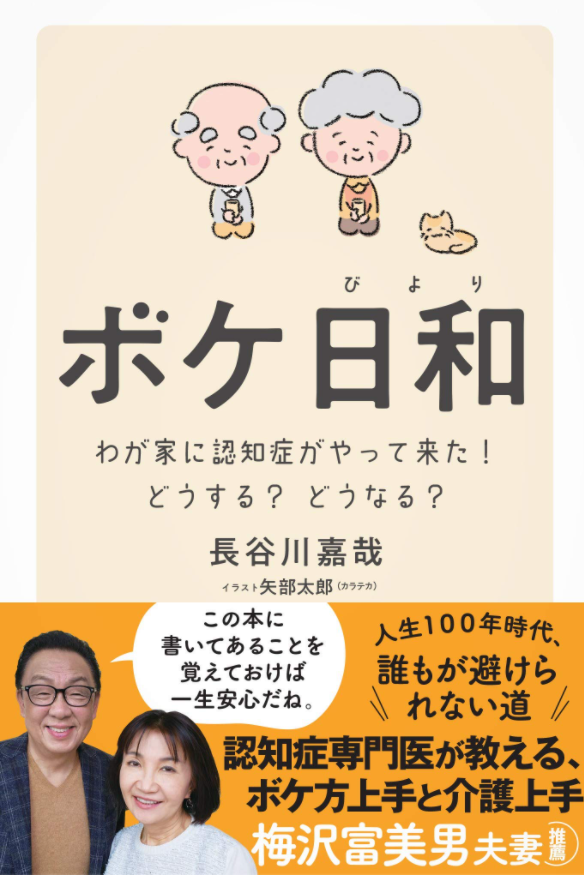
認知症の進行具合を、春・夏・秋・冬の4段階に分けて、そのとき何が起こるのか?どうすれば良いのか?を多数の患者さんのエピソードを交えて描いた、心温まるエッセイです。
人生100年時代、誰もが避けられない道知っていれば、だいたいのことは何とかなるもんです。
認知症専門医が教える、ボケ方上手と介護上手。
レビュー・口コミ
未来に対する不安に応える やさしい指南書
病気の経過を季節で表現されていて、分かりやすく、とても勉強になりました。
誰でも老いて衰え、死を迎えます。
問題なのは老いていく過程で、認知症や寝たきりなどで介護が必要になるかならないかでしょう。
親や配偶者が要介護になったらどんな対処をしたらよいか?自分自身がなったら?
未来に対する不安に応える、やさしい指南書です。
先々心配なので
まだ両親ともに元気ですが、認知症が心配なので勉強のために本書を手に取りました。
認知症のことを考えると、ただ漠然と「怖い」「親がボケたら終わり」という印象を持っていましたが、
この本を読むと、「年を取ればボケるのはある程度自然なこと」
「家族が認知症になっても、知識を持っていれば必要以上に認知症介護で苦しまなくても済むのではないか」
という印象に変わり、以前ほど親の認知症が怖くなくなりました。
現実の認知症介護は、書かれているよりもっと大変なのだと思います。
それでも、本書に書かれていることを知っていれば、上手に付き合って行けると思わせてくれます。
身近な人が認知症だと診断されたら、読んでおくとうろたえなくて済みそうです。
全イラスト版 認知症は接し方で100%変わる!
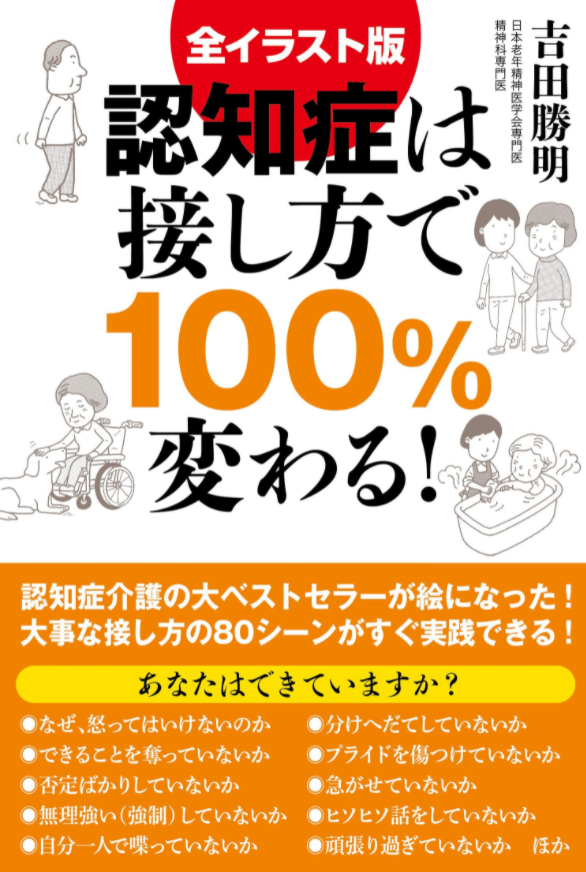
介護でしてはいけないこと、接し方のポイント、困ったときの対処法、自宅でできる認知症改善法など、認知症介護をする上で、大事な接し方の80シーンをイラストでわかりやすく解説しています。
看護師、介護職、家族が知っておかなければならない新たな認知症へのアプローチをシーン別にイラストで解説。
レビュー・口コミ
イラストが大きくて分かりやすい
認知症の介護の仕方が大きなイラストで説明されているので、とても分かりやすかったです。
イラストの数も豊富で、様々なシーンで役に立っています。
介護を受ける側の気持ちにも寄り添った内容なので、安心して介護ができています。
介護をする中で、自分がやっている「些細なこと」が「実は大切なこと」というのを気づかせてくれる本です。
体を壊す前に読んで
これまで、認知症介護の本を何冊か読みましたが、この本が一番良かったです。
認知症介護の悩みは無くなることはありません。
そのため、他の本では、忍耐を強いることや理不尽を飲み込む事だけを解決策として書いていることも少なくありません。
そのような本を読んでいると、介護をしている身としては辛くなってきます。
この本では、ストレートに「介護はいつか終わる」などが書かれていて、介護者も少し気が楽になります。
介護に疲れていると思ったら、体を壊す前に読んでみて欲しいです。
マンガ 認知症
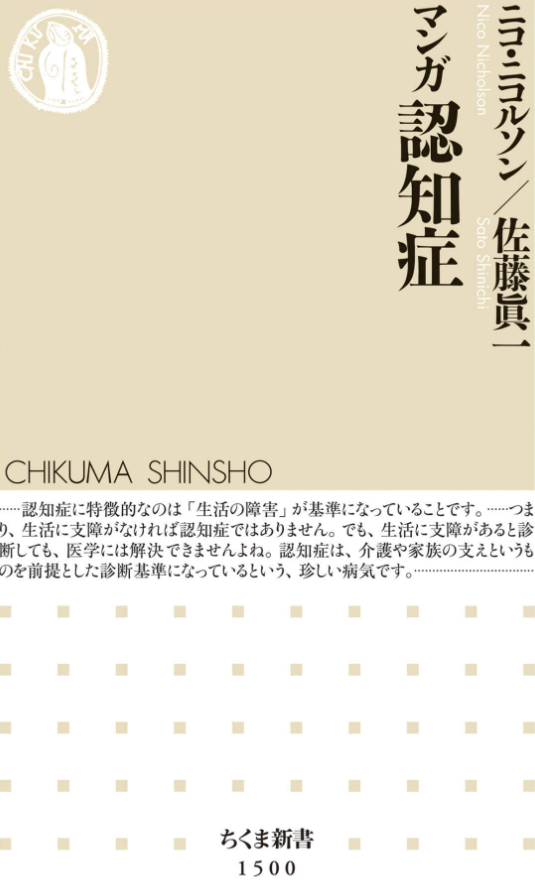
「お金を盗られた」と言うのはなぜ? 突然怒りだすのはどうして?
認知症の人の心のなかを、マンガでわかりやすく解説します。
認知症の人が既に五〇〇万人を超え、誰もが認知症になったり、認知症介護をしたりする時代です。
読めば心が楽になる、現代人の必読書!
レビュー・口コミ
「お金を盗られた」と言うのはなぜ?
認知症の方は、認知機能に障害が起こることによって、新しいことが覚えられなくなります。
そのため、聞いたことや行動したことを記憶するのが困難になります。
大切なお金などのものを自分でしまったのに、お金をしまったこと自体を忘れてしまうのです。
当事者の元々の性格、生活背景などから、分からなくなってしまった記憶を取り戻そうとするため、物盗られ妄想が引き起こされるとされています。
認知症の入門書
友人に薦められてKindleで購入。
活字の認知症の本も多くの良書があると思いますが、漫画の絵で見る方がより深く理解できる場合があると思いました。
なるほど、これは確かに読みやすく、わかりやすい。実話ベースなだけあって説得力もあります。
かといって暗くなるような描写でもなく、読後感は良いです。
私の母はアルツハイマーですが、この本に出てくるお婆さんと非常に似ています。
認知症患者の事を本当に良く見て描かれたんだなと思います。
認知症に関してまず何を読めば良いのか悩んでる方には入門としてもお薦めです。
ボクはやっと認知症のことがわかった 自らも認知症になった専門医が、日本人に伝えたい遺言
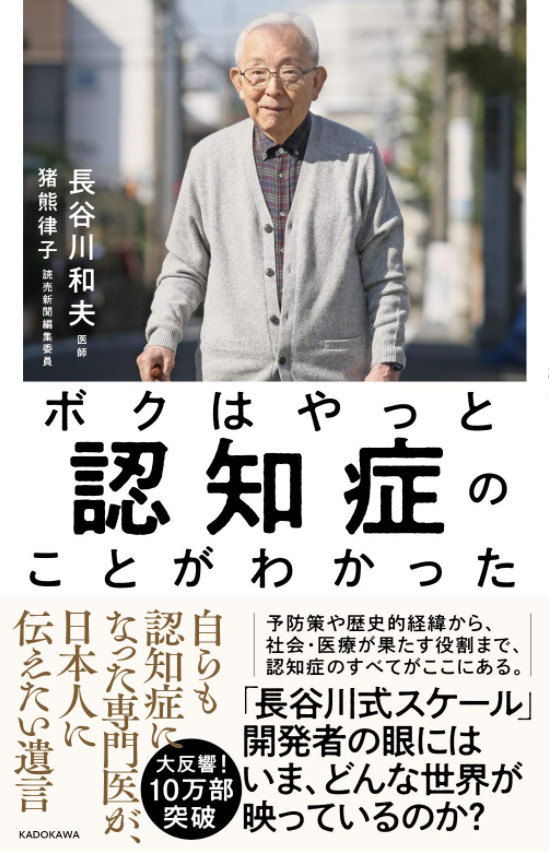
「この本は、これまで何百人、何千人もの患者さんを診てきた専門医であるボクが、また、『痴呆』から『認知症』への呼称変更に関する国の検討委員も務めたボクが、実際に認知症になって、当事者となってわかったことをお伝えしたいと思ってつくりました」――(「はじめに」より抜粋)
予防策、歴史的な変遷、超高齢化社会を迎える日本で医療が果たすべき役割までを網羅した、「認知症の生き字引」がどうしても日本人に遺していきたかった書。認知症のすべてが、ここにあります。
レビュー・口コミ
大変貴重な本です!
認知症の人を介護する家族に読んでほしい本です。
患者本人の「やりたいこと」「やりたくないこと」を聞いてほしいという思いは、認知症の人と接するうえでとても重要でありながら、見落とされがちなことだと思います。
認知症ケア従事者だけでなく、患者家族も知っておくべき内容が満載です。
認知症専門医の知識と体験が生み出した、大変貴重な本です!
少しは安しくなれそう
医者が認知症になった立場から書いてある面白い本です。
ちょうど祖母が認知症になり対応に困っているところでした。
毎日同じ事を何度も聞かされ、ストレスが溜まって怒ったり疲弊しています。
ちょうど今日もついカチンときて嫌味を言ってしまいました。
認知症の人にも感情があり、嫌な気持ちは同じ。そうですよね。
この本を読んで、少しは安しくなれそうです。
認知症の人を理解したいと思ったとき読む本
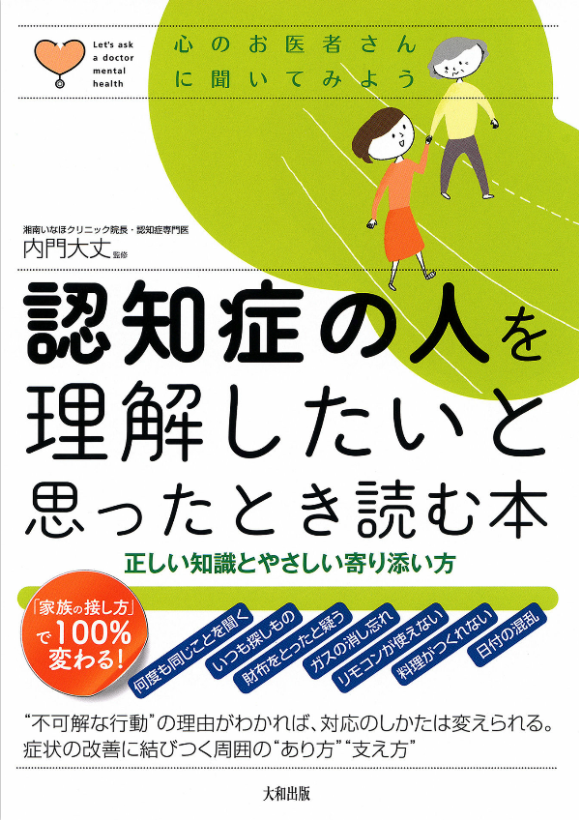
何度も同じことを聞く、いつも探しものをしている、ガスを消し忘れる…。
不可解な行動の理由がわかれば、対応のしかたは変えられます。
戸惑い振り回される家族に向けて、認知症の人の気持ちを知り、どう対応すべきかを解説しています。
どうしてこんな行動をするの?
いったい何を考えているの?
軽度認知症の不可解な行動に戸惑い、振り回される家族に向けて、患者が生きている世界を訪問診療を行う専門医が説き明かす。
これで接し方と介護のコツがわかります。
レビュー・口コミ
くっきーさん
祖母の介護が始まったのですが、私も母も認知症への知識がほとんどないため、本書を手に取りました。
挿絵や図が多くて、大変わかりやすい内容になっています。
祖母の場合、嫉妬妄想が激しくなんとかならないかと困っていたのですが、認知症の人に寄り添う事の大切さを痛感しました。
祖母が穏やかに暮らせるために頑張りたいと思います。
とても分かりやすい
本書では、日常生活の中での本人の気持ちや、必ず意味のある症状や行動、その対応の仕方などが項目ごとに見やすく具体的に解説されていて、とても分かりやすいです。
毎日必死になっていると置き去りになってしまいがちなことを取り戻させてくれる本だと感じました。
心に余裕がなくなっていると思ったときはこの本を開き、寄り添う気持ちを忘れないようにしていきたいと思います。
認知症の人が「さっきも言ったでしょ」と言われて怒る理由
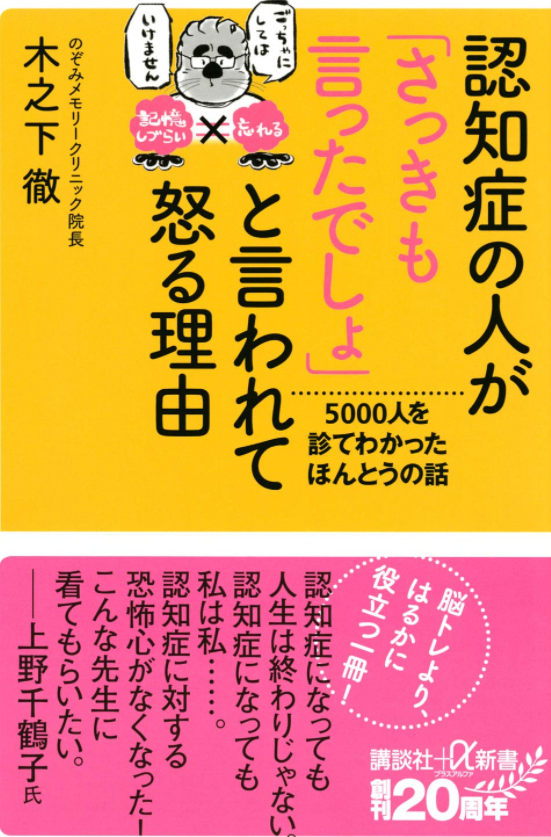
認知症に脳トレは効きません。
いまのところ、認知症が治る薬もありません。
でも、「認知症になる=絶望」ではありません。
認知症1000万人時代を迎えようとするいま、認知症とともに、「よりよく生きる」備えをするための一冊。
レビュー・口コミ
「さっきも言ったでしょ」と言われて怒る理由
認知症の人が「さっきも言ったでしょ」と言われて怒る理由。
本書によれば、それは、言ったことを忘れているのではなく、そもそも覚えていないから、ということらしいです。
その理由として、記憶のメカニズムについて細かく説明されています。
ほかにも、薬のことや周りの人はどのように関わっていけばいいのかについても書かれています。
認知症を正しく理解
本書では、現状、認知症の進行を遅らせたり、予防したりする方法はないと書かれています。
だから、今世間で喧伝されている「サプリ」や「脳トレ」というのは、残念ながら人々の期待を搾取する「商売」だそうです。
今のところ治し方がないので、なった時の準備をしておくことが重要だと言っています。
認知症を正しく理解したい人におすすめの一冊です!
認知症の人のイライラが消える接し方
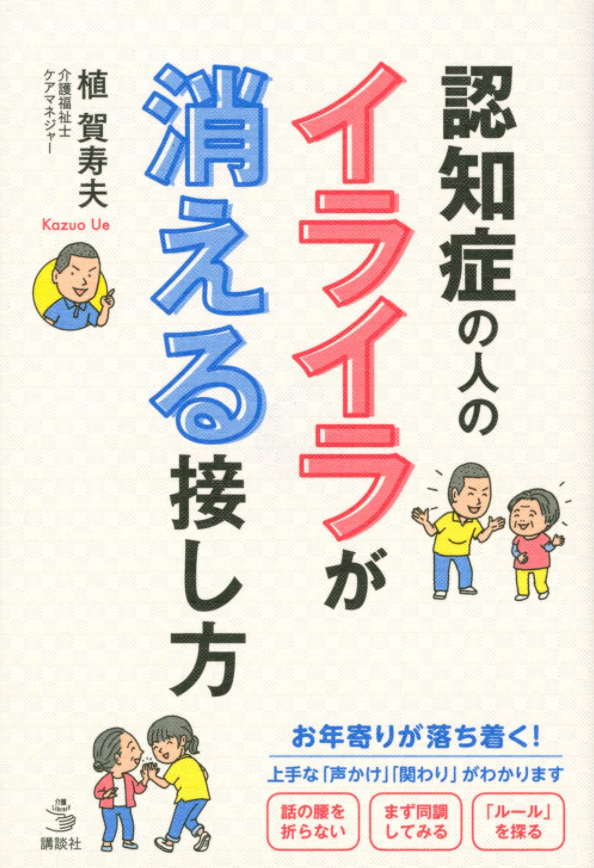
認知症ケアの本質、それは「人間関係を整えること」にあり!
お年寄りが「イライラ・ソワソワ」と落ち着かない……。そんなとき、どうすればいい?
認知症のお年寄りは、困りごとが増えるためイライラ・ソワソワと落ち着かなくなるのです。
おまけに「介護している人」との間に誤解やすれ違いが生まれやすくなるため、円満だった関係が壊れ、つい怒ったり、乱暴な言葉が出たりします。
では、どうすれば「いい関係」を作れるのか? この本には、そのヒントが満載。
レビュー・口コミ
介護職になるための必読書
認知症の色々なケース(俗にいう問題行動)がたくさん紹介されており、その解決方法が説明されています
介護職になるための必読書だと思います。
本書は、試行錯誤しながら真摯に認知症の方と向き合おうとする、介護現場で働く人の役に立つでしょう。
大変参考にさせてもらいました
所々に漫画が入っており、とても読みやすく分かりやすいです。
つばを吐く、暴言、じっとできない、突然怒り出す、物を投げる、などの問題行為に対し、どのように対応すればいいのかが書かれており、大変参考にさせてもらいました。
書いてあることは、人として当たり前の事なのですが、現場の人が忘れがちなことです。
こんなふうに出来てないと反省してしまいましたが、少しでも近づけたらと思いました。
消えていく家族の顔 ~現役ヘルパーが描く認知症患者の生活~

徘徊、せん妄、失禁、幻視、暴力、抑うつetc…。
その時、認知症患者が感じている気持ちとは?
現役ヘルパーの筆者が描く主人公は「認知症患者」。
アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、若年性認知症…さまざまな認知症患者が多数登場し、その「心」を明らかにします。
レビュー・口コミ
この漫画に出会えて良かった
祖父が認知症になったため、情報収集のためにこの漫画を買いました。
本書は、認知症の患者さん側からの気持ち等が描かれており、普段や介護を受ける時にどのように思っているのかがわかります。
描写が素晴らしく、最後は感動で号泣してしまいました。
家族だけじゃなく病院や施設スタッフさんに読んでほしいです。この漫画に出会えて良かったです。
介護に前向きになれました
祖母が認知症で 介護しています。
同じ話を延々と繰り返したり、もの取られた妄想で私に当たられたりと、散々な日々を送っています。
気分が滅入って体調を崩しそうになっていましたが、この本を読んで、問題行為にも意味があることが分かり、以前よりも介護に前向きになれました。
介護をしているすべての人に読んでもらいたいです。










