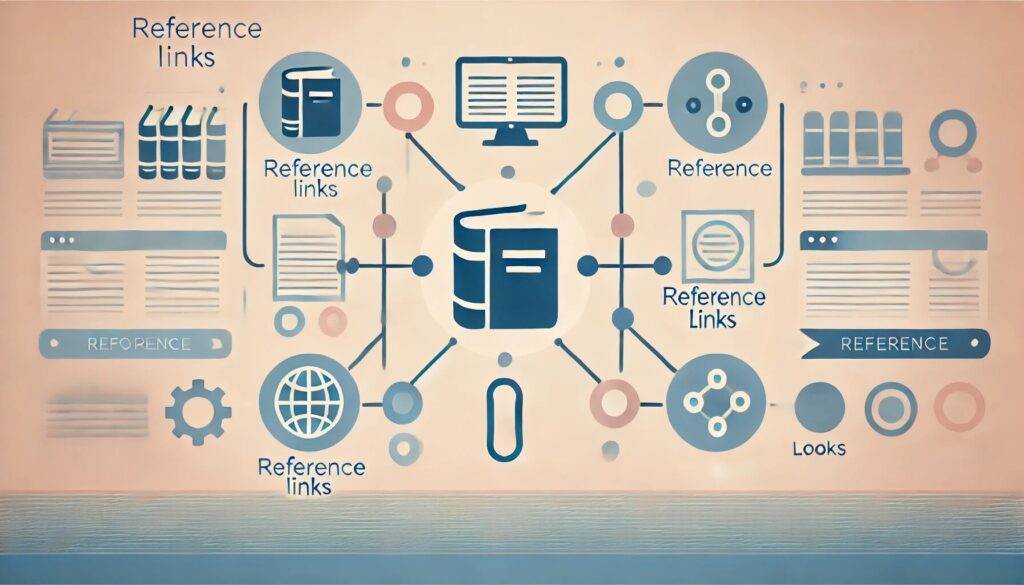長い間、障害のある方々の暮らしは、病院や施設といった「限られた空間」の中で続くものだと考えられてきました。しかし、近年では「誰もが地域で自分らしく生きる」という考え方が広まり、入所や入院に頼らない新しい暮らし方が注目を集めています。その実現を支える制度が「地域移行支援」です。

地域移行支援とは、施設や病院から地域社会へと移る際に、住まいや生活スキルの準備、社会とのつながりづくりなどを包括的に支援する障害福祉サービスです。
本人の意思を尊重しながら、自立した生活への一歩を支えるこの仕組みには、どのような背景や仕組み、メリット・デメリットがあるのでしょうか?
この記事では、地域移行支援の制度の概要から、対象者の条件、支援内容、手続きの流れ、費用負担、そして利用する上での注意点や課題までを丁寧に解説します。
福祉関係者だけでなく、ご本人やご家族にも役立つ内容を目指して、分かりやすくお届けします。

合わせて読みたい記事
-

-
障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年版】
障害のある子どもを育てている親御さんへ——日々の子育ての中で、こんなふうに感じたことはありませんか?「子どもの気持ちがうまくわからない」「どうサポートすればいいのかわからない」「このままでいいのかな… ...
続きを見る
-

-
障害者福祉について学べるおすすめの本3選【2026年版】
この記事では、障害者福祉について学べるおすすめの本を紹介していきます。障害者福祉を扱っている本は少ないため、厳選して3冊用意しました。障害者福祉とは、身体、知的発達、精神に障害を持つ人々に対して、自立 ...
続きを見る
-

-
障害年金について学べるおすすめの本4選【2026年版】
障害を負う可能性は誰にでもあり、その時に生活の支えになるのは障害年金です。その割に障害年金について理解している人は少ないのではないでしょうか?この記事では、障害年金について学べるおすすめの本を紹介して ...
続きを見る
地域移行支援とは何か?

障害のある方が、施設や病院などの入所環境から地域社会で暮らせるようになるためには、多面的な支援が欠かせません。地域移行支援は、こうした生活の転換を支える公的な制度です。
このセクションでは、初心者でも理解しやすいよう、次の4つの観点から詳しく解説していきます。
- 制度の概要
- 必要とされる背景
- 実施主体
- 費用負担と補助金の割合
それぞれのポイントを知ることで、なぜこの支援が重要なのかが見えてくるはずです。
制度の概要
地域移行支援とは、障害のある方が入所施設や精神科病院などから地域へと移り、より自立した生活を営めるようにするための支援制度です。これは「障害者総合支援法」に基づいて市町村が実施するサービスであり、「地域相談支援」という位置づけで提供されています。
この制度の目的は、施設や病院での長期的な生活に終止符を打ち、本人の希望や生活スタイルに応じた地域での暮らしを実現することにあります。つまり、「支えられるだけの生活」から「自分で選び、動かす生活」へと、一歩踏み出すための支援です。
たとえば、長年施設で暮らしてきた方が、「自分でアパートを借りて暮らしたい」と考えたとします。こうしたときに、地域移行支援が活用されます。この支援では、住まいの確保から生活に必要なスキルの練習、実際に地域で暮らすための相談・調整まで、総合的なサポートが提供されます。
また、いきなり一人暮らしを始めるのではなく、実際の地域生活を“体験する機会”も設けられています。具体的には、外出や買い物の練習、体験宿泊、地域サービスの試用などを通じて、自信と安心を積み上げながら段階的にステップアップしていくことができます。

自立生活って言われても…。
本当に一人でやっていけるのかな?
その不安はとても自然なことです。
地域移行支援は「いきなり一人で全部こなす」ことを求めるのではなく、「必要な練習と準備を、支援を受けながら少しずつ進めていく」ことを大切にしています。

この情報を深掘りする
-

-
地域相談支援とは何か?「支援の種類」や「サービスの内容」をわかりやすく解説
障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、適切な支援が欠かせません。 しかし、「どんな支援が受けられるの?」「どこに相談すればいいの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。 ...
続きを見る
必要とされる背景
地域移行支援が制度として位置づけられた背景には、日本の障害者福祉を取り巻く大きな転換点があります。
かつて、日本の障害者福祉は「保護」「隔離」を中心とした施設中心型の支援体制が一般的でした。障害のある方は、生活支援・医療・見守りなどを受けるために、障害者支援施設や精神科病院に長期的に入所・入院するのが当たり前とされてきました。しかし、その生活は“安心”と引き換えに、“自由”や“選択”を失っているという現実がありました。
この状況に対して大きな影響を与えたのが、2006年に国連で採択された「障害者権利条約」です。この条約では、障害のある人が地域で暮らす権利を明確に保障しており、日本も2014年に批准しています。これを受けて、国の福祉政策も「施設から地域へ」という流れへと大きく舵を切ることになりました。
さらに、施設や病院での長期入所が「生活を支える」どころか、「社会的孤立」や「人間関係の喪失」につながっているという課題も顕在化しています。閉鎖的な環境で暮らし続けることで、地域社会とのつながりが途絶え、生活の質が低下してしまうケースも少なくありません。
そこで、本人の「地域で暮らしたい」「自由に生活したい」という思いを尊重しながら、安心して地域生活を始められるようにする支援が求められたのです。それが「地域移行支援」という仕組みです。

確かに、施設には整った支援環境があります。
ただし、それは“自由”や“選択肢”を制限することと表裏一体でもあります。
地域移行支援は、“支援を受けながら自由に生きる”という新しい選択肢を提供するものです。

実施主体
地域移行支援は、法律に基づいて各市町村が主体となって実施する公的なサービスです。市区町村の障害福祉担当部署が利用申請を受け付け、サービスの支給決定を行います。そのうえで、具体的な支援は「指定相談支援事業所」に委託または委ねられます。
指定相談支援事業所には、「相談支援専門員」という専門スタッフが在籍しており、地域移行支援の中心的な役割を担います。彼らは、本人の希望や生活歴、心身の状況などを丁寧にヒアリングし、個別の「地域移行支援計画」を作成。その上で、本人が地域で自立した生活を実現できるよう支援します。
また、支援は1人の相談員だけで行うわけではありません。地域移行支援は、「多職種連携」と呼ばれる仕組みを通じて、医師、看護師、福祉施設職員、地域包括支援センター職員、住宅支援関係者など、さまざまな専門家がチームで関わることが基本です。
これにより、医療面、生活面、精神的な支え、住まいの確保など、あらゆる角度から総合的なサポートが可能になります。

まずはお住まいの市区町村の障害福祉課に連絡してみましょう。そこから相談支援事業所につないでもらえます。
一人で抱え込まず、最初の一歩を誰かと一緒に踏み出すことが大切です。

費用負担と補助金の割合
地域移行支援の大きな特徴の一つに、「原則として無料で利用できる」という点があります。障害福祉サービスには利用者負担が発生することもありますが、地域移行支援は「地域相談支援」という区分に属しており、本人の費用負担はありません。
この制度が無料で利用できる理由は、支援費用が公費によって賄われているからです。具体的には、国・都道府県・市町村がそれぞれ一定の割合で費用を負担し、支援を提供する事業所には「地域移行支援給付金」が支払われます。
この給付金は、支援内容や期間に応じて定められた報酬単価に基づいて支払われるため、事業所は安定した財源をもとに、質の高い支援を提供できます。
ただし、一部のケースでは例外もあります。たとえば、体験的な宿泊支援を行う際にホテル等を利用する場合、その宿泊費は実費で利用者負担になることがあります。ただし、これも相談の上で費用を抑える工夫ができる場合が多いため、事前に相談支援員に確認するのが安心です。

その疑問は重要です。地域移行支援は、税金によって支えられている公的サービスです。
つまり、社会全体で障害のある方の自立を応援する仕組みなんです。
だからこそ、必要な方は遠慮せずに活用してほしい制度です。

地域移行支援の利用条件

地域移行支援を利用するためには、いくつかの条件が設けられています。これは誰でも自由に受けられるサービスというわけではなく、「どんな状況にある人に、どんな支援が必要か」という点を踏まえて制度設計されているからです。
このセクションでは、利用を検討している方が知っておきたい以下の4つのポイントについて詳しくご紹介します。
- 対象となる障害者の要件
- 障害支援区分の必要性
- 支給決定期間と利用可能期間
- サービス提供事業者の選定基準
それぞれの条件は、制度を適切に利用するうえでの重要な要素です。
一つひとつ丁寧に確認していきましょう。
対象となる障害者の要件
地域移行支援を利用できるのは、「地域生活への移行のための支援が必要と認められる障害のある方」に限られます。この制度は、すでに何らかの施設や病院などで生活している人の地域移行を目的としているため、対象は非常に明確です。
まず、障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設、療養介護を行う病院などに入所している方が該当します。特に15歳以上の方(施設によっては18歳以上)が対象とされるため、未成年のケースも含まれます。
また、精神障害のある方で精神科病院に入院している場合も対象となりますが、原則として「直近の入院期間が1年以上」である必要があります。ただし、例外として、措置入院や医療保護入院といった法的根拠に基づく入院で、かつ住居の確保など支援が必要な方、あるいは今後長期入院になる恐れのある方についても対象となる可能性があります。
その他、救護施設や更生施設に入所している方も含まれますし、障害を抱えたまま刑務所や少年院などの刑事施設に収容されている方も対象になり得ます。こうした方に対しては、地域で生活するための準備や支援が行われ、再出発に向けた重要な支えとなります。
また、自立更生促進センターや自立準備ホームなどに宿泊している障害のある方、更生保護施設を利用している方についても、地域移行支援の対象とされています。いずれの場合も、「指定一般相談支援事業者による効果的な支援が期待できること」が前提条件とされています。

こんなに多くの人が対象になるの?
もっと限定されていると思ってた…。
地域移行支援は、施設や入院生活が長期化しやすい人ほど対象になります。
大切なのは、地域での暮らしを目指す意志があるか、そしてそのために支援が必要かという点です。

障害支援区分の必要性
地域移行支援の利用にあたって、障害支援区分の認定を受けていることは必須条件ではありません。これは、他の多くの障害福祉サービスと異なる点であり、「区分がなければ利用できない」というものではないのです。
とはいえ、心身の状況を正確に把握することは支援計画の策定において極めて重要であるため、市区町村は障害支援区分認定調査の調査項目に基づいて、同様の調査を行うことが一般的です。つまり、あくまで“区分そのもの”ではなく、“調査項目による実態把握”が目的なのです。
もしすでに障害支援区分の認定を受けている場合は、その結果が地域移行支援の給付決定において考慮されます。これは、支援の内容や必要度を客観的に評価し、より適切な支援を届けるための基準として用いられるからです。
このように、障害支援区分は「絶対に必要」というわけではありませんが、心身の状態や支援の必要度を把握する上で、事実上、重要な判断材料となっています。

市町村は、認定調査の項目を使って身体状況や生活のしづらさを把握します。
つまり、形式としての“区分”は不要でも、実態の確認はきちんと行われる仕組みなんです。

支給決定期間と利用可能期間
地域移行支援は、永続的に続く支援ではありません。これは、あくまで「地域での生活を始めるための準備期間」に提供される支援であるため、市町村ごとに定められた一定の期間内で利用することになります。
一般的には、支給決定期間はおおむね6か月から12か月程度とされ、最長でも1年間が一つの目安です。ただし、地域によって運用に若干の違いがあるため、実際の支給期間は市区町村に確認する必要があります。
この期間内に、支援者とともに移行計画を立てて、体験的な生活支援や住まいの確保、福祉サービスの活用などを進めていきます。そして、計画通りに地域生活へ移行できると判断された場合には、地域定着支援などの次の支援ステージへと移行します。
反対に、支給決定期間中に移行が難しいと判断された場合には、期間の延長や別の支援への切り替えが検討されることもあります。

1年で本当に地域生活に移れるのかな?
間に合わなかったらどうしよう…
焦らなくても大丈夫です。支援は“段階的に進める”ことが基本ですし、必要に応じて支援期間の延長や内容の見直しも行われます。
まずは今の状況をしっかり伝えることがスタートです。

サービス提供事業者の選定基準
地域移行支援は、指定を受けた相談支援事業所が提供する必要があります。つまり、どこでもサービスを受けられるわけではなく、一定の基準を満たした「指定一般相談支援事業者」に限られます。
この指定は、都道府県または市町村が実施しており、基準には職員体制、相談支援専門員の配置、業務遂行能力などが含まれます。中でも特に重要なのが、相談支援専門員の資格と経験です。利用者のニーズを正確に把握し、他機関と連携しながら支援計画を立てるためには、高い専門性と実務経験が求められます。
また、地域ごとに特色のある事業所もあり、精神障害に強いところ、発達障害の支援に実績があるところなど、得意分野が異なります。そのため、事業所を選ぶ際には、自分の障害特性や移行希望先の条件に合った支援が可能かどうかを確認することがとても重要です。

どの事業所にすればいいのか全然分からない…。
選ぶ基準ってあるの?
選定はとても大切なポイントです。自分の障害特性や支援の希望を伝えたうえで、経験豊富で連携体制が整っている事業所を選ぶと安心です。
自治体に相談すれば、候補を紹介してくれますよ。

地域移行支援の具体的な支援内容
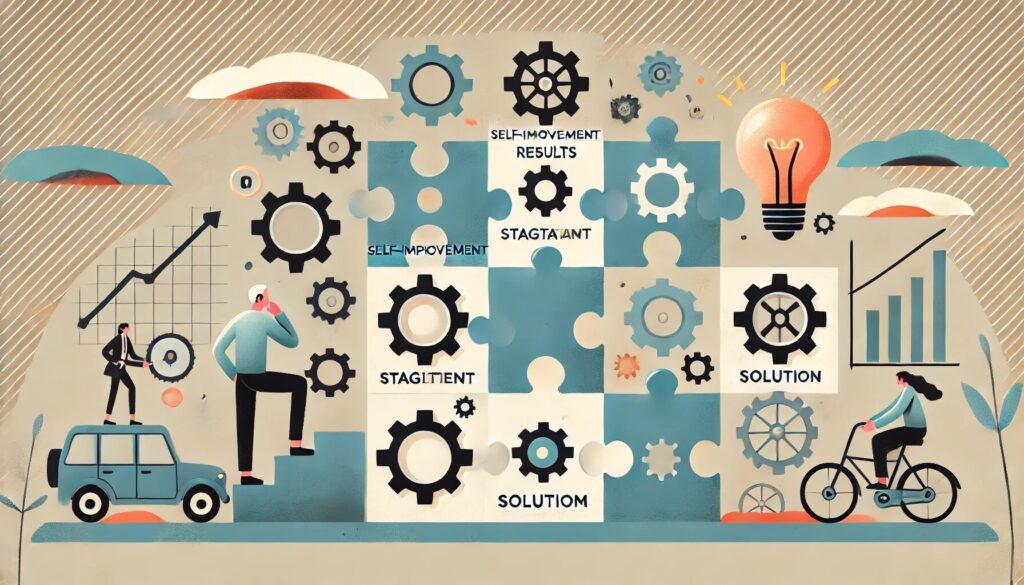
施設や病院などから地域社会へと生活の場を移すには、住まいや生活能力の準備、地域とのつながりづくりなど、幅広い支援が必要になります。地域移行支援では、個々の状況に応じて以下のような支援が段階的に行われます。
- 地域移行支援計画の作成
- 住居の確保と住環境整備の支援
- 日常生活スキルの習得支援
- 地域資源や社会資源の活用支援
- 障害福祉サービスの体験的利用支援
これらの支援はすべて、「地域で安心して暮らせるようになる」ことを目的とし、相談支援専門員を中心としたチームで進められます。
地域移行支援計画の作成
地域移行支援は、本人の希望や課題に沿って適切な支援を行うため、まず最初に「地域移行支援計画」を作成することから始まります。この計画は、単なる書類ではなく、本人がどのような地域生活を望んでいるか、どのような不安や支援ニーズがあるかを整理し、関係者と共有するための重要な指針です。
計画の作成は、指定相談支援事業者に所属する相談支援専門員が担当します。専門員は本人や家族と何度も面談を重ね、現在の生活状況や障害特性、将来の希望などを丁寧に聞き取ります。そして、移行に必要なステップを一つひとつ明文化し、地域生活への道筋を描きます。
たとえば「まずは外出の練習から始めたい」「買い物が苦手だから同行してほしい」といった要望があれば、それらを支援目標として明記します。このように、支援計画は“本人の思い”を具体的な支援として形にする作業であり、全体の支援の土台となる非常に重要な工程です。

最初はそれで大丈夫です。支援者と話す中で、「これが苦手」「これならできそう」といった気づきが少しずつ出てきます。
その小さな発見を大切にしながら、計画は一緒に作っていくものです。

住居の確保と住環境整備の支援
地域で生活するためには、まず住まいが必要です。しかし、障害のある方が自力で住まいを探すのは簡単なことではありません。家賃や保証人の問題、大家さんの理解、バリアフリーの有無など、さまざまな壁に直面することがあります。
そのため、地域移行支援では、本人の状況に合った住まい探しを専門員が支援します。相談支援事業所と地域の福祉担当、あるいは不動産会社が連携し、アパートやグループホームなどの住まいを一緒に検討します。選択肢には、完全な一人暮らしだけでなく、世話人の支援が受けられるグループホーム、シェアハウス型の住居などもあります。
住居が決まった後には、電気やガス、水道といったライフラインの契約や、必要な家具・家電の準備、障害特性に応じた安全対策の整備も支援の対象となります。たとえば、認知機能に不安がある方には火の元の安全を確保するグッズの設置が検討されることもあります。

その不安こそ、支援のスタート地点です。
あなたの暮らしに必要な条件を一緒に整理しながら、希望と現実のバランスを見て、無理のない形で住まいの準備を進めていきましょう。

日常生活スキルの習得支援
施設や病院での生活では、日常の家事や身の回りのことを職員に任せていた方も多く、地域での生活に移る際に「本当に一人でできるのか?」という不安を抱くのは自然なことです。地域移行支援では、こうした不安に寄り添いながら、生活に必要なスキルを一緒に身につけていく支援が行われます。
たとえば、炊飯器の使い方を覚えたり、食材をムダなく使い切る方法を学んだり、ゴミ出しのルールを練習したりと、地域での暮らしを現実的にイメージできるようになる支援が重視されます。また、電車やバスに乗って通院する練習や、銀行や役所での手続きに付き添ってもらうなど、社会生活に必要な経験を実地で積むことも行われます。
このような支援は、本人の「できた!」という実感を大切にしながら進められます。少しずつ自信をつけていくことで、地域生活へのハードルを下げていくことができるのです。

一つずつ小さな成功体験を積み重ねることが、生活力の土台になります。
あなたのペースに合わせた支援があるので、焦らなくて大丈夫ですよ。

地域資源や社会資源の活用支援
地域生活を始めたばかりの頃は、孤立を感じやすくなったり、「誰に何を相談すればいいのか分からない」と感じたりする場面が出てきます。こうした状況に備えて、地域の中にある支援先や活動の場とつながっておくことはとても大切です。
地域移行支援では、地域にどのような資源があるかを調べ、本人に合いそうな場所や人を紹介するところから始まります。福祉サービスや医療機関はもちろん、地域の集いの場、ボランティア団体、趣味のサークルなど、生活に彩りを与えてくれる“人とのつながり”にも目を向けます。
一人で飛び込むのは不安でも、支援者が同行したり、仲介役として紹介してくれたりすることで、自然なかたちで地域との接点を持つことができます。「ただ住む」だけでなく、「地域で生きる」ための準備を整える支援といえます。

その一歩を支援者が一緒に踏み出してくれます。
新しい場所を知るだけでなく、「この地域で安心して生きていける」と思えるつながりづくりが支援の一環なのです。

障害福祉サービスの体験的利用支援
地域生活への移行をスムーズに進めるためには、実際に利用を予定しているサービスを“体験”しておくことが重要です。これは、本番前に練習をするようなもので、安心感や自信を得る機会になります。
体験的利用支援では、グループホームや福祉事業所など、移行後に利用する可能性のあるサービスを短期間お試しで利用します。たとえば、3日間だけグループホームに宿泊してみる、就労支援事業所に通ってみる、日中活動の場に参加してみるなど、実際の環境に身を置いてみることで、見えてくる課題や希望があります。
この体験の中で、「ここは合いそうだ」「少し不安だから別の選択肢を考えたい」といった本人の感覚が明らかになり、それをもとに支援計画を見直すことも可能です。また、現場で支援するスタッフとの関係づくりも、移行後の安心感につながります。

体験利用は、まさにその“心配を解消するための機会”です。
支援者も事業所も「初めての人」を受け入れる準備ができており、失敗も含めて一つの学びと捉えています。
自分に合う生活スタイルを探すための大切なプロセスです。

地域移行支援の利用手続き

地域移行支援を実際に利用するには、いくつかの手続きステップを踏む必要があります。制度の内容が分かっても、「どうやって申し込むの?」「どこに行けばいいの?」という疑問を抱える方は少なくありません。
このセクションでは、最初の相談からサービス利用開始までの一連の流れを5つのステップに分けて解説します。
- step1 市区町村の障害福祉課への相談
- step2 障害福祉サービス受給者証の申請手続き
- step3 認定調査とヒアリングの実施
- step4 受給者証の発行と利用契約の締結
- step5 サービス利用開始と個別支援計画の策定
以下で、それぞれのステップについて詳しく解説します。
step1 市区町村の障害福祉課への相談
地域移行支援を利用する第一歩は、お住まいの市区町村役場にある障害福祉課への相談です。制度を使うには行政による認定や手続きが必要なため、「困っていること」「支援を受けたいと思っていること」をまず行政に伝える必要があります。
市区町村では、本人や家族からの話をもとに、現在の生活状況や支援ニーズを確認し、地域移行支援の対象に該当するかを判断します。このとき、すでに福祉サービスを利用している方は、担当の相談支援専門員に一度相談し、行政との調整を進めてもらうのがスムーズです。
相談の時点では、明確な希望が定まっていなくても構いません。「地域で暮らしてみたい気持ちはあるけれど、何から始めればいいか分からない」といった漠然とした悩みも、十分に相談の対象となります。市区町村の窓口は、“制度の利用を始めるきっかけを作る場所”として重要な役割を担っているのです。

いきなり役所に相談ってハードル高いなあ…。
話がうまく伝えられるか心配。
不安なときは、信頼できる支援者や家族に付き添ってもらいましょう。
行政の担当者も、初めての方に丁寧に制度の説明をしてくれるよう心がけていますよ。

step2 障害福祉サービス受給者証の申請手続き
地域移行支援を正式に利用するには、「障害福祉サービス受給者証」の取得が必要になります。これは、障害福祉サービス全般を受けるための行政からの認可証であり、言わば“制度利用のための許可証”です。
申請は障害福祉課で行います。窓口で申請書を記入し、本人確認書類や障害者手帳、医師の意見書など必要書類を提出します。市区町村によっては、支援者が代理で申請することも可能です。提出書類の細かい内容は自治体ごとに若干異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
申請が受理されると、行政は支給の必要性について審査を行い、対象者に適切なサービスが何か、どれくらいの期間支給するかを検討します。申請は手続きの一部ですが、これによって初めてサービス利用の基盤が整うことになります。

不安な方には相談支援専門員が一緒に申請に同行することもあります。
心配せず、一歩ずつ進めていけば大丈夫です。

step3 認定調査とヒアリングの実施
申請後には、市区町村の職員や認定調査員による認定調査とヒアリングが行われます。これは、支援の必要性を正確に把握し、本人に合った支援内容を決定するためのプロセスです。調査では、本人の身体的な動作や精神的な状態、日常生活で困っていることなどが丁寧に確認されます。
調査は本人の居住場所や施設、病院などで実施され、1時間程度をかけて行われることが一般的です。聞き取り内容は、食事や排泄、移動といった日常生活の基本動作に加え、コミュニケーションの状況、服薬管理、金銭管理の能力なども含まれます。
また、本人がうまく説明できないことがあれば、家族や施設職員、支援者が補足することも可能です。調査の目的は、本人の困りごとを行政が正確に把握し、適切な支援を組み立てるための情報収集であるため、ありのままを伝えることが最も大切です。

調査はあなたの暮らしを整えるための大切なプロセスです。
率直に話してもらえれば、最適な支援につながりますよ。

step4 受給者証の発行と利用契約の締結
認定調査とヒアリングの結果をもとに、市区町村が支援の必要性を認めた場合、障害福祉サービス受給者証が発行されます。この受給者証には、利用できるサービスの種類や支給決定期間などの情報が記載されています。これを受け取ることで、ようやく正式に地域移行支援の利用準備が整います。
受給者証が発行された後は、実際に支援を提供してくれる指定事業所と契約を結びます。契約内容には、サービスの提供期間、支援の具体的内容、支援者との連携方法などが含まれており、本人と家族も交えながら慎重に確認が行われます。この契約が完了することで、サービスの利用がスタートできる状態になります。

ご安心ください。契約は“義務を負わせる”というより、“支援者と利用者が共通理解をもつ”ための確認書です。
内容を理解しながら納得の上で進めていけば大丈夫です。

step5 サービス利用開始と個別支援計画の策定
契約が完了したら、いよいよ地域移行支援のサービスがスタートします。しかし、ただサービスを開始するのではなく、本人に合わせた「個別支援計画」を策定するところから始まります。この計画は、移行後の生活目標や、そこに至るまでの支援の内容、支援者の役割分担などを明文化したもので、本人の意思を中心に据えて作られます。
計画作成には、相談支援専門員やサービス提供事業所のスタッフが参加し、必要に応じて医療・福祉の関係機関や家族とも連携します。内容は、住まいの確保、日常生活スキルの向上、地域とのつながりづくりなど多岐にわたり、実際の生活に直結する具体的な目標が盛り込まれます。

こんな計画通りにうまくいくのかな…。
途中で挫折したらどうしよう。
大丈夫です。支援計画は一度きりの“完成形”ではなく、必要に応じて何度でも見直せる“成長する計画”です。
自分のペースに合わせて進めていきましょう。

地域移行支援の費用と負担額

地域移行支援は、障がいのある方が施設や病院から地域での生活に移る際に重要なサポートですが、「お金はどれくらいかかるのか」「自己負担が必要なのか」といった費用面の不安を抱えている方も少なくありません。
そこで、このセクションでは、支援を利用するうえでの金銭的な仕組みや負担の有無について、以下の3つの視点から分かりやすく説明していきます。
- 利用者の費用負担はありません
- 事業所側に対して地域移行支援給付金
- サービス利用に伴う費用は自己負担
実際にかかる費用と、誰がどこまで負担するのかを具体的に見ていきましょう。
利用者の費用負担はありません
地域移行支援は、障害福祉サービスの中でも「地域相談支援」という区分に含まれる制度です。このため、基本的に利用者本人が費用を負担する必要はありません。つまり、相談や支援の提供を受けるにあたって、自己負担が生じることはないというのが原則です。
これは、障害のある方が地域での生活に一歩踏み出す際に、経済的な負担を理由に支援を断念することがないよう、制度設計されているからです。とくに、長期にわたって入所施設や精神科病院にいた方の場合、貯金がほとんどなく、生活基盤もないことが多いため、無料で支援が受けられるという点は非常に大きな安心材料となります。
制度の対象となる方は、市区町村から支給決定を受けることで、無料でこの支援を受けることができます。相談や面談、地域生活に向けた準備の支援など、すべてのプロセスが公費で賄われるため、費用面の心配をせずに必要な支援に集中することができるのです。

不安になるのも無理はありませんが、これは障害者総合支援法に基づいて自治体が実施する正式な制度です。
無料であることは、必要な人が制度からこぼれ落ちないようにという国の配慮でもあるのです。

事業所側に対して地域移行支援給付金
地域移行支援の運営にかかる費用は、利用者本人が負担するのではなく、国や自治体が指定相談支援事業所に対して支払う「地域移行支援給付金」によってまかなわれています。これは、支援の実施に対する対価として事業所に支払われる報酬で、国が定めた報酬単価に基づいて算出されます。
この給付金は、計画相談支援の提供、本人や家族との面談、地域での住まい探しや体験活動の調整、関係機関との連携など、実際に行った支援内容に応じて市町村から支払われます。これにより、相談支援事業所は持続可能な体制で支援を行うことができ、結果として利用者に対する支援の質が担保される仕組みになっています。
給付金によって支えられているため、相談支援専門員は利用者に対して追加費用を求めることはありません。つまり、制度として「支援する側への報酬」が別途確保されているからこそ、利用者は無料で安心してサービスを受けることができるのです。

その点は心配ありません。地域移行支援は公的制度として運用されており、給付金によって支援者側の活動が正当に評価・報酬化されています。
だからこそ、質の高い支援を持続的に提供できるのです。

サービス利用に伴う費用は自己負担
地域移行支援自体には費用はかかりませんが、支援を受ける過程で発生する日常的な出費については、利用者が自己負担する必要がある場面もあります。これは、いわば生活に伴う実費であり、支援の対価とは異なる扱いとなっています。
たとえば、グループホームなどでの体験的宿泊を行う場合、宿泊に伴う食費や日用品費、光熱費といった生活にかかる基本的な出費が発生することがあります。また、移動支援の際にバスや電車を利用した場合の交通費や、外出先での買い物の費用なども原則として自己負担です。
このような出費は、地域で生活するうえで自然に生じるものであり、支援とは切り離して考えるべき費用とされています。ただし、こうした実費がどの程度かかるのかは、支援計画の段階で事前に説明されるのが一般的で、急に思いがけない請求が来るようなことはありません。
支援者と一緒に体験活動の内容や費用を話し合い、無理のない範囲で実施することが大切です。経済的に不安がある場合は、生活保護などの他制度と併用することも検討できます。

はい、支援サービス自体は無料ですが、それに付随する実費は自己負担です。
どのくらい必要になるかは、事前に確認できるので安心してください。

地域移行支援を利用するメリット

地域移行支援は、施設や病院などの入所生活から地域での自立した生活へ移行したいと考える障害のある方にとって、多くの利点をもたらす支援制度です。この制度を活用することで、生活のあらゆる面で前向きな変化が期待できます。
以下のような観点から、その効果を具体的に見ていきましょう。
- 住居の確保と生活基盤の安定
- 社会参加の機会拡大と孤立防止
- 日常生活スキルの向上と自立促進
- 家族や支援者の負担軽減
それぞれの項目がどのようにメリットにつながるのかを詳しく見ていきましょう。
住居の確保と生活基盤の安定
地域移行支援を利用することで、まず重要な第一歩として住まいの確保が支援されます。長期にわたって入所施設や精神科病院などにいた方の多くは、地域での暮らしを希望していても、住宅の探し方が分からなかったり、入居審査に不安があったりして、自力での住まい探しが困難です。そうした状況に対して、地域移行支援では相談支援専門員が一緒に物件を探し、大家や不動産業者との調整、引っ越しや契約のサポートまで幅広く支援します。
また、アパートへの一人暮らしだけでなく、グループホームやシェアハウス型の住まいなど、本人の状態や希望に合わせて複数の選択肢が提示されるため、自分に合った生活スタイルを検討することができます。住居の確保は「自分の居場所ができる」という心理的な安心感につながり、地域生活への大きな一歩となります。

そう思う方は多いですが、地域移行支援では経験豊富な支援者が住宅探しをサポートしてくれます。
選択肢も豊富で、一人で抱える必要はありませんよ。

社会参加の機会拡大と孤立防止
地域で生活を始めると、自然と他者との接点が生まれます。地域移行支援では、単に住まいを用意するだけでなく、地域との関わりを持つための活動や機会も意識的に組み込まれています。長年施設や病院に入っていた場合、外の世界と関わる時間が極端に少なくなっていることが多く、人との関係の築き方がわからない方も少なくありません。
そうした方に対して、地域活動支援センターへの参加、地域のイベントへの同行、就労支援やボランティア活動の紹介などを通じて、外とのつながりを少しずつ再構築できるよう支援が行われます。社会参加の経験を重ねることで、自分が地域の一員として受け入れられている実感が生まれ、孤立のリスクが大きく軽減されます。

不安があって当然です。地域移行支援では、最初から一人で動く必要はなく、支援者が付き添ってくれます。
小さな活動から始めて、少しずつ慣れていくことで大丈夫です。

日常生活スキルの向上と自立促進
施設の生活では、職員に日々の家事や管理を任せていた方も多く、地域での生活では突然「全部自分でやらなければいけない」という不安に直面することがあります。地域移行支援では、こうした不安に寄り添いながら、一つずつ生活スキルを身につけていけるよう訓練や実地支援が行われます。
たとえば、食材の買い方や調理の仕方、掃除の仕方、ゴミ出しのルール、薬の管理や金銭のやりくりといった、生活に欠かせないスキルを支援者と一緒に練習します。本人のペースに合わせて無理なく進められるため、「自分でできた」という自信が積み重なり、やがて本当の意味での自立につながっていきます。

自分で全部やるなんて無理だと思う…。
施設にいたときは何もしてなかったし…。
できないのではなく、やったことがないだけです。
支援は、一人ひとりのペースに合わせて丁寧に進められるので、少しずつ生活の中でできることが増えていきますよ。

家族や支援者の負担軽減
地域移行支援の対象は本人だけではありません。これまで生活を支えてきた家族や施設職員、支援者にとっても、大きなメリットがあります。特に家庭で介護や支援をしていた家族にとっては、地域での自立生活が始まることで、心身の負担が大きく軽減されます。
また、施設職員にとっても、長期入所者が地域に移行することで新たな利用者の受け入れが可能になり、支援のリソースを分散できます。さらに、支援計画の中に家族支援が組み込まれることで、家族の悩みや不安への相談支援も行われるため、「見守る側」としての安心感が生まれやすくなります。

地域移行支援は、本人のためだけでなく、支えてきた人たちの暮らしを見直す機会でもあります。
支援者を含めた“みんなの生活の質”を整える制度として位置づけられているのです。

地域移行支援を利用するデメリット

地域移行支援は、障害のある方が施設や病院から地域社会へ移行するうえで大きな助けとなる一方で、実際に利用するとなるといくつかの難しさや不安が伴うこともあります。制度の仕組みや支援体制の変化によって、人によっては思わぬ負担や課題を感じる場面も出てきます。
以下のような点が主な注意点として挙げられます。
- 地域生活への適応に伴うストレス
- 自立生活への不安や孤独感
- 支援体制の変化によるサポート不足の懸念
- 経済的負担の増加
- 社会的偏見や差別のリスク
これらの側面を事前に理解し、適切な準備や相談を重ねておくことで、移行後の生活がより安定したものになります。
それぞれの課題について、順を追って詳しく解説していきます。
地域生活への適応に伴うストレス
施設や病院での生活に長年慣れてきた人にとって、地域での生活への移行は大きな変化となり、その分だけ心身にストレスがかかります。生活リズムが自由になる一方で、自分で物事を判断しなければならない場面が増え、戸惑いや不安を感じやすくなるのです。例えば、食事の準備や掃除といった日常生活の細かなタスクに一つひとつ対応しなければならず、周囲に常に頼れる人がいないことで心理的なプレッシャーが強まるケースもあります。
環境の変化はそれ自体がストレスの原因になりやすいため、たとえ望んで地域に出たとしても、慣れるまでに時間がかかるのはごく自然なことです。移行後しばらくは、不安定な気持ちが強くなることがあり、誰しもが安定した生活をすぐに築けるわけではないことを理解しておく必要があります。


自立生活への不安や孤独感
地域での生活は自由度が高く、個人の意思を尊重した暮らしが可能になりますが、その反面、孤独や不安に直面することがあります。施設では常に周囲に誰かがいて、何か困ったことがあればすぐに相談できる体制が整っています。しかし、地域では一人の時間が増えるため、「誰にも頼れないのではないか」「急に体調を崩したらどうしよう」といった不安が生じることがあります。
特に、もともと対人関係が苦手だったり、長期間社会との接点がなかった人にとっては、新しい人間関係を築くこと自体が大きな課題となり、それが孤立感を深める要因になることもあります。支援者が定期的に訪問する仕組みや連絡体制があるとはいえ、本人が心細さを感じやすい状況であることには変わりありません。

そのような気持ちは自然な感情です。
地域移行支援では、孤立を防ぐために支援者が定期的に訪問したり、地域の交流の場を紹介するなど、継続的なつながりづくりが重視されています。

支援体制の変化によるサポート不足の懸念
施設では日常生活のほとんどをスタッフが見守り、支援を受けながら生活できる体制が整っていますが、地域での生活になると支援のスタイルが大きく変わります。基本的には必要なときに必要なサービスを受ける「点」での支援になるため、困ったときにすぐ手が届かないと感じることもあるかもしれません。
また、自治体や事業所によってサービスの内容や提供時間帯にばらつきがあり、自分が思うような支援が受けられない場合もあります。そうした状況で「支援が足りない」と感じてしまうと、不安や不満が生じやすくなります。

地域では事前に支援の計画を立てることで、必要なときに必要な支援が受けられるよう工夫されています。
不安は事前の話し合いで解消していきましょう。

経済的負担の増加
地域での生活を始めると、これまで施設で一部負担または免除されていた費用が自己負担になることが増えます。住居の家賃、電気やガス、水道代、食費、日用品、交通費など、毎月の生活にかかる費用は決して少なくありません。特に収入が年金や生活保護に限られている場合、毎月の収支バランスに頭を悩ませることになります。
また、地域生活を安定して送るためには、家計管理や節約の工夫も必要であり、これまでこうした経験が少なかった人にとっては、それ自体が新たな学びの課題となります。金銭的な理由で生活が不安定になってしまうと、せっかく始めた地域生活が継続困難になるリスクもあるため、支援計画には経済的な支援や就労支援の導入が重要となります。

そうした不安を軽くするために、支援者と一緒に収支計画を立てたり、福祉サービスの活用、生活保護制度との併用などを検討することができます。
経済的な備えも支援の一部です。

この情報を深掘りする
-

-
公的扶助とは?公的扶助(生活保護)の詳細をわかりやすく解説
この記事では、日本の「公的扶助」制度について解説していきます。公的扶助(生活保護)の基本的な情報を網羅していますので、コレだけ読めば公的扶助による自身や家族の保障状況を理解できます。公的扶助制度は社会 ...
続きを見る
社会的偏見や差別のリスク
地域の中には、障害に対する理解が十分でない住民や環境が残っている場合があります。たとえば、障害があることを理由にアパートの入居を断られたり、近所の人から距離を置かれたりするケースも現実に存在します。本人の行動に対して無理解な言葉が投げかけられることで、精神的なダメージを受けることもあります。
また、地域での暮らしを始めることがニュースや自治会で共有されることにより、本人の望まない形で情報が広まり、ストレスになることもあるでしょう。こうした環境下では、「地域に溶け込めるかどうか」という不安が強くなるのも無理はありません。

そういった不安に向き合うために、支援者は地域との橋渡しも行います。
理解を広げる活動を通じて、少しずつ安心して暮らせる環境を築いていく努力が続けられています。

地域移行支援に関するよくある質問(FAQ)

地域移行支援を検討している方やその家族からは、事前に知っておきたい疑問が多く寄せられます。制度の仕組みや利用条件は少し複雑に感じるかもしれませんが、ここで基本的なポイントを整理しておくことで、不安なく準備を進めることができます。
代表的な疑問点としては、以下のような項目がよく挙げられます。
- 地域移行支援の利用に費用はかかりますか?
- 地域移行支援の利用期間に制限はありますか?
- 地域移行支援を受ける際に必要な書類は何ですか?
- 地域移行支援を受けるために障害者手帳は必要ですか?
- 地域移行支援を利用しながら就労することは可能ですか?
それぞれについて、具体的に見ていきましょう。
地域移行支援の利用に費用はかかりますか?
地域移行支援は、障害のある方が病院や施設などから地域での暮らしに移行する際に、必要な準備を支える福祉サービスです。原則として、このサービス自体にかかる費用は公費によってまかなわれるため、利用者には負担がかかりません。つまり、相談や支援の提供に対する利用料は基本的に発生しません。
ただし、サービスに付随する実費については、自己負担が生じることがあります。たとえば、支援員と一緒に住まいを見に行く際の交通費、食事代、役所の手続きに必要な証明書の発行手数料などが挙げられます。また、一部の自治体では利用者の所得に応じて負担額が設定される場合もあります。

はい、支援そのものは無料ですが、日常生活に必要な実費は自己負担となることがあります。
事前に支援者と内容を確認しておけば、思いがけない出費に戸惑うことはありませんよ。

地域移行支援の利用期間に制限はありますか?
地域移行支援は、基本的に一時的な支援として位置づけられており、原則として利用期間は最長でおおむね1年とされています。この期間内に、地域での生活を始めるための準備や、必要なスキルの習得、支援体制の構築などが行われます。制度上、支援は永続的に提供されるものではなく、あくまでも「移行」に特化した支援であることが前提です。
ただし、支援を受けている本人の状況によっては、1年という期間内で十分な移行準備が整わないこともあります。そのような場合には、市区町村や相談支援事業者と協議のうえで、延長が認められるケースもあります。延長の判断には、生活能力や精神状態、社会資源の状況などが考慮されます。

1年以内に準備を終えられるか不安です。
もっと時間が必要になったらどうしたらいいんでしょう?
その場合は支援者が状況を整理し、自治体と連携して延長の申請を行うことが可能です。
支援期間に縛られすぎず、必要な準備を着実に進めることが大切です。

地域移行支援を受ける際に必要な書類は何ですか?
サービスを利用するためには、いくつかの書類を用意しなければなりません。代表的なものとしては、障害福祉サービス受給者証の申請に必要な書類一式や、医師の意見書、本人の意思を確認するための面談記録などが挙げられます。
また、障害者手帳を持っている場合には、その提示が求められることもありますが、手帳がない方でも医師の診断や市区町村の判断により支援対象とされるケースもあります。書類の内容は自治体ごとに異なることがあるため、詳しくは地域の障害福祉課などに問い合わせるのが確実です。

支援員が手続きのサポートもしてくれるので、すべてを一人で準備する必要はありません。
心配せず一緒に確認していきましょう。

地域移行支援を受けるために障害者手帳は必要ですか?
必ずしも障害者手帳を持っていないと地域移行支援が受けられない、というわけではありません。確かに、手帳を持っていると障害の有無や程度を行政が把握しやすくなり、手続きがスムーズになる傾向はありますが、手帳がない場合でも医師の診断書などで支援が必要と認められれば、対象となることがあります。
とくに精神障害や発達障害など、手帳の取得にハードルがあるケースでも、地域での生活に困難を抱えていれば支援の対象となる可能性があるため、あきらめずに相談することが重要です。自治体ごとに判断基準が異なるため、早めの確認がおすすめです。

もちろん大丈夫です。
手帳がなくても支援が受けられる可能性がありますので、まずは自治体の窓口に相談してください。

地域移行支援を利用しながら就労することは可能ですか?
サービスを受けながら働くことは可能です。むしろ、地域での生活を安定させるためには、経済的な基盤として就労が重要になる場面もあります。そのため、就労支援の関係機関と連携しながら、仕事と生活支援を並行して受けられるように支援計画が組まれることもあります。
たとえば、「就労移行支援」や「就労継続支援A型」、「就労継続支援B型」などの障害者就労支援サービスと併用しながら、地域生活への移行を進めるケースもあります。無理のない範囲で働きながら自立を目指せるよう、支援者と一緒にバランスを取りながら計画を立てていくことが可能です。

はい、むしろ働いている方の生活を支えるためにも地域移行支援は活用されています。
生活面と仕事面を分けずに支えてくれる制度として、心強いパートナーになりますよ。

この情報を深掘りする
-

-
就労移行支援とは何か?「利用条件」や「サービス内容」をわかりやすく解説
就労移行支援は、障がいを持つ方が一般企業で働くための準備を支援する重要な福祉サービスです。 このサービスでは、個々の特性や希望に合わせたスキル訓練や職場実習、就職活動のサポートが提供され、利用者が安心 ...
続きを見る
-

-
就労継続支援A型とは何か?「利用条件」や「仕事内容」をわかりやすく解説
就労継続支援A型は、障害や病気を持つ方が社会で働きながら自立した生活を送るための大切な支援制度です。 この制度では、利用者が事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の給与を受け取りながら働くことができます ...
続きを見る
-

-
就労継続支援B型とは何か?「利用条件」や「仕事内容」をわかりやすく解説
障害を持つ方が社会で自立した生活を送るためには、適切な支援や働く場の確保が欠かせません。 その中で「就労継続支援B型」は、働く意欲があるものの、一般就労が難しい方々に対して、柔軟な就労機会を提供する重 ...
続きを見る
地域移行支援の課題と今後の展望

地域移行支援の充実は、障害のある方の自立と社会参加を促進するうえで非常に重要な取り組みですが、その一方で、実際の運用現場ではさまざまな課題や改善すべき点が指摘されています。福祉制度としての成熟度を高めるには、制度の枠を超えて地域社会全体で向き合う必要があるのが現状です。
現時点で特に注目されている論点は、次の5つです。
- 多様化する居住ニーズへの対応
- 地域住民の理解促進と偏見の解消
- 地域移行後のフォローアップ体制の強化
- 地域資源の活用と連携強化
- 地域移行支援の効果検証と改善
それぞれのテーマについて、順に詳しく見ていきます。
多様化する居住ニーズへの対応
地域移行支援において最も重要な前提の一つが、「住まいの確保」です。しかし実際には、障害のある人が希望する住環境は一様ではなく、支援者側が従来の支援モデルに当てはめようとすると、本人の希望とかみ合わないことがあります。例えば、静かな環境で一人暮らしを望む人もいれば、安心できる仲間と共に過ごしたいという理由からグループホームを選ぶ人もいます。また、通院や買い物など日常生活の利便性を優先する人もいれば、自然の中で落ち着いた暮らしをしたいと考える人もいます。
このように、暮らし方の価値観が多様化する中で、支援側には「本人の希望を起点とする」視点がより強く求められます。ところが、現実の住宅事情や支援体制の地域格差などにより、理想通りの選択肢がすぐに用意できるとは限らないのが現状です。柔軟な住居支援の体制を整備することが、今後の地域移行支援の質を左右するといっても過言ではありません。

支援者と一緒に話し合いながら、条件に近い環境を探すことができます。
すぐに理想が見つからなくても、少しずつ整えていくことは可能です。

地域住民の理解促進と偏見の解消
制度として支援が整っていても、地域での生活がうまくいくかどうかは、住民との関係に大きく左右されます。障害への理解が乏しい地域では、「何かあったら困る」といった不安から、アパートへの入居を拒否されたり、近隣住民との摩擦が生じたりすることがあります。また、障害に対する固定観念や誤解が原因で、本人が地域に居づらさを感じるという事例も後を絶ちません。
このような問題を解決するには、単に障害についての説明をするだけでなく、日常的な交流の中で「顔の見える関係」を築くことが重要です。地域住民と障害のある人が自然な形で関われるイベントや活動、地域包括支援センターや自治会との連携などが、偏見を少しずつ解消していく鍵となります。理解を広げるには時間がかかりますが、誤解は接点を持つことで確実に和らいでいきます。

最初からすべてを理解してもらう必要はありません。
支援者が間に入って丁寧に説明を重ねていくことで、徐々に信頼関係が築かれていきます。

地域移行後のフォローアップ体制の強化
地域への移行が終わったからといって、それで支援が完了するわけではありません。むしろ、ひとりでの生活が本格的に始まってからこそ、新たな困りごとが生じやすくなります。体調の変化、生活費のやりくり、近隣との関係、役所や病院とのやり取りなど、日々の生活の中で出てくる課題に一人で向き合うのは簡単ではありません。
にもかかわらず、移行後の支援が手薄になってしまうケースが多く見られます。これは、制度上の支援期間が限られていることや、自治体の人手不足、関係機関との連携不足などが背景にあります。今後は、移行後の生活が安定するまでの長期的な見守りや、緊急対応が可能な仕組みを整えていくことが求められます。定期的な訪問や連絡手段の確保、安心して相談できる窓口の整備が、継続的な地域生活の鍵になります。


地域資源の活用と連携強化
地域で生活を続けていくには、医療、福祉、就労、教育などの多様な支援機関が連携しながら、利用者を支える必要があります。しかし、実際にはそれぞれの機関が縦割りに運営されていることが多く、情報共有や役割分担がうまくいかないこともあります。
また、地域によってはリソースそのものが不足しており、支援につなげたくても適切なサービスが存在しないという問題も指摘されています。こうした状況を改善するためには、地域全体でのネットワークづくりと、支援者同士の連携強化が求められます。

相談支援専門員が中心となって、関係機関の間を調整する役割を担ってくれます。
複雑な手続きや連絡は一人で背負わなくて大丈夫です。

地域移行支援の効果検証と改善
制度として地域移行支援が全国に広がってきた現在、今後はその実施状況や成果を客観的に検証する仕組みが必要です。支援がどの程度利用者の自立や生活の安定に寄与しているのか、あるいはどこに課題が残っているのかを明らかにし、それに基づいて制度の見直しや改善を行うことが重要です。
そのためには、利用者本人の声や家族の意見を丁寧に聞き取り、支援記録や生活状況を継続的に評価していく必要があります。また、自治体ごとに制度運用に差がある現状も踏まえ、全国的なガイドラインの整備や好事例の共有も求められています。

支援の質ってどうやって見える化されているんだろう?
本当に役立ってるのかな…。
効果を定量・定性の両面で検証する取り組みが進められています。
これからは「実感にもとづいた支援の見直し」が、より重要になっていきます。

まとめ

地域移行支援は、長年にわたり施設や病院で生活していた障害のある方々が、地域社会で自立した生活を営めるように支援する国の福祉制度のひとつです。単なる「退所」や「退院」ではなく、本人の意思を尊重しながら、住まいや日常生活の環境、社会とのつながりを整えることで、その人らしい暮らしの実現を目指す点に、この制度の本質的な意義があります。
支援の対象となるのは、障害者支援施設や精神科病院などの入所・入院者にとどまりません。救護施設、更生施設、刑事施設、さらには更生保護施設などに滞在する障害のある方も対象となっており、制度としては幅広い立場にある人々の地域生活への移行を後押ししています。加えて、支援内容も多岐にわたり、住居の確保から生活スキルの習得、地域資源の活用、就労との両立支援まで、段階的かつ包括的に支援が行われる仕組みとなっています。
しかしながら、制度を活用すればすぐにすべてがうまくいくわけではありません。地域での生活には、施設生活とは異なる責任や困難も伴います。生活環境への適応、支援体制の変化、経済的負担、社会的偏見など、乗り越えなければならない課題も少なくありません。そのため、制度を使う本人だけでなく、支援者や自治体、地域住民、そして社会全体が連携しながら「誰もが暮らしやすい地域づくり」を目指す視点が非常に重要になります。
近年、障害のある人が「地域で暮らすこと」を前提とした支援体制の整備が全国的に進められており、制度の改善も繰り返されています。とはいえ、まだ地域によって支援の質や選択肢に差があったり、効果検証の仕組みが十分でなかったりと、制度の成熟にはさらなる取り組みが求められます。
地域移行支援は、「施設から出ること」自体がゴールではなく、本人が自分らしい暮らしを築き、それを持続できる環境をつくることを最終的な目標としています。そうした意味で、これは一人の人生を支える福祉であると同時に、地域社会の成熟度や包摂力を問う制度でもあります。
もしあなたの周囲に、施設や病院から地域生活への移行を考えている方がいる場合には、ぜひこの制度の存在を伝えてください。そして、支援が必要な人に必要なサポートがきちんと届くよう、社会全体で理解と関心を深めていくことが、これからの福祉に求められているのではないでしょうか。
参考リンクとリソース