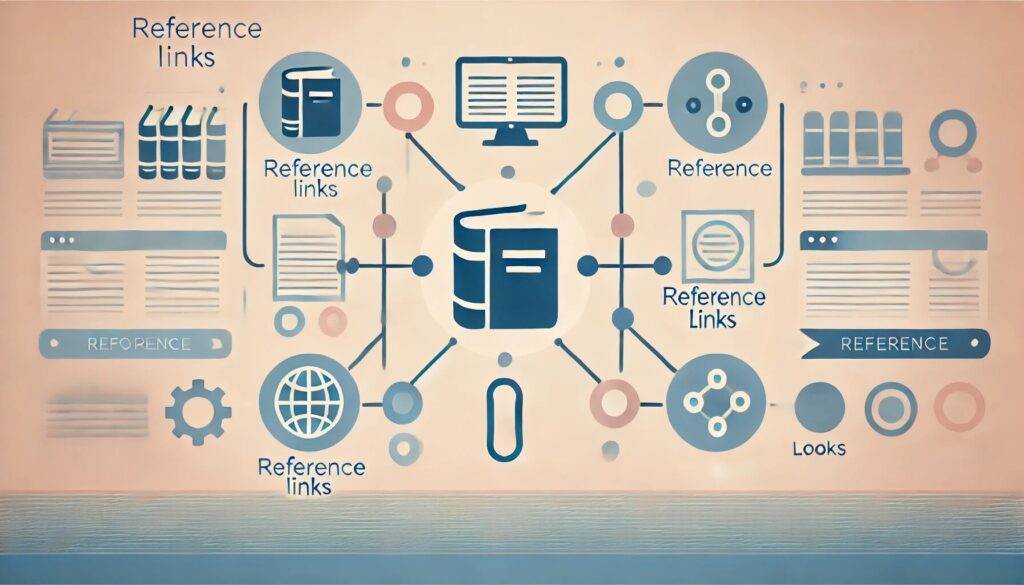地域で一人暮らしを始めた障害のある方にとって、日々の暮らしには期待と同時にさまざまな不安がつきものです。
「急に体調が悪くなったら?」「困ったとき、誰に相談すればいいの?」——そんな声に応えるのが、「地域定着支援」という制度です。

この記事では、地域定着支援とはどんな仕組みなのか、どんな人が対象になるのか、どのような支援が受けられるのかといった基本から、利用手続き、費用、支援のメリット・デメリット、さらには現在抱える制度の課題まで、初心者にも分かりやすく丁寧に解説していきます。
「ひとりでも安心して地域で暮らしたい」「支援が必要な家族の力になりたい」と考えている方にとって、きっと役立つ情報が見つかるはずです。
まずは、制度の全体像から一緒に見ていきましょう。

合わせて読みたい記事
-

-
障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年版】
障害のある子どもを育てている親御さんへ——日々の子育ての中で、こんなふうに感じたことはありませんか?「子どもの気持ちがうまくわからない」「どうサポートすればいいのかわからない」「このままでいいのかな… ...
続きを見る
-

-
障害者福祉について学べるおすすめの本3選【2026年版】
この記事では、障害者福祉について学べるおすすめの本を紹介していきます。障害者福祉を扱っている本は少ないため、厳選して3冊用意しました。障害者福祉とは、身体、知的発達、精神に障害を持つ人々に対して、自立 ...
続きを見る
-

-
障害年金について学べるおすすめの本4選【2026年版】
障害を負う可能性は誰にでもあり、その時に生活の支えになるのは障害年金です。その割に障害年金について理解している人は少ないのではないでしょうか?この記事では、障害年金について学べるおすすめの本を紹介して ...
続きを見る
地域定着支援とは何か?

障害のある方が、地域社会の中で自分らしく安心して暮らしていくためには、日常的な支援だけでなく、万が一の時の体制も整っていることが重要です。特に一人暮らしをしている方や、身近に頼れる家族がいない方にとっては、日常のちょっとした不安や緊急時のトラブルへの備えが大きな課題になります。
地域定着支援は、そうした不安を抱える障害者のために設けられた福祉サービスのひとつです。常時連絡体制を整え、緊急時にはすぐに相談や訪問支援が受けられるようにすることで、地域での生活を継続的に支えていきます。この支援は、「何かあったときに誰が来てくれるのか」「誰に頼ればいいのか」という心配を解消し、利用者に安心感をもたらす重要な制度です。
このセクションでは以下の4つの視点から、この制度について詳しく解説していきます。
- 制度の概要
- 必要とされる背景
- 実施主体
- 費用負担と補助金の割合
それぞれの内容を順に確認していきましょう。
制度の概要
地域定着支援とは、障害のある方が地域で自立した生活を送る中で、万が一の緊急事態が発生した際に、すぐに連絡・相談・訪問が受けられるようにするための支援制度です。対象となるのは、主に単身で暮らす障害者で、近くに頼れる家族や支援者がいない方が想定されています。たとえば、急に体調を崩してしまったときや、生活上のトラブルで混乱してしまったときなど、「いざという時」に対応できる体制を整えることが目的です。
この支援では、普段から支援機関と連絡が取れる状態を保っておき、緊急時には電話や訪問によって迅速な対応が取られます。また、必要に応じて医療機関や警察などの関係機関とも連携し、利用者の安全を守るよう努められます。日常的な生活援助や定期的な訪問を行う他の障害福祉サービスとは異なり、地域定着支援は「常時待機」と「緊急対応」に特化している点が特徴です。
この制度の背景には、施設や病院から地域へと生活の場を移す「地域移行」が進む中で、障害者の孤立や再入所を防ぐ必要性がありました。つまり、「一人で暮らすことはできるけれど、万が一のときに誰かが助けてくれる体制が欲しい」という声に応える仕組みなのです。


必要とされる背景
地域定着支援が必要とされるようになった背景には、障害のある方々の生活環境の大きな変化があります。近年、国の政策として「施設から地域へ」という流れが強まり、これまで病院や入所施設で暮らしていた障害者が、地域社会で自立した生活を送るケースが増えてきました。これは、本人の生活の質を高め、地域での共生社会を実現するための重要な取り組みです。
しかし、現実には一人で暮らすことに伴うリスクや不安も多く、特に緊急時に支援が得られないことが大きな課題となっていました。家族と離れて暮らす障害者の場合、突然の体調不良や精神的な不調、生活上のトラブルなどに対して、即座に対応できる人が身近にいないという状況が少なくありません。その結果、再び入院や入所が必要になったり、地域生活を維持できなくなったりするケースも見られました。
こうした背景から、障害者が地域で安心して生活を続けていくためには、「何かあったときにすぐに相談できる」「必要なときにすぐに誰かが来てくれる」体制の整備が不可欠とされ、地域定着支援が制度として創設されることとなったのです。これは、地域移行を一過性の支援で終わらせず、生活を安定して継続していくための「定着」支援を重視する考え方に基づいています。


実施主体
地域定着支援は、障害者総合支援法に基づく「地域相談支援」の一種であり、市町村がその実施主体となります。ただし、実際の支援業務は市町村が直接行うのではなく、委託を受けた指定相談支援事業所や地域活動支援センターなどが担います。自治体は全体の制度設計やサービスの調整、対象者の認定などを行い、事業所と連携して制度運用を進めています。
支援の現場では、担当支援員が一人ひとりの利用者と連絡体制を構築し、日々の見守りや必要な対応を行っています。支援員は、本人の生活状況や疾患特性に応じた支援計画を策定し、万が一の際には迷わず動けるように準備を整えます。また、医療機関や福祉施設、行政機関など、他の関係機関と連携して対応する場面も多く、総合的な支援ネットワークの一翼を担っているのです。
市町村と事業所、そして地域の関係機関が連携することで、孤立しがちな単身生活者を地域全体で見守る仕組みが成り立っています。制度としての枠組みだけでなく、地域の「顔の見える関係性」が重要な土台となっているのが、この支援の大きな特徴です。

市町村は制度全体の責任主体ですが、実際の支援は専門性を持つ民間の事業所が行います。
現場では柔軟な対応ができる体制が整えられています。

地域定着支援の利用条件

地域定着支援は、障害のある方が地域で安心して生活を続けるための支えとなる制度ですが、誰でも自由に利用できるわけではありません。このサービスを活用するには、いくつかの基準が設けられています。本人の生活状況や家庭環境、これまでの経緯などをもとに、市区町村が必要性を判断し、適切な形でサービスが提供される仕組みになっています。
具体的には、次のような要素が確認されます。
- 対象となる障害の種類
- 単身生活者における支援要件
- 同居家族がいる場合の利用基準
- 利用期間と更新手続き
- 障害支援区分の必要性
これらを踏まえて、支援の必要性が認められた方に対し、24時間体制で安心できる暮らしを支えるサポートが行われます。
それでは順番に、各条件について詳しく見ていきましょう。
対象となる障害の種類
地域定着支援の対象となるのは、障害者総合支援法に基づいて「障害者」と認定された方々です。この「障害者」には、身体障害、知的障害、精神障害、そして難病などで日常生活に支障をきたす疾患を抱えている方も含まれます。障害の種別によって支援内容が大きく変わることはありませんが、支援の必要性や状況は一人ひとり異なるため、個別の状況をふまえた支援計画が必要になります。
たとえば、身体的な障害によって緊急時に連絡手段をとるのが困難な場合や、知的障害がありトラブルの際に適切な対応をとるのが難しいと想定される場合には、地域定着支援の重要性がより高まります。精神障害や発達障害がある方についても、急な体調変化や不安定な状況に陥りやすいため、予期しない事態に備える体制が不可欠です。

難病の方も対象になるケースがあります。
具体的な該当条件は自治体ごとに異なることがあるため、まずは市区町村の障害福祉課に相談してみるとよいでしょう。

単身生活者における支援要件
地域定着支援の中心的な対象となるのが、単身で生活している障害のある方です。身近に頼れる家族や支援者がいない、もしくは日常的に連絡がとれないような状況では、緊急時の対応が遅れがちになります。そうした状況を未然に防ぐため、地域定着支援は「いざというときに誰かが対応してくれる」仕組みとして機能します。
制度上は、障害者が単身で生活していることに加え、緊急時の連絡や支援を行うための体制が必要だと市町村が認めた場合にサービスの対象となります。たとえば、服薬管理に不安がある方、突発的に混乱することがある方、災害や事故などの際に自力で助けを求めるのが難しい方などが典型例です。このように、ひとり暮らしという生活形態と支援の必要性の両面から判断されるのが特徴です。


同居家族がいる場合の利用基準
一見すると、家族と同居していれば地域定着支援の対象外になると思われがちですが、実際には必ずしもそうではありません。同居している家族が高齢であったり、重い疾病を抱えていて緊急時に適切な支援を提供できないと判断される場合には、単身者と同様に対象とされる可能性があります。
また、家族の就労状況によっては昼夜問わず不在がちで、実質的にひとりで生活している状態と同じであるとみなされることもあります。たとえば、介護が必要な家族を抱えている、夜勤で不在になることが多い、障害者本人の症状に対して対応が困難であるといった状況が該当します。こうした家庭状況は、単に「家族がいるかどうか」ではなく「支援が実際に受けられるかどうか」に基づいて判断されます。

はい。実際に支援が得られるかどうかがポイントです。
表面的な同居の有無ではなく、家庭内の実情に基づいて判断されます

利用期間と更新手続き
地域定着支援の利用期間は、地域によって異なりますが、概ね1年間の利用を基本としています。この期間は、地域生活を開始したばかりの方や、支援の必要性が高いと判断された方にとって、最も不安定な時期であり、その期間に重点的な見守りと支援を行うことを目的としています。
ただし、1年経過後に支援の必要性が依然として認められる場合は、所定の手続きを踏むことでサービスの継続が可能です。更新には、市区町村の判断を仰ぐ必要がありますが、利用者の状況や緊急時対応の実績、今後の見通しなどを総合的に評価して決定されます。更新手続きの際は、相談支援専門員と協議を行い、支援の必要性が改めて確認される仕組みです。

必要があれば更新できます。
事前に担当者と相談し、必要な書類や手続きを準備しておきましょう。

障害支援区分の必要性
地域定着支援の利用にあたっては、障害福祉サービスでよく求められる「障害支援区分」の認定が必須ではありません。つまり、この制度を利用するために、あらかじめ区分1〜6のいずれかを取得しておく必要はないということです。他の居宅介護や生活介護などのサービスとは、この点が大きく異なります。
ただし、まったく調査が不要というわけではありません。地域定着支援の給付決定を行うためには、本人の心身の状態や生活上の課題などを把握する必要があるため、障害支援区分認定調査で用いられている調査項目を基にした聞き取りや確認が行われます。これは、実際に区分の認定を求める手続きではなく、あくまで必要な情報を把握するためのものです。
また、すでに障害支援区分の認定を受けている方については、その調査結果が活用されます。市区町村は、過去の認定調査の内容を勘案しながら、支援の必要性を判断して給付決定を行います。これにより、調査の重複や手続きの煩雑さを避けつつ、実情に即した判断がなされるよう配慮されています。

そうなんです。この制度は緊急対応に特化しているため、利用のハードルを下げる工夫がされています。
ただし、必要な情報は市町村がしっかり把握した上で判断しますので、事前の相談はとても重要です。

地域定着支援のサービス内容
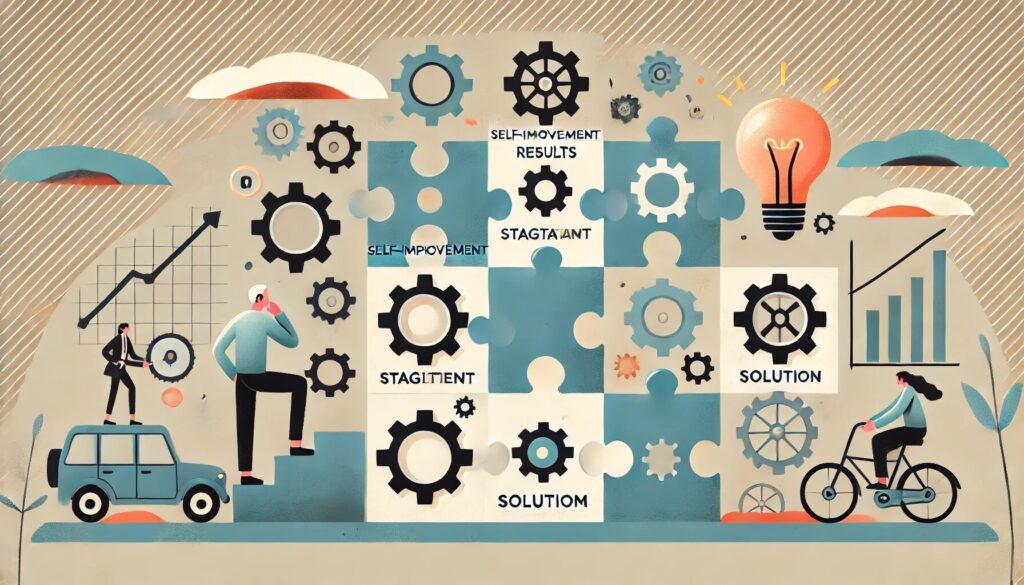
一人暮らしをしている障がいのある方が、地域の中で安心して生活を送るためには、日常的なサポート以上に「いざというとき」に備えた仕組みが欠かせません。地域定着支援では、そうした突発的な状況にも対応できるよう、様々なサービスが用意されています。
具体的には、次のような支援が提供されます。
- 常時の連絡体制の確保
- 緊急訪問支援
- 関係機関との連携
- 利用者情報の管理と共有
これらの取り組みを通じて、利用者が孤立することなく、地域の中で継続的に安心して暮らせるよう支援体制が整えられています。
常時の連絡体制の確保
地域定着支援の中核を担うのが、24時間いつでも連絡がとれる体制の確保です。これは、単身で生活している障害のある方にとって、日常生活の安心感を支える非常に重要な仕組みです。たとえば、深夜に体調が急変したとき、あるいは不安や混乱に襲われたとき、すぐに誰かに連絡できる手段があるかどうかで、その後の対応や心の安定は大きく変わってきます。
この支援では、事前に連絡先を共有し、利用者からの問い合わせや緊急連絡に対応する窓口を常設することで、昼夜問わず支援者とのつながりを保つ仕組みを整えています。具体的には、専用の携帯電話を事業所が保持していたり、当番制で相談支援専門員が対応にあたったりすることもあります。
「もし何かあったら、ここに電話すればいい」という明確な連絡先があることは、利用者にとって非常に大きな安心材料となります。とくに、精神的に不安定になりやすい方や、対人関係に苦手意識がある方にとっては、この「つながりの手段」があるだけで生活のハードルがぐっと下がるのです。

そういった不安を少しでも減らすために、この制度では24時間連絡できる体制が整えられているんです。
安心して地域で暮らし続けるための土台ともいえる仕組みです。

緊急訪問支援
電話やメールでの相談だけでは対応しきれない場合、支援員が実際に利用者の自宅や現場に駆けつけて支援するのが「緊急訪問支援」です。これは、地域定着支援の中でも特に迅速性と柔軟性が求められる重要な機能です。
たとえば、電話が通じなくなった、約束の時間になっても利用者が現れない、近所の人から「様子がおかしい」と連絡が入った場合など、安否確認が必要とされる状況では、すぐに現地に行って様子を見たり、必要な支援を行います。また、本人が混乱して自力ではどうにもできないような場面では、支援員の存在が安心材料となり、状況の安定化につながることもあります。
訪問はあくまで「緊急時」の手段ですが、その中で得られる情報や、実際の様子から今後の支援方針を見直すきっかけにもなります。直接会って話すことで初めて分かることも多く、地域定着支援では「駆けつける力」が非常に重視されているのです。

必要と判断される場合には、夜間や休日でも訪問対応を行う体制が整えられています。
むしろ緊急時こそ支援の本領が発揮される場面ですから、遠慮せず連絡してください。

関係機関との連携
地域での生活は、ひとつの支援機関だけで支えられるものではありません。医療、介護、福祉、住宅、行政など、多くの関係者と協力しながら成り立っています。地域定着支援は、その“つなぎ役”としての機能も担っています。
たとえば、ある利用者が精神的に不安定になっているとき、支援員が一人で解決しようとするのではなく、必要に応じて主治医や訪問看護師と連絡を取り、状況を共有します。また、金銭管理に課題がある人であれば、地域包括支援センターや成年後見制度の窓口と連携し、支援体制を整えるといった調整も行われます。
支援員は、利用者の状況を一番近くで見ている存在として、それぞれの関係機関と情報をすり合わせながら、無理のない支援の形を築いていきます。この「連携のハブ」としての役割があることで、必要なときに必要な支援が届きやすくなり、生活の安定にもつながります。

はい。定着支援の大きな強みは「孤立させないこと」。
多方面との協力によって、どんな局面にも対応できるよう体制が整えられています。

利用者情報の管理と共有
地域定着支援では、支援の精度を高めるために、利用者の生活状況や過去の支援内容などを記録・管理し、それを必要に応じて関係機関と共有することが重要とされています。この情報共有が適切に行われることで、たとえば別の支援者が対応することになっても、一貫した支援が提供できるというメリットがあります。
記録には、日々の連絡内容や訪問時の様子、支援を通じて分かった課題や対応方針などが詳細に残されます。また、共有する際には、プライバシー保護に十分配慮され、同意を得たうえで必要最小限の範囲に限って情報が扱われます。これにより、支援の質を保ちつつ、個人の尊厳を損なわないバランスが確保されています。
特に、精神的に不安定な状況にある利用者の場合、支援者によって言うことが変わると混乱を招きやすいため、「誰が関わっても一貫した対応ができる」状態を作っておくことが大切です。そのために、情報の丁寧な記録と正確な共有は欠かせない作業なのです。

情報は本人の同意を前提に、支援に必要な範囲でのみ共有されます。
本人の意思やプライバシーを尊重することは、支援の基本ですので安心してください。

地域定着支援の利用手続き

制度の対象になっていることが分かったとしても、実際に支援を受けるまでにはいくつかのステップを踏む必要があります。これらの手順は一見すると複雑に感じるかもしれませんが、順を追って対応すれば安心して申請を進められるようになっています。ここでは、初めて制度に触れる方でも無理なく理解できるよう、必要な流れを丁寧にご紹介します。
手続きは、大きく分けて以下の5つの段階に分かれています。
- step1 市区町村の障害福祉課への相談
- step2 障害福祉サービス受給者証の申請手続き
- step3 認定調査とヒアリングの実施
- step4 受給者証の発行と利用契約の締結
- step5 サービス利用開始と個別支援計画の策定
これらを順にたどっていくことで、正式に地域定着支援を開始することができます。
次に、それぞれの段階で必要なことを詳しく見ていきましょう。
step1 市区町村の障害福祉課への相談
地域定着支援を利用したいと考えたとき、まず最初に行うべきことは、お住まいの市区町村にある障害福祉課への相談です。市区町村は地域定着支援の実施主体でもあり、制度の案内や利用希望者の状況確認を行う窓口となっています。ここでは、本人の障害の状態や生活状況を簡単に伝えたうえで、地域定着支援の対象となる可能性があるかを確認します。
この段階では、まだ申請や認定などの正式な手続きには入りません。まずは「制度について正しく知る」「自分が対象になるのかを知る」という情報収集と相談が目的です。状況によっては、制度の説明だけでなく、他に適した福祉サービスの提案がなされることもあります。

制度について知りたい」と伝えるだけで大丈夫です。
窓口の職員が順を追って案内してくれますから、気軽に行ってみてください。

step2 障害福祉サービス受給者証の申請手続き
地域定着支援を正式に利用するには、障害福祉サービスのひとつとして「受給者証」の取得が必要です。この受給者証は、各種障害福祉サービスを利用する際の「許可証」のような役割を持ち、市区町村に対して申請を行うことで発行されます。
申請にあたっては、専用の申請書類のほか、本人確認書類や医師の診断書などが求められる場合があります。書類の内容が難しいと感じる場合でも、福祉課の職員が記入方法をサポートしてくれるので心配はいりません。また、支援を受けたい内容や希望する事業所などがある場合は、この時点であわせて伝えておくとスムーズに手続きが進みます。

職員が丁寧に説明してくれますし、相談支援専門員がいれば一緒に手続きを進めることもできます。
気負わずに進めましょう。

step3 認定調査とヒアリングの実施
申請が受理されると、次に行われるのが「認定調査」と「ヒアリング」です。これは、実際に支援が必要かどうかを見極めるために、市区町村の担当職員や相談支援専門員が本人のもとを訪問し、心身の状態や生活の様子を聞き取るものです。
調査では、日常生活にどれだけ支障があるのか、どのようなときに不安や困りごとが生じるのかといった点を中心に確認が行われます。また、本人だけでなく、必要に応じて家族や支援者からの意見も参考にされます。あくまで支援の必要性を把握するためのものであり、「できないこと」を責めるための調査ではありません。

ちゃんと説明できるか自信がないです。
調査って厳しく見られるんじゃないかと緊張します。
緊張しなくても大丈夫です。調査員は“支援の必要性を見つけるため”に来ています。
困っていることがあれば遠慮せずに伝えることが大切です。

step4 受給者証の発行と利用契約の締結
調査結果をもとに、市区町村が地域定着支援の給付決定を行うと、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。この受給者証には、利用できるサービスの種別や期間などが記載されています。交付された後は、実際にサービスを提供する相談支援事業所と契約を交わす必要があります。
契約の際には、事業所の担当者からサービスの具体的な内容や連絡体制、緊急時の対応方法などについて詳しい説明があります。納得したうえで契約書に署名をし、サービス提供が正式に開始される準備が整います。契約内容について分からない点があれば、その場で何でも質問して構いません。

受給者証ってどこかに提示しないと使えないんですか?
契約って何を決めるんですか?
受給者証は実際の利用手続きや請求処理のために使われます。
契約では、サービスの内容や体制を明確にして、お互いの役割を確認するための大事なプロセスです。

step5 サービス利用開始と個別支援計画の策定
契約が完了すると、いよいよサービスの利用がスタートします。ただし、その前にもう一つ大切な準備があります。それが、個別支援計画の作成です。これは、利用者一人ひとりの生活状況や支援の必要性に応じて、どのような支援をどのように行っていくかを具体的にまとめた計画書です。
この計画は、相談支援専門員が中心となって、本人の希望や不安を丁寧に聞き取りながら作成されます。「何をしてほしいのか」「どんなときに助けが必要か」など、利用者自身の思いを反映させることがとても重要です。完成した計画に基づいて、地域定着支援の支援内容が実際に提供されることになります。

専門員がしっかりサポートしてくれます。
普段の生活で困っていることや気になっていることを素直に話すことが、良い計画づくりにつながります。

地域定着支援の費用と負担額

この制度を利用するにあたって、費用面での不安を感じる方も少なくありません。「無料で使えるの?」「自己負担はあるの?」といった疑問の声も多く寄せられます。制度の仕組みを理解しておくことで、安心してサービスを利用できるようになります。
費用に関して押さえておきたいポイントは、次の3つです。
- 利用者の費用負担はありません
- 事業所側に対して地域相談支援給付金
- サービス利用に伴う費用は自己負担
それぞれの内容を理解することで、安心して地域生活を支える仕組みを利用できるようになります。
次に、それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
利用者の費用負担はありません
地域定着支援は、障害者総合支援法に基づく公的な福祉サービスとして提供されています。そのため、原則として利用者本人が支援を受ける際に直接的な費用を支払う必要はありません。つまり、サービス利用料は全額、国と自治体の公費によって賄われているのです。
これは、地域で自立した生活を送る上で、経済的な負担が支援の妨げにならないようにするという制度の理念に基づいています。特に、単身で暮らす障害のある方にとって、金銭面の不安は生活そのものを不安定にさせてしまう要因になります。そのため、安心して支援を受けられるように、費用面での配慮がなされているのです。
ただし、全くの無償というわけではなく、後述するように特定の状況においては一部自己負担が発生する可能性もあるため、実際の利用にあたっては詳細を確認しておくことが大切です。

その通りです。
制度として基本的なサービスは無料で提供されるため、生活保護を受給している方や年金収入のみの方でも利用しやすくなっています。

事業所側に対して地域相談支援給付金
地域定着支援は、指定を受けた相談支援事業所によって提供されます。これらの事業所には、サービス実施にかかる人件費や運営費の一部を補助するため、自治体から「地域相談支援給付金」が支払われます。この給付金は、利用者が支払う料金ではなく、国と地方自治体が財源を分担するかたちで事業所に支給されるものです。
この仕組みによって、事業所は常時連絡体制の維持や緊急時対応など、利用者の生活を支えるサービスを安定して提供することが可能になります。

運営費の多くは、国と自治体からの給付金によって賄われています。
だからこそ、利用者に直接負担を求めずに済むんです。

サービス利用に伴う費用は自己負担
地域定着支援そのものの利用料は無料ですが、サービスを受ける過程で発生する実費については、利用者が自己負担しなければならない場合があります。たとえば、医療機関への同行にかかる実費、相談支援専門員が外出先に出向いたときの出張費などがその一例です。
また、本人の希望によって支援時間中に発生した食事代や消耗品なども、制度の給付対象外となるため、別途支払う必要が出てくることがあります。これらはあくまで「サービス本体以外」の費用であり、地域定着支援の枠組みそのものとは別扱いになります。
こうした実費の範囲や金額は、事業所によって運用が異なる場合があるため、利用開始前に事前説明を受けることがとても重要です。契約時には、自己負担が想定される費用についても明示されるのが一般的ですので、納得したうえでサービスを開始するようにしましょう。

はい、サービス提供そのものには費用はかかりませんが、交通費や食費などの実費は自己負担となることがあります。
あらかじめ説明を受けておくと安心です。

地域定着支援を利用するメリット

地域定着支援を利用することで、障がいのある方が地域社会で安心して生活を続けるためのさまざまなメリットが得られます。
主なメリットとして、以下の点が挙げられます。
- 緊急時の迅速な対応が可能
- 精神的な安心感の向上
- 地域社会での生活継続の支援
- 家族等支援者の負担軽減
それぞれのメリットについて、詳しく説明いたします。
緊急時の迅速な対応が可能
地域定着支援の大きな特長のひとつが、緊急時にすぐ支援が届く体制があらかじめ整えられている点です。障がいのある方が一人暮らしをしていると、体調の急変や精神的な不調、不意のトラブルなどに自力で対応することが難しい場面が多々あります。たとえば、夜中に激しい動悸や不安感が襲ってきたとき、自分ひとりではどうすることもできず、不安がさらに増してしまうということも少なくありません。
こうしたときに、あらかじめ支援者と連絡体制が構築されていることで、電話一本で状況を伝え、場合によってはその場で助言を受けたり、必要に応じて訪問対応をしてもらえるのです。まるで、いつでも呼び出せる「見守り隊」がいるような感覚です。この迅速な対応が可能だからこそ、利用者は安心して日々を送ることができ、万が一の事態も大きな問題に発展する前に対処することが可能になります。

地域定着支援は、その「何かあったとき」にすぐに対応できることを目的とした制度です。
孤立を防ぎ、安心できる環境を支えるのがこの支援の大きな価値です。

精神的な安心感の向上
生活の中で予測できない事態に対処できる備えがあるということは、それ自体が大きな安心感につながります。障害のある方が地域で暮らす際、外から見て何も問題がないように見えても、実際には常に「何か起きたらどうしよう」「誰にも相談できなかったら」という不安を抱えていることが少なくありません。とくに精神障害や発達障害がある場合、その不安感や孤立感は日々の生活に大きく影響を及ぼします。
地域定着支援では、電話や訪問によって「困ったら話を聞いてくれる人がいる」「自分のことを気にかけてくれている人がいる」という人とのつながりが常に確保されています。このことが、生活の土台に安定感をもたらし、不安定な状況に陥りにくくなる大きな効果を生み出しています。

まさにその通りです。
地域定着支援は、日常の中に“安心のつながり”を提供することで、精神的な安定を支える役割も果たしています。

家族等支援者の負担軽減
障がいのある方を支える家族や支援者にとって、24時間体制での見守りや緊急対応を一手に担うのは、大きな心理的・身体的負担となります。とくに高齢の親が単身の子どもを支援している場合、自分の健康や体力に不安を感じながら支援を続けているケースも多く見られます。
地域定着支援を利用することで、そうした家族の負担を軽減し、役割を分担することが可能になります。支援員が常時の連絡体制を担い、緊急時にも対応してくれることで、家族は「自分がすべてを抱え込まなくてもよい」と思えるようになります。実際に、「夜間は電話がつながる先があるだけで安心できる」と話すご家族も少なくありません。

そのお気持ちはとても自然なことです。
地域定着支援は、家族を“支える側”から“協力する仲間”へと立ち位置を変え、支援の負担を分け合う仕組みでもあります。

地域定着支援に関するよくある質問(FAQ)

この制度については、「どこで使えるのか」「どのくらい利用できるのか」といった基本的な疑問から、「他の支援と何が違うのか」といった制度の特徴に関するものまで、さまざまな質問が寄せられています。
初めて制度を検討する方にとって、事前に押さえておきたいポイントを以下に整理しました。
- 地域定着支援と地域移行支援の違いは?
- 地域定着支援の費用負担はありますか?
- 地域定着支援の利用期間はどのくらいですか?
- 地域定着支援を利用する際の注意点は?
以下では、それぞれの疑問に対して丁寧に解説していきます。
制度を検討する際の参考にしてください。
地域定着支援と地域移行支援の違いは?
地域定着支援と地域移行支援は、どちらも障害のある方の地域生活を支えるための制度ですが、その役割や目的にははっきりとした違いがあります。地域移行支援は、長期間入所していた障害者支援施設や精神科病院などから、地域の住まいへ移り住むことを希望する人を対象としています。退所や退院後にスムーズに地域生活へ移行できるよう、事前の準備や住居の調整、関係機関との橋渡しなどを行うのがその主な目的です。
一方で、地域定着支援は、すでに地域で単身生活を始めている障害のある方が、その生活を安定的に継続していくための支援です。特に、身近に支援者がいない人や、日常生活で突発的な問題が起きたときに孤立しやすい人を対象に、24時間体制の連絡窓口や緊急訪問などを通じて安心して生活を送れるようサポートします。
つまり、移行支援は「地域に出るための準備と移行」を支える制度であり、定着支援は「地域で生活を続けるための見守りと対応」を目的とした制度です。どちらも連続的に利用されることがあり、地域に出た後に定着支援へ移行するケースも多く見られます。

名前が似ていて混乱してしまいます。
どちらが自分に必要な支援なのか、どうやって見分ければいいのか不安です。
迷ったときは、現在の生活状況を整理することがポイントです。
今いる場所が施設や病院であれば移行支援、すでに一人暮らしをしている場合は定着支援が基本の目安になります。

地域定着支援の費用負担はありますか?
この支援は、公費によって運営されている制度であり、原則として利用者には費用の負担はありません。つまり、申請をして利用が認められれば、制度の範囲内で提供されるサービスについては無料で受けることができます。
ただし、支援の過程で発生する交通費や、外出先での食事代などの実費については自己負担となることがあります。たとえば、緊急時に医療機関を受診する際のタクシー代や、通院同行の際の昼食代などは、支援とは別の生活費として扱われます。

制度そのものの利用料はかかりませんが、生活に付随する実費は発生することがあります。
契約時の説明をきちんと聞いて、分からないことは遠慮せず質問しましょう。

地域定着支援の利用期間はどのくらいですか?
地域定着支援の利用期間は、原則として1年間と定められています。これはあくまで目安であり、初めから無期限の支援を想定しているわけではありません。地域生活に移行したばかりの時期は、生活のリズムが不安定だったり、予期せぬトラブルが起こりやすいため、特に支援が必要とされる期間として1年が設定されています。
ただし、1年を過ぎても引き続き支援が必要と判断される場合には、継続のための再申請を行うことができます。再申請の際には、これまでの支援の実施状況や利用者の生活の安定度、今後の見通しなどを踏まえて、市区町村が継続の可否を判断します。

1年で終わってしまったら、その後が不安です。
支援が途中で切れてしまわないか心配です。
原則は1年ですが、必要な場合には再申請を行うことで継続が可能です。
支援の必要性がある限り、きちんとフォローされる仕組みになっています。

地域定着支援を利用する際の注意点は?
制度を利用するうえでの注意点としてまず挙げられるのは、利用対象者の条件をしっかり確認することです。地域定着支援は、誰でも利用できる汎用的な相談支援ではなく、原則として単身生活を送っている障害のある方や、身近に頼れる家族や支援者がいない方などが対象となっています。また、退院・退所後に地域での生活を始めた方など、特定の条件に該当するかが利用の前提になります。
次に重要なのが、支援の内容や範囲をよく理解しておくことです。この制度は、あくまで「緊急対応」と「見守り」を中心としたサービスであり、日常的な家事援助や外出支援といった身体的な介助を行うものではありません。求めている支援が制度の範囲外であると、期待とのズレが生じてしまいます。
また、相談支援専門員や事業所との連絡体制を日頃からしっかり構築しておくことも大切です。連絡が取りにくい状態が続いたり、情報が共有されていなかったりすると、緊急時に適切な対応ができなくなる可能性もあるためです。

不安なときは、まず市区町村の障害福祉課や相談支援事業所に相談してみてください。
制度の対象かどうかも含め、分かりやすく案内してもらえます。

地域定着支援の課題

地域定着支援は、障害のある方が地域社会で安心して生活を続けるための重要なサービスですが、いくつかの課題も指摘されています。
主な課題として、以下の2点が挙げられます。
- 支援終了後のフォロー体制の課題
- 支援期間の制限
これらの課題について、以下で詳しく解説します。
支援終了後のフォロー体制の課題
地域定着支援は、地域で単身生活を送る障害のある方が、急な体調不良や生活上の困りごとに対応できるよう、常時の連絡体制や緊急訪問を整えた心強い仕組みです。しかし、支援にはあらかじめ定められた期間があり、終了した後のフォロー体制については、地域や事業所によって差があるのが実情です。
例えば、1年間の支援期間が終了した後に「生活は安定したように見えていたが、実は一時的な安定に過ぎなかった」というケースでは、支援の打ち切りが早すぎると感じる当事者も少なくありません。支援が終了したとたん、孤立感が強まり、再び精神的に不安定になったり、再入院のリスクが高まったりする可能性もあります。
本来であれば、支援終了後も何らかの形で「つながり」を残し、困った時にすぐ相談できる窓口があることで、再び生活が傾くのを防ぐことができます。しかし現状では、「定着支援が終わる=見守りが完全に終了する」といった断絶的な運用になっていることも多く、制度的な「継続的支援の橋渡し」が十分に整っていないのです。

そうした不安に対応するには、地域包括支援センターや相談支援事業所など、支援終了後も相談できる機関とつながりを持ち続けることが大切です。
制度的にも、他の支援サービスと連携しやすい体制の構築が求められています。

支援期間の制限
地域定着支援の利用期間は、原則として1年間とされています。これは制度として「一時的な支援で生活の安定を促す」ことを目的にしているからです。しかし、すべての利用者が1年という期間で生活を完全に安定させられるわけではありません。精神障害や発達障害などのある方の場合は、生活リズムを整えるのに時間がかかったり、支援を通じて信頼関係が築かれるまでに数か月以上を要したりすることもあります。
支援が本格化し、やっと本人が安心して生活できるようになった矢先に「支援期間満了」という理由で終了せざるを得ないケースもあり、これでは定着支援の本来の目的である「地域での安定した生活の確保」が十分に達成されないこともあるのです。

支援の延長は可能ですが、仕組みを知らないと終了してしまうこともあります。
支援者と早めに今後の見通しを話し合い、継続の可能性について確認しておくと安心です。

まとめ

地域定着支援は、地域で一人暮らしをする障害のある方が安心して生活を継続できるよう、24時間の連絡体制や緊急時の訪問支援を通じて見守る制度です。特に、施設や病院を退所・退院した後の「孤立」や「再入院」のリスクを軽減し、地域社会で自分らしく暮らし続けることを可能にする、重要な仕組みといえます。
本記事では、制度の概要から利用条件、支援内容、手続きの流れ、費用負担、そしてメリット・デメリットや課題まで、包括的に解説しました。制度の設計には一定の制限や改善点もありますが、正しい知識を持ち、適切に利用することで、当事者やご家族にとって大きな安心につながります。
「支援が必要だけど、どこに相談すればいいか分からない」「一人で生活していて不安がある」——そんなときこそ、地域定着支援という選択肢があることを、ぜひ知っておいてください。まずはお住まいの市区町村や相談支援事業所に問い合わせてみることが、第一歩になります。
参考リンクとリソース