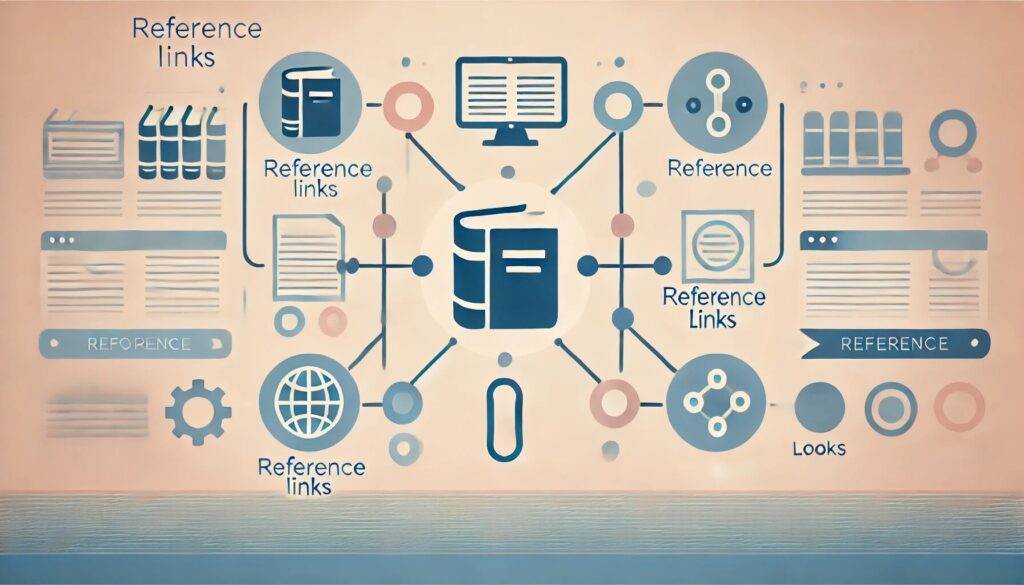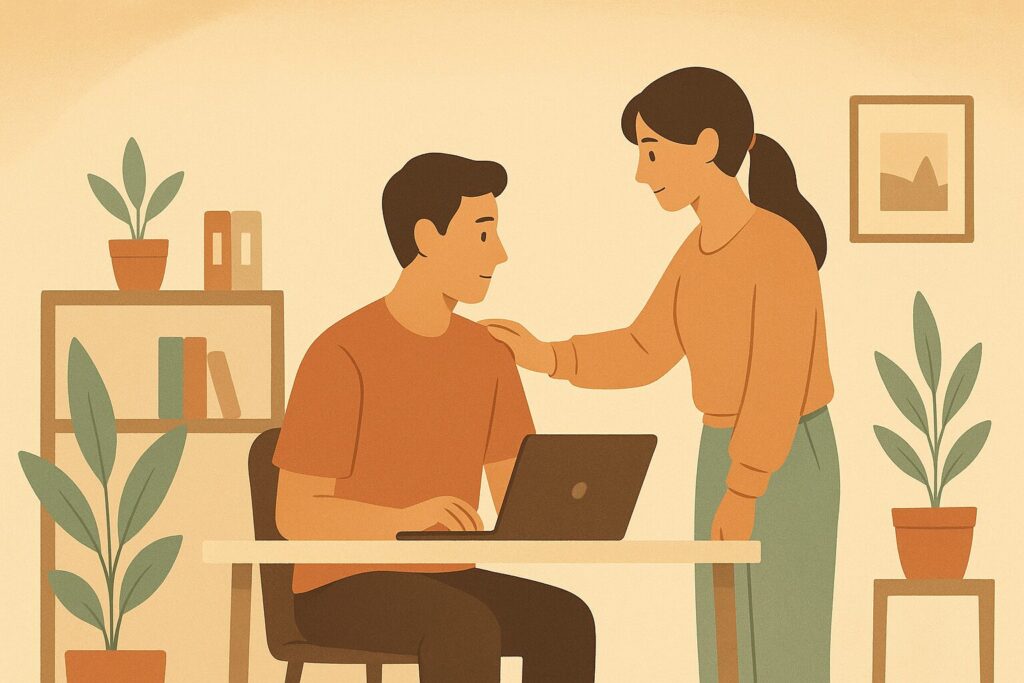
障がいのある方が一般企業に就職した後、長く安定して働き続けるためには、職場での悩みや生活上の不安を一人で抱え込まず、適切な支援を受けることがとても大切です。そんなとき、心強いサポートとなるのが「就労定着支援」です。

就労定着支援は、職場でのコミュニケーションや業務の悩み、体調管理など、働き続けるうえで直面しやすいさまざまな課題に寄り添い、解決に向けた支援を行う制度です。
しかし、まだこの制度の内容や利用方法について詳しく知らない方も多いかもしれません。
この記事では、就労定着支援の基本的な仕組みから、対象となる方、利用の流れ、支援内容、利用するうえでのメリット・注意点まで、初心者にも分かりやすく体系的に解説していきます。
初めての方でも安心して理解できるよう、専門用語には補足説明を加えながら丁寧に紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

合わせて読みたい記事
-

-
障害のある子どもを持つ親が読むべきおすすめの本 8選!人気ランキング【2026年版】
障害のある子どもを育てている親御さんへ——日々の子育ての中で、こんなふうに感じたことはありませんか?「子どもの気持ちがうまくわからない」「どうサポートすればいいのかわからない」「このままでいいのかな… ...
続きを見る
-

-
障害者福祉について学べるおすすめの本3選【2026年版】
この記事では、障害者福祉について学べるおすすめの本を紹介していきます。障害者福祉を扱っている本は少ないため、厳選して3冊用意しました。障害者福祉とは、身体、知的発達、精神に障害を持つ人々に対して、自立 ...
続きを見る
-

-
障害年金について学べるおすすめの本4選【2026年版】
障害を負う可能性は誰にでもあり、その時に生活の支えになるのは障害年金です。その割に障害年金について理解している人は少ないのではないでしょうか?この記事では、障害年金について学べるおすすめの本を紹介して ...
続きを見る
就労定着支援とは何か?

障害のある方が一般企業に就職した後、長く安定して働き続けるためには、就労後も適切な支援が欠かせません。就職できたからといってすべてが順調に進むわけではなく、職場での人間関係、体調管理、生活リズムの維持といった問題に直面することが少なくないためです。
こうした課題をサポートするために設けられた福祉サービスが「就労定着支援」です。この支援を受けることで、就職後の不安を抱えたまま孤立することなく、安心して仕事を続けることができる環境づくりが目指されています。
本章では、次の3つの観点から就労定着支援について詳しく解説します。
- 制度の概要
- 必要とされる背景
- 実施主体
それぞれ順番に見ていきましょう。
制度の概要
就労定着支援は、障害者総合支援法に基づき2018年4月から新たに設けられた福祉サービスです。対象は、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練などを経て一般企業へ就職した障害のある方で、就職後6か月以上が経過していることが利用の条件となります。この制度は、就労後に起こりやすい生活面や体調面、職場内での悩みや不安に対応し、本人と企業の両方を支えることを目的としています。
支援内容は多岐にわたり、利用者本人との定期的な面談、職場担当者との情報共有、生活リズムの安定に向けた助言、人間関係の調整支援などが含まれます。特に、働きながら直面する日常的な課題を見逃さず、早期に対応することで、離職リスクを低減する役割を果たしています。単に「就職させる」ことがゴールではなく、「働き続けること」を重視する制度です。


必要とされる背景
障害者の一般就労が進む一方で、職場に長く定着できず離職してしまうケースが多いことが社会課題となっていました。特に就職後1年以内に離職する割合は3割近くに上るとされており、その背景には職場環境への適応困難、生活リズムの乱れ、健康管理の難しさ、対人関係のストレスといった複合的な要因が存在しています。
こうした問題を放置すれば、本人の自信喪失や再就職の困難さを招くだけでなく、企業側にとっても障害者雇用の定着促進という社会的要請に応えられなくなるリスクが高まります。そのため、就職後も継続的に支援を行う枠組みが必要とされ、就労定着支援が制度化されたのです。本人、企業、社会全体にとって、安定した職場定着を支えるための仕組みが求められていました。


実施主体
就労定着支援を実施しているのは、厚生労働省の基準に基づいて指定を受けた障害福祉サービス事業所です。多くの場合、就労移行支援や生活訓練などのサービスを行っている事業所が、併設する形で就労定着支援も提供しています。支援を担当するスタッフには、相談支援専門員やサービス管理責任者、職業指導員など、福祉や医療分野での専門資格を持った人材が配置されています。
彼らは、利用者本人への支援はもちろん、企業担当者と連絡を取り合い、職場内の課題把握や調整を行う役割も担っています。また、支援活動の質を維持するため、月1回以上の面談を義務づけるとともに、支援内容を記録し管理する仕組みも整えられています。これにより、単なる相談役ではなく、利用者と企業をつなぐ橋渡し役として、より実践的な支援が可能となっています。


就労定着支援の利用条件

就労定着支援を受けるためには、誰でも利用できるわけではなく、一定の条件が定められています。
これらの基準は、支援が本当に必要な方に確実に届くように設計されており、利用開始のタイミングや対象となる人の要件も明確にルール化されています。
このセクションでは、次の4つのポイントに沿って、制度のしくみを丁寧に解説していきます。
- 利用対象者の基本要件
- 利用開始のタイミングと期間
- 特例的な対象者と条件
- 利用期間中の転職や中断時の取り扱い
これらのポイントを順に確認していきましょう。
利用対象者の基本要件
就労定着支援を利用するためには、一定の条件を満たしていることが必要です。単に「障害がある」「就職している」だけでは利用できるわけではなく、障害福祉サービスを受けたうえで一般企業に就労していることが前提とされています。
対象者となるのは、たとえば就労移行支援や就労継続支援A型を利用してきた方です。これらの支援を経て、一般就労に至った実績が必要とされます。障害の種類に制限は設けられておらず、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害など、さまざまなケースに対応しています。
また、障害者手帳を持っていることが一般的ではありますが、手帳を取得していない場合でも、医師の診断書や自治体の意見書により、就労に特別な支援が必要と認められれば対象になることがあります。つまり、手帳の有無だけで利用可否が決まるわけではありません。
注意すべきなのは、単に企業に就職しているだけでは対象外となる点です。必ず、障害福祉サービスと就労支援の流れを経ていることが求められます。この点を押さえておかないと、利用希望を出しても認められないことがあるため、事前に確認が必要です。

その通りです。障害特性が診断書などで証明できれば、手帳なしでも利用対象となることがあります。
ただし、最終的な判断は自治体に委ねられるので、早めに相談することをおすすめします。

この情報を深掘りする
-

-
障害者手帳とは何か?「手帳の種類」や「メリット・デメリット」をわかりやすく解説
日常生活において、障害のある人が受けられる支援はさまざまですが、その中でも「障害者手帳」は公的な支援を受けるための重要なツールです。 手帳を持つことで、税金の控除や医療費の助成、交通費の割引など、多く ...
続きを見る
利用開始のタイミングと期間
このサービスは、就職した直後から自動的に受けられるわけではありません。一般企業への就労後、まずは6か月間の「定着支援期間」が設けられています。この期間中は、就労移行支援事業所などが中心となり、本人と企業双方を見守りながら必要な支援を行います。
6か月を経過した後、本人の状況に応じて、正式に就労定着支援が始まります。この区分けは非常に重要で、就職直後の急激な環境変化に順応できるかどうかを見極めるために設けられています。職場になじめるか、業務に適応できるか、生活リズムが安定しているかといった点が、この期間中に確認されます。
正式に利用が始まったあとは、最長で3年間の支援を受けることが可能です。ただし、単に機械的に3年続くわけではなく、1年ごとに支援計画を作成し直し、その年ごとの必要性を検証していきます。支援が必要ないと判断されれば途中で終了することもあり、逆に必要性が続けば満期まで支援が続けられます。

はい、最初の6か月は"定着支援期間"と呼ばれ、支援の形態が異なります。
本格的な就労定着支援は、その後に始まる段階的な支援になります。ここを押さえておくと、混乱せずに進められます。

特例的な対象者と条件
通常の条件に加えて、特例的な取り扱いがなされる場合もあります。たとえば、週20時間未満の短時間勤務の方でも、継続的に支援が必要だと認められれば、就労定着支援を利用することができます。
特例の対象になるのは、たとえば障害特性により体力が続きにくく、通常勤務が困難な場合や、企業側が障害に対する理解や配慮が十分でない環境で働いている場合などです。短時間勤務というだけで自動的に対象外になることはなく、個別の状況を丁寧に見たうえで支援の必要性が判断されます。
また、65歳以上の方でも、障害福祉サービスを利用していた実績があれば、特例で支援が認められるケースもあります。これらの特例利用を希望する場合は、通常以上に丁寧な書類提出(診断書、意見書など)が求められるため、早めの準備が肝心です。

短時間勤務でも、職場への適応に特別な支援が必要と認められれば、支援の対象になります。
単なる勤務時間の長さだけで判断されるわけではないので、ぜひ相談してみてください。

利用期間中の転職や中断時の取り扱い
支援利用中に転職や就労中断が発生することは、めずらしいことではありません。こうした場合でも、基本的には就労定着支援を継続できる仕組みが用意されています。
転職した場合は、退職後1ヶ月以内に新しい職場で働き始めた場合は、1回に限り利用を継続できます。転職先が一般企業であれば支援はそのまま引き継がれます。ただし、企業環境が変わるため、あらためて支援計画の見直しや支援内容の再調整が必要になります。転職後の業務内容や環境によって、新たな課題が発生する可能性があるため、早めに事業所と連携を取ることが求められます。
一方、体調不良や家庭の事情などで一時的に就労を中断する場合には、支援は一時停止扱いとなり、復職後に再開することができます。


就労定着支援の具体的な支援内容
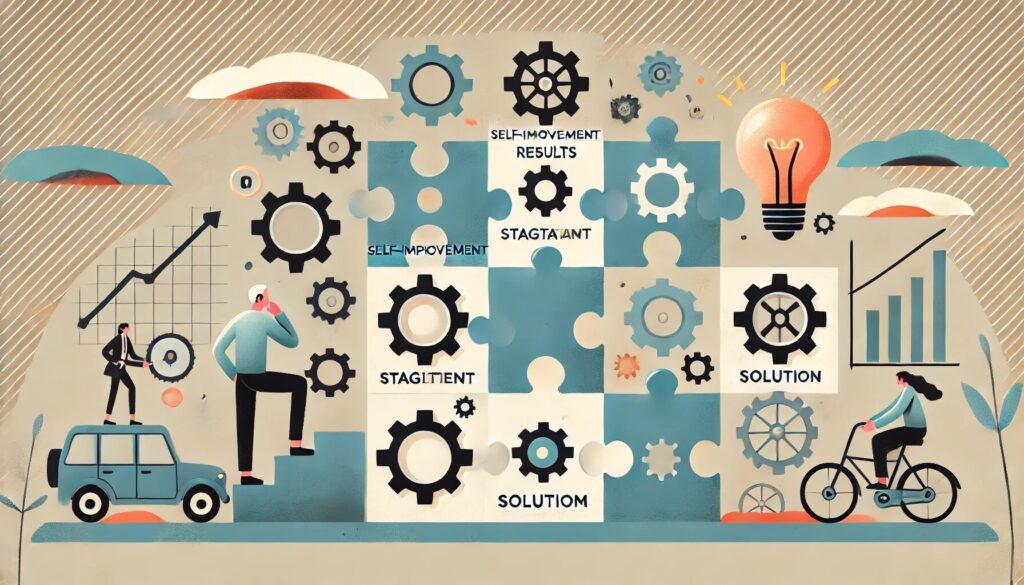
障害のある方が職場に長く安定して働き続けるためには、就労後のきめ細かなサポートが欠かせません。就労定着支援では、単に困りごとを聞くだけでなく、働く上での環境づくりや生活面の安定支援まで、さまざまな側面から支援が行われます。
具体的には、次のような内容に分かれています。
- 利用者との定期的な面談とヒアリング
- 企業担当者との連携と情報共有
- 生活面の支援(体調管理・生活リズム・金銭管理)
- 就業面の支援(業務上の課題・人間関係の調整)
- 関係機関との連携(医療機関・福祉サービス事業所・家族)
それぞれの具体的な取り組みを順に確認していきましょう。
利用者との定期的な面談とヒアリング
就労定着支援では、本人との定期的な面談が支援の軸となっています。働き続けるうえで小さな不安や問題が積み重なると、離職につながるリスクが高まるため、定期的に状況を把握して早期に対応することが非常に重要です。
面談は原則として月に1回以上実施され、対面を基本としながら必要に応じて電話やオンラインも活用されます。支援員は「最近困っていることはないか」「体調はどうか」「職場で何か変化がなかったか」などを丁寧に尋ね、本人が話しやすい空気を作るよう心がけています。特に、表面的な「大丈夫」という言葉にとどまらず、本人も気づいていない違和感や負担を引き出すために、雑談を交えたリラックスした雰囲気で進めることが多いです。
こうした継続的な対話を通じて、本人自身が気づきにくい変化や小さなストレスを支援員が早期に察知し、必要な支援につなげる仕組みが整えられています。

毎月ちゃんと話せるか自信がないな…。
面談で何を話したらいいのか分からなかったらどうしよう。
うまく話そうとしなくても大丈夫です。支援員は、あなたのちょっとした言葉や表情から、必要な支援を汲み取るプロです。
自然な会話の中で、少しずつ一緒に整理していきましょう。

企業担当者との連携と情報共有
就労定着支援では、利用者本人との面談だけでなく、企業担当者との連携も非常に重要な役割を担っています。支援員は、利用者の状況に応じて職場の担当者と定期的に情報交換を行い、就労環境や業務上の課題、配慮事項について確認を重ねます。この連携を通じて、企業側に適切な支援や理解を促し、職場内での問題発生を未然に防ぐことが目指されています。
特に、職場での人間関係や仕事の進め方に悩みが生じた場合、支援員が間に入り企業と調整を行うことで、利用者自身が直接伝えにくいこともスムーズに解決できる体制が整えられています。企業と支援者、利用者の三者で協力しながら、働きやすい職場環境を作ることが、定着支援の大きな柱となっています。


生活面の支援(体調管理・生活リズム・金銭管理)
働き続けるためには、職場での適応だけでなく、生活全体の安定が不可欠です。そのため、就労定着支援では生活面への支援も重視されています。支援員は、本人と一緒に体調や生活リズムの管理について話し合い、必要に応じた助言やサポートを行います。
たとえば、睡眠不足が続いていたり、食生活が乱れていたりすると、体調不良を引き起こし、最終的には就労継続が難しくなる恐れがあります。そのため、日々の生活リズムや健康状態についても定期的に確認し、無理のない改善策を一緒に考えます。
さらに、給与を得ることによって新たに生じる金銭管理の問題にも対応します。初めての収入で無計画に使ってしまわないよう、支出の管理方法や貯蓄の始め方についても助言が行われます。生活と就労は密接に結びついているため、こうした支援を並行して行うことが、長期的な職場定着には欠かせないとされています。

生活面の安定は、仕事を無理なく続けるための土台です。
体調や金銭管理など、仕事以外のことも含めて総合的にサポートするのが就労定着支援の特徴ですので、安心して相談してくださいね。

就業面の支援(業務上の課題・人間関係の調整)
職場での仕事の進め方や人間関係でつまずくことは、誰にとってもストレスの原因になります。就労定着支援では、こうした就業面の課題に対しても積極的にサポートを行っています。
業務上のミスが続いてしまう、指示の理解がうまくできないといった場合には、支援員が一緒に原因を整理し、改善に向けた具体策を考えます。また、同僚や上司との人間関係で困りごとがある場合にも、本人に代わって支援員が間に立ち、職場に必要な配慮を求めるなどの対応を取ることが可能です。直接伝えにくいことでも、支援員を介することで円滑な調整が図られます。


関係機関との連携(医療機関・福祉サービス事業所・家族)
障害のある方が長く働き続けるためには、職場と本人だけの努力では限界があります。就労定着支援では、医療機関や福祉サービス事業所、家族と連携しながら、総合的な支援体制を築くことを重視しています。
たとえば、体調面に不安がある場合には、医師と情報を共有して職場環境の調整に役立てることができます。また、生活支援が必要な場合には、福祉サービス事業所と協力して支援の手配を行います。さらに、家族とも定期的に状況を共有し、本人を支える家庭環境を整えるためのサポートも行われます。関係機関と連携することで、単独では対応しきれない課題にも総合的に取り組むことができるのです。

いろんな人と連携してくれるってすごいな。
家族にも負担をかけずに働けたらうれしいな。
はい、就労定着支援は本人一人に任せるのではなく、周囲と協力しながら支えていく体制づくりを重視しています。
無理なく続けられるよう、一緒に支えていきましょう。

就労定着支援の利用手続き

就労定着支援を利用するためには、決められた手続きの流れに沿って進める必要があります。はじめて申し込む方にとっては少し複雑に感じるかもしれませんが、各段階を順番に踏んでいけば、安心して利用開始にたどり着くことができます。
ここでは、手続きの流れを次の5つのステップに分けて説明します。
- 市区町村の障害福祉窓口などで、サービスを利用したいことを告げる
- 調査員による生活状況などの聞き取り調査を受ける
- 指定特定相談事業者、または自分自身でサービス等利用計画案を作成、提出
- サービスを受けるための受給者証が発行される
- 就労定着支援サービスの利用開始
これらのステップを順に進めることで、支援を受けるための準備が整います。
step1 市区町村の障害福祉窓口などで、サービスを利用したいことを告げる
就労定着支援を受けたいと考えたら、最初に行うべきは、市区町村役所や福祉事務所などの障害福祉窓口に行き、利用希望を伝えることです。この時点では、具体的な書類をすべてそろえていなくてもかまいませんが、障害者手帳、医師の診断書、または支援学校や福祉サービス利用歴の資料など、障害の状況を示すものが求められることが多いです。
窓口では、担当者が本人の希望や現在の就労状況を簡単にヒアリングし、正式な申請の流れや必要書類について説明してくれます。申請は本人または家族が行うことが基本ですが、支援者(相談支援専門員など)が同行する場合もあります。
地域によって手続きの詳細が若干異なるため、案内に沿って一つ一つ進めていくことが重要です。初めての場合でも、窓口で丁寧に教えてもらえるので安心してください。


step2 調査員による生活状況などの聞き取り調査を受ける
申請の意思を伝えた後は、生活状況や就労状況を詳しく確認するための聞き取り調査が行われます。通常、調査は市区町村から委託された調査員が担当し、本人の自宅や指定された施設で実施されることが一般的です。聞き取りでは、現在の勤務先での就労状況、生活リズム、体調管理の状況、人間関係など、就労定着に関連する幅広い情報が確認されます。
この調査の目的は、単なる形式的な確認ではなく、本人にとって必要な支援内容を具体的に把握することにあります。そのため、良いことだけを話そうとせず、困っていることや不安に感じていることも率直に伝えることが大切です。

無理にうまく答えようとしなくて大丈夫です。
普段の生活や仕事の様子をそのまま話してくれれば問題ありません。

step3 指定特定相談事業者、または自分自身でサービス等利用計画案を作成、提出
聞き取り調査が終わった後は、「サービス等利用計画案」と呼ばれる書類を作成して提出する必要があります。これは、本人がどのような支援を必要としているかをまとめた計画書であり、就労定着支援における支援内容の基本となる重要な資料です。
この計画案は、多くの場合、指定特定相談支援事業者に依頼して作成してもらいます。相談支援専門員が本人や家族と面談を行い、支援目標や具体的な支援内容を整理してくれます。自分で作成することも認められていますが、福祉制度に詳しい人でなければ難しいことが多いため、専門事業者に依頼するのが一般的です。


この情報を深掘りする
-

-
サービス等利用計画とは?「利用の流れ」や「記入例」等をわかりやすく解説
「サービス等利用計画」とは、障害を持つ方が生活の中で自立し、より良い生活を送るために必要なサポートを計画的かつ総合的に提供するための重要な仕組みです。 この計画は、利用者一人ひとりのニーズや生活の目標 ...
続きを見る
step4 サービスを受けるための受給者証が発行される
サービス等利用計画案が提出されると、市区町村による審査が行われます。審査の結果、支援の必要性が認められると、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。この受給者証は、就労定着支援を正式に利用するために必要なものであり、利用者の支給決定内容や自己負担額などが記載されています。
受給者証が発行されるまでの期間は、自治体によって異なりますが、通常は1〜2週間程度を目安と考えておくとよいでしょう。受給者証が届いたら、記載内容に間違いがないかを確認し、もし不明な点があれば早めに自治体へ問い合わせることが大切です。


step5 就労定着支援サービスの利用開始
受給者証が手元に届いたら、いよいよ就労定着支援サービスの利用が開始されます。まずは指定された支援事業所と正式に契約を結び、支援計画に基づいた支援がスタートします。利用開始後は、月1回以上の定期的な面談や職場訪問などを通じて、本人の就労状況や生活状況を把握し、必要に応じた支援が提供される仕組みになっています。
支援内容は、生活面、就業面、企業との連携調整など、本人の状況に応じて柔軟に対応されるため、困ったことがあれば都度相談することができます。支援は3年間を上限とし、その間も定期的に見直しや更新が行われるため、常に本人に最適なサポートが提供され続けます。

支援内容は利用者ごとにカスタマイズされますが、基本は月1回以上の面談や、必要に応じた企業との連携支援が行われます。
あなたに最適な形で進めていくので安心してくださいね。

就労定着支援の費用と負担額

就労定着支援を利用するにあたり、費用の負担はどのようになっているのか気になる方も多いかもしれません。支援を受ける際の経済的負担は、制度上きちんと配慮されており、世帯の所得状況に応じて細かくルールが設けられています。
ここでは、負担の仕組みを整理して紹介します。
- 費用負担の基本構造(1割自己負担と9割公費負担)
- 世帯所得に応じた自己負担額の上限
- 自治体の補助制度
それぞれ順番に詳しく見ていきましょう。
費用負担の基本構造(1割自己負担と9割公費負担)
就労定着支援にかかる費用は、原則として公費によって9割が賄われ、利用者本人の自己負担は1割となる仕組みが整えられています。この方式は、障害福祉サービス全般に共通する基本的なルールであり、経済的負担を大幅に軽減することを目的としています。支援を必要とする人が、費用面での不安から利用を断念することがないよう、公的支援による大きなサポート体制が用意されています。
この1割負担にはさらに上限額が設定されており、仮に支援にかかる費用が高額になった場合でも、利用者が無制限に負担しなければならないわけではありません。負担の上限額については、後述するように世帯所得に応じた細かな基準が設けられています。

自己負担には上限があるので、収入に応じて一定額以上になることはありません。
詳細は次の項目で解説します。

世帯所得に応じた自己負担額の上限
就労定着支援にかかる自己負担額は、本人だけでなく世帯全体の所得状況を基準にして決められています。これにより、経済的に厳しい家庭でも、負担なくサービスを受けられるよう配慮されています。
具体的な負担上限額は、世帯の所得区分ごとに次のように定められています。
- 生活保護世帯:0円
- 市町村民税非課税世帯:0円
- 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満):月額9,300円
- 市町村民税課税世帯(所得割16万円以上):月額37,200円
このように、負担がまったく発生しないケースから、一定の上限額が設定されるケースまで、細かく区分されています。自己負担額が無制限に膨らむことはなく、あくまで所得に応じた適切な範囲に抑えられるようになっています。
どの区分に当てはまるかは、市区町村役場の福祉窓口で、世帯の課税状況に基づいて正式に確認することができます。わからない場合は、申請前に相談しておくと安心です。


自治体の補助制度
一部の自治体では、国の基準に加えて独自に負担軽減措置や補助制度を設けている場合があります。たとえば、就労定着支援に伴う交通費の一部補助、自己負担額のさらなる減免、あるいは就労支援に関連する助成金の支給など、多様な支援が提供されることがあります。こうした補助制度は、利用者の経済的負担を一層軽くし、サービスを受けやすくするために工夫されています。
ただし、自治体ごとに制度の内容や利用条件が異なるため、自分の住んでいる地域にどのような支援策があるのかは事前に確認が必要です。窓口での相談や、自治体の公式ホームページに掲載されている情報をチェックすることが推奨されます。


就労定着支援を利用するメリット

就労定着支援を活用することで、障害のある方が職場で安心して働き続けるためのさまざまなサポートを受けることができます。仕事を始めたばかりの時期や、働き続ける中で生じる悩みに対して、専門的な支援を受けられることは大きな安心材料となります。
ここでは、サービスを利用することで得られる代表的なメリットを4つ紹介します。
- 職場での悩みや不安を相談しやすくなる
- 生活面・体調面の安定を図れる
- 長期的な就労継続が期待できる
- 企業は障がい者雇用のノウハウを蓄積できる
このような効果を得られることで、利用者自身も、職場も、より良い関係を築きやすくなります。
職場での悩みや不安を相談しやすくなる
就労定着支援を利用すると、働く中で感じる悩みや不安を支援員に相談しやすくなります。職場では、上司や同僚に直接言いにくいことも多く、困りごとを抱えたまま我慢してしまうケースが少なくありません。こうしたとき、支援員が定期的に面談を行い、本人の小さな変化や違和感にも丁寧に耳を傾けることで、早期に問題に気づき、適切な対策を講じることができます。
支援員は、必要に応じて企業側とも連携し、利用者本人に代わって職場環境の調整や業務内容の見直しを提案することができます。そのため、自分一人で悩みを抱え込まず、専門的なサポートを受けながら安心して働き続けることが可能になります。


生活面・体調面の安定を図れる
就労が長く続くためには、仕事だけでなく日常生活の安定も欠かせません。就労定着支援では、生活リズムや体調管理の支援も積極的に行われています。たとえば、睡眠不足や偏った食生活、服薬の管理がうまくいかないといった生活習慣上の課題に対して、支援員が本人と一緒に具体的な改善策を考え、無理のない形で生活を整えるサポートを行います。
また、生活の不安定さが原因で体調を崩し、就労に支障が出るケースも少なくありませんが、支援員が定期的に状況を確認しながら、必要に応じて医療機関や福祉サービスと連携を取ることで、より安定した生活環境づくりが可能になります。生活面と体調面のサポートが一体となって行われるため、安心して仕事に集中できる環境が整います。

はい、むしろ生活面の安定こそが仕事を続ける土台になります。
遠慮せず、何でも支援員に相談して大丈夫です。

長期的な就労継続が期待できる
就労定着支援を活用することで、長期的に安定して働き続けられる可能性が大きく高まります。支援員が定期的に本人と面談を行い、仕事上の悩みや体調面の変化を把握しながら必要な支援を提供するため、職場で困ったことがあっても早い段階で対応できる仕組みが整っています。
働き続ける中では、環境の変化や体調不良、仕事のストレスなど、さまざまな課題が生じますが、それらを一人で抱え込まず、継続的なサポートを受けながら乗り越えることができる点が大きな強みです。また、職場との調整や医療機関との連携など、必要に応じた多面的な支援が受けられるため、離職リスクを減らし、安心してキャリアを積み重ねることができます。

支援員が一緒に問題を整理しながら支えてくれるので、無理せず少しずつ職場に馴染んでいけます。
焦らなくて大丈夫です。

企業は障がい者雇用のノウハウを蓄積できる
就労定着支援のメリットは、利用者本人だけでなく、受け入れる企業側にも大きな恩恵があります。支援員が企業の担当者と定期的に情報共有を行い、障がいのある従業員に対してどのような配慮が必要か、どのような支援が効果的かを一緒に考えるため、企業も障がい者雇用に関する知識や経験を積み重ねることができます。
この積み重ねによって、企業側は次に新たな障がい者雇用を進める際にも、よりスムーズに受け入れ体制を整えることが可能になります。また、職場全体での理解促進にもつながり、働きやすい環境づくりに結びついていきます。支援員の存在が橋渡し役となり、利用者と企業双方にとってプラスとなる関係を築くサポートをしています。


就労定着支援の提供事業所の選び方

就労定着支援を受ける際、どの事業所を選ぶかは非常に重要なポイントです。支援の内容や事業所の体制によって、その後の就労の安定度にも大きく影響してきます。自分に合った事業所を見つけるためには、いくつかの視点から慎重に検討することが大切です。
ここでは、事業所を選ぶ際に確認しておきたいポイントを整理して紹介します。
- 自身の障害種別に対応しているかを確認する
- 支援内容やカリキュラムが自分のニーズに合っているか
- 就職実績や定着実績があるかを確認する
- 利用者の声や口コミの活用
これらの視点を押さえることで、自分に合った最適な支援環境を見つけやすくなります。
自身の障害種別に対応しているかを確認する
就労定着支援事業所を選ぶ際、まず大前提として考えたいのは、自分自身の障害種別にしっかり対応しているかという点です。障害とひとことで言っても、その特性や支援の必要性は大きく異なります。たとえば、精神障害のある方にはメンタルケアに配慮した支援が求められる一方、身体障害のある方には物理的な移動支援や職場設備の調整が重要になります。発達障害のある方にとっては、コミュニケーション方法の工夫や業務の見える化など、きめ細かなサポートが必要です。
すべての事業所がすべての障害種別に精通しているわけではないため、事前に「どの障害種別に対応しているか」「これまでどのような利用者を支援してきたか」などを確認することが欠かせません。見学の際には、具体的な支援事例を聞いてみたり、支援員に直接相談してみるのも有効です。自分の特性を理解し、適切にサポートしてくれる事業所を選ぶことが、安定した就労生活への第一歩となります。

遠慮せず、自分の得意なことや苦手なことを伝えることが大切です。
事業所側もより適切な支援を提供できるようになりますし、相互理解が深まることで支援効果も高まります。

支援内容やカリキュラムが自分のニーズに合っているか
就労定着支援を受けるうえで、自分の目標や課題に合った支援内容が用意されているかを確認することは非常に大切です。事業所によって、重視している支援の内容や提供しているプログラムには違いがあります。たとえば、対人関係のサポートに力を入れているところもあれば、ビジネスマナーや職場での適応力向上を重視しているところもあります。
自分が今困っていること、今後身につけたいスキルに合わせて、どのような支援が用意されているかを事前に確認し、ニーズにマッチしているかを見極めることが、支援の効果を最大限に引き出すポイントです。見学の際には、実際の支援内容やプログラムの流れを確認し、質問することをおすすめします。


就職実績や定着実績があるかを確認する
支援の質を見極めるうえで、その事業所がどれだけの就職実績や定着実績を持っているかを確認することは非常に重要です。多くの事業所は、自身の支援実績を公表しており、何人の利用者が就職に至ったのか、就職後にどれくらいの割合で職場に定着できているのかといったデータを提示しています。
特に、就職できた人数だけでなく、定着率に注目することが大切です。就職後すぐに離職してしまうケースが多い場合は、支援の質や職場選びのマッチングに課題がある可能性も考えられます。自分の希望に近い職種での実績が豊富かどうかも合わせて確認しておくと、安心して利用を検討できるでしょう。


利用者の声や口コミの活用
事業所選びでは、実際に利用した人たちの体験談や口コミを参考にすることもとても有効です。公式情報だけでは分からない雰囲気や支援の実態を知るうえで、リアルな声は貴重な手がかりとなります。インターネット上のレビューサイト、SNS、または地域の支援団体などで情報を集め、複数の意見を比較して判断することが大切です。
ただし、口コミはあくまでも個人の感想に過ぎないため、極端に良い・悪い意見だけを鵜呑みにせず、あくまで参考情報として活用することが重要です。最終的には、自分の目で確かめ、自分に合っているかを見極めることが求められます。

口コミはあくまで参考の一つと考え、複数の情報を見比べましょう。
そして最後は、実際に見学して自分の目で確かめるのが一番確実です。

就労定着支援に関するよくある質問(FAQ)

就労定着支援に関しては、制度や手続きに不安を感じる方が多く、よく寄せられる質問も幅広くあります。これから支援を利用しようと考えている方に向けて、よくある疑問点を整理してまとめました。事前に疑問を解消しておくことで、安心してサービスを活用できるようになります。
以下に、特によく聞かれるポイントを紹介します。
- 就労定着支援と就労継続支援の違いは何ですか?
- どのタイミングで就労定着支援を受けられるのですか?
- 就労定着支援はどのくらいの期間利用できますか?
- 支援を受けている途中で転職した場合はどうなりますか?
- 支援を受けるために費用はかかりますか?
これらの疑問を解消することで、サービスをより安心して利用できるようになります。
就労定着支援と就労継続支援の違いは何ですか?
就労定着支援と就労継続支援は、どちらも障害のある方が働くことを支える福祉サービスですが、支援対象者や目的に明確な違いがあります。
就労定着支援は、すでに一般企業に就職した障害者を対象とし、職場での長期的な定着をサポートするために提供されるサービスです。就労後に起こるさまざまな課題、たとえば職場での人間関係や業務の悩み、生活リズムの乱れなどに対応し、継続就労を支援します。
一方、就労継続支援は、すぐに一般企業で働くことが難しい障害者が、福祉事業所内で働きながら就労スキルを高めるための仕組みです。A型では雇用契約を結んで働き、B型では雇用契約なしで作業に従事し、工賃を受け取ります。
つまり、就労定着支援は「一般就労後の支援」、就労継続支援は「一般就労前または別の形の就労支援」という違いがあります。


この情報を深掘りする
-

-
就労継続支援A型とは何か?「利用条件」や「仕事内容」をわかりやすく解説
就労継続支援A型は、障害や病気を持つ方が社会で働きながら自立した生活を送るための大切な支援制度です。 この制度では、利用者が事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の給与を受け取りながら働くことができます ...
続きを見る
-

-
就労継続支援B型とは何か?「利用条件」や「仕事内容」をわかりやすく解説
障害を持つ方が社会で自立した生活を送るためには、適切な支援や働く場の確保が欠かせません。 その中で「就労継続支援B型」は、働く意欲があるものの、一般就労が難しい方々に対して、柔軟な就労機会を提供する重 ...
続きを見る
どのタイミングで就労定着支援を受けられるのですか?
就労定着支援は、一般企業に就職してからすぐに利用できるわけではありません。まず、就職後6ヶ月間は、もともと利用していた就労移行支援や継続支援の事業所が定着支援を行うことが基本とされています。そして、就職から7ヶ月目以降に、必要に応じて正式に就労定着支援事業所へと支援を移行する流れになります。
この制度設計は、就職初期の不安定な時期を支えるため、馴染みのある支援機関によるフォローアップを優先しているためです。もし6ヶ月経過する前に不安を感じる場合でも、事前に相談をしておくと、スムーズに切り替え準備を進められます。

最初の6ヶ月間は以前の支援事業所がサポートし、その後必要に応じて就労定着支援へ移行します。
早めに相談しておくと安心です。

就労定着支援はどのくらいの期間利用できますか?
就労定着支援の利用期間は、原則として最大3年間と定められています。1年ごとに支援内容の見直しや契約更新があり、その都度、支援の必要性を確認しながら継続される仕組みです。この3年間の間に、安定して働くためのスキルや生活習慣を身につけることが期待されています。
なお、就職してから最初の6ヶ月間は、別の支援(移行支援など)が行われるため、実際には就職後トータルで最大3年6ヶ月間、支援を受けられる可能性があります。支援期間終了後も、必要に応じて他の福祉サービスや地域の支援機関に相談できる体制が整っているので、支援が切れた後の不安も軽減されています。


支援を受けている途中で転職した場合はどうなりますか?
就労定着支援の利用中に退職し、別の職場へ転職する場合、一定の条件下で支援を継続できる制度が用意されています。原則として、転職後1ヶ月以内に新しい職場に就職した場合には、1回に限り支援を継続することが可能です。もし1ヶ月を超えてしまった場合や、転職しない期間が長引いた場合は、支援は終了となるのが基本ルールです。
この制度は、急な事情による転職でも支援を断絶させないように設けられていますが、転職が見込まれる場合には、事前に支援事業所へ相談し、手続きや支援計画を調整してもらうことが推奨されます。

1ヶ月以内に新たな職場に就職できれば、1回に限り支援を継続できます。
転職が決まりそうな時点で早めに支援員に相談しましょう。

支援を受けるために費用はかかりますか?
就労定着支援は公的な福祉サービスの一環として提供されており、費用の9割が自治体などによって負担されます。利用者は原則1割の自己負担のみで支援を受けることができます。ただし、自己負担額には世帯の所得に応じた上限が設けられており、たとえば生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯であれば負担は0円となります。
課税世帯の場合も、月額9,300円または37,200円という明確な上限があるため、過度な負担になることはありません。これにより、経済的な不安を抱えることなく、必要な支援を安心して利用できる仕組みが整っています。

自己負担は世帯の所得に応じて上限が決まっているので、ほとんどの方が無料または少額負担で利用できる場合が多いです。
まずは自治体窓口で確認してみましょう。

就労定着支援の課題

就労定着支援は、障害のある方が一般企業で長く働き続けるための重要な制度ですが、運用の中でさまざまな課題も指摘されています。支援をより効果的に活用するためには、あらかじめどのような課題があるのかを把握しておくことが大切です。
ここでは、現在見られる主な課題について整理し、詳しく解説していきます。
- 利用期間の制限と支援終了後の不安
- 賃金水準の低さとキャリアアップの難しさ
- 定期的な面談や連絡が負担に感じる場合がある
- 企業側の理解不足による支援の難航
順番に、それぞれの内容について見ていきましょう。
利用期間の制限と支援終了後の不安
就労定着支援は、最長3年間という利用期間が定められています。この期間内で職場への適応や生活基盤の安定を目指す仕組みになっていますが、期間終了後の支援体制について不安を抱く方も少なくありません。特に、3年経過時点でまだ職場での課題を抱えている場合、突然支援が終わることに大きな不安を感じることがあります。
また、支援終了後に相談できる窓口やサービスが周知されていないケースもあり、支援が途切れることで孤立感を強めてしまうリスクも指摘されています。本来であれば、支援終了後に地域の障害者就業・生活支援センターなどにつなぐなど、次のサポートへとスムーズに移行できる体制が望まれますが、実際にはその橋渡しが十分とは言えない場合もあるのが現状です。

支援終了後も地域には障害者就業・生活支援センターなどの相談窓口があり、引き続き支援を受けられるので安心してください。
早めに支援員と今後の相談先について話し合っておくとより安心です。

賃金水準の低さとキャリアアップの難しさ
障害者雇用の現場では、依然として賃金水準が低いという課題が根強く残っています。就労定着支援を利用して職場に定着できたとしても、生活を安定させるには十分とは言えない給与水準にとどまる場合が少なくありません。特に、非正規雇用や短時間勤務での就労が多い障害者にとっては、経済的な自立が大きな壁となっています。
また、キャリアアップの機会が限られていることも問題視されています。長く働き続けたとしても、昇進や職務拡大が難しいケースが多く、本人のやる気や成長意欲が十分に評価されないまま固定化されてしまうリスクがあります。これにより、働きがいの低下や、将来への不安感が強まることも少なくありません。
よりよい支援のあり方としては、単なる就労定着にとどまらず、スキル向上支援や資格取得支援などを組み合わせ、障害者本人のキャリア形成を後押しする仕組みづくりが求められます。

支援の中で、スキルアップやキャリア形成の機会を広げる取り組みが進められています。
自分の強みを活かして、将来の可能性を一緒に考えていきましょう。

定期的な面談や連絡が負担に感じる場合がある
就労定着支援では、定期的に支援員と面談や連絡を取り合いながら、就労状況や生活面の課題を確認していきます。本来は、本人の負担を軽減し、課題を早期に発見・解決するための重要なプロセスですが、人によってはこの定期的なやり取り自体が負担に感じてしまうこともあります。
特に、精神的なストレスを抱えている場合や、プライベートな話題について話すことに抵抗感がある場合、面談や報告の機会がプレッシャーとなり、かえって就労意欲に悪影響を与えてしまう恐れがあります。支援のペースや関わり方について、本人の希望に合わせた柔軟な対応が求められていますが、現場によっては画一的な支援スタイルになりがちなことも、課題のひとつとされています。

支援の頻度や面談の方法は相談によって調整できます。
無理せず、自分に合った関わり方を支援員に伝えることが大切です。

企業側の理解不足による支援の難航
障がいのある方が職場で安定して働き続けるためには、企業側の理解と協力が不可欠です。しかし、現実には障害特性や必要な配慮について十分に理解していない企業も少なくありません。その結果、適切なサポートが受けられず、本人が孤立感やストレスを抱えることにつながるケースも見られます。
また、企業と支援員との連携が不十分な場合、職場で起きている小さな課題が支援側に伝わらず、対応が後手に回ってしまうこともあります。本来、就労定着支援は企業と本人、支援者が三者で情報を共有しながら進めるものですが、企業側に協力体制が整っていないと、支援が形骸化してしまう恐れがあるのです。

企業向けの障害者雇用支援セミナーや研修を利用することで、職場全体の理解を促すことが可能です。
支援者と協力して働きかけていきましょう。

まとめ:就労定着支援を活用して安定した就労を目指そう

就労定着支援は、障害のある方が一般企業で長く安定して働き続けるための重要なサポート制度です。単に就職するだけでなく、職場に定着し、自立した生活を送るためには、働く中で生じるさまざまな課題に継続的に対応していくことが求められます。そのため、この支援を上手に活用することが、より良い就労生活を築くための大きな鍵となります。
制度の仕組みや利用条件、支援内容をしっかり理解し、自分に合ったサービスを受けることで、職場での不安や悩みを一人で抱え込まずにすみます。また、支援を受けるだけでなく、将来に向けたスキルアップやキャリア形成も視野に入れ、自分らしい働き方を模索していくことが大切です。
就労定着支援には、利用期間や費用負担といった制度上の制限もありますが、必要に応じて地域の支援機関と連携することで、支援終了後も切れ目のないサポートを受けることができます。不安や疑問があれば早めに支援員や相談窓口に相談し、無理なく、前向きに就労生活を続けていくための道筋を整えていきましょう。

働くことは、生活を支える手段であると同時に、自分自身の成長や社会とのつながりを感じられる大切な機会でもあります。
就労定着支援を賢く活用しながら、安心して、そして自分らしく働き続ける未来を目指していきましょう。
参考リンクとリソース