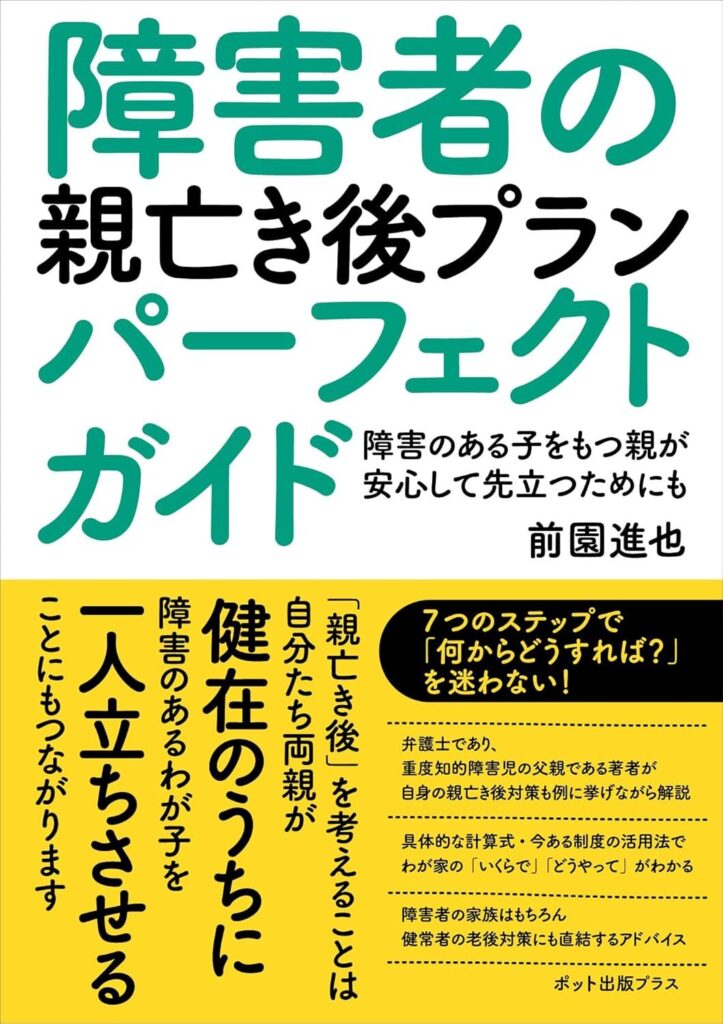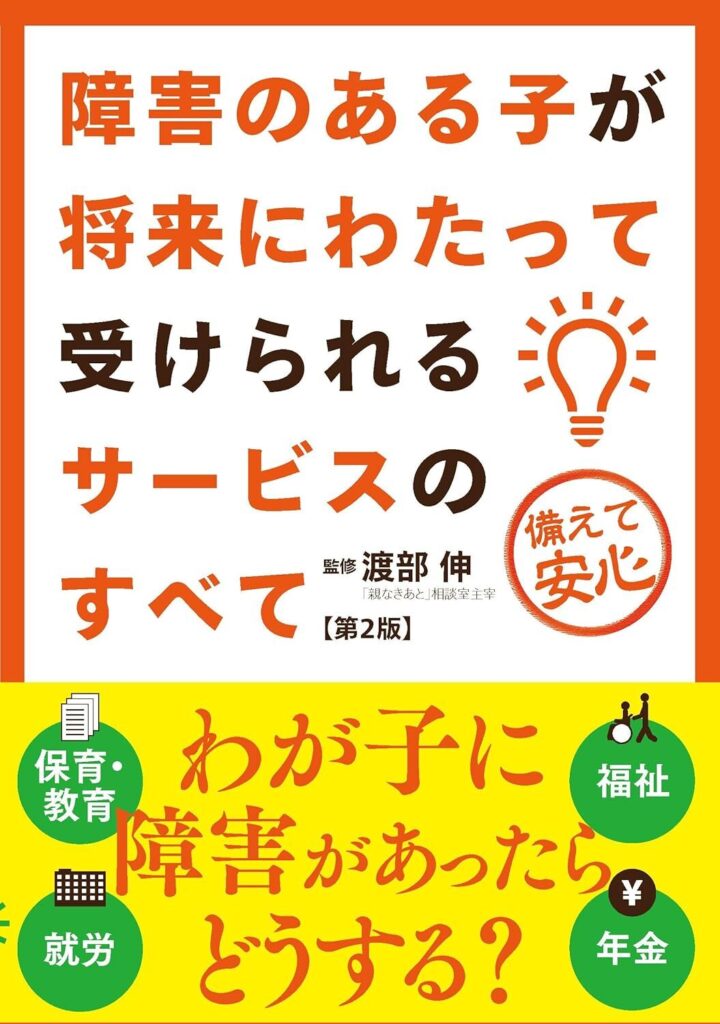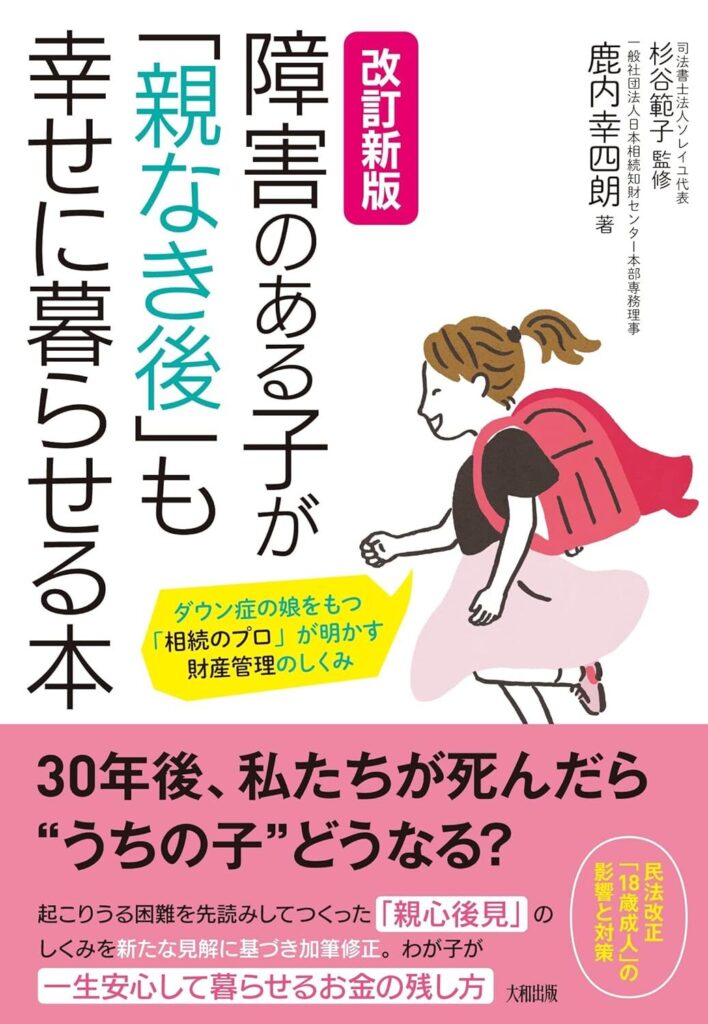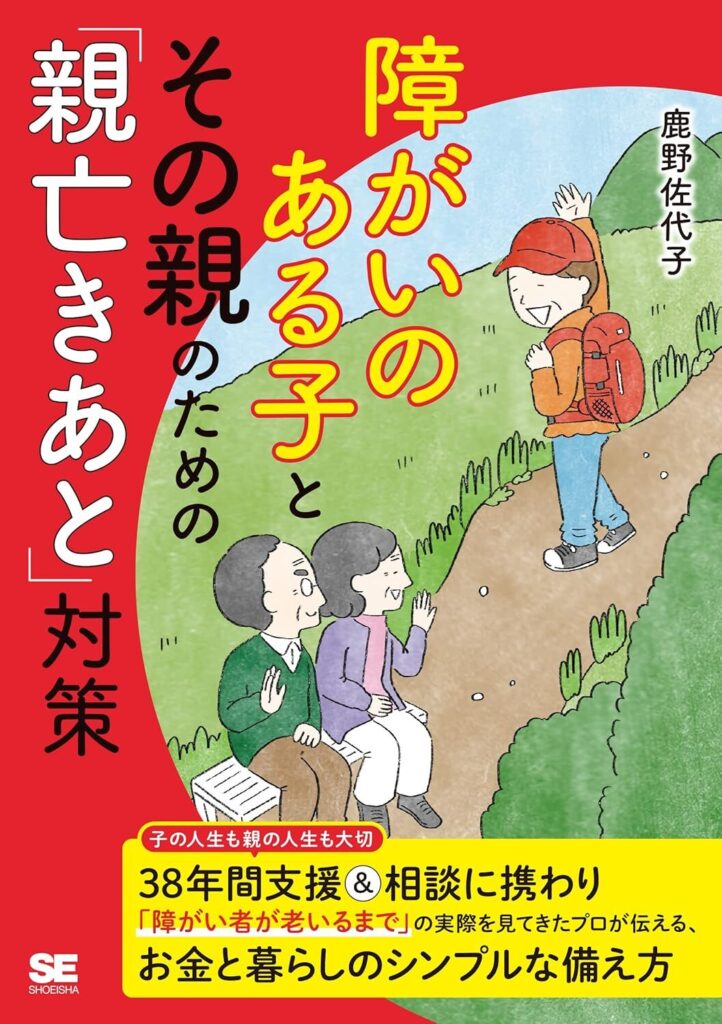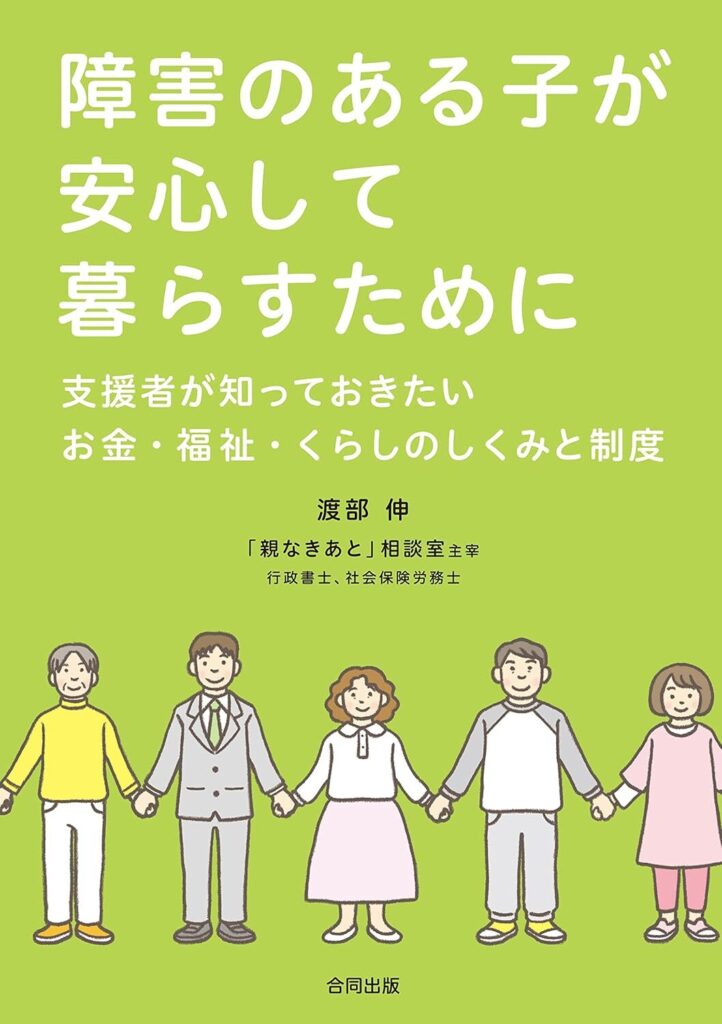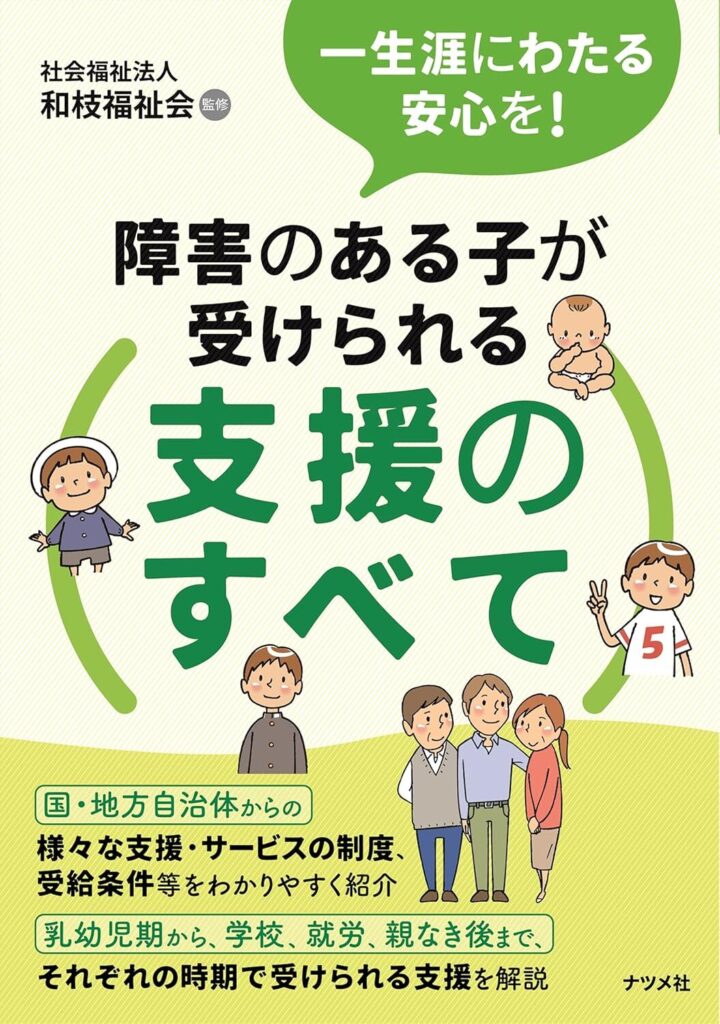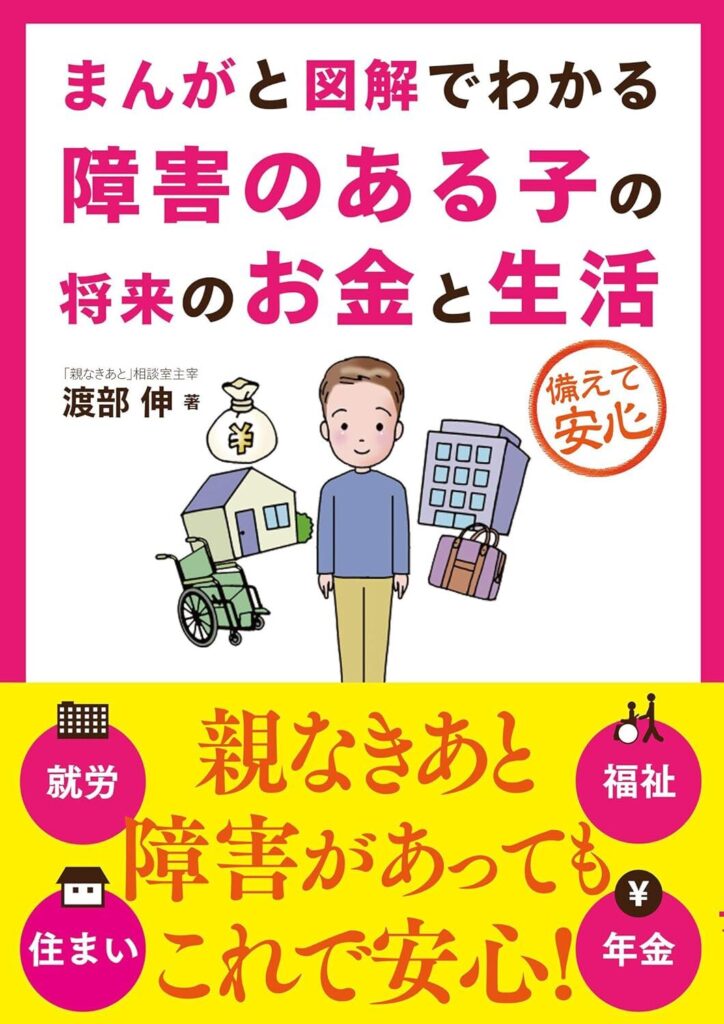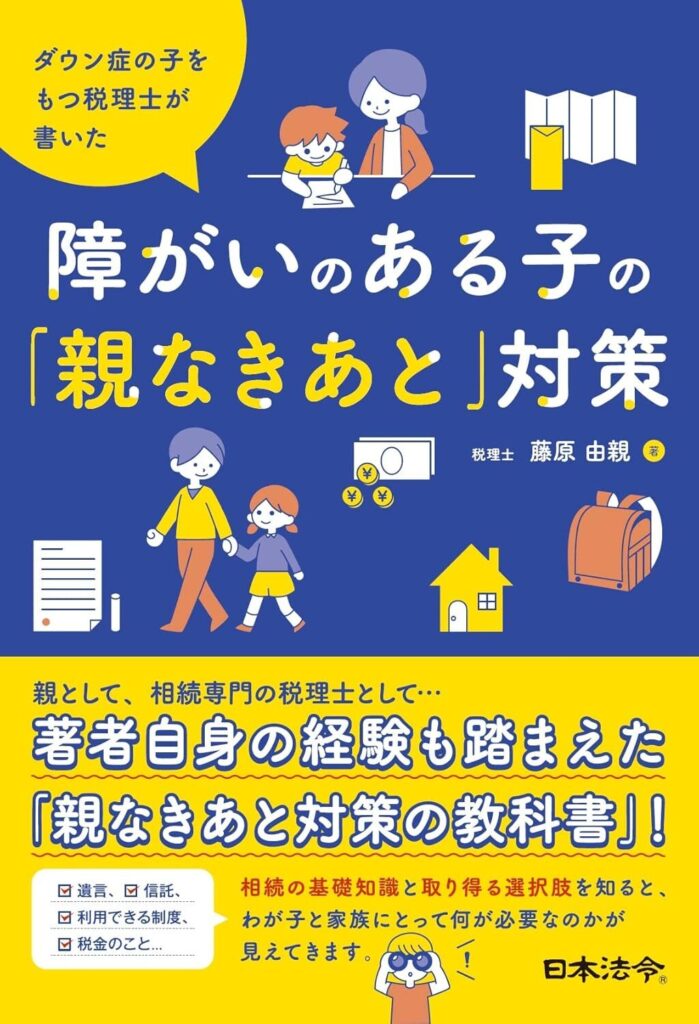障害のある子どもを育てている親御さんへ——
日々の子育ての中で、こんなふうに感じたことはありませんか?
「子どもの気持ちがうまくわからない」「どうサポートすればいいのかわからない」「このままでいいのかな……」
障害のある子どもを育てるということは、ただでさえ大きな責任を伴う子育てに、さらに特別な配慮や情報、心の準備が求められる場面がたくさんあります。まわりに相談できる人がいなかったり、情報が多すぎて何を信じていいのかわからなくなったりすることもあるでしょう。

ガイドさん
そんなとき、同じ経験をしてきた人の言葉や、専門家の知識に触れられる「本」は、心の支えになる貴重な存在です。
悩みに寄り添い、気持ちを整理するヒントをくれる本、明日からの子育てに役立つ具体的なアドバイスをくれる本……それぞれの親子に必要なメッセージが詰まっています。
この記事では、障害のある子どもを持つ親御さんにぜひ読んでほしい、おすすめの本を厳選し、人気ランキング形式でご紹介します。
きっと、今のあなたにそっと寄り添い、勇気をくれる一冊に出会えるはずです。

読者さん
1位 障害者の親亡き後プランパーフェクトガイド
「私たちが死んだあと、この子はどうやって生きていくのだろう」。
障害のある子を育てる親であれば、誰もが一度は胸を締めつけられるようなこの問いに直面するはずです。今この瞬間、日々の介護や療育に追われながらも、心のどこかで漠然とした不安を抱えている――そんな親御さんたちにこそ手に取ってほしいのが、本書『障害者の親亡き後プランパーフェクトガイド』です。
本書の著者である前園進也氏は、弁護士という法律の専門家でありながら、重度知的障害を持つ実子の父でもあります。だからこそ、この本には「理屈」と「実感」の両方が込められています。制度を知識として知っているだけでなく、実際にどう向き合い、どんな手続きを踏み、どこでつまずき、何を悩んだのか。読み進めるうちに、ただの制度解説書ではない、同じ立場の親としての等身大の言葉が響いてきます。
続きを読む + クリックして下さい
本書では、障害のある子どもの将来を見据えた備えを、「7つのステップ」に整理して体系的に解説しています。例えば、障害基礎年金や手当などの収入源、グループホームの生活費や医療費などの支出、親亡き後に必要な資金の計算、老後資金の貯め方、財産の残し方、成年後見制度の活用、そして信頼できる相談先の見つけ方まで。読み手の立場に立って、複雑な制度や用語はやさしい言葉に言い換え、具体例や図表を交えて、まるで伴走してくれるような丁寧さで解説してくれます。
さらに、各章には「深掘りコラム」や「著者自身の実例」も豊富に挿入されており、「自分の家庭に置き換えるとどうなるのか」がイメージしやすくなっています。中でも、巻末に収録された計算シートは、親が亡くなった後に必要となる金額を実際に試算できる実用的なツールです。これにより、漠然とした不安が「数字」として可視化され、必要な行動が明確になります。
そして本書の根底には、著者自身の切実な願いが込められています。それは、親が自分たちの人生を取り戻し、子どもがひとりで生きていける未来を現実のものとすること。障害があるからといって、親が一生背負い続けなければならないという考え方を見直し、子と親がそれぞれの人生を歩んでいく準備をする。そのために必要な制度、知識、支援の在りかを、親の目線でわかりやすく伝えてくれる一冊なのです。

ガイドさん
この本は、障害のある子どもを持つ親御さんはもちろんのこと、将来を不安に思う障害当事者本人、福祉や医療の現場で支援に携わる専門職、さらには法律や制度に携わる実務家にとっても、貴重な実務書であり指針です。
親として「その時」を迎える前に何ができるのか。悩み、迷い、立ち止まりそうなときに、そっと背中を押してくれる伴走者のような一冊です。
本の感想・レビュー
障害のある子どもを育てる私にとって、将来のことを真剣に考える時間は、正直なところ「怖い」と思ってしまうものでした。毎日をこなすだけで精一杯で、いつかは向き合わなければと思いつつも、つい目をそらしていたのが現実です。
この本に出会い、「親亡き後」を考えることは、恐怖や不安だけでなく、自分たちが元気なうちに子どもを一人立ちさせる希望の一歩だと気づかされました。具体的な制度の紹介や、著者自身の体験が豊富に盛り込まれていて、読み進めるほどに「うちの子にも応用できそう」と思える内容が見つかりました。
特に心に残ったのは、「障害のある子どもの親だからといって、一生世話をすることが当たり前ではない」という著者の視点です。親も子も、それぞれの人生を歩めるようにすることが本当の支援なのだと感じ、重くのしかかっていた責任感の中に、新しい目標のようなものが生まれました。
他7件の感想を読む + クリック
これまで何となく名前だけ聞いたことがあった「障害者扶養共済」について、ようやく具体的に理解できたと感じました。インターネットでは断片的な情報しか得られず、掛金や給付金、制度のメリット・デメリットまで一貫して説明された資料に出会ったことがありませんでした。
本書では、加入条件、制度の仕組み、年金の金額だけでなく、「掛金の総額が年金の給付額を上回ることがある」といった現実的なリスクにもきちんと触れられています。その上で、どんな家庭に向いていて、どんなタイミングで加入するのが効果的かといった点まで具体的に書かれていて、判断材料として非常に有益でした。
また、障害者扶養共済は親の死亡を前提とする制度であることから、親自身の老後との両立をどう考えるかという視点もあり、「制度の仕組み」だけではなく「家庭の人生設計」の中でどう位置づけるかが見えてきました。
成年後見制度に関しては、正直なところ「制度の名前は知っているけど、どう使うのかはわからない」という状態でした。加えて、後見人の報酬が高額だとか、手続きが煩雑だという噂に尻込みしていたのも事実です。
本書では、法定後見と任意後見の違い、後見人の選定、監督人の役割などを、図解や例を用いながら丁寧に説明しています。さらに、どのような場面でどのタイプの後見が適しているかが具体的に紹介されており、「わが家の場合なら…」と想像しながら読み進めることができました。
「親族は後見人になれない」という誤解にもきちんと言及してくれていた点は大きな安心感でした。制度の限界や問題点にも触れていて、利用を検討する際の注意点も抜かりなく、単なる制度紹介にとどまらない内容だと感じました。
信託については、これまで自分とは無縁の制度だと思っていました。どこか「お金持ちの話」という印象があり、関心すら持たなかったのですが、この本を読んで初めて、「むしろ一般家庭にも向いている制度かもしれない」と思うようになりました。
信託の基本的なしくみから、受託者・受益者といった登場人物の関係性、契約の柔軟性などを具体例を交えて解説してくれており、「子どもが自分で契約できない」という前提に立った制度設計ができることを知って目から鱗が落ちました。
同時に、自由度が高いからこそ、契約内容の設計が重要であり、監督者を誰にするか、契約書に何をどう書くかによって大きく変わるというリスクも示されていました。メリット一辺倒ではなく、読者に判断の材料を与えてくれる構成がとてもよかったです。
これまで「遺言は高齢者のもの」と思い込んでいました。しかしこの本を読み進める中で、障害のある子どもを持つ親にとって、早めに準備しておくべき手段であることを強く意識させられました。
単に「遺言を作りましょう」という話ではなく、自筆証書と公正証書の違いや、遺言執行者をどう決めるか、何を記しておけばトラブルを避けられるかという細かなポイントまで説明されており、非常に実用的でした。
特に印象に残ったのは、「遺言では『毎月○円』というような定期的な支給の設計ができない」という指摘です。信託制度などと併用することの必要性も説かれており、単独の制度ではなく、複数を組み合わせて備えるという考え方が学べました。
生活保護については、正直これまでネガティブな印象がありました。「最後の手段」というイメージが強く、可能なら頼りたくないという気持ちがどこかにありました。しかしこの本では、制度としての現実的な側面と、障害のある子どもを持つ家庭がどう向き合えばよいのかを、客観的に説明してくれています。
特に印象的だったのは、障害基礎年金の金額が生活保護費を下回るケースがあるという点です。これには驚きました。さらに、親にある程度の収入があっても、本人が独立しているならば生活保護の対象になる可能性があることや、「親に収入があると生活保護がもらえない」というのが誤解であると明記されていたことで、考えを大きく改めさせられました。
著者自身の視点も加わることで、制度の建前だけでなく実態や矛盾にも目が向けられており、「知っておくべき知識」としてとても大切な内容だと感じました。偏見ではなく、正確な知識で備える必要があると、強く思わされました。
読んでいて「ここは現場目線だな」と感じたのが、住まいに関するパートでした。グループホーム、障害者支援施設、公営住宅、UR賃貸、そして一般賃貸に至るまで、それぞれの特徴や条件、メリット・デメリットが本当に丁寧に書かれていて、支援者として読んでいても勉強になりました。
グループホームの種類についても詳しく紹介されていて、支援内容の違いや金銭的な負担までしっかりカバーされています。単に「こういう住まいがありますよ」だけではなく、どんな人に向いているのかまで考察されているので、保護者の方にも安心材料になると思います。
住まいは人生の基盤です。だからこそ、このように一つ一つの選択肢を丁寧に解説してくれることで、「どこに住まわせるか」ではなく「どの暮らし方が合っているか」という視点で選べるようになるのは、とても意味のあることだと感じました。
死後のことに触れるのは、決して気が進む話ではありません。しかし、本書で取り上げられていた「死後事務委任契約」の章は、読む価値があると感じました。親としての責任をまっとうするには、子どもが亡くなった後のことも、ある程度は計画しておかねばならないのだと、改めて考えさせられました。
障害をもつわが子が亡くなったとき、誰が手続きをするのか。あるいは親自身が亡くなったあとの事務を誰が担うのか。現実問題として、身寄りが少ない家庭や、兄弟姉妹に頼れないケースもあるでしょう。本書ではそういった状況を想定した上で、契約の仕組みや委任できる範囲を具体的に解説してくれていました。
特に、施設入所中や一人暮らしの場合の対応方法についても触れられており、現場で起こり得る問題に対する解決策が示されていたのは安心材料になりました。死後の事務も、きちんと法的に整えることで、残された家族の負担を減らせる。そう考えると、これは「死後の話」ではなく、「生きているうちにやるべきこと」なのだと実感しました。
2位 障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて 第2版
「障害があるわが子の将来が心配でたまらない」「支援制度がたくさんあると聞くけれど、どれをいつ、どう使えばいいのかわからない」――そんな悩みや戸惑いを抱えるご家族に向けて書かれたのが、本書『障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて 第2版』です。
障害のある子を育てることは、日々の暮らしを支えるだけでなく、その子の“これから先の人生”をどう守っていくかという大きなテーマと向き合い続けることでもあります。保育・教育の場選び、就職への道筋、障害年金などの経済的支え、さらに親なきあとの財産管理や法律的サポートまで――情報は広範囲にわたり、どこから手をつけていいかわからず、心が折れそうになることもあるでしょう。
本書では、そんな「将来への漠然とした不安」を、「具体的な選択肢」へと変えるために、年齢別・生活場面別に利用できる公的サービスや支援制度を、丁寧に、そして実務的に解説しています。たとえば、就学前の「児童発達支援」や「通級指導」、高校卒業後の「就労移行支援」「グループホーム」など、実際の支援を受けるまでの流れや申請方法が具体的に示されており、「知っていればできたのに」と後悔せずに済むような構成が特徴です。
続きを読む + クリックして下さい
また、2024年4月に施行された「改正障害者総合支援法」や「障害者差別解消法」の最新情報も反映されており、今後の制度の動向にも対応できるようになっています。親なきあとの財産管理や相続、成年後見制度に関しても、信託や遺言の実例まで踏み込んで紹介されており、法的な備えに自信がない方にも安心して読める内容です。
本書の監修は、長年にわたり障害福祉の現場と制度設計の最前線に携わってきた渡部伸(わたなべ しん)氏。社会福祉士・ファイナンシャルプランナーとしての専門知識に加え、重度の知的障害のある娘を持つ父親としての実体験が、全編に温かくリアリティある視点を与えています。単なる制度の解説書ではなく、同じ立場の親だからこそ語れる励ましやヒントが散りばめられており、「読んでよかった」と心から思えるはずです。

ガイドさん
誰もがいつか直面する「親なきあと」の問題に、冷静に、着実に備える――その第一歩として、本書は最良のパートナーとなるでしょう。
「うちの子には何が必要なのか」「私たち親は、いま何を準備しておくべきか」。そんな問いに、明確な道しるべを示してくれる実用書であり、心を支えてくれる一冊です。
本の感想・レビュー
子どもに障害があると診断されたとき、私は本当に何も知らなかったんです。福祉の制度、支援の仕組み、将来の経済的な不安――全部が漠然としていて、誰に何を聞けばいいのかすらわからない状態でした。そんな中でこの本を読み進めていくうちに、まるで霧が晴れていくように、制度の全体像が見えてきたのです。
目の前の悩みにどう対応すればいいのかだけでなく、その先に何が待っているのかが具体的にわかるようになり、「今やるべきこと」と「将来に備えること」がはっきりしてきました。まさに、地図を渡されたような感覚です。
私は読みながら何度もマーカーを引きました。制度がつながっていること、年齢や生活シーンに応じて変化すること、そうした構造を知らずにいることが、あの不安の正体だったんだと気づかされました。
他5件の感想を読む + クリック
私は特別支援学級の担任をしています。保護者からの相談を受ける機会も多いのですが、「将来どうなっていくのか不安です」と言われるたびに、自分の中でも答えが曖昧なことがありました。そんなときに出会ったのがこの本です。
何より感心したのは、内容が子どもの年代や生活の段階ごとに整理されていること。保育期、学齢期、就労期、そして親が亡くなった後まで、順を追って支援制度が説明されているので、場面ごとに知っておくべきことが整理しやすく、とても実用的でした。
教育現場にいると、どうしても“学校まで”の視点になりがちですが、この本を読んで「学校を出たその後の支援」についても具体的に語れるようになったことが、自分の支援者としての視野を広げてくれたと感じています。これからも手元に置いて、何度も参照していきたいと思える一冊です。
社会福祉士として相談業務に関わっていますが、法制度が変わるたびに「正確な情報をどう手に入れるか」が課題でした。その点、この本は2024年の障害者総合支援法の改正にしっかり対応しており、制度の最新の動きを踏まえた上で解説してくれているのがとても助かりました。
たとえばグループホームや就労支援の部分では、今回の法改正によって強化されたポイントをわかりやすく取り上げており、現場で支援を考える上で非常に有用です。制度は知っているつもりでも、変更点を的確に把握していなければ、支援の質に直結します。
また、法改正がどのような理念に基づいて行われているのか、その背景もふまえて書かれているのがよかったです。読み物としても実用書としても、高い完成度だと感じました。
私にとって一番気がかりなのは、「自分がいなくなったあと、この子はどうやって生きていけるのか?」ということでした。重度の障害がある息子の将来を考えると、夜眠れなくなることもあります。ですが、この本には、その不安に真っ向から向き合ってくれる章があって、本当に救われました。
相続のこと、遺言のこと、成年後見制度のこと。聞いたことはあっても、「自分に関係あるのか分からない」と避けていた話題が、親の視点で丁寧に説明されていて、読んでいるうちに「今から準備できることがこんなにあるんだ」と気づかされました。
私のように、「心配はしているけど、具体的には何もしていない」という親御さんに、ぜひ読んでほしいです。先延ばしにしていた問題に、勇気を出して取り組もうと思わせてくれる本でした。読み終えた今は、ひとつひとつ備えを整えていこうという前向きな気持ちになれています。
私は福祉施設に勤務しており、利用者のご家族からさまざまな相談を受ける立場にありますが、「自分が本当に必要な情報を届けられているのか」と自問する日々でした。この本を手にしたとき、「ああ、こういう整理のされ方があったのか」と目から鱗が落ちる思いでした。
制度を解説する際に、どうしても“制度名ありき”で話を進めがちですが、この本は逆です。親の目線、生活の流れに寄り添いながら、自然と制度を紹介していく構成になっているので、支援者としても「どう伝えたら伝わるか」のヒントが随所にあります。
また、改正された法律や制度にも触れられていて、支援現場にいる私自身がアップデートされる感覚もありました。相談支援に携わる方、施設職員、医療関係者など、対人支援に関わるすべての人にとって、実務の土台を強くしてくれるような一冊です。
私はきょうだい児として、兄に知的障害がある家庭で育ちました。大人になってから、家族の将来について話す機会が増えましたが、「難しい話は父や母に任せていた」自分に少しずつ責任が回ってきていることを感じています。そんな時に読んだのがこの本です。
驚いたのは、情報がとにかく整理されていて、読みやすく、そして「家族みんなで話しやすい」ように設計されていること。どの年代でも共通して気になるポイントを押さえているから、「今は違っても、将来的には必要になる情報」として自然に読めるんです。
兄の将来を見据えるにあたって、私自身が制度を理解するだけでなく、家族みんなが共通認識を持てるようになることが何より大切なんだと感じました。兄弟姉妹も、親も、そして本人も、それぞれが当事者であることを改めて思い知らされました。
3位 改訂新版 障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本
障がいのある子どもを育てている親にとって、「自分がいなくなった後、この子はどうやって生きていくのだろうか?」という将来への不安は、決して他人事ではありません。医療や福祉の制度が充実してきた現代においても、親の死後に残された子どもが安心して暮らし続けられる保証はなく、むしろ「制度の空白」によって、思いもよらない困難に直面することさえあります。
そうした“親なき後”の課題に、法的・実務的なアプローチで真正面から応えたのが、鹿内幸四朗著『改訂新版 障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本』です。著者自身がダウン症の娘を持つ父親であり、相続のプロフェッショナルとして3万人以上の相談を受けてきた経験を基に、「どうすれば、子どもが一生安心して暮らせるのか?」というテーマに本気で向き合い、その実践知を惜しみなく公開しています。
続きを読む + クリックして下さい
本書では、成年後見制度の問題点や、18歳成人の影響、公正証書遺言や任意後見契約といった具体的な制度の活用方法、さらには“親の思い”をどう法的に残すかという視点まで、多角的に網羅されています。なかでも注目すべきは、「親心後見」という画期的な仕組みです。これは、親が元気なうちに信頼できる後見人候補と任意契約を結ぶことで、子どもの将来を自分の手で守るという発想。制度の“壁”にあきらめず、“抜け道”でもない、れっきとした合法的な新提案として多くの読者から支持を集めています。
また、2022年1月の民法改正に対応し、最新の法的見解を反映した内容になっている点も大きな特徴です。従来の本では得られなかった、実際に「今すぐ使える」知識と、「動き出すきっかけ」を与えてくれる構成は、福祉・法律・教育といった現場のプロからも高い評価を得ています。
「もっと早く出会いたかった」「親だけでなく支援者も読むべき本」といった声が多数寄せられているのは、理論だけでなく“親の本音”と“行動するための術”が同時に書かれているからこそ。

ガイドさん
「親なき後 対策」「障害児 相続」「成年後見制度 問題点」「親権 任意後見契約」「障がいのある子 遺言」 などで調べている方にとって、本書はまさに答えとなる一冊です。
親である“今”だからこそできることがあります。ぜひ、本書を手に取り、わが子の未来を「制度にゆだねる」のではなく、「自分の意思で築く」ための第一歩を踏み出してみてください。
本の感想・レビュー
私は福祉に詳しくない、いわゆる「一般の親」です。障がいのある娘がいますが、法制度や財産管理などの話になると、「専門家に任せるしかない」と思っていました。でもこの本は、そんな私の考えを変えてくれました。
まず、説明が本当に丁寧で分かりやすいんです。成年後見制度のしくみや限界、遺言や財産の残し方といったテーマが、難しい言葉ではなく、生活の延長線上にある言葉で語られています。だから、専門知識がなくてもすっと内容が入ってくる。しかも、「このタイミングでこれをやっておくといい」というアクションも具体的に書かれていて、「何をすればいいのか」が明確になりました。
安心したのは、「完璧に準備しなくても、できるところから始めればいい」と背中を押してくれたことです。まずは家族で話し合って、少しずつ動いてみようと思えたのが、私にとって何よりの収穫でした。
他8件の感想を読む + クリック
私は、特別支援学校に通う息子を育てる母です。普段は家事や通院、福祉サービスの調整に追われていて、正直「将来」のことをしっかり考える時間が持てませんでした。でも、この本を読んで、「このままじゃいけない」と心から思わされました。
「親心後見」という仕組みは、制度では救いきれない現実に対して、親が必死に考えた“知恵”の結晶だと感じました。なぜなら、そこには机上の理論ではなく、「わが子の人生を絶対に守りたい」という切実な思いが込められていたからです。誰かに任せるのではなく、自分で考え、行動した鹿内さん夫妻の取り組みには、強い説得力があります。
読み進めるうちに、胸が熱くなりました。涙が出るほどというと大げさかもしれませんが、「子どもを守りたい」という思いが共鳴したのだと思います。私も息子の将来に、今できることから向き合っていこうと決めました。
読んでいて一番衝撃だったのは、「18歳成人」が親にとってこんなにも重要な意味を持つということでした。ニュースでは耳にしていたものの、それが我が子の人生にどう関係するのかは、正直まったくわかっていなかったんです。
本書では、18歳を過ぎると親権が使えなくなるという現実を踏まえ、「それまでに備えておくこと」の重要性が繰り返し述べられていました。それを読んで、ゾッとしました。私の子どもは現在中学生で、あと数年で成人を迎えます。「まだ時間がある」なんて思っていた自分が、いかに楽観的だったかを思い知らされました。
時間は有限で、子どもの未来は“今”の行動にかかっている。目の前のことばかりに気を取られていてはダメだと、心から思いました。今からでも間に合うことがあると信じて、一歩を踏み出します。
私は障がい福祉に携わる仕事をしており、成年後見制度についてもある程度の知識は持っていました。しかし、この本を読んでみて、自分の理解が「制度の表面」に過ぎなかったと痛感しました。
本書では、実際に親が後見人になれないケースや、報酬の負担が長期的に家計を圧迫する問題、本人の意向を十分に反映できない仕組みなどが、当事者の目線でリアルに描かれています。その内容は、制度の説明書では決して得られない、切実な体験と気づきの連続でした。
これまで「後見制度はあるから大丈夫」と安心していた親御さんも多いと思います。ですが、それだけに頼る危うさをこの本は明確に伝えてくれます。制度はあくまで「道具」であり、本当に大切なのは、その使い方なのだということを教えてくれました。
これまで「法律」というものは、どこか遠い存在でした。自分には縁のない世界、難しい世界。そう思い込んでいた私が、本書を読み進めるうちに、その考えの甘さに気づかされました。障がいのある子どもを育てている限り、法的な手続きや制度の選択が、子どもの人生に直結するのだという現実に向き合わざるを得なかったのです。
特に、任意後見契約や財産管理等委任契約、公正証書遺言など、一つひとつの手続きが持つ意味や効力を知ったときの衝撃は忘れられません。どの書類も単なる「紙」ではなく、親がわが子に残せる「未来への約束」なのだということが、身に沁みました。
法律は冷たいものではなく、正しく使えば希望の手段になる。そのことを教えてくれたのが、この本です。親としての責任を果たすには、やはり学びが必要だと実感しました。
障がいのある長男を育てる中で、いつも心にあったのは「私が死んだ後、誰がこの子を守ってくれるのか?」という不安でした。そんな漠然とした不安に、この本は答えをくれた気がします。特に印象に残ったのは、公正証書を通して「想い」を形に残すというアプローチでした。
法的効力のある文書に、親の気持ちや願いを込めることができる。これは私にとって、まさに「光」でした。制度や契約だけでは補えない「心の部分」を、ちゃんと法の枠の中で記録として遺せる。そのことに、大きな救いを感じました。
本書に出てくる事例の中には、「親心遺言」と名付けて自分たちの意思をしっかりと残した親御さんの話がありました。それを読んで、私も書いてみようと決意しました。まだ元気なうちに、子どもの未来を明るく照らす準備を始めたいと思えたのは、この本のおかげです。
この本を手に取ったきっかけは、友人に「読むといい」と勧められたからでした。正直、最初は重たいテーマだなと思いながら読み始めたのですが、ページをめくるごとに、心がざわざわと揺さぶられていきました。
「30年後、私たちが死んだら——」という問いかけに、思わず本を閉じてしまったほどです。自分も子どもも、どこまで生きられるのか、どんな社会の中で暮らしているのか。その現実に真正面から向き合って書かれていたからこそ、「親なき後」が他人事ではないと痛感しました。
特に印象に残っているのは、障がいのある子が親の死後に抱える社会的孤立や、後見制度を巡る制度上の壁。自分の子にも起こりうる話だと分かって、震えるような気持ちになりました。この本を読まずにいたら、そのまま目を背けていたかもしれません。
この本は、夫婦でじっくり読みました。いつもは子どものケアを私一人が背負いがちで、将来のことについて夫と深く話し合う機会はあまりなかったんです。でも、本書を読んで、「これは二人で考えないと」と自然に会話が生まれました。
話題になったのは、財産の残し方や遺言のこと、そして親なき後の見守り体制。普段の生活ではなかなか話しづらい内容ですが、本に出てくる実例や仕組みが非常に現実的で、だからこそ話の土台になりました。
今では、毎月一度は「家族の未来会議」を開くようになり、子どもが安心して生きていける環境づくりに取り組んでいます。難しいテーマを、夫婦の対話に変える力を持つ一冊でした。
私は福祉施設で支援員をしています。日々、障がいのある方と接する中で、「この人たちの未来は本当に守られるのだろうか」と思う瞬間がありました。そんな折に出会ったのが本書です。
最初は親向けの本だと思っていたのですが、読み進めるにつれて「これは支援者こそ読むべき内容だ」と気づきました。親の目線、子の立場、そして制度の不備が立体的に描かれていて、現場では見えにくい部分がクリアになるからです。
特に、「法的な制度だけでは支援しきれない」という視点は、自分の支援の在り方を見直すきっかけにもなりました。福祉職である自分も、法律の知識をもう少し学ばなければならないと痛感しました。親だけでなく、支援者の責任も問われる時代が来ている。そう感じた一冊でした。
4位 障がいのある子とその親のための「親亡きあと」対策
「わたしがいなくなったあと、この子はどうやって生きていくのだろう――」
障がいのある子を育てる親にとって、「親亡きあと」の問題は、ずっと心の奥に横たわり続ける重くて深いテーマです。経済的な不安、制度の複雑さ、身近に相談できる人がいない孤独感。考えるほどに「正解」が見えにくく、先延ばしにしてしまいたくなる気持ちもよくわかります。しかし、だからこそ“今”考え、備えておくことが、子どもの人生を守る第一歩になるのです。
本書『障がいのある子とその親のための「親亡きあと」対策』は、そんな不安と迷いを抱えるすべての人に向けた、実践的かつ温かみのある一冊です。著者の鹿野佐代子氏は、入所施設や通勤寮、グループホームなど、障がい者支援の第一線で長年にわたり活動してきた福祉の専門家であり、現在はファイナンシャルプランナー(FP)としても活躍しています。福祉とお金の両側面から寄り添い、支援を続けてきた38年の経験が、本書のすべてのページに込められています。
続きを読む + クリックして下さい
「お金はどのくらい残せばいいのか?」といった多くの親が抱く素朴な疑問に対し、本書は明快に応えます。漠然とした心配を解きほぐし、現実的なライフプランを立てるための具体的な手法を、事例をまじえて丁寧に解説。また、障がい者本人が将来、どこで・誰と・どのように暮らしていくのかを想像しながら、制度やサービス、金銭管理の実態にも踏み込んでいきます。成年後見制度の注意点や、遺言・相続の準備、死後事務の委任契約など、親としての最後の役割を果たすための情報も充実しています。
さらに注目すべきは、「備えはシンプルでいい」「やらなくてもいいこともある」という、著者ならではのバランス感覚。多くのケースに携わってきたからこそ分かる、「やりすぎず、でも手を抜かない」支援の形が、現実的かつ心強く伝わってきます。理想論にとどまらず、地に足のついたアドバイスを求めている人にとって、本書はまさに待望の一冊といえるでしょう。
また、親だけでなく「きょうだい」や福祉・医療関係者、特別支援学校の教員、成年後見制度に関心のある人にとっても、学びと気づきの多い内容です。制度のしくみや相談窓口、支援体制の現状を知ることで、当事者以外の周囲の人々も“支える立場”として備えることができます。

ガイドさん
将来が見えない不安を、行動できる「準備」に変える――。
本書は、障がいのある子の暮らしと人生を守るために、今からできることを優しく、そして的確に教えてくれる人生の羅針盤です。
本の感想・レビュー
数字が苦手で、将来に向けたお金の計算を避けてきた私にとって、この本の「金額の試算」は衝撃でした。明確な目標金額が示されているわけではないけれど、いくつかの実例をもとに、「どんな暮らしをするか」によって必要な額がまったく変わってくることがわかりました。
暮らし方のモデルケースがあって、その中で収入と支出の流れがどうなるかを丁寧に追ってくれます。「なんとなく不安」を「こういう理由で必要なんだ」に変えてくれる試算が載っていたことで、これからどれだけ準備すればいいのか、我が家なりの計画を立てる第一歩を踏み出せました。
お金の話になると気持ちが重くなりがちですが、この本はそこを避けず、でも押しつけがましくなく教えてくれたことがありがたかったです。
他5件の感想を読む + クリック
私はずっと「親亡きあと」という言葉の重さに押し潰されそうになっていました。正直、制度の名前を聞いても何が何だかわからず、準備どころか情報収集すらできない状態でした。そんな私でも、この本を読み進めるうちに「なるほど、ここから始めればいいんだ」と思えるようになったのです。
言葉遣いがやさしくて、しかも複雑な制度も順序立てて説明されているから、まるで隣で話してくれているような安心感がありました。「もらえるお金」や「利用できるサービス」といった内容も、生活の実際に即して書かれていて、頭にすっと入ってきました。これまで「わからないから放っておいた」ことが、ひとつずつクリアになっていく感覚が嬉しかったです。
私は福祉関係の制度に興味はあっても、正直なところ、全体像が見えず混乱ばかりしていました。そんな中でこの本に出会い、点と点が線になった感覚があります。制度を紹介するだけではなく、それがどんなときに役に立つのか、具体的にどう使うのかが描かれていて、「なるほど」と膝を打つことの連続でした。
特に、公的支援と民間サービスの違いや、それぞれのメリット・限界まで踏み込んで書かれている点に誠実さを感じました。ただ羅列された情報ではなく、どう選び、どう相談すれば良いかまで書いてあるので、実際の行動につなげやすいです。
これまで情報があっても、それをどう使えばいいか分からなかった人には、本当に心強いガイドになると思います。
グループホームの話に関しては、これまで他の資料では表面的な説明しか見たことがなく、実際の暮らしがどうなのか見えてきませんでした。でもこの本では、グループホームという選択肢がどう機能しているのか、経済面や生活面の両方からきちんと描かれていて、とても参考になりました。
それだけでなく、「入らないという選択」についても触れている点に、著者の視野の広さを感じました。全員が同じ選択をするわけではないし、状況によって選ぶべき方向は変わります。その柔軟なスタンスが、読者である私にも「選ぶ自由」を与えてくれたように思います。
誰かが決めた“正解”を押し付けるのではなく、ひとりひとりの暮らしに寄り添っているからこそ、リアリティがあって信頼できるのだと思います。
この本に出会うまで、私は「子にどれだけ残してあげられるか」という視点でばかり物事を考えていました。ところが読み進めるうちに、その視点が大きく揺さぶられたのです。著者は、「お金を残す」こと以上に、「それをどうやって使ってもらうか」に焦点を当てていて、まさに目から鱗でした。
親として、お金さえあれば子どもは困らないと思い込みがちです。でも実際には、そのお金が必要なときに本人の意思で使えなかったり、周囲の支援者がうまく扱えなかったりすると、意味をなさなくなる。だからこそ、お金を“使うしくみ”や“使いやすくする工夫”が大切なのだと、本を通して学びました。
とくに、「使い道に名札をつけておく」というアドバイスは、具体的かつ実行しやすく、すぐにでも取り入れたくなりました。準備とは「残すこと」ではなく、「生かすこと」。その考え方に大きく心を動かされました。
福祉関連の本をいくつか読んできた中で、この本が特に優れていると感じたのは、成年後見制度に関する記述の丁寧さです。制度の概要を紹介するだけでなく、その制度が持つ制約や留意点にまで踏み込んでいるところが、他の書籍とは一線を画していると感じました。
私の娘はまだ若いのですが、先を見据えて後見制度の利用も検討していたところでした。しかし、制度を一度開始すると原則的に取り消せないこと、自由にお金を使えなくなる可能性があることなど、この本を通じて初めて知る事実も多くありました。表面的なメリットだけではなく、長期的な視点での判断材料を与えてくれる内容に、大きな信頼を寄せています。
また、申立て前に知っておくべきポイントが簡潔かつ明快に整理されていたことで、慌てて決断する必要はないのだと肩の力が抜けました。制度を使う側の立場に立った誠実な筆致に、安心感を覚えました。
5位 障害のある子が安心して暮らすために
障害のある子どもを持つ家族にとって、「親なきあと」という問題は、いつか必ず直面する現実であり、そして多くの家族が漠然とした不安を抱え続けているテーマです。親が高齢になり、いなくなったあとの子どもの暮らしはどうなるのか。お金は十分にあるのか、どこに住めばいいのか、どのような支援制度を利用できるのか——その疑問は尽きません。
そんな家族の不安に寄り添い、安心して子どもの将来を考えられるように導いてくれるのが、『障害のある子が安心して暮らすために』です。本書は、障害のある子どもの「親なきあと」の生活設計を支援者の立場から解説する実践的なガイドであり、福祉施設や行政機関、特別支援学校などで働く支援者が家族からの相談を受けたとき、どのように対応すれば良いのか、そのヒントが詰まった一冊です。
続きを読む + クリックして下さい
著者の渡部伸氏自身、障害のある子どもを持つ親として「親なきあと」に直面し、支援者としても数多くの家族から相談を受けてきた経験から、制度や制度の使い方だけでなく、家族の気持ちや不安に寄り添うことの大切さを深く理解しています。そのため、本書では単なる制度解説にとどまらず、実際にどのように支援の手を差し伸べられるのか、具体的な事例をもとに解説されています。
本書の特徴は、複雑な制度をわかりやすく解説しながらも、実際の事例や家族の悩みを通じて「自分の家庭の場合はどうすればいいのか」を考えられるようになっている点です。成年後見制度、福祉型信託、障害年金、生活保護、そして地域での支え合いの作り方まで、幅広いテーマをカバーしています。また、子どもの希望や家族の状況を最優先に考え、支援者が「何をどう説明し、どのタイミングでどの制度を紹介すればいいのか」といった実践的な視点を持てるようになるのも、本書の大きな魅力です。
さらに、支援者だけでなく、親御さんや家族自身が読んでも役立つ一冊になっています。親御さんにとっては、自分たちの将来計画を立てるきっかけとなり、支援者にとっては、家族に寄り添うための知識と心構えが身につきます。

ガイドさん
「親なきあと」に備えることは、障害のある子どもと家族にとって決して避けられないテーマです。
しかし、本書を手に取ることで、その不安を少しでも軽くし、支援者も家族も一緒に未来を考え、安心して暮らせる道筋を見つけることができるでしょう。
本の感想・レビュー
障害福祉の現場で日々、親御さんや本人の不安に向き合っている支援者として、この本を読んで一番に感じたのは「親なきあと」の問題に対する相談対応のヒントがとても多いということでした。これまで、親御さんから「もし自分がいなくなったらこの子はどうなるんでしょうか」と相談を受けても、具体的にどこから説明したらいいのか、何を優先したらいいのか悩むことが多かったんです。
この本は、ただ制度を羅列するのではなく、実際にあった相談事例をもとに、一人ひとりの不安や状況に合わせて、どのように話を聞いて、どんなアドバイスをすればいいのかを具体的に教えてくれます。相談事例を通して、親御さんの気持ちを受け止めながら、「住まいのことから話を始める」といったステップや、「家族だけで抱え込まないで地域を巻き込む」大切さなど、これからの支援にすぐに活かせる知識がたくさんありました。
また、相談室の取り組みについても詳しく書かれていて、支援者自身がどのような心構えで相談に臨むべきか、地域のネットワークをどう活かしていくかという点も非常に勉強になりました。支援者として、この本を一度手に取っておくことで、今後の相談対応に自信を持って臨めそうだと思えたのが大きな収穫でした。
他6件の感想を読む + クリック
障害のある子どもを持つ親として、「親なきあと」という言葉を聞くたびに胸が苦しくなる思いをしてきました。頭では「準備が必要」とわかっていても、どこから手をつければいいのか分からず、正直これまで避けてきたテーマでもありました。そんな私でも、この本を読んで「これなら私でもできるかもしれない」と思えたんです。
本書では、親が元気なうちからできることや、いざというときに備えておくべきことが丁寧に書かれていました。しかも、難しい言葉を使わず、実際の相談事例を交えて説明してくれるので、「このケース、うちのことみたい」と感じる場面も多く、すごく共感できました。家族が抱える不安を「一人で抱え込まないでいいんだ」と思わせてくれるところが、特に心に響きました。
読み進めるうちに、親として何を考えておけばいいのかが少しずつ見えてきて、「家族でまずは話し合ってみよう」という気持ちが湧いてきました。今までずっと後回しにしてきたテーマだけど、この本があったからこそ、「私たちにもできる準備がある」と背中を押してもらえた気がします。
この本を読んで、私が一番ありがたかったのは、やっぱり具体的な相談事例がたくさん載っていたことです。親御さんや本人がどんな状況で、どんな不安を抱えているのか、そして支援者がどんなふうに寄り添って話を進めたのか、その一つひとつがすごくリアルで、「ああ、こういう形で相談に行けばいいんだな」ととても参考になりました。
親が高齢になったときの不安や、本人が働けないときのお金の問題など、実際に多くの家庭が抱えている問題がケースとして紹介されていて、「うちだけじゃないんだな」と思えたのも心強かったです。何度も読み返しながら、「このケースは自分たちに似ている」と思った部分を家族と一緒に話し合いたいなと感じました。
支援者のアドバイスが具体的で、今後私が相談する時にも「こうやって相談したらわかりやすいかも」と思えたので、家族としても支援者としても役立つ一冊だと思います。読むことで、今すぐできることが見えてきたような気がしました。
障害のある子の将来のために、制度について知ることが大事だというのは分かっていたのですが、正直、制度の本を読むと難しい言葉ばかりで、いつも途中で読むのを諦めてしまっていました。でも、この本はそんな私でも最後まで読めたんです。家族の相談事例をもとにした説明なので、制度の話がとても具体的で、「こういう状況のときには、こんな制度が使えるんだ」と自然に理解できました。
成年後見制度、福祉型信託、障害年金、生活保護…これまで聞いたことはあっても、実際にどう手続きを進めていけばいいのか分からなかったものが、この本を読んで「こうすればいいんだ」と一歩踏み出せそうな気持ちになれました。特に、制度の解説の部分では、難しい言葉を噛み砕いて説明してくれているので、福祉や法律の知識がなくても安心して読み進められるのがありがたかったです。
自分だけでなく、家族みんなでこの本を読んで「うちはどうだろうね」と話し合いながら読み進めたいと思いました。制度の話が身近に感じられる一冊だと思います。
「親なきあと」の準備って、お金のことと暮らしのこと、どっちも大事なのに、これまで読んだ本はどちらか一方しか取り上げていないことが多かったんです。でもこの本は、福祉の制度も、お金の管理方法も、信託や保険のことまで、全部まとめて教えてくれていて、本当に助かりました。
親の立場からすると、子どもの暮らしを守るために「いくらあればいいのか」「どんな制度を使えばいいのか」が不安で仕方ないんですよね。この本を読んで、「たくさんお金を残すよりも、定期的に収入が得られる仕組みを作る方が安心」というアドバイスが特に印象に残りました。これまで大きなお金を残すことばかり考えていたけど、それだけじゃないんだと目からウロコでした。
お金と福祉の両方を一緒に考えられるから、家族だけじゃなく、支援者にとっても必読の一冊だと思います。「親なきあと」の準備は本当に大変だけど、この本があれば安心して一歩を踏み出せる気がしました。
「親なきあと」のことを考えると、ずっと心の中で大きな不安が重くのしかかっていました。自分がいなくなった後、子どもは本当に安心して暮らせるんだろうか。お金は足りるのか。誰が面倒を見てくれるのか。そんなことばかり考えて、何から手をつければいいのか分からずにいました。
この本を読んで、その不安が少しずつ希望に変わっていくのを感じました。文章の中にある一つひとつの事例や支援者の声、家族へのアドバイスがとても丁寧で、「私たちでもできることがあるんだ」と思えるようになりました。特に、「お金をたくさん残すことだけが大事じゃない」という言葉には救われました。これまでずっと、「もしものときのためにたくさん残さないといけない」と焦っていたけれど、それだけではない準備の仕方があるのだと知り、心が軽くなった気がします。
この本に出会えたことで、少しずつでも前向きに「親なきあと」に向き合っていけるんじゃないかと感じられるようになりました。これからは、この本で学んだことを家族と一緒に話し合いながら、一歩ずつ進めていきたいです。
成年後見制度について、これまでも何度か耳にしたことはあったのですが、実際にどんなときに利用できるのか、どんな手続きを踏めばいいのかはよく分かりませんでした。この本は、そんな私にとってとても心強い一冊でした。制度の仕組みだけでなく、家族の状況に応じた利用のタイミングや注意点などがわかりやすく書かれていて、「ああ、こういうときに使うんだ」とイメージがはっきりしました。
特に印象に残ったのは、「あわてて手続きを進める必要はない」というメッセージです。これまで、制度を使うなら早く決めないといけないんじゃないかと焦っていましたが、家族の気持ちや本人の希望を大切にして、じっくり話し合ってからでもいいのだと知り、ホッとしました。これから家族と一緒に成年後見制度についても考えていこうと思います。安心して相談できる場所があることの大切さも、この本を通じて改めて感じました。
6位 一生涯にわたる安心を! 障害のある子が受けられる支援のすべて
障害のある子どもの将来を考えるとき、多くの親御さんが感じるのは「この子が大人になったら、どんな生活を送れるのだろうか」「私がいなくなった後、この子はちゃんと暮らしていけるのだろうか」という漠然とした不安です。医療の進歩や福祉制度の充実で、昔に比べて支援制度は整ってきていますが、それでも制度の全体像や手続き、必要な準備は複雑で、「どこから手を付ければいいのかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そんなときに手に取っていただきたいのが、『一生涯にわたる安心を! 障害のある子が受けられる支援のすべて』。この本は、障害のある子どもが誕生したときから、学校生活、成人後の就労、そして親が亡くなった後の生活まで、一生涯にわたるライフステージに沿って利用できる制度や支援を一冊にまとめた、まさに“人生の羅針盤”ともいえる一冊です。
続きを読む + クリックして下さい
たとえば、乳幼児期には「乳幼児健診」や「児童発達支援」、重度障害児には「居宅訪問型保育」など、家庭の状況に応じた支援制度があり、親御さんの孤立を防ぎます。就学期になると「インクルーシブ教育」や「特別支援学校」、「訪問教育」など、子どもの学びの場を広げる制度が整っています。卒業後には「ハローワーク」や「障害者就業・生活支援センター」、さらに「就労移行支援」「就労継続支援A型・B型」など、就職・職場定着を後押しする仕組みがあり、子どもが社会で活躍できるようサポートが続きます。
生活面でも、居宅介護やショートステイ、税金の控除、手当の受給、住宅設備の助成など、多岐にわたる制度をわかりやすく解説。さらに、20歳からの障害年金の申請方法、親が元気なうちに考えておきたいお金の準備、親亡き後の住まいや財産管理、成年後見制度の活用まで、この一冊で“今から備えること、これから考えること”が見渡せるようになっています。
この本の魅力は、単なる制度の羅列ではなく、親子のリアルな悩みや支援現場での実例を交えながら、イラストや図解で具体的に説明している点です。監修は長年にわたり障害児支援の現場を担ってきた社会福祉法人和枝福祉会。だからこそ「机上の空論」ではなく、現場の声を反映した“本当に役立つ知識”が詰まっています。

ガイドさん
「うちの子の場合はどうなんだろう」「どこに相談したらいいのかわからない」という方でも、まずはこの本を開いてみてください。きっと、「次に何をすればいいのか」が見えてくるはずです。
障害のある子どもを育てるすべてのご家族にとって、そして支援に携わるすべての方にとって、手元に置いておきたい“一生涯の安心を支えるガイドブック”です。
本の感想・レビュー
この本を開いてまず目に飛び込んできたのは、全体構成のわかりやすさと、豊富に取り入れられたイラストやカラーでした。一般的に、障害福祉の制度や支援の説明というと、文字ばかりで読みにくい印象があるのですが、この本はそのイメージを一新してくれました。
特に印象的だったのは、制度の説明をただ文章で伝えるのではなく、図やチャート、吹き出しコメントなどを駆使して、一目でパッと理解できるようにデザインされている点です。複雑な制度の内容や、利用手続きの流れなどが、イラストで視覚的に整理されていて、どこから読み始めても「ここを見れば大事なところがわかる」という安心感がありました。
また、章立てもとても分かりやすく、誕生から学校卒業まで、大人になってからの支援、そして親亡き後のことまで、子どものライフステージごとにきれいに区切られているので、必要なところだけをピックアップして読むこともできました。「どのページをめくっても、親の気持ちに寄り添うように優しく手を差し伸べてくれているな」と感じられる一冊でした。
他5件の感想を読む + クリック
私は障害のある子どもを育てる親として、日々「この子の将来のために何をしてあげられるのだろう」と悩むことが多いです。この本を読んだとき、「これはまさに親目線で作られている!」と感じました。とにかく、実務的に「次に何をすればいいか」がはっきり書かれているので、不安でいっぱいの親にとって大きな支えになります。
たとえば、支援制度の概要だけでなく、実際に利用するまでの流れ、必要書類のこと、窓口での相談の仕方まで、現実的で具体的な情報が豊富に盛り込まれていて、「これなら自分でもすぐに動けるかもしれない」と思えました。特に、乳幼児期から学校生活、そして就職期や親亡き後までを網羅してくれているので、「今知りたいこと」だけでなく「この先、どうなるんだろう」という不安も軽くしてくれます。
本当に親として欲しかった情報がぎゅっと詰まっている一冊だと感じました。机の上に置いておいて、何か困ったときにすぐに開ける「親の味方」になる本だと思います。
この本を読み進めるうちに、「障害のある子どもを育てる上で、ここまで制度があるのか」と驚かされました。国の制度から自治体のサポート、民間のサービスまで、本当に幅広い支援が網羅されていて、一冊でここまでまとめられている本は初めて見た気がします。
制度が羅列されているだけではなく、各制度の利用条件や手続き方法まで丁寧に解説されているので、「これって実際に使えるのかな?」という疑問もすぐに解消できました。さらに、制度の解説だけでなく、実際に制度を使って支援を受けた家族のケーススタディも随所に挿入されていて、「ああ、こういうときにこういう制度を使えるんだな」とイメージがわきやすかったです。
この網羅性と具体例の豊富さのおかげで、自分の子どもに当てはめて考えながら読み進めることができました。支援制度の本というと「堅苦しい」「とっつきにくい」と感じてしまいがちですが、この本はそんな心配を吹き飛ばしてくれる、心強い味方になってくれると感じました。
障害のある子どもの将来を考えるとき、一番不安になるのは「自分がいなくなった後、この子はどうなるんだろう」ということでした。正直、このテーマにはいつも向き合うのが怖かったです。でも、この本はそんな親の気持ちをちゃんとわかってくれているように感じました。
相続や後見制度、グループホームのことなど、親亡き後の生活設計について具体的に、しかもわかりやすく書かれていて、「こういうふうに準備しておけばいいのか」と思えました。ページを読み進めるたびに、「自分が元気なうちに少しずつ準備していこう」という前向きな気持ちになれました。こういう情報はネットでも探せますが、まとまっていて、しかも親の気持ちに寄り添ってくれる言葉で書かれているのは本当に助かります。
自分だけじゃなくて、きょうだいや親戚にもこの本を見てもらいたいなと思いました。家族みんなで子どもの将来を考えるためのきっかけになる、そんな大切な一冊だと思います。
障害福祉の制度って、法律の改正や自治体ごとの運用の違いで、「ネットで調べた情報が古いままじゃないか」といつも不安でした。でもこの本を読んで、「最新情報がしっかり押さえられている」という安心感がありました。
たとえば、障害者総合支援法や障害年金の解説では、利用条件や手続きの流れがステップごとに詳しく説明されていて、しかも図やイラストでポイントを整理してくれているので、「ここは押さえておきたい」というところがすぐにつかめました。専門用語もきちんと補足がついていて、「専門家に聞かないとわからないかも」と思っていた部分も自力で理解できるようになっていて、とても助かりました。
こういう情報ってネットだと断片的にしか見つからないので、一冊にまとまっているのは本当にありがたいです。何度でも開いて確認したくなる、そんな一冊になりました。
障害のある子どもが大人になってからの「働く」ことについては、漠然とした不安がありました。でも、この本の就労支援のパートを読んで、その不安が少し軽くなったような気がします。支援機関やハローワークのこと、チーム支援の仕組み、さらには就労継続支援やジョブコーチ制度まで、幅広く載っていて、親として何を知っておけばいいのかが具体的にわかりました。
特に印象に残ったのは、企業への就職だけでなく、特例子会社の話や在宅就労の話も含まれていて、子どもの特性や希望に合わせて働き方を選べるんだと知れたことです。これなら子どもの将来に向けて、少しずつ選択肢を増やしてあげられるかもしれない、そんな勇気をもらいました。
7位 まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活
もしあなたが、障害のあるお子さんやご家族と一緒に暮らしているのなら、一度はこう思ったことがあるのではないでしょうか——「私がいなくなったあと、この子はどうやって生活していけるんだろう」「生活費は足りるだろうか」「安心して暮らせる場所はあるだろうか」「信頼できる人が側にいてくれるだろうか」。
これらは、誰しもが抱える切実な悩みでありながら、多くの人が「何をどうすればよいのか分からない」「情報が複雑で、読んでも理解できない」といった理由から、具体的な行動に移せずにいます。さらに、制度の仕組みや法律の用語は、専門家でなければ難解で、読んでも頭に入りにくいのが現実です。
そんな親や家族のために書かれたのが、本書『まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活』です。
続きを読む + クリックして下さい
この本では、法律や制度、年金や信託、遺言の書き方といった専門的なテーマを、できるだけ文字数を抑えながら、ストーリー形式のまんがと視覚的に理解できる図解で解説しています。難しい知識を「まるで会話のように」読み進められる工夫が詰まっており、「本を読むのが苦手」「活字は辛い」という方でも、手に取りやすい内容となっています。
例えば、障害のある子どもに残すお金の準備の仕方や、成年後見制度をいつ・どう使えばよいのか、家族信託や障害年金のしくみ、さらにはきょうだいとの話し合い方に至るまで——親なら誰しもが知っておくべき内容が、体系的かつ実践的にまとめられています。
本書の監修・執筆を務めた渡部伸氏は、「親なきあと相談室」の代表として、全国の自治体・福祉団体などで講演や個別相談を行ってきた実績のある行政書士です。障害のある子の将来に備えるためのアドバイスに長年携わり、多くの家庭に寄り添ってきた彼の知見が、この本には詰まっています。

ガイドさん
「知らないままにしていた不安」が、「知ることで行動に移せる安心」へと変わる。まさに、読者が“今”からできる具体的なステップを、やさしく、ていねいに導いてくれるのが本書の最大の魅力です。
未来への不安を抱えたまま立ち止まるよりも、まずはこの本を手に取り、できることから始めてみませんか?
あなた自身と、あなたの大切な人の人生を守るために——。
本の感想・レビュー
発達障害のある娘がいて、私はずっと「この子はひとりで生きていけるのか」という悩みを抱えてきました。学校や行政の支援もありがたいのですが、具体的に「将来の生活をどうデザインするか」までは踏み込んだ支援がなく、頼れる人も少なくて孤独でした。
そんな中でこの本を読んだとき、「これはただの情報本じゃない」と感じたのを覚えています。親ができる準備にはどんなものがあるか、子どもに何を伝え、誰に何を託すべきかまで丁寧に書かれていて、「ああ、これなら少しずつ進められるかもしれない」と思えました。
とくに印象的だったのは、「親がいなくなったあと」の話にとどまらず、「今」から何をしておくか、という視点が強調されていたことです。支援者を増やす、トリセツを作っておく、地域とつながっておく……そのひとつひとつが、親だけでなく、子どもにとっても安心につながるのだと思いました。
他5件の感想を読む + クリック
私は40代の母親で、知的障害のある息子を育てています。療育や就学、日々の生活の支援など、目の前のことに精一杯で、将来のことはどこか「そのときが来たら考えよう」と後回しにしてきました。でも心のどこかではずっと、「自分に何かあったとき、この子はどうやって生きていけるのだろう」という不安がつきまとっていました。
この本を読んで感じたのは、もっと早く知っておけば気持ちの余裕ができたのに、という後悔に近い思いです。まんがで始まる構成がとてもとっつきやすく、絵で状況が描かれているので「うちと似てる」と思う場面もたくさんありました。文章も図解も難しすぎず、でも内容はしっかり専門的で、読んでいるうちに「じゃあ次に何をしようか」と前向きな気持ちが生まれたのです。
制度の名前だけ知っていたけど、内容まではわかっていなかったというものが多く、知識としても勉強になりました。この本に出会ったのが今だったことには意味があると思いますが、できればもっと早い段階で手に取っていたかったと思わずにはいられませんでした。
私の弟は中度の知的障害があり、今は両親と暮らしています。私は長男で、将来的には弟のことを支えることになると何となく思っていましたが、実際にどうすればよいかは全くわかっていませんでした。両親も高齢になり、漠然とした不安だけが増えていく日々でした。
そんなときに見つけたのがこの本です。最初は軽く目を通すつもりでしたが、読み進めるうちに、これまでの不安の正体が少しずつ言語化されていく感覚がありました。親なきあと、住まい、年金、お金の残し方、そして信託や後見制度まで、まさに「知りたかったけど知らなかったこと」が整理されていたのです。
読み終えたあとは、弟の将来を考える視点が変わったと思います。「心配だから見ないふりをする」のではなく、「知ることで行動に変える」ことの大切さを感じました。不安がなくなったわけではないけれど、不安を動力に変えられるようになった気がしています。
私は福祉の現場で働いていますが、正直なところ、利用者の家族の立場になって考えることは少なかったかもしれません。この本を手にしたのは、仕事の参考になればと思ってのことでしたが、予想以上に新しい発見が多く、自分の知識の浅さを痛感しました。
たとえば年金制度の中でも「20歳前の障害基礎年金」や「有期認定」「永久認定」など、細かな分類があることを詳しく知る機会はこれまでありませんでした。また、障害者手帳と税制優遇のつながり、就労支援の選択肢の広さも、この本で初めて具体的に理解できた部分です。
福祉職であっても、全体の制度を網羅して説明できる人は多くありません。その点で、この本は職員研修の教材としても非常に有用だと感じました。親御さんだけでなく、支援する側の人間にも読んでほしい内容が詰まっています。
私は本を読むのがあまり得意ではないのですが、表紙の「まんがと図解」という文字にひかれて手に取ってみました。読み始めてすぐ、まんがのエピソードに引き込まれました。登場人物の悩みや不安が自分と重なる部分が多かったからです。
とくに印象に残ったのは、兄弟が障害のあるきょうだいのことで葛藤する場面や、母親が将来のことを考えて眠れなくなる描写でした。文章ではなかなか伝わらないような、感情の揺れやリアルな会話がしっかり描かれていて、読む手が止まりませんでした。
制度や支援の話ももちろん役に立ちましたが、まんがの部分があることで、「難しい話だけじゃない」と思えたのがよかったです。この本は、情報を届けるだけでなく、気持ちにも寄り添ってくれる存在だと思いました。
福祉や相続の現場で日々、行政書士として相談を受けている者です。業務の性質上、「障害のある子の将来」に関するご相談も多く、親御さんたちの切実な悩みに触れてきました。法律や制度に詳しい立場から見ても、この本は非常に丁寧に書かれていると感じました。
特に感心したのは、制度の紹介の仕方において「机上の理論」だけでなく、現実に即した利用の流れや手続きの注意点まで、図解や事例とともに明確に伝えている点です。遺言書の種類や成年後見制度の類型、家族信託の説明など、行政書士が日々説明している内容が、非常にやさしい言葉で整理されている印象を持ちました。
著者が実際に「親なきあと」相談を長年手がけてきた経験から来る視点と、法律家としての立ち位置が絶妙にバランスされていて、安心して人に薦められる本です。「制度を知れば、備えは進む」――そのことを実感できる一冊です。
8位 ダウン症の子をもつ税理士が書いた 障がいのある子の「親なきあと」対策
もし自分に何かあったとき、障がいのある我が子はどうやって生きていけるのか――。この問いは、障がい児の親であれば誰しもが一度は向き合う深刻なテーマです。「親なきあと」という言葉は近年ようやく社会に浸透し始めたものの、現実にはまだまだ情報不足で、何から手をつけるべきか分からない家庭が多いのが実情です。
そんななか、障がいのある子どもを育てながら、相続・税務のプロフェッショナルとして2,000件を超える相談を受けてきた税理士・藤原由親氏が、その経験と知識を余すところなく注ぎ込んだ一冊が本書『ダウン症の子をもつ税理士が書いた 障がいのある子の「親なきあと」対策』です。
続きを読む + クリックして下さい
本書は単なる制度の解説書ではありません。著者自身が「親なきあと」に不安を抱える当事者であり、読者と同じ目線に立って構成された“実践的な教科書”です。遺言や信託、成年後見制度といった法律知識はもちろん、子どものライフステージに応じた行動の優先順位や、具体的なマネープランの立て方、税制上の注意点などが丁寧に解説されています。
また、本書の最大の特徴は、「今の行動が、将来の安心につながる」という視点です。制度を知っていても、実際に行動に移せなければ意味がありません。本書では、親が元気なうちから備えることの重要性を説き、そのために必要な準備を段階的にわかりやすく示しています。
「何となく不安だけど、専門家に相談するのはハードルが高い」「自分にできる範囲から始めたい」「制度の違いがよく分からない」――そんな悩みを抱える方こそ、まずはこの本を手に取ってほしいのです。文章は平易で、専門用語には解説が付き、図や事例も豊富。まさに、法律や税の知識に自信がない方でも安心して読み進められるよう配慮されています。

ガイドさん
障がいのある子の将来のために「今」できることが何かを知り、そして実際に一歩を踏み出す。
そんな行動を後押ししてくれる、親としての責任と希望に満ちた一冊です。
本書は、あらゆる家庭の“未来を守る”ための確かな道しるべとなるでしょう。
本の感想・レビュー
私は正直、これまで「親なきあと」という言葉を見聞きしても、どこか他人事のように感じていたのだと思います。頭の中では「準備が必要だ」という意識はありながらも、どう動けばいいのか、何から始めればいいのか分からず、日々の忙しさを言い訳にして先延ばしにしていました。
そんな私にとって、この本はまさに目を覚まさせてくれる一冊でした。読み進めるうちに、「備えなければならない理由」が徐々に腹落ちしていき、ようやく“自分の家庭の話”として向き合う覚悟ができました。何より心を動かされたのは、著者自身が障がいのある子を持つ親であること。机上の空論ではなく、自らの実体験と長年の専門的な知見に基づいた言葉だからこそ、読む側の背中を押してくれたのだと思います。
「先のことだから、まだいい」と無意識に思っていた自分を、やさしく揺さぶってくれるような、でも確かな説得力のある内容でした。
他6件の感想を読む + クリック
私は福祉業界で働く中で、親御さんから「親なきあとが不安だ」という声を何度も聞いてきました。でも実のところ、自分自身が制度を深く理解できていたかというと、自信がありませんでした。専門用語が多く、法律や税制に関する話はどうしてもハードルが高く感じてしまいます。
ところがこの本は、その“わかりにくさの壁”を見事に取り払ってくれました。内容はしっかり専門的なのに、語り口はとても平易で、読み進めるごとに理解が深まっていく感覚がありました。特に相続の基礎知識や「法定相続分」「遺留分」といった部分は、これまで曖昧だった理解が一気にクリアになりました。
実際のご家庭の中で起き得る状況を想定して説明してくれているので、理屈だけでなく「こういうときどうすれば?」という疑問にも自然と答えが見つかる構成です。読者の立場をよく理解した本づくりだと感じました。
私は障がいのある中学生の娘を持つ父親です。この本に出会うまでは、正直“親なきあと”の準備は妻に任せきりにしていました。「いずれ自分も考えなきゃな」とは思っていたものの、行動にはなかなか移せずにいたのが本音です。
ですが、著者が同じ“お父さん”の立場で語ってくれていることに、大きな安心感と共感を覚えました。「仕事に追われて家庭のことは妻任せになってしまっている父親こそ、この問題に向き合ってほしい」というメッセージが、どこか自分への手紙のように響いたのです。
読み進めながら、初めて「自分が何をするべきか」「家族のためにどこで力になれるのか」が見えてきました。大げさでなく、この本に出会えたことで、父親としての責任の輪郭がようやくはっきりした気がします。
私がこの本を手にしたのは、漠然とした不安がピークに達していたときでした。子どもが成人を迎える節目で、「このままでいいのか」と焦りながらも、何から始めたら良いのかわからず、インターネットで情報を調べる日々。けれど情報は点在していて、どうにも全体像が見えませんでした。
本書を読んでまず感じたのは、必要な知識が順序立てて整理されていることの安心感です。そして読み終えたときには、「今のわが家に必要なことはこれだ」と、自信を持って行動に移す準備が整っていました。
私はすぐに、手帳に“親なきあと対策リスト”を作りました。遺言の準備、後見制度の検討、信託についての勉強…。一つ一つが明確に「To Do」として可視化されていったのです。本を読み終えることがゴールではなく、「次に何をすればいいか」が自然とわかる構成だったからこそ、こうした変化が起きたのだと思います。
金融関係の仕事をしているので、こうした制度系の本を手に取ることは多いのですが、この書籍には感心しました。税理士としての実務経験が随所に反映されていて、信託や保険の仕組みの説明に説得力があります。特に「生命保険信託」や「特定贈与信託」など、比較的新しい仕組みにも触れていて、実務での関心ポイントがきちんと盛り込まれている点は見逃せません。
また、制度の紹介にとどまらず、「どう使いこなすか」「家族構成や資産状況によって選択肢が変わる」という実務視点が豊富です。理論と実践の橋渡しができるこうした書籍は非常に貴重で、専門家にも推奨できるクオリティだと感じました。
単なる啓発本ではなく、最新動向にもアンテナを張った実用書として完成度が高いです。
この本を読み終えたあと、自然と夫婦で“親なきあと”の話をする流れになりました。それまでは、お互いに漠然と心配していたけれど、言葉にするのが怖かったんです。何をどう決めていいのかわからないし、感情的な話にもなりやすいので、つい避けてきました。
でも、この本には「どんなテーマを、どのタイミングで考えるべきか」が明確に示されていて、それが会話の“導入”としてとても助かりました。読んだ内容を見せながら「この制度は知ってた?」とか、「うちはどうする?」と聞いていくと、自然と会話がつながっていく。家族の誰かが専門家じゃなくても、この本をもとに一緒に考えることができるのは本当に大きなメリットだと感じました。
結果として、私たちの家では“今後についての方針”を初めて共有できました。「きっかけになる本」って、なかなかないですが、これはまさにそういう一冊でした。
“このままでいいのか?”というモヤモヤがずっと心にあって、でも誰にも相談できず、何から始めればいいかもわからなくて。そんな状態の中でこの本に出会い、読み終えたときの感覚は、まさに“霧が晴れた”というものでした。
不安が消えたわけではないけれど、それを「備え」に変える方法がわかった。これは大きな一歩でした。制度や法律は変わることもあるけれど、「今できること」を知っておくことで、将来の選択肢を増やすことができるというメッセージに、とても励まされました。
今まで頭の中だけで抱えていた心配が、行動に置き換わった。そんな感覚を持てたのは、この本が初めてです。読んだ人すべてが、前を向けるようになるはず。そう確信できる一冊です。